[一押し、この1枚]


日刊工業新聞社 編集局写真部 編集委員 田山浩一
2017年1月12日撮影、13日付紙面掲載
ドローン(飛行ロボット)が私たちの生活を変えると言われて久しい。
今回、福島県南相馬市で行われたドローンによる実験で、あらかじめ設定した緯度・経度の場所にGPS全地球測位システムによる誘導で無人で12キロメートル先に配送する実験が行われた。
米国の通販大手であるアマゾンがドローン配送の実証を進める中、出遅れ感の否めない日本勢。
今回の12キロという配送距離は自律制御のドローンでは世界最長であり、巻き返した。
千葉市に本社を置くベンチャー企業の自律制御システム研究所が実施し、NECや楽天も協力した。
飛行速度は時速43キロ。人間の目視内飛行を求める規制があり、沿岸を併走する船から監視しながら。
同社製ドローンは最高時速70キロ超。ただ、船が追いつけず、43キロにとどめた。
実験の舞台は、東日本大震災で津波が襲った南相馬の海岸線でもある。
だが、震災からもうすぐ6年。津波の爪痕をこの岩壁から見ることはない。
サーファーから注文された温かいスープを届けるという今回の状況設定。
注文通りのスープが届けられた。
今後は、ロボット活用先進地として、サーファーだけでなく、
被災地の産業界全体を温かく盛り上げてほしいと願わずにはいられなかった。
以上

共同通信社 ビジュアル報道局写真部
八田尚彦、播磨宏子、坂本佳昭、矢島崇貴、遠藤弘太
今年3月、岩手県陸前高田市旧市街地の震災から5年間の移り変わりを写したパノラマ写真6枚を配信した。これまで写真部全体で定点撮影を続けてきた。がれきに覆われた町はかさ上げ工事が進み、盛り土が目立つようになった。新たに建設された災害公営住宅も写真からうかがえる。
私は震災前の陸前高田の町並みを知らない。発生翌日に取材で市内に入ったのが初めて。海から数キロも離れた場所まで流入したがれきを前に愕然とした記憶が残る。定点撮影が複数の先輩カメラマンたちによって企画されたのは震災発生から間もなくたってからだ。GPS機能で撮影場所情報を取得しデータベースに入力していく作業は大変なもので、被災地全域の撮影対象は膨大な数に上る。地道な作業を続ける先人たちの背中を見つめてきた。今はその中に自分もいる。次世代に繋げるために継続していかなければならない。
以上

産経新聞社写真報道局 春名 中(はるな あたる)
2016年2月3日未明撮影、
3日付けサンケイスポーツ、夕刊フジ1面、4日付け産経新聞などに掲載
「警視庁は覚せい剤取締法違反容疑で元プロ野球選手の清原和博容疑者を逮捕…」。間もなく日付が3日に変わろうとしている2月2日深夜、仕事帰りに寄った地元の居酒屋で晩酌をしていた。常連客との会話が途切れ、なんとなくスマホのニュースサイトを流し見た時、驚愕し一気に酔いがさめた。
「すぐ出社するから」。デスクに連絡を入れてタクシーに飛び乗った。息を切らして到着した写真報道局にいたのは、険しい表情の当番デスクだけ。夜勤や泊まりの写真記者は既に取材現場へ向かい、もぬけの殻だった。デスクには警視庁に向かうよう指示を受けた。庁舎の車両出入り口に張り込み、移送される容疑者を狙うのだ。
その時、かつて同じ容疑で芸能人が逮捕されたときのことを思い出した。マスコミ各社は血眼になって立ち回り先や警察を取材したが、どこも空振り。容疑者は身柄を確保された後、警察病院で検査を受けてから警察署へ移されたことが、後になって分かった。
自分は出遅れている。この時点で警視庁前にカメラの砲列ができあがっているのは間違いない。「(取材者が)手薄な病院の出入り狙いで勝負したい」。デスクに申し出ると快諾してくれた。焦る気持ちを抑えながら、容疑者を護送した車両のナンバー情報を握りしめ、タクシーに飛び乗った。深夜の首都高で現場を目指す。車内では昔の思い出が頭の中を駆け巡った。
現役時代、自分の撮った写真で何度もスポーツ紙の1面を飾った強打者。右打者ながら、右翼へ放つ強烈な本塁打は今も鮮明に記憶している。1967年生まれの同学年。彼が在籍中、巨人担当になりキャンプや遠征先で酒席を共にしたこともある。〝片思い〟ではあるが他の選手以上に親しみを感じていた。
警察病院に到着しても容疑者を乗せた車両は見当たらない。辺りは静まりマスコミもいない。病院の外観を撮りながら駐車場も探す。「いないのかも…」。弱気な考えが頭をよぎる。次の瞬間、離れた場所にある救急搬送の出入り口に車が着いた。あわてて駆け寄るとメモと同じナンバー。同時に車は走り出した。
車中に人の姿は見当たらない。「空かも…」。そう思いながらも全力で追いかける。信号で止まったところで車内をうかがうが暗くて見えない。車内に向かってストロボで撮影すると後部座席に人が居るのが分かった。
信号が変わり発信する寸前、テレビ局のカメラクルーが現れ照明で車内を照らした。見慣れた〝野球選手〟が容疑者として座っていた。残念だが仕方ない。自分には撮影する以外、選択肢はなかった。これまで経験したことがない感情が交錯する中でシャッターを押した。わずか数秒の出来事。複雑な感情を押し殺し写真送信を急いだ。最終版に間に合う可能性があった。
パソコンに取り込んだ画像を見ると、かつての大打者が、気のせいなのだろうか少し小さく写っていた。
以上

読売新聞東京本社写真部 片岡航希(かたおか こうき)
中東などから連日多くの難民流入が続く欧州各国。秩序だった支援体制を構築できるのか議論が継続する中、今年に入り海路で欧州に渡った難民や移民は50万人を超えた。
その主な玄関口となっているのが、ギリシャ東部・レスボス島。トルコから10キロほどしか離れていないこの島には、難民を乗せてトルコを出発したゴムボートが連日続々と到着する。普段は観光客でにぎわうリゾート地の路上や海岸は、多くの難民であふれている。
9月上旬、取材活動をサポートしてくれるギリシャ人の助手と2人で島へ入った。上陸ポイントになっていると島の住人が教えてくれた海岸を目指すと、そこにはゴムボートやライフジャケットの残骸が無数に残されていた。つい数時間前に上陸した難民たちが残していったものらしい。
島の高台に車を止め、目をこらすこと約2時間、沖合に黒いゴムボートを見つけた。助手に車を飛ばしてもらい、上陸ポイントの海岸へ急行した。徐々に近づくボートをレンズ越しに確認すると、簡素な作りのゴムボートに50人近い難民たちがぎゅうぎゅう詰めで乗り込んでいる。もし波にあおられてバランスを崩したら・・・考えるとゾッとした。
居合わせたボランティアや観光客が旗を振りながら歓迎ムードを作る中、ゆっくりと岸に近づきボートは止まった。歓喜の声が聞こえてくる。足がふらつく難民の上陸をサポートしようと、オランダ人観光客が海へ入っていく。それにつられて自分も海の中へ歩を進めていた。両脇を支えられ涙ながらに上陸するイラクの数学教師、ラグダ・アルハシムさん(48)の表情にくぎ付けになった。家族6人でボートに乗り込み約3時間。背後には、対岸のトルコがくっきりと見えた。
「何度も波が襲ってきて怖かった。本当に良かった」。上陸後、こちらの拙い英語の問いかけに涙ながらに答えるアルハシムさんの姿に、これが不安と闘いながらの命がけの移動であることを改めて理解した。「ドイツで家族6人平和な暮らしをしたい」。彼女はこれからの生活への希望を語った。それと同時に母国への複雑な思いも。「私は母国を愛している。でもこうするしかなかった」。そう答えると、彼女は再び涙を流した。
以上

読売新聞東京本社写真部 佐々木 紀明(ささき のりあき)
2015年7月1日撮影
標準時と地球の自転による「天文時」とのずれを修正するため、1日の時間を1秒長くする「うるう秒」の調整が、日本時間7月1日午前9時前に世界で一斉に行われた。約3年に1度、「うるう秒」の調整が行われるが、平日に行われるのが18年ぶりとのこと。
平日もあって、東京都小金井市のJR武蔵小金井駅のコンコースには、たくさんの通勤するサラリーマンや学生らが足を止めその瞬間を見守った。
1時間前に到着すると、雨にもかかわらずすでにたくさんの人が待機していた。
電光掲示は撮影時のシャッタースピードによっては筋が入るなどの影響を受けるので、何度かテスト撮影を行い電光表示が消えないように設定した。
いざ、1分前になると我々取材する側も含め集まった人たちがソワソワし始めた。5秒前から「7、8、9」と大合唱が起こるなか、「60(秒)」の表示を多くの人たちが見守った。
撮影出来るのが当たり前であったが、画像を確認するまでは生きた心地はしなかった。撮影を終え、脚立から降りると同じ場所で撮影していたカメラマン同士で「撮れるのが分かっているけど緊張したね」と感想の声。
撮影後に取材した法政大学院の学生(24)は、「ほんの一瞬ですが、非日常の1秒を共有でき楽しめました。年越しカウントダウンとは異なり、余韻もなくまた日常に引き戻されました」と話していた。
コンパクトデジタルカメラやスマートフォンで撮影する様子は、まるで「60(秒)」の表示をバンザイして祝福しているようだった。
以上

東京中日スポーツ写真課 潟沼義樹(かたぬま よしき)
(2015年5月24日撮影・1面掲載)
大相撲夏場所で初優勝し、大関昇進を果たした関脇・照ノ富士。平成生まれでは初という若い大関だが、土俵上ではまさに鬼の形相を浮かべる。仕切りでは相手を穴でも開きそうなくらい鋭い眼光でにらむ。土俵際で撮影しているこちらまで、その気迫に寄り切られそうになる。
そんな照ノ富士も祝勝会では伊勢ヶ浜親方と女将さんから大盃に日本酒を注がれ、満面の笑みを浮かべた。一升瓶2本を最後まで注ぎきっても、関係者の祝福の声とカメラマンのシャッター音は鳴り止まず、「重い重い」と言いながら笑顔でポーズをとり続けてくれたサービス精神に感謝したい。
以上

共同通信社 稲熊 成之(いなくま しげゆき)
(2015年4月9日撮影、同日配信)
「西太平洋戦没者の碑」に供花後、アンガウル島(奥)に向かって拝礼される天皇、皇后両陛下=9日、パラオ・ペリリュー島(共同)
先の大戦の激戦地となり、日本兵約1万人がほぼ全滅したペリリュー島。同様に約1200人が玉砕したアンガウル島。今回の両陛下の慰霊訪問により、広くその名前が知られたのではないか。
戦後70年を経て、パラオは多くの観光客が訪れる南国のリゾート地になった。しかしその青く美しい海には旧日本軍の給油艦や〝ゼロ戦〟が沈み、うっそうと茂るジャングルには朽ちた戦車が残る。ペリリュー島でも戦死者の遺骨約2600柱が未収集のままだ。
4月9日午前、ペリリュー島南端に建つ「西太平洋戦没者の碑」に供花、拝礼の後、両陛下は青い海の先に浮かぶアンガウル島に向かい静かに頭を下げられた。このアンガウル島への拝礼は、訪問直前に陛下のご意向で予定に加えられたと聞く。今回の慰霊訪問に同行した東京写真記者協会加盟7社のうち、4社がこの「西太平洋戦没者の碑」を担当。私の撮影位置からは、10年来の宿願を果たされた陛下のご表情は見えなかった。しかし、ペリリュー島の紺ぺきの海に向かい深く拝礼される両陛下の姿を拝見して、これは速やかに日本に送るべき1枚になると思った。
「太平洋に浮かぶ美しい島々で、このような悲しい歴史があったことを、私どもは決して忘れてはならないと思います。」
8日、羽田空港出発時の、陛下のお言葉が胸に残る。
以上

日刊工業新聞写真部編集委員 田山浩一(たやま・こういち)
(2015年4月9日撮影)
全国農業協同組合中央会(全中)の定例記者会見で万歳章会長が涙をぬぐった。JAグループ解体につながる政府の農協法改正法案が閣議決定されたことを受け、辞意を表明した直後だ。
各社のカメラマンが並ぶ前で、ひと通りの質疑応答が終わり、これで会見も終わるかなという雰囲気。パソコンで本社に写真を送稿していた最中に、会長が腰ポケットからハンカチを取り出し、めがねを外して目をぬぐい始めた。
思わず、これは「まずいっ」と、すぐにカメラを構え直し撮った5秒間ほどのシーン。
「新しい全中のあり方を新会長の下でつくってもらいたい。私なりの区切りだ」と任期2年を残して退任することになった万歳会長。いろいろな思いがこみ上げたのにちがいない。
以上

東京新聞写真部 笠原 和則(かさはら かずのり)
(2015年3月13日撮影)
昨年から予告されていた日がやってきた。JRグループのダイヤ改正による寝台特急北斗星が定期運行を取りやめる3月13日が。前日は大阪と札幌を結んでいたトワイライトエクスプレスの最終運行日、翌日は北陸新幹線の金沢延伸開業と鉄道の話題が続く週末となった。私は現在、会社からデスク業務を命じられているが、この列車には様々な思い出があったので志願して取材に出かけた。
3月のダイヤ改正における寝台特急廃止はここ数年、毎年行われてきた“恒例”のイベントだが、今年の北斗星廃止で、とうとう「ブルートレイン」と呼ばれた青い寝台特急は日本から姿を消す。そんな思いもあってか、上野駅13番ホームには約3000人のファンが集まっていた。よりよい写真を撮ろうと大声を上げる人もおり、列車到着の際には緊張が走る場面もあった。
JR東日本から提示された撮影位置は、ホーム先頭の機関車が見える「プレスエリア」と、それ以外の場所。私は見送るファンと客車が撮影できるホーム終端を担当、もう1人が先頭に入った。プレスエリア外では脚立の使用が禁止されたこともあり、ファンの頭越しに撮影するのに苦労した。ホームの電光掲示板には行き先である「札幌」の文字が表示されていたので、これを味付けに、掲示板、北斗星、ファンの3つがうまく納まる位置にカメラを持って行って撮影した。しかし、高く掲げたカメラの背面液晶モニターはよく見えず、なかば当てずっぽうで撮影するため、なかなか構図が決まらない。何度か撮影してようやく納得できる写真が撮影できた。
翌日早朝には北陸新幹線金沢延伸、上野東京ライン開業と、明るい鉄道の話題が続々と入ってきたため、北斗星の話題はすぐに忘れられてしまったように思う。思い出の列車の廃止を残念に思うもやもやとした気持ちにも、こうした明るいニュースに触れ、また定期運行終日の取材を終えたことで一区切り付けることができた。
以上

デイリースポーツ東京報道部写真担当 村中拓久(むらなか たく)
(2015年2月2日撮影)
キャンプは、シーズン中とは違って選手とファンの距離が近い。サインをもらったり、記念撮影をしたり。そんな楽しみを求めて各球団のキャンプを訪れるファンが多いだろう。この期間中は選手の方も普段とは違うファンとの触れ合いを楽しみにしているものだ。
日本ハムの中田翔。チームの4番であり、今では侍ジャパンの4番も勤める日本屈指のスラッガー。時には髪の毛を金髪に染めたり、モヒカンに刈り上げたりと少し怖いイメージをお持ちのファンが多いかもしれない。
そんなこわもての中田が沖縄・名護で行われていたキャンプ2日目の全体練習終了後、クールダウンのため、後輩の白村投手と球場近くの海岸に向かった。近寄りがたい雰囲気の中、1人の少女がサインをもらおうと恐る恐る近づいた。するとその姿を見つけた中田は逆に自分から手招きして少女を呼び寄せた。持っていたボールにサインでもしてあげるのだろうと思ったら、なんと自身が着ていたシャツを脱いでサインし、その少女に優しく着せてあげたのだ。思いがけないプレゼントに少女は大喜びし、ぶかぶかのシャツを揺らしながら両親の元へ走って行った。
おそらく、その少女はこの日のことを忘れないだろうし、中田をずっと応援し続けるだろう。お決まりのサイン会やトークショーももちろんいいが、こんな形のファンサービスはさらにいいなと思いながら、シャッターを押した。
以上

時事通信社写真部 鴻田 寛之(こうだ ひろゆき)
(2015年3月1日撮影)
初来日した英国のウィリアム王子は3月1日、宮城県石巻市にあるニュース博物館「石巻ニューゼ」を訪れた。館内取材は事前の取り決めで、日英それぞれの新聞・通信とテレビ局4社が代表撮影することになった。
石巻ニューゼには、石巻日日新聞(いしのまきひびしんぶん)社が、東日本大震災直後に手書きで発行した号外「壁新聞」が展示されている。同社は輪転機などが津波で水没して使えない状況でも、炊き出しやラジオの安否情報放送、翌日の気候など生活に直結する情報を、ロール紙に直接油性フェルトペンで書き込み、毎日6部を避難所などに貼って新聞発行を続けた。その壁新聞は国内外で評価され、日本新聞博物館と米国の報道博物館でも永久保存されている。
当日、ウィリアム王子が到着すると、大勢の人々から歓声が上がった。震災当時、石巻日日新聞の報道部長として編集を指揮した武内宏之館長(現同社常務取締役)が王子を先導、震災翌日に撮られた衛星写真を前に説明を始めた。しかし、移動不可の撮影エリアからは王子の顔がよく見えず、私は5、6人のカメラマンと一緒に、王子が壁新聞を見ながらこちらに歩いてくる場面を緊張して待った。できれば「壁新聞の前でたっぷり立ち止まってほしい」と思ったが、壁新聞6枚が展示された数メートルを歩く時間は一瞬に感じた。「壁新聞を見ている時間より衛星写真を見ている時間の方が長い」と、焦って撮影した。
取材後、武内館長から王子について聞いた。「じっくり話を聴く誠実な方だった」と語り、壁新聞を見た後に子ども3人を津波で亡くした被災者の話を聞いて、退館前の記帳をする際に深く息を吐いたそうだ。その時そばにいた武内館長は「話をしっかり受け止めたのだろう」と語った。
石巻ニューゼには、壁新聞のほかに火がついて燃えた跡のある腕章も展示してあった。JR石巻駅から歩いて行けます。ぜひ見に行って下さい。
以上

読売新聞東京本社写真部 三浦 邦彦(みうら くにひこ)
(2015年2月7日撮影)
泊まり勤務に向かう電車の中で、渋谷のマンションで立てこもり事件が発生したことを知った。出社すると交代要員として現場に向かうことを命じられた。600mmの望遠レンズを持って現場へ。時間がかかると想定してまずは腹ごしらえだと食堂に入った。食べている間に解決しないかなと思いつつ外に出ると雨が降っていた。
男が立てこもるマンション14階のベランダが見通せる歩道には、写真部の先輩があらかじめ三脚を据えてくれていたのでそこにカメラをセットした。ピントを合わせようとAFボタンを押すと「ウィーン、ウィーン」とピントを探す往復運動を繰り返す音だけだった。現場が暗くコントラストが少ないからだろうか。あぶない、あぶない。本番でこれが起きたら撮り逃すと、男がベランダに立てかけた白いついたてにピントを合わせ、もうAFボタンは押さないと決めた。そのような現場なのでISO感度は51200まで上げ、シャッタースピードを100分の1、絞りf4に設定して警察官の突入を待った。現場到着から2時間弱が経過した午後8時40分頃、マンション屋上に5人の人影が現れた。黒い姿の特殊班がするするとロープで降下して男の部屋に入ると、あっという間に事件は解決した。
会社に戻ると、「10年前だったらこんな写真は絶対撮れなかった」と先輩に言われた。暗い現場でも写真が撮れるように高感度、高画質にカメラを進化させてくれたカメラメーカー。早い段階から現場入りし、絶好の取材位置を確保してくれた先輩。肉眼ではなかなか動きが見えない中、「今、捜査員がロープを垂らしました」など動きを実況してくれた隣にいたTV局リポーターに感謝したい。
以上

東京スポーツ新聞社、写真情報システム部 菊池 六平(きくち ろっぺい)
(2015年2月12日撮影、14日付紙面掲載)
<取材者の弁>
キャンプで初めての紅白戦を迎えた巨人のドラフト1位・岡本和真。試合開始前にベンチで素振りをしていると、グラウンドキーパーが散水を始めた。
普段からよく見かける光景なのだが、このような時は太陽光線で被写体の周りなどに虹が見えたりする。ドーム球場が増えた昨今ではなかなか狙えないチャンスだが、屋外の球場では“自然の恵み”によって思わぬ写真が撮れたりすることがある。
私が狙ったのは「巨人のドラ1岡本と虹」。ところが撮れた写真はまるで水を噴射するようなバットで素振りする岡本になった。写真には写っていないが、岡本の左手前に散水するグラウンドキーパーがいる。偶然のタイミングで素振りをしていた岡本のバットと重なり、まるでバットから水が噴射しているように写ったのだ。
狙って撮ったものではなく偶然写っていた写真でも、読者が目に留めてくれるならまぁいいか。
以上

読売新聞東京本社写真部 林 陽一(はやし よういち)
(2014年12月27日撮影)
<取材者の弁>
冒頭の4回転サルコーで転倒し、「あれっ」と一瞬思うも次々と演技をこなし、終わってみれば圧勝の3連覇を果たした。写真は終盤の回転での一コマで、体が細い羽生選手にもかかわらず手を高く上げた姿が力強く、掲載されたのがこの写真でよかったなと感じた。なにしろ女子ショートプログラム終了後に行われた男子フリーは締切時間ぎりぎりで、写真の加工も写真説明もつけず東京本社へ送っていたため、じっくりと写真を見返したのは送られてきたゲラを見た時だった。つまりこの写真は大量に撮影したカットを本社で選んでトリミングなど画像修整して出稿したデスクの仕事があってのもの。しかも近年はジャンプや回転の写真は表情などの問題であまり使われなくなっていたため意外に感じたのも正直なところだった。
さてフィギュアスケートは昔から好きではあったが、ちゃんとした大会を取材したのは2回目で、2003年に同じ長野のビッグハットだった。11年前のこの日は安藤美姫選手が女子初の4回転ジャンプを成功させて初優勝した日。2位は村主章枝選手、3位は荒川静香選手だった。
この全日本選手権大会で村主選手は引退を発表し、荒川選手はスケート連盟副会長としてプレゼンテーターを務めたのも印象的であった。そして忘れられないのは浅田真央選手で、11年前のこの大会がシニア大会デビューで8位だった。男子では高校生の高橋大輔選手が3位で表彰台に上がったのを覚えている。
今回、超満員の観客席や取材陣の多さに目を丸くし、出場選手や演技などに11年という時を感じた大会であったが、羽生選手は今後10年経っても現役で活躍し、素晴らしい演技をするのではないかと感じさせる大会であった。
以上

時事通信社写真部 田口 元也(たぐち もとや)
(2014年12月10日撮影)
<取材者の弁>
青色発光ダイオード(LED)の開発で赤崎勇名城大教授、天野浩名古屋大教授、中村修二米カリフォルニア大教授の3名が受賞したノーベル物理学賞。その授賞式がスウェーデン・ストックホルムで行われた。
出席者は最上級のドレスコードである「ホワイトタイ(燕尾服に白い蝶ネクタイ)」の着用が義務づけられ、報道陣にも厳粛な式の雰囲気を妨げない振る舞いが求められる。
今回の取材で一番重要な写真は、3人が一緒にメダルを持つ姿が収まっているもの。しかし式典中にそういった場面はないので、終了後に3人を呼び止めて絵作りする必要がある。つまり、取材のクライマックスは式の終了直後ということだ。
式が終了し、係員のゴーサインとともにステージに駆け上がる。息急き切って3人のもとへ行くと、教授たちは他の受賞者たちと和やかにあいさつを交わしている。ここはマナーが求められる場。強引に割って入るわけにもいかず、はやる心をグッと抑えて声を掛けるタイミングをうかがう。そうする内にも、受賞者の家族や関係者らが晴れの舞台で記念撮影しようとステージに上がってくる。あっという間に多くの人でごった返し、身動きすらとれなくなった。押しかける人たちに、最初に報道用の撮影をさせてもらうように頭を下げる。なんとか落ち着いたところで、3人にメダルを持ってもらうよう頼んだ。
24ミリの広角レンズでファインダーを覗く。「ち、ちかすぎる」。後ろから押される重圧を背中で押し返し、3人を画角に入れ声を掛ける。「メダルをもっと上にして、笑顔でお願いします!」。
時間にして10秒足らず、切ったシャッターはわずか数コマ。「終わりです」。係員の無情の声で撮影は終了した。
すぐにカメラの液晶画面で写真を確認。なんとか3ショットは撮れたが、表情が堅い・・。忸怩たるものがあったが、大急ぎで写真を日本へ伝送する。
すさまじい慌ただしさの中で授賞式の取材は終わった。無事にやり遂げた安堵感はあるものの、満面の笑顔をたたえた3人の写真を撮れなかったのが悔やまれる。少しのほろ苦さを胸に会場のコンサートホールを後にした。
以上

デイリースポーツ東京写真部 吉澤 敬太(よしざわ けいた)
(2014年10月30日撮影、31日付紙面掲載)
<取材者の弁>
ソフトバンクの3勝1敗で迎えた2014年プロ野球日本シリーズ第5戦は、序盤からソフトバンク・攝津と阪神・メッセンジャーの両エースの好投と、ファインプレー続出で7回まで0行進のしびれる展開。だが8回裏にソフトバンク・松田がメッセンジャーの左手の先をかすめる適時打を放ち、ついに均衡が破れる。
しかし9回、ホークス守護神・サファテのまさかの3四球で1死満塁。打席には阪神のムードメーカー・西岡剛。その5球目。一塁ゴロを捕った明石が本塁へ送球し、封殺。間髪置かずに捕手・細川が一塁へ送球するも、西岡に当たったボールが転々とする間に二走・田上が同点のホームイン…したかに思えた。しかし、審判は一塁を指差しアウトのポーズ。
「?????」
混乱のざわめきの後、球場は歓喜するファンの声で溢れかえった。結果は、打者・西岡が一塁へ向かう際にラインの内側を走ったとして守備妨害の判定。併殺となり、ソフトバンクの日本一が決まった。抱き合うホークスナインの手前には、審判団に猛然と抗議する阪神・和田監督。飛び交う怒号と交錯する歓声。撮影している自分も訳が分からない。今までプロ野球や高校野球など数え切れないくらい撮影してきたが、こんな優勝の決定シーンなんて、初めてだ。
ナインと抱き合いながらソフトバンク・秋山監督が、まだ抗議を続けている和田監督の方をちらりと見た。嬉しいけれど微妙な表情…。いったいどんな顔で胴上げされるのだろう?笑顔のない胴上げは華がないな…と心配したが、いざ胴上げとなったら満面の笑みで10回宙を舞った。「いままで10回胴上げされた優勝監督はいないから」という内川の粋な計らい。その10回目が、最も嬉しそうだった。今年で勇退する事になっていた秋山監督は、満面の笑みで有終の美を飾った。
一方で、阪神をひいきの球団としている我がデイリースポーツは、悲壮感たっぷりの紙面になったことは言うまでもない…。
以上
--------------------------------------------------------------------------------------------

毎日新聞社写真部 小川 昌宏(おがわ まさひろ)
(2014年10月16日撮影 毎日新聞ニュースサイトに掲載)
<取材者の弁>
36人が死亡、3人が行方不明の東京都大島町の土石流災害から1年となる10月16日朝、更地となった被災現場の献花台に、喪服の男性が2人、花束を抱えて訪れた。手を合わせる2人の向こうには、青い海と空が広がっていた。大島での取材は今回が初めてだった。前日、悪天候で見えなかった山が、この日ははっきりと見えた。
まさに「爪痕」のように残る山肌の土石流の跡に息をのんだ。一方、大勢が犠牲になった現場は、土砂だけが広がり、そこにあった人々の暮らしを想像することすら容易ではなかった。
だが、午後になると献花台が花であふれた。遺族や地元住民が、長い列を作って焼香していた。その光景が、この地にあった生活を、この地で生きた人たちを、想像させてくれた。忘れてはいけないと感じさせられた。
この災害現場を訪れたことがない大勢の読者に、人々の暮らしがあったことに少しでも思いを馳せてもらえる写真を撮らなければ、と強く思った。
以上
--------------------------------------------------------------------------------------------

産経新聞社写真報道局 大山 文兄(おおやま ふみえ)
(2014年9月28日撮影、29日付けグラフ面に掲載)
<取材者の弁>
長野・岐阜県境の御嶽山が噴火した翌日の9月28日、東京ヘリポートからチャーターヘリで現地に向かった。現場上空まで約1時間半。取材時間は1時間ほどだった。
秋が深まり色付く山々と対照的に、火山灰に覆われた御嶽山はグレー1色。太陽光を反射する山肌は雪景色のようでもあった。斜面を1列になって救助に向かう捜索隊の背後には登山者を楽しませていたはずの紅葉が広がっていた。
今回の空撮では主に800ミリの超望遠レンズを使った。揺れる機体からの手持ち撮影ではブレる可能性が高く不向きなレンズ。通常、航空取材で使用頻度が高い望遠レンズは400ミリ程度。しかし、噴火から丸1日たった現場の取材で、当たり前のことをやっていては前日と同じようなカットしか撮れない。写真に変化をつけようと、他社のカメラマンが使わないと思われるレンズをあえて選択した。
また、再噴火の恐れもあるため、普段より高い取材高度でも対応できるように考えた結果でもあった。過去には噴石に取材ヘリが直撃された事故も起きているほか、火山灰を吸い込みエンジンが停止する恐れもあるなど、噴火の航空取材には細心の注意が必要だ。
あえて超望遠レンズで撮った現場は、細部が表現されており「自然の脅威」を、より強く伝えられたと考えている。
最後に、今回の噴火で亡くなられた方々のご冥福を心からお祈り致します。
以上
--------------------------------------------------------------------------------------------


中日新聞社写真部 中森 麻未(なかもり まみ)
(2014年9月27日撮影、28日付け中日新聞、東京新聞に複数枚掲載)
<取材者の弁>
9月27日午前11時53分ごろ、御嶽山が噴火した。予知の難しい水蒸気爆発から起こった噴火とのことで、山頂付近にいた大勢の登山者が巻き込まれる大惨事となった。一報が入るとすぐにヘリコプターで離陸、雲の上に噴煙が上がる様子を岐阜県側から撮影し、夕刊の締め切りに間に合わせた。
その後、再び御嶽山上空に戻って撮影して松本空港に着陸、約1時間給油作業等を行い、16時ごろ再び御嶽山へ向かい、日没後まで撮影して名古屋空港に帰投した。
現場に向かうヘリコプターの中では、噴火と言っても湯気が上がる程度だろうと思っていた。しかし現場に着いてみて、その規模の大きさと、まるで生き物のようにもくもくと噴煙を上げる様子に驚き、ひたすらシャッターを切り続けた。ふと我に返り、噴煙の下にまだ何人もの人がいると思うと、大丈夫だろうかと心配でならなかった。
また、避難者を撮影しようと雲の下まで高度を下げると、撮影場所によってはヘリコプターのフロントガラスに火山灰混じりの灰色の雨粒が当たることもあり、運行乗務員も飛行に細心の注意が必要だったようだ。
私は2011年に企画取材で御嶽山を撮影したことがあった=雪に覆われた山頂の写真=ので、着陸後にその時撮影した夕日に輝く御嶽山のようすを思い返してみた。しかし27日に撮影した噴煙を上げる御嶽山と、噴火前の穏やかな御嶽山がどうしても同じ山だとは思えなかった。今回の噴火で不幸にも亡くなった方々のご冥福をお祈りします。
以上
--------------------------------------------------------------------------------------------

スポーツニッポン新聞社東京本社写真部 沢田 明徳(さわだ あきのり)
(2014年8月16日撮影、17日付紙面掲載)
<取材者の弁>
残暑厳しいお盆明けの8月16日。オーストラリアで行われる競泳のパンパシフィック大会の壮行イベントの取材に向かった。萩野、瀬戸らの活躍で注目度の高い競泳だが、この日のイベントには現役トップ選手の姿は無し。「今日はボツかな」と紙面掲載を半ばあきらめていたのだが、会場に水泳界の「レジェンド」北島康介選手が現れた。そしてイベント会場の中心には巨大な金魚鉢のような透明の特設プールが。
「これは面白いことになるかも」と期待すると、水着姿の北島選手が特設プールに入り泳ぎ方の見本を披露しはじめた。真剣に平泳ぎを披露する北島選手だったが、何かが変だ。水上の上半身と水面下の下半身が横にズレて見えるのだ。空中と水中での光の屈折率の違いから起こる現象で、思わぬ珍ショット撮影機会の幸運に心弾ませシャッターを切ったが、イベントを見に来た人たちにとっては泳法の良い見本になったのだろうか?
以上
--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社大阪支社写真映像部 八田 尚彦(はった なおひこ)
(2014年3月15日ほか撮影 6月12日前編、8月下旬に後編配信)
<取材者の弁>
1キロにも満たない体重のカラスにしたら、さぞかし重労働なのだろう。路上の針金ハンガーをくちばしでくわえると、脚を深く折り、地面を蹴るようにして飛び上がった。目指す先は目下、巣作り中の電柱の上だ。住宅の屋根にとまってときどき翼を休めつつ、最後は意を決したような大ジャンプ。「この1枚」の写真は、まさに巣に迫らんとして渾身の力で羽ばたいているところだ。
苦労して運んだハンガーも、しかし、置き場所が悪いと地上に落下してしまう。電柱の下には、巣から落ちてきたと思われる木の枝やらハンガーやらが散乱。このハンガーもどうやら一度誤って落下させたもので、カラスが再びチャレンジする場面に私は出くわしたというわけだ。
カラスが巣材としてのハンガーに目を付けたのは、もう何十年も前のこと。クリーニング店などを通して家庭に普及したハンガーを、
巣の土台として強度十分な格好の巣材になるということで、ベランダから失敬していくようになったのだ。
そんなハンガー好きなカラスを、同僚の武隈周防カメラマンと追い続けること1年。毎日のように巣を探しては空を見上げ、ツイッターなどのSNSで「ハンガーを使った巣がある」という情報があれば、東京や広島などへも飛んだ。警戒心の強いカラスの執拗な威嚇に、何度もくじけそうになりながら、大津市内でようやく撮影にこぎつけた。
共同通信社大阪支社では2013年春から1年間、動物をテーマにした企画取材を行った。若手中心の有志9人のカメラマンが、のべ700時間の張り込みと、仕掛けカメラなどで撮影。野生動物だけでなく、ペットや動物園の動物も対象にした。タイトルは、生きものたちの強い生命力を表す、鳥獣戯画ならぬ『鳥獣VIVA!』。全28回を今年6月から8月にかけて配信し、現在、加盟社の紙面で好評連載中だ。
・彼岸の墓地でお供えの花や菓子を盗み食うニホンザル
・繁華街の自転車の車輪で羽化を始めた蝉の幼虫
・未明の住宅街のごみ置き場でごみを漁るイノシシ―
出会った動物たちはみな人間社会の傍らで、人の生活をうまく利用し、したたかにたくましく命を紡いでいる。しかし時としてそれは、人の暮らしとの間に摩擦も生む。動物たちの写真を通して、両者の関わり合いを見つめ、いのちを考えるひとつのきっかけになれば、と思っている。
(これらの一部が、共同通信47newsウェブのトピックス覧に掲載されている。http://www.47news.jp/47topics/e/256592.php)
以上
--------------------------------------------------------------------------------------------


共同通信社写真部 遠藤 望(えんどう のぞむ)
(2014年9月8日撮影=現地時間、同日配信)
<取材者の弁>
錦織圭が順調に勝ち上がり、米大リーグヤンキースの取材をしているカメラマンの間で「これはテニス取材に行かねば」との話が出ていた。錦織圭がジョコビッチ戦に勝ち決勝進出が決まった後、私もテニス全米オープンの取材申請を出した。
昨年までは読売新聞も大会初日から取材をしていたが、今年はしておらず、共同通信の現地カメラマンだけが取材を継続。そのため弊社だけがコート脇に入れる腕章とカメラポジションを一つ割り振られていたことに、実は助けられた。
追加で取材に入った私と他社カメラマンが受け取ることができたのはデイリーパス(一日限りの取材パス)。このパスではコート脇に入ることは認められず、3階席コンコースからの撮影位置になる上、取材用腕章を30分ごとに報道受付に返却せねばならない。順番待ちしているカメラマンがいなければ再度腕章を受け取って再取材することになる。実にばたばたした取材となった。
錦織圭が必死の表情でリターンしている「この1枚」は、3階席から撮影したものだ。バックがすっきりしていて形もよく、迫力のある1枚となった。実は、現地カメラマンと調整し、第1セットだけ交代する形でコート脇に入って撮影をした。私の方がカメラとレンズ装備が充実していたこともあり、了承を得たのだった。なんと言っても近い分だけ気迫が伝わってくる場所だ。しかし、ナイスショットはどの場所で撮れるか分からない。
決勝会場は満員で日本からの観客も多く錦織圭への声援が多かったが、ストレート負けを喫してしまい、準優勝の快挙であるが終始、表情は暗いままだった。やはり準決勝でジョコビッチに勝った時が一番の盛り上がりだった。
毎年取材している外国通信社の撮影ポジションは非常によい場所で、写真データは全量送信し、フォトエディターが素早く配信。写真のクオリティも速報性も全くかなわないが、日本人の歴史的快挙を日本のカメラマンとして伝えることができて良かったと痛烈に思った取材だった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞大阪本社写真部 大久保 忠司(おおくぼ ただし)
(2014年8月23日撮影、25日夕刊グラフ面に掲載)
<取材者の弁>
広島市で土砂災害が発生した8月20日、早朝に大阪を発ち、現地に入った。夕刊グラフ面「ズームアップ」の取材を続けていた時に、本社デスクから米グーグル社の「ストリートビュー」画像と現状を比較して、災害の恐ろしさを表現できないかという提案があった。
対象はやはり、最も被害が大きかった安佐南区八木地区しかない。ストリートビューを見ると、かつて私が広島総局で勤務していた頃と変わらぬ、自然に恵まれた町並みがあった。しかし、今は「本当に同じ場所だろうか」と目を疑いたくなるような惨状が広がっていた。笑顔の子供たちが行き交った生活道路が、大量の土砂に埋まり、大きな岩が散乱していた。
広島市、呉市などを集中豪雨が襲い、多くの死者を出した1999年の土砂災害を機に、危険の周知や警戒態勢整備などを目的とした土砂災害防止法が制定された。あれから15年。行政は適切な対応を取ってきたのか。「失った歳月」を思わずにいられなかった。
亡くなられた方や、その家族、関係者の悲しみを忘れず、丁寧な取材をこれからも続けていきたい。
--------------------------------------------------------------------------------------------

中国新聞社編集局映像部 荒木 肇(あらき はじめ)
(2014年8月23日撮影、24日付朝刊 写真グラフ面に掲載)
<取材者の弁>
20日早朝に発生した広島市北部の土砂災害。初めての週末となった23日には多くのボランティアが現地に入っていました。青空が見えた昼ごろ、被害の多かった地区の一つ、緑井にも多くの人たちの姿がありました。道路は山から流れてくる水が川のように流れ、民家にたまっている状態だった。
撮影した写真は、被災した住宅周辺で、地元沼田高校の女子柔道部員が泥だらけになりながら庭先にたまった土砂を取り除く場面でした。周りには被災者の知り合いや、手助けになればと集まった人たちが協力していました。
災害から1週間が経ちましたが、まだまだ土砂の多くは片付いていない状況です。天気も不安定で住民の方も不安な毎日を過ごしています。全国から多くのボランティアの方々が集まってきています。一刻も早い復旧を願っています。
28日午後7時までの警察情報では、死者72人、行方不明4人。
--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社広島支局 西詰 真吾(にしづめ しんご)
(2014年8月20日撮影 同日配信)
<取材者の弁>
広島市で大規模な土砂崩れが発生した20日前夜、大阪写真映像部から広島支局に赴任している私が住む同市内の地域では、遠くに雷鳴が聞こえるだけで雨はあまり降らず、このまま大雨の峠は越えるかと思っていた。翌朝6時過ぎ、同部からの連絡で出社し、午前8時45分、現場に向けて広島ヘリポートを飛び立った。
当初の連絡は男児2人が生き埋めという情報しかなく、土砂崩れ発生は一カ所というイメージだったが、実際に現場上空に到着して、息を飲んだ。同市安佐南区の八木地区から緑井地区にかけての山肌のあちこちで、まるで巨大な手の爪でひっかかれたかのように土砂崩れが発生しており、ふもとの住宅地では、数多くの家屋が被害に見舞われていた。
今まで見たことのない光景が目の前に広がっている。倒壊した家屋、一階部分が土砂で埋もれた家屋、横転した自動車、屋根の上で救助を待つ住民、流れ落ちる濁流・・・。自然災害が比較的少ないと言われる広島でこんな事が起こるとは・・・正直、息をのむ感じで目の前の光景が信じられなかった。
21日までに入った情報では、39人が死亡、26人が行方不明になっている。住宅は45棟損壊し、120棟以上で浸水被害、110か所以上で崖崩れが見つかった。359世帯830人が避難しているという。被害が集中した安佐南区では、20日から夜を徹して救助、捜索活動を続けている。これ以上犠牲者が出ないことを祈るばかりだ。
--------------------------------------------------------------------------------------------


朝日新聞社写真部 日吉 健吾(ひよし けんご)
(2014年8月7日撮影、8日付け朝刊社会面に掲載)
<取材者の弁>
当初、取材する予定はありませんでしたが、土地のかさ上げ工事が本格化し、かつての土地でおこなわれるのは今年最後になりそうだと分かりました。今の岩手・陸前高田を象徴する写真にしたいと思い、背景に高台造成地から出る土砂を運ぶ巨大ベルトコンベヤーを写し込むことにしました。
ところどころに高さ5メートル程度の盛り土があったので、そこに上って移動しながら撮影しました。山車が動くので複数台をからめることに苦労しましたが、土砂と巨大ベルトコンベヤーの背景も分かる1枚となりました。
東日本大震災から3年5カ月あまり。これからも被災地の今を伝える写真を発信していきたいです。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 平野 皓士朗(ひらの こうしろう)
(2014年7月26日撮影、27日朝刊社会面に掲載)
<取材者の弁>
昨年は突然の大雨のため途中で中止となってしまった東京の夏の風物詩・隅田川花火大会。今年はバッチリ晴れてくれた。さて、肝心の撮影ポイントだが、スカイツリーを絡めた撮影ポイントは探求の余地ありだが、今年も昨年先輩が撮影した場所と同じビルの屋上から撮影した。
いろいろな地方の花火大会を撮影してきたが東京では初めての経験。今までは下地の建物や観客などを撮影し、その部分を隠して多重露光でカメラを左右や上下に振り画面に花火を配置して撮影してきた。
しかし今回はスカイツリーを入れるため、そういうことはなかなか出来ない。
ツリーと花火が上がる部分がほぼ同じためバランスよく配置するには花火の広がりや高さを注視せねばならず、長時間露光でシャッターを切っていった。
個人的には少しボリューム不足だったことと絞りすぎて光の線が細くなってしまったのが反省点だ。自分の周りでは当然宴会をやっていて、お客さんからお裾分けの誘惑に耐えた自分をちょっとだけ褒めてあげたい。
花火はどこで見ても美しい。今年はいい天気で、観客たちもじっくりと味わえたのではないだろうか。来年はどんな場所からどのように撮ろうか今からゆっくりと考えてみたい。
--------------------------------------------------------------------------------------------

報知新聞東京本社編集局写真部 頓所 美代子(とんしょ みよこ)
(2014年7月20日撮影、21日付朝刊7面に掲載)
<取材者の弁>
所属のイタリア1部(セリエA)・インテルでの5年目のシーズンに向け、成田空港から出発した長友選手。午前の空港は長友到着やいなやスマホをかざしながら殺到するファンで騒然となった。
普通、出発前の選手はあまりファンサービスせずに淡々と搭乗口に向かう。けれども長友選手は通りすがりのちょっと無遠慮な男性ファンに対してさえ握手で応対していた。
写真は搭乗ゲートで同じイタリア行きチケットを持った親子3人組みが報道陣と同じ場所で仁王立ち、お父さんがカメラを構え小学生の男の子と母親が手を振っていた近くで撮影したもの。
マスコミやファンに「塩対応」する選手を見慣れているせいか、飛行機に乗り込む直前まで見送る人々に丁寧に応えながら歩く長友選手の姿に感心してしまう1コマだった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

日本経済新聞社写真部 上間 孝司(うえま こうじ)
(2014年7月13日撮影=現地時間、14日夕刊に掲載)
<取材者の弁>
0-0のままもつれ込んだ延長後半113分、左サイドのドリブル突破から上がったクロスに、ゲッツェが見事な胸トラップでボレーシュート――。素早い展開だったが、不思議と落ち着いてシャッターを切ることができた。
ドイツ-アルゼンチンの組み合わせとなったサッカーワールドカップ(W杯)ブラジル大会の決勝戦、カメラマンの場所取り争いも熾烈を極めた。ゴールライン沿いで唯一空いていたのは、足元の電源機器が邪魔くさい、ゴールポストに最も近い席だった。死角が多いためにあまり好まれない位置だが、W杯を経験した先輩からは「良い写真を狙うならポスト寄りも悪くない」とのアドバイスをもらっていた。ゴールに向かってくる選手を真正面から捉えられるからだ。このゴールシーンについてはコーナーに近い席ほどゲッツェの背中しか見えない角度となり、結果的には私の席がベストポジションになった。運も味方してくれたようだ。
この1年間、W杯に照準を合わせて数々のサッカー取材を積んできたが、あえてゴールポスト寄りの位置で撮影することも多かった。「W杯では撮りたい場所で撮れることのほうが少ない」という先輩の言葉ゆえだ。実際、その通りだった。
これまで積み重ねてきた経験、先輩の教え、そして運。決勝という舞台で全てが上手く結び付いてくれた。この瞬間のために準備をしてきた、そう感じられる1枚になった。
--------------------------------------------------------------------------------------------


朝日新聞社写真部 高橋 雄大(たかはし ゆうた)
(2014年7月10日撮影、同日夕刊1面掲載)
<取材者の弁>
午後7時過ぎ、機材を片付けて帰宅しようかというタイミングで、土砂に一家が巻き込まれたという一報が届いた。自分が現在赴任している朝日新聞名古屋本社は原則、愛知、岐阜、三重の三県が管轄エリアだ。とはいえ、東京から現場に向かうより名古屋から近い今回の南木曽町のような場所は当然名古屋から向かう。
デスクと相談し、雨具やヘルメット、衛星電話などの災害取材用の機材をまとめて、すぐ現場に向かった。あちこちで通行止が発生した影響でカーナビは全く役にたたない状態。地図を頼りに現場に向かったものの途中で渋滞に巻き込まれ、現場に着いたのは日付が変わる直前だった。周囲は真っ暗で、二次災害の危険性もわからないため、目の前で行われていた警察の捜索作業の様子をとりあえず朝刊用に出稿するのが精一杯だった。
夕刊用には被害状況がわかる写真が必要になるだろう。夜が明けて見えてきたのは、橋脚が流されて宙ぶらりんになった線路、土砂に流された住宅の跡、ひっくり返しになった車…。あちこち夢中になって撮影し、夕刊用に出稿した。しかしながら、想像を上回る被害に言葉が出なかった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

日刊スポーツ新聞社写真部 狩俣 裕三(かりまた ゆうぞう)
(2014年7月4日撮影、6日付け紙面掲載)
<取材者の弁>
ネイマールがボールを持った瞬間、スタンドのボルテージは一気に高まり、歓声のボリュームも一層大きくなる。今大会の紛れもない主役、そのパフォーマンスに全世界が注目している。カメラを構える私もそれは同じ。主役の一挙手一投足は、すべてカメラに押さえる気概でピッチと対峙(たいじ)している。
ハプニングが発生したのは試合終了間際の後半41分だった。ルーズボールを追うネイマールの背後を、コロンビアDFスニガが急襲した。プロレス技のジャンピングニーの様な体勢から右ひざが腰に打ち付けられ、ネイマールはピッチに倒れ込んだ。
普段は「倒れすぎる」と評されるネイマールだが、今回は様子が違う。なかなか起き上がってこないまま時が流れ、異変を察知したDFマルセロがチーム医師を呼んだ。ブーイングと悲鳴が激しく交錯する中、ネイマールは担架で退場した。診断の結果は第3腰椎の骨折で全治4週間。この瞬間、今大会最大の主役は試合を残したまま、大会から去ることになった。
私にとって、このコロンビア戦が初めてのネイマール取材だった。身のこなし方や表情、すべてに華があった。「撮り逃しは許されない」緊張感を抱えながらも、その一挙手一投足に魅了されていく自分に気付いた。「撮っていて楽しい」そんな気分にさせてくれた。「もう少し撮影していたかった」は、偽らざる本音である。
--------------------------------------------------------------------------------------------

撮影:東京中日スポーツ 沢田 将人(さわだ まさと)
(2014年6月24日撮影、26日朝刊運動面掲載)
<取材者の弁>
サッカーのワールドカップブラジル大会1次リーグC組の試合が終わった。 日本は1勝もできない残念な結果で、勝っても負けても新聞紙面に写真は載るが、1面に大きく写真が掲載されても、現場のカメラマンたちの気持ちは「晴れやか」ではないだろう。
新聞紙面で要求されるサッカーの写真はゴールシーン。ところがサッカーを担当するプロカメラマンでも、必ず撮影できるわけではない。手前にディフェンスの選手がかぶることもある。そのため、ゴールとその後の喜びが撮影できる確率の高い撮影位置に皆が入りたがる。具体的にはゴールライン後方のコーナーフラッグに近い位置。皆入りたい場所が同じということはその場所取りがいつも熾烈を極める。今回日本が入ったC組は、ブラジルやスペインなど世界中の注目を集めるチームがいなかったためか、取材するカメラマンの数が、他の試合に比べれば少なかったようだが、だからといって場所取りが楽になることはなかった。
カメラマンは試合当日の朝5時や6時にはホテルを出て競技場に向かう。競技場入り口で開門を待ち、その後プレスセンターで座席の割り当てを受けることになる。場所取りがすむまで気が気ではなく、競技場外にサポーターを撮影に行く余裕もないのが現実だ。
この写真は日本-コロンビア戦の先制ゴールとなったPKの場面。クアドラド選手が放ったPKが、ゴールネット後ろに設置したリモートカメラの目の前に飛び込んできたもの。無線撮影装置が普及してからこうした写真をよく目にするようになったが、ここまでカメラの正面にボールが飛び込んでくることはまずない。試合は日本にとって厳しい結果だった。皮肉にも、試合結果の悲運とは逆に写真は偶然にも上出来だった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

デイリースポーツ写真部 西岡 正(にしおか ただし)
(2014年6月8日撮影、9日付け競馬面に掲載)
<取材者の弁>
数日前から激しく降り続く雨は、東京競馬場の芝コースをかなりの不良馬場にしていた。それまでのレースでは泥状態となったインコースを避ける馬が多い中、始まった安田記念。外側から抜き出たグランプリボス(左)に内側から世界王者・ジャスタウェイが迫る。両者が並んでコース中盤で一度、接触。更に激しいたたき合いで共に譲らない。
ゴール直前で二度目の接触、激しく競り合う両馬の鞍上ではグランプリボスの三浦皇成がジャスタウェイに騎乗する先輩の柴田善臣の顔面に強烈な肘打ちを浴びせた。ジャスタウェイは一瞬、よれるも根性を発揮し約9センチの鼻差で貫禄勝ちした。馬だけで無く、騎手のプライドがぶつかり合う一戦だった。
「トリッキーな馬場で、今までにないぐらいの疲労度だった。メンテナンスにも時間が掛かると思う」と調教師は語った。
--------------------------------------------------------------------------------------------

産経新聞社写真報道局 松本 健吾(まつもと けんご)
(2014年5月26日撮影(現地時間)、27日付朝刊2面掲載)
<取材者の弁>
会社で帰り支度をしていた5月22日の夜7時過ぎ。「タイで軍がクーデター」との一報が入り、急きょ、その日の便でバンコクに飛ぶことになった。首都・バンコクに特派員は不在で、外信部記者の現地入りも遅れそうという。予備知識がほとんどないまま深夜の便に飛び乗り早朝、現地入りした。
空港でつかまえたタクシーの運転手は、英語が通じず四苦八苦。それでも、市街地で警戒する兵士の様子などを取材し、何とか夕刊用に原稿と写真を送った。午後、同僚が東京から予約してくれた日本円で1泊約3000円のホテルで荷ほどきを始めた。騒々しいエアコンの音にイライラしながら、今後の取材を考えて途方に暮れた。テレビを付けても軍の規制でニュースが映らない。そのとき突然、部屋の電話が鳴った。カウンターに来客だという。訪ねてくる知り合いがいるはずもなく、「誰だ?」と思いながらフロントに出向くと、いかにも調子よさそうな男が立っていた。
「クーデターの取材だって? 俺に任せてくれ」。恰幅のいい、20歳代後半とみられる坊主頭。普通ではない風体だが、タクシー運転手だという。男は「ジョジョ」と名乗った。日常会話程度の英語はしゃべれるといい、「報道の客は初めて」としながらも、スマートフォンで新たなデモの予定や軍の動きらしきものを調べ、しきりにアピールしてくる。いかにも怪しかった。ニコニコと近づいてくる人間ほど、危ないものはない。しかし、そのときの私には他にあてがなかった。現地の相場よりも少し高めの値段を提示されたが、悩んだ挙句に雇うことにした。
結論から言えば、ジョジョは驚くほど有能だった。反クーデターデモ隊のスケジュールはピンポイントで把握。どこから仕入れるのか、軍の動きにも精通していた。渋滞に巻き込まれれば、すぐにバイクタクシーを止め、私だけ先に目的地に行かせる機転も利かせてくれた。
取材4日目の26日。ジョジョが「今日は(クーデターを起こした)プラユット陸軍司令官が初めて会見する。入れるかどうか分からないが会場に行ってみよう」と言うので、会見場の軍施設に向かった。クーデター側のトップの会見。入り口では、険しい表情をした兵士が目を光らせていた。 ジョジョが検問所の警備兵におもむろに向かっていく。現地の報道関係者でさえも施設の外で待っている状況だ。彼に呼ばれて、慌てて兵士に首にかけていた日本のプレスカードを見せた。兵士は、不思議そうな表情でしばらく思案していたが、ジョジョがさらに何事か声を上げるとうなずいた。「よし、入ろう」。ジョジョは得意げに言った。
ふと自分の胸元を見ると、記者証は裏返り、表に出ていたのは本社で泊まり勤務の際に使う「夜食券カード」。いぶかしげな兵士の表情が納得できた。振り返ると、地元の報道陣がカメラを抱えて慌てて追いかけてくる。なんと、一番乗りだったのだ。クーデターを起こしたプラユット陸軍司令官の記者会見【
--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 仙波 理(せんば さとる)
(2014年4月18日撮影 5月5日朝刊総合面掲載
<取材者の弁>
東京・高円寺。JR中央線沿いの、そこはかとなく懐かしさが漂う街の一角、テナントビル2階の薄暗い店内でその集いはあった。
東日本大震災後、被災者支援に加え、原発事故や放射能などの問題で政府方針に疑問を感じつつも、一方では抗議や抵抗をする旧来型の「護憲運動」には限界があるとも考える人。昨秋に強行採決された特定秘密保護法や、集団的自衛権の行使容認に向けて舵を切ろうとする政府に対し、不安や不満を抱える人。憲法解釈の変更に危機感を覚える人・・・。そんな人たちがフェイスブックなどで知り合い、ワインバーに集まった。
「肩に力を入れず、改めて憲法と向かい合うことができたら」。中心になったのは男女2人の弁護士。2012年、改憲を目指す第2次安倍内閣が発足してから、バーやカフェでの小規模な会合を続けてきたという。
女性弁護士が「ワインのように、比較すると個性が引き立ちます」と言えば、男性弁護士が「憲法はロック。特に俺は13条(=国民の個人の尊厳。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利)にロックの魂を感じる」と切り返す。集いでは2人がコントのように掛け合いながら、紙芝居あり、意見交換ありで、現行の憲法と自民党の憲法改正草案との比較が行われた。だが意見の押しつけはしない。違いを比べることで、それぞれが自分なりに憲法を解釈する判断材料にしてもらうのが目的だからだという。
5月。毎年この時期になると、憲法記念日の3日に向け、報道各社が各様に憲法を論じる。しかしながら、市民が自らの目線や立ち位置で日本国憲法についてカジュアル向かい合い、語り合う。そんな集まりがあってもいい。それこそワイングラスを片手にでも。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 松崎 浩一(まつざき こういち)
(2014年4月23日撮影 24日付け朝刊早版掲載)
<取材者の弁>
3度目の来日で羽田到着後の4月23日夜。オバマ米大統領は東京・銀座のすし店「すきやばし次郎」に向かった。安倍首相との非公式会食の取材は店の入りと出のみの代表撮影。前日に設定されたが当日昼に取材不可との連絡があり一旦は消滅した。
ところが午後8時前に官邸報道室から「なんだか撮れることになりそうです、15分後です」と突然の電話。内幸町の本社から車で向かうが交通規制で日比谷から動かず、走って現場へ急ぐ。大勢の見物客に封鎖で渡れない外堀通り。「間に合わずに撮れなかったらどうしよう」 かなり焦ったが無事到着。
すし店のあるビル地下に続く階段入り口で待つが現場仕切るのはアメリカの担当者。大統領同行プレスが到着するまで動くなと指示してくる。外務省の報道担当者が事前に取材ポイントに案内しようとするが、アメリカ側が阻止する。
「我々がホストであなたたちはゲスト」。外務省が抗議するが聞き入れない。ここは日本なのに・・・。同行プレスが到着、地下に下り撮影場所のすし屋玄関前に。カメラ代表社の東京新聞・フジテレビに内閣公式カメラマン、アメリカ側は代表を組むことなくペン・カメラ17人全員が。
日本人のペン記者は一人も現場に入ることが許されることなく、安倍首相・オバマ大統領は笑顔で店内に消えていった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

日本農業新聞写真部 福本 卓郎(ふくもと たくお)
(2014年3月撮影、4月6日付け朝刊掲載)
<取材者の弁>
佐賀県でタカやミミズクを巧みに操る女子大生に会うまでは、鷹匠(たかじょう)というと、武家時代にタカで狩りをする伝統を重んじる人のような印象を持っていた。取材してみると、この女性は、県内の短期大学に通うごく普通の学生。一見、猛禽類を飼っているような雰囲気ではない。しかし、自宅ではタカやミミズクなどを、多い日で1日6時間、調教に励む姿を見ると、〝猛禽使い(ファルコナー)〟としての技量の大きさに驚いた。5種類の猛禽類を使い分けて、田畑や果樹園に放し被害を食い止めているという。全国各地で、カラスなどによる農作物被害が年々広がり深刻化している中で、この取り組みが、害鳥対策の一つとして注目を集めて、自治体や企業から害鳥対策の依頼を受けるようになった。
ハリスホークやオオタカを、カラスを蹴散らすように飛ばし、もともと生息していた場所まで追い払うのが目的。成果をあげるには、ねぐらを見つけて、その場に居つかなくさせることだという。害鳥の種類や場所によって、猛禽類を使い分ける。中でも注目株は、夜行性のヨーロッパワシミミズク。昼間は、速く小回りが効くオオタカと比べのんびりしているが、暗闇になると夜目が効き、カラスのすみかにまっしぐら。カラスは恐れ驚き、居つかなくなり、その結果、被害を最小限に食い止められる。
この害鳥対策は、農産物の収穫期など期間が限定している場合、猛禽類を集中して飛ばし続けることで効果をあげられる。しかし、米倉庫など1年中食べ物がある場所の場合、毎日現場行って放し続けることは、現実的ではない。そこで、猛禽による追い払いと鳥が嫌がる忌避剤の設置を組み合わせて効果を高めることが分かったという。現在、鹿追いなどに使うため、ワシとタカを交配したゴールデンハリスイーグルを調教中。「困っている農家のために、一役買いたい」という女子大生。これからの活躍に期待したい。
--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社 ビジュアル報道局写真部 遠藤 弘太 (えんどう こうた)
(2014年3月11日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
東日本大震災発生から3年を迎えた3月11日。震災取材班の一員として岩手県陸前高田市に取材に出かけた。人が多く集まる一本松周辺ではなく、市内中心部のかつて駅前通や住宅があった場所で取材した。遺族やその土地に思いを寄せる多くの方々が足を運ぶと考えたからだ。
正午すぎ、山の方から雪を含んだ白い冷気が近づいて来るのが見えた。話すこともままならないほどの吹雪が辺り一面を覆い、それと時を同じくして花束を抱えた女性が近づいてくる姿を見つけた。彼女が勤めていた写真店の社長夫婦がそこで津波の犠牲になった。雑草が生え、更地となった場所に花束を置き、涙を流して祈っていた。悲しみに包まれた時間だった。
はじめは今回の撮影した写真の半分ほどの距離で約1、2枚撮ったが、シャッター音が想像以上に響き、彼女が静かに祈れるよう少し離れた場所で撮影したと記憶している。普段思い出したくない気持ちはあるが、この日だけは祈りを捧げたいという彼女の気持ちを大切にしようと思った。
--------------------------------------------------------------------------------------------

時事通信社写真部 落水 浩樹(おちみず ひろき)
(2014年2月23日=日本時間24日未明撮影、同日配信)
<取材者の弁>
ソチ五輪が閉幕した。羽生結弦、平野歩夢、平岡卓らが初出場でメダルを獲得する一方で、葛西紀明、渡部暁斗、竹内智香といったベテラン勢も活躍した。
誰もが目を疑った高梨沙羅の失速、そして浅田真央の挫折と復活。取材に予断は禁物と自分に言い聞かせて臨んだつもりだったが、事前にこうなるだろうと
予想した展開を何度もひっくり返され、右往左往しているうちに閉会式を迎えてしまった。五輪取材の恐ろしさであり、おもしろさでもある。
閉会式では、スタジアムの外から聖火台と花火などをからめた全景を撮影した。開会式で聖火の点火が選手や観客から全く見えない位置で行われただけに、
消灯の際にも場外で何か撮影できるのではないかと考えたのだが、またしても予想を裏切られてしまった。何の前触れもなく炎は消え、まもなく花火が打ち上げられ、噴水に合わせてショスタコーヴィチの祝典序曲が人影もまばらな公園内に鳴り響いた。
今回の五輪が地元ロシアの人たちに大きな感動と勇気をもたらしたことは間違いないだろう。ただ、スポーツ観戦どころではなかった人たちも多かったはずだ。反政府デモからロシアの軍事介入へと緊張が高まるウクライナ。ソ連崩壊後、対ロシアの紛争、テロ行為を繰り返してきた北カフカスの国々。ソチはその中心に位置している。
軍隊と警察を大量投入し、外界から完全に隔離された五輪公園内はたしかに今のところ安全を保っているが、これは「平和」のショーケースのようなものだ。スタジアムの外から見た閉会式には、地元住民が一緒に盛り上がるお祭り騒ぎの喧噪は感じられず、静かな閉幕という印象を持った。
--------------------------------------------------------------------------------------------

毎日新聞北海道支社報道部写真グループ 貝塚 太一(かいづか たいち)
(2014年2月20日撮影 同21日夕刊1面掲載)
<取材者の弁>
ソチ五輪フィギュアスケート女子シングルに出場した浅田真央選手は、前日のショートプログラムで16位と出遅れた。フリープログラムを当日に控えた早朝の練習、一人遅れてリンクに登場した浅田選手の表情は痛々しく、とても競技ができる状況には見えなかった。
目の前にいる23歳の女性の肩にかかっていた期待や責任感はどれほどのものだったのか、満足行く演技が出来なかった絶望感は想像すらできない大きな苦しみだと感じた。私にとって今回が初めての五輪取材。この日までの取材では自分の実力や運のなさに落ち込む日々もあったが、自分の苦しみなど彼女の抱えるそれとは比べようがないものと反省させられた。
迎えたフリープログラム本番。昨夜とは打って変わり、力強い表情をした彼女の姿に自然と気持ちが入る。冒頭のトリプルアクセルに成功すると会場の空気が一変した。ここ数年見たことがない完璧な演技に心奪われ、4分あまりの時間があっという間に過ぎた。演技を終えた直後に表情を崩した浅田選手の姿に手が震え、ファインダーが涙で曇った。リンク中央でのあいさつ。審判側にあいさつした後、一回転して振り返り、観客の声援に応えた。瞳にあふれる大粒の涙、そして対照的に輝く笑顔。一人の人間があんな絶望的な状況から復活し、蘇生する力を目の当たりできたこと、あの瞬間にあの場所にいられたことに感謝する思いだ。
--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞社写真部 菊政 哲也(きくまさ てつや)
(2014年2月15日撮影(現地時間)、同17日夕刊1面掲載=日本時間)
<取材者の弁>
15日のジャンプ男子個人ラージヒルで葛西紀明選手が銀メダルを獲得した。私と同年代で「レジェンド」と呼ばれる彼の跳躍をこの目で見られる機会とあって、光栄な気持ちでその時を待った。
1回目のジャンプ。美しい飛型で落下してくる彼が、両手の平を最大限効果的に使って浮力を得ようと奮闘する姿がファインダーの中で確認出来た。わずか数秒の跳躍に全身全霊をかけている様子が心を打つ。1回目を終えて2位。一気にメダル獲得の期待が高まった。メダルより本人が納得できるジャンプをしてもらえればそれでいいのではないか、と思っていた私も「ここまで来たら」と欲が出始めていた。
2回目のジャンプを終えた葛西選手がガッツポーズしながら戻ってきた時、メダル獲得を確信した。彼を慕い、飛びつくように駆け寄る後輩たちを、両腕を広げて迎え入れた姿に思わず目頭が熱くなった。結果的に最終ジャンパーが葛西選手を上回り、金メダルはならなかったが、満足そうな彼の姿にこちらもすがすがしい気持ちにさせてもらった。
フラワーセレモニーを控えたミックスゾーン付近で、他の外国人選手やボランティアらが葛西選手に握手やサインを求めていた。丁寧に対応する葛西選手の姿を見て、なぜ彼が「レジェンド」と呼ばれるに至ったのかを垣間見た気がする。私より一つ年下、7度目の五輪を41歳で迎えた大ベテランは、どの大会でもこうして誠実に対応してきたのだろう。大活躍に心の中で拍手を送りながら、涙で曇るファインダー越しに捉えた彼の最高の笑顔を忘れることはないと思う。
--------------------------------------------------------------------------------------------

中日新聞社写真部 内山田 正夫(うちやまだ まさお)
(2014年2月14日撮影・15日夕刊掲載)
<取材者の弁>
フィギュアスケート男子で日本に待望の金メダルがもたらされた。獲得したのは宮城県出身の19歳、羽生 結弦(はにゅう ゆずる)選手。前日のSPで100点を超える歴代最高得点をたたき出していた彼に日本中が注目したフリー演技だった。最初の4回転などジャンプを2回失敗し、ひやひやしたものの、羽生選手の次に滑ったカナダのチャン選手の得点が伸びず、金メダルを獲得。この撮影ができたことで、連日夜遅くまで続く取材の疲れも一気に吹き飛んだ。
羽生選手の演技では今までの大会では見られないほど、必死で気合いの入った表情を見せる場面が数多く見られ、これが五輪なのかと、そのことがとても印象に残った。
15日までに日本が獲得したメダルは金1個、銀3個、銅1個。10代選手が3個のメダル、41歳の葛西選手が銀メダル。新しい力と「レジェンド(伝説)」と呼ばれるベテラン選手の双方が活躍する見応えのあるオリンピックとなっている。今後も選手たちの活躍する瞬間を撮影すべく、日々長時間の撮影を楽しもうと思う。
--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 伊藤 智昭(いとう ともあき)
(2014年2月8日撮影=日本時間、同日配信)
<取材者の弁>
ソチ冬季五輪開会式で小笠原歩旗手を先頭に入場する日本選手団。正直言って有名かつ有力選手が少なすぎで、自分にとってはもう一つ盛り上がりのない入場行進だった。第22回冬季五輪ソチ大会は7日夜(日本時間8日未明)にロシア南部ソチのフィシュト五輪スタジアムで開会式が行われ、4年に1度の雪と氷のスポーツの祭典が開幕した。
私にとって冬季五輪取材はトリノに続き2度目だ。ソチ大会は冬季史上最多の87か国・地域と個人資格で参加のインドから約2870選手が出場した大きな開会式だった。
自分に与えられた撮影ポジションで、いかに一味違う日本選手団を捉えようかと必死に狙った。日本列島が会場に浮かび上がることは資料で分かっていたが、いざその場面になると、もう一つはっきりしない。北方四島も雲に隠れて分かりにくい。しかしながら「列島と選手団絡みはこのタイミングかな」とワイドレンズをつけたリモートカメラを意識しながら多めにシャッターを切った。
自分としては「分かりやすい構図の写真に」と試みたものの、もう一つビシッとこない写真になったと思ったが、読者の中には、これがいいと指定してきた人がいたというから「まあ、いいか」。おまけに聖火点灯が会場外で行われたときには、開会式会場内にはしらけた雰囲気が漂い、会場内の極めて小さく画質の悪いモニターでは点火の様子もよく分からない。外では盛大に花火の音が響いたが、会場内では申し訳程度の花火があがっただけだ。テレビ映像を最優先して構成された開会式は、20万円もするチケットを買った観客や、入場行進に参加したアスリートにクライマックスを見せない消化不良の開会式だったと思ったのは自分だけだろうか。テレビで見た家族は結構楽しめたようだが・・
--------------------------------------------------------------------------------------------

中日新聞静岡総局 立浪 基博(たつなみ もとひろ)
(2014年1月7日撮影、同1月28日夕刊1面に掲載)
<取材者の弁>
潜水取材で伊豆半島西北端の大瀬崎に向かっていると、駿河湾を隔てた富士市や富士宮市が浮き上がって見えた。蜃気楼だ。富山湾は有名だが、駿河湾にも現れることにびっくりした。400ミリの望遠レンズで右から左へと追っていくと、確かに浮き上がって見えるがそれだけではインパクトが足りなかった。富士川にかかる新幹線の鉄橋の半円状のアーチが楕円になり、リングが連なっているように見えた。これだ、と思いシャッターを切り、中日新聞の翌朝刊1面に掲載された。実は、これとは別に「だるま太陽」を狙った。
大瀬崎も蜃気楼で浮かび上がっていたが、それだけでは読者を納得させられる写真にはならない。もう一つポイントが欲しい。太陽か月はと考えて調べてみると、太陽の蜃気楼で「だるま太陽」という現象があることを知った。四角い太陽を狙っていた大先輩を思い出し、蜃気楼の太陽と大瀬崎を撮影しようと決めた。日没と重なる場所を計算して、ちょうどいい場所を探り当てた。前回の蜃気楼を撮影した気圧配置や、風など天気を予想して何度か訪れた。
西の水平線に太陽が沈んでいくと、海面からもう一つの太陽が現れる。それが歪んだようにくっつき、沈んでいった。薄い雲が重なって徒労に終わった日や、空気が澄みすぎるために太陽の光が強くて大瀬崎とのバランスが悪くなった日もあったが、なんとか撮影できた。
太陽や月を撮影対象とどのようにからませるかは、計算で場所を探せる。便利なソフトもあるが、お金を払いたくないので利用しない。事前にその場所に行き、計算通りの写真が撮れるかなど障害物の有無を確認して撮影に臨む。天気にも恵まれ計算通りの撮影ができると、卓上の苦労も一瞬にして喜びに変わる。
--------------------------------------------------------------------------------------------

スポーツニッポン新聞社写真部 久冨木 修(くぶき おさむ)
(2014年1月15日撮影、同1月16日付朝刊6面に掲載)
<取材者の弁>
大相撲初場所4日目に両国国技館で行われた時天空・佐田の富士戦で、珍事は起きた。「まわし、まわし、動かない!」――行司・木村晃之助の声が飛んだ。佐田の富士のまわしの結び目がほどけ、取り組みを止めて締め直したのだ。しかし、再び外れてしまった。
見かねた土俵下の朝日山審判長が「手伝ってやれ」と声を掛け、控えの嘉風が土俵に上がった。取り組みをファインダー越しに見ていた私は土俵に力士が3人上がるという〝珍光景〟に遭遇。まさに「ごっつあんです」の「この一枚」になった。行司・木村晃之助は嘉風の手伝いを固辞し、まわし直しに四苦八苦したが何とか締め直した。
後で聞いた話だが、嘉風は「審判に言われて行ったのに、土俵で『いいよ』と言われてめっちゃカッコ悪かった」といい、行司の晃之助は「関取に手伝っていただくことはできない。私は進行係だから」と言っていたそうだ。再開した取組では時天空があっさり寄り切った。
--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞東京本社写真部 菊政 哲也(きくまさ てつや)
(2013年12月28日撮影、2014年1月1日、1面掲載)
<取材者の弁>
今年2月7日開幕予定のロシアのソチ冬季五輪。昨年暮れ、元旦紙面を目指してソチ五輪スタジアムのライトアップを狙った。この日は雲が少なく、夕焼けが奇麗に出そうだったこともあり、事前に下見していた五輪公園北側の丘陵地帯に登って日没を待った。競技施設のライトアップ試験が行われていたことはすでに知っていた。ただ、あまり早く撮影しても元旦付けには撮影日が社内で問題になりそうだと思い、年末ぎりぎりまで待ちたかった。その後の天候に不安があったので、28日の空の雰囲気を見て撮影を決行した。
撮影場所はまだ貧しい地域で、道路も舗装されておらず、悪路の上に、一部道路は陥没、タクシーの車体を傷めないように時間をかけゆっくりと登った。一般市民が来そうな場所までは警戒のためパトカーが停まっており警察官が目を光らせていたが、撮影を止められることはなかった。
そこからさらに登って、民家が4~5軒あるだけの寂しい場所にたどり着くと、「その時」を待った。運転手には誰かが不審がって近づいたら事情を説明してくれるようにお願いし、車から50メートルほど離れた丘陵斜面に登って撮影した。全く明かりのなし斜面なのでスマホの明かりだけが頼りだった。
素晴らしい夕焼けや五輪スタジアムの真後ろの黒海に太陽が沈んでいく様子を撮影した後、本命の五輪スタジアムのライトアップを待った。ただし、この日に点灯する確証はなかった。
日没とともに、カーリング会場やスピードスケート会場などが少しずつ点灯し、未完成といわれている五輪スタジアムの屋根にもようやく光がともり始めた。はじめは青、緑、赤、白、と単色を切り替えていただけだったが、周囲が暗くなる頃には屋根の表面を色彩が移動するようなパターンに変化。様々なパターンがあることが分かったので、ロンドン五輪で紙面化したスタジアムの色彩変化の分解写真を狙ったが、常灯していた他の競技施設と比べ、五輪スタジアムはまだ調整中なのか、時々ライトアップが消灯するなど、未完成具合を感じさせた。
元旦の東京1面には分解写真ではなく、1枚で3色に輝く五輪スタジアムの写真が使われたが大阪本社発行の社会面最終版には、狙った通りの分解写真が掲載された。様々な色に変化する五輪スタジアムの姿が今でも自分の脳裏に焼き付いている。
--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞北海道報道センター 堀 英治(ほり えいじ)
(2013年10月6日撮影、7日社会面掲載)
<取材者の弁>
今年も残り少なくなった。今年忘れられないワンショットが撮れた。それはシロザケの遡上写真。「生まれ故郷へジャンプ」という見出しで社会面に掲載された。昨年9月に北海道へ赴任してから初めてのチャンスだった。
朝日が差す中、波間のあちこちにサケの背びれが見え隠れし、時折、跳びはねる姿が北方領土の国後島を背後に見えた。密集した群れの中にいるストレスか、遡上する川の位置確認をしているかもしれない。「跳ねた」と、その瞬間、本能的にシャッターを切った。3日間通ってようやくモノにした。10月初旬といえども朝方の気温は約2度、風が吹けばさらに寒さが身にしみた取材だった。
自然豊かな北の大地。雄大な自然に新鮮味を感じる。道内全域をほぼ制覇した。1年を思い起こせば、1月、札幌市内でも積雪が多く、異常低温が続いた。3月、道東では暴風雪の災害で死傷者がでた。6月、日ハムルーキー・大谷投手の初勝利、二刀流の姿も話題になった。7月、JR北海道の脱線事故から始まった不祥事など。事件事故が結構多かった。
しかし、何と言っても自然相手の取材は事欠かない。道東地区へは道が真っ直ぐで、いくら走ってもすれ違う車もなく、渋滞など無関係。ただ、エゾシカ、キタキツネやヒグマ(なかなか遭遇しないが)、堂々と信号無視で車道に出てきていることもあり、衝突事故を避けるため運転には注意が必要だ。知床半島周辺は野生動物の宝庫で、たびたび取材に訪れている。来年早々には、この海原に次第に流氷が押し寄せ、凍てつく場所になる。また良い写真テーマもやってくる。厳冬の地を取材で満喫しなければと思っている。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 笠原 和則(かさはら かずのり)
(2013年12月14日撮影)
<取材者の弁>
「2013年 報道写真展」が日本橋三越本店で始まった。今年はゲストにプロ野球巨人軍の長嶋茂雄終身名誉監督を迎えた。“ミスター”が報道写真展にゲストとして登場するのは1974年以来2度目。開会式では他のゲストとともにテープカットを行い、その後自身が写った5月の国民栄誉賞授賞式の写真などを見学した。協会の花井事務局長の説明を受けながら会場を回った長嶋さんは、時折笑顔を見せ、「いいねー」を連発しながら写真展を楽しんでいた。
また、長嶋さんには記念品としてキヤノンマーケティングジャパン(株)から国民栄誉賞の賞品「黄金のバット」にちなんで世界で唯一カバーとネックストラップが金色特別仕様のカメラ「パワーショットN」が贈られた。
この模様は東京写真記者協会加盟各新聞社、通信社とNHK、民法各局、日本新聞協会などが取材し、報道された。
今年の展示は世界遺産に登録された富士山コーナー、5月に国民栄誉賞を受賞した長嶋さんと松井さんコーナー、80歳でエベレスト登頂に成功した三浦雄一郎さんコーナー、被災から2年が過ぎた東日本大震災コーナーなど、国内外の約250点の作品を展示し、24日まで開催している。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 嶋 邦夫(しま くにお)
(2013年12月3日撮影、4日朝刊特設面に掲載)
<取材者の弁>
東日本大震災の発生から1000日目を迎えるあたり、上空から未だに収束しない東京電力福島第一原発の事故現場を空撮した。
東京新聞は定期的に原発の現状を記録している。今回私が撮影したのは、震災発生の翌日(2011年3月12日)以来二度目のことだ。最初の撮影時は東北の被災地に向かう途中に約10㎞離れて水素爆発前の最後の建屋を空撮した。
二度目の今回は晴天で空気も澄んでいたが肉眼では建物の形状を確認するのが限界。作業員の姿や使用済み燃料プールを撮影するには超望遠の800mmレンズが必要。主に野球取材のセンターカメラとして使用するレンズで、大きな三脚に固定して使用するのが常識。揺れる機内で“手持ち”撮影するなんてメーカーも全く想定外の使い方だろう。肉眼では詳細が視認することができない新たな放射性物資で汚染された廃棄物や、増設される処分場、無残なまま残る建物の瓦礫の側で、防護服を着て復旧作業を行う作業員。汚染水タンクのサビ?や汚れなどがリアルにレンズを通して飛び込んできた。
特に不思議だったのが汚染水を入れるため増設が進む溶接型のタンク。基礎の形が六角形?狭いスペースを最大限に利用する工夫だろうが、増え続ける汚染水に有効な手が打てない現状が透けて見えた気がした。一日も早く本当の“アンダーコントロール”が実現してワイドレンズで撮影できる原発になることを願うばかりだ。
--------------------------------------------------------------------------------------------

報知新聞東京本社編集局写真部 矢口 亨(やぐち とうる)
(2013年11月3日撮影、4日付朝刊野球面に掲載)
<取材者の弁>
中日、阪神監督時代に計3度日本シリーズに挑み、日本一を逃してきた楽天・星野監督の悲願の胴上げ。三塁側内野カメラマン席から見る胴上げは、手前の選手の背中が邪魔をして、上がりきるまで監督の表情が見えない。いわば歓喜のびっくり箱のようなもの。
雨の中で目の前に突如現れた表情は、闘将にとっての日本一の重さや喜び、そこにたどり着くまでの苦しみが詰まった最高のものだった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 関口 聡(せきぐち さとる)
(2013年10月21日撮影、22日付夕刊社会面)
<取材者の弁>
震災からの復興のシンボル「奇跡の一本松」(陸前高田市)を背景に能楽師たちが能を奉納した。演目は「羽衣」。犠牲者の鎮魂と復興への祈念を込めた笛と太鼓の音が、夕暮れの空に響いた。
復興支援NPO「JIN’S PROJECT」(折尾仁代表)が企画し、陸前高田市の協力を得て、「能楽の心と癒やしプロジェクト」の能楽師・八田達弥代表らが演じた。折尾代表は「震災遺構の多くが解体され、記憶の風化が心配。伝統芸能を通して地元の人たちを支援すると同時に、被災地以外も含め語り継ぐことの大事さを考えるきっかけになれば」といい、震災3年にあわせて本格的な上演を目指すという。
今回の上演は奉納が目的で、事前の告知をしなかったため観客は少数だった。両団体は今年、宮城県石巻市などでボランティア公演を行っている。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 平野 皓士朗(ひらの こうしろう)
(2013年10月21日撮影、22日朝刊社会面に掲載)
<取材者の弁>
伊豆大島で発生した土石流災害。当日朝まで避難勧告が出ており、この日は捜索活動が2日ぶりに再開された。災害発生から数日、捜索活動の写真はあらかた出ており、どういう風にこの日の捜索活動再開を表現しようかと1日歩き回り、気がつくと日が落ち、真っ暗に。
現場付近を歩きながらあれこれ考えているとパラパラと雨が降ってきた。また雨だ。毎日降る雨には住民達同様にうんざりしていた。自衛隊ら捜索活動している人たちも同じ気持ちなのだろうなと顔を上げると一筋、いや何筋もの光。雨がライトを照らし暗闇を切り裂く。
二次災害がいつ起きるかもしれない、住民や報道陣の不安が続く島内でその光はより一層の力強さを見せていた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 武居 雅紀(たけい まさのり)
(2013年10月5日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
最後の技の直前、姿勢を正した白井健三が少し強ばった表情で大きく息をつく。天真爛漫を地でいく体操ニッポンの新星もさすがに緊張しているのかと思うと、こちらもカメラを持つ手に力が入った。
ベルギーのアントワープで開かれた体操の世界選手権。種目別の床運動で日本史上最年少優勝を果たした白井健三は「シライ」と自身の名前が付いた新技「後方伸身宙返り4回ひねり」を成功させるなど、超人的なひねりの技術で世界を驚かせた。
衝撃デビューの新技を感覚的にわかりやすく伝えるには、真横からの連続合成写真が適切だと思い、技の開始位置、最高到達点、着地点、テレビクルーの位置などに気を使ってカメラを設置した。
出来上がった写真を見て驚いた。頭を中心に回転し、きれいに伸びた足がまるで扇のようだった。最後のさわやかなガッツポーズがこの画を一層引き立ててくれた。
締めきり時間が厳しいなか、「出来栄え抜群」に奮闘していただいた画像編集記者の皆様にこの場をお借りして大いに感謝。
--------------------------------------------------------------------------------------------

毎日新聞社写真部 手塚 耕一郎(てづか こういちろう)
(2013年8月26日代表撮影、同日配信)
<取材者の弁>
福島第1原発で茂木経産相が汚染水漏れタンクを視察することになり、代表撮影を担当した。当初は現場の放射線量が高いため、視察する大臣をバス内から撮影するという話だったが、当日になって報道陣もバスを降りての取材が可能になり、全員防護服・全面マスク姿でタンク前に先回りし、大臣を待った。会社から持参した放射線量計のアラームが鳴動し続けている。
やがて大臣が到着して取材開始。大臣は遠目にタンク群を見るだけ・・・、と聞いていたが突然、タンクに向けて歩き始めた。取材者も慌てて追いかける。代表撮影といってもテレビクルーや省庁の撮影担当者などもいるため、良いアングルを求めて先回りしたり、引いたりと動き回る。そんな時、汚染水が漏れたタンクのすぐ近くで、水たまりを踏んで歩いている人が何人かいた。取材者か警護の関係者かは分からなかったが、特に誰も気に留めていない。おそらく雨水の残りか何かだろうとは思うが、「おいおい、大丈夫なのか?」と直感的に感じた。汚染水ではないとしても気分の良いものではない。タンクでの取材時間は10分弱、原発海側の汚染水対策現場の取材も合わせて、線量計の値は130μSVとなった。
写真は漏水タンクの取材を終えて離れ際に撮影した1枚。立ち並ぶタンク群の中で、水漏れが起きたタンクだけ不気味に×印が付けられていた。しかし、印や土のうがなければ、どのタンクから水漏れがあったのか見分けがつかない。取材の後もあちこちのタンクで汚染水漏れが発覚している。暑苦しく動きづらい防護服姿でもあり、つい注意が散漫になってしまうが、危険がどこに潜んでいるか分からない場所だからこそ、慎重な取材を心がけなければと感じた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 大森 裕太(おおもり ゆうた)
(2013年8月27日撮影 同29日付20面掲載)
<取材者の弁>
2013年8月22日、突然の悲報。「藤圭子飛び降り自殺か?」
娘の宇多田ヒカルが対面に来るのはいつか?動向に注目が集まった。1日が経ち、2日が経ち、未だ姿を現さない宇多田ヒカル。結局彼女が母・藤圭子さんの遺体と対面出来たのは27日の午前中だった。
1日2交代、若手中心でシフトを組み24時間体制で張り込むこと5日目。
たまたま私の張り込み中にその時はやってきた。霊柩車の助手席に乗り込み火葬場へ向かう彼女、しかしその姿は突然の悲報にどうして良いか分からず、うつむくばかりの一人の少女の様にさえ見えた。
私も仕事とは言え、悲しんでいる女性を撮影することはとても辛く、出来れば避けたい現場であった。私も子を持つ親として、もし私達報道陣がいなければもっと早く会えていたのではないか、遺族の方々の苦しみを余計にこじらすことはなかったのではないか、などと思うととても複雑な心境になった。ここでは、故人への御冥福を心より祈るしかなかった。合掌。
--------------------------------------------------------------------------------------------

日刊スポーツ新聞社写真部 野上 伸悟(のがみ しんご)
(2013年7月21日=日本時間22日撮影、同23日付野球面掲載)
<取材者の弁>
どんな時でも平静を装うイチローらしからぬ行動に映った。大記録達成後、二塁に進んだ際に、敵チームの川崎に向かって自らグータッチを求めた。普段から仲がいい2人とはいえそこは勝負の世界。逆に、こぶしを差し出された川崎が一瞬戸惑っているように見えた。
日米通算4000本安打という、米国人、メジャーリーグにとってはなんとも「微妙な」記録とあって、達成時にも特別なアクションはないのではとささやかれていた。よもや試合が中断することになるなんて。イチロー自身が何よりも驚いたというように、ベンチからヤンキースの選手たちが出てきて祝福した。観客もスタンディングオベーションで偉大な記録を称えた。まさに台本なし、自然発生的なサプライズにイチローの心も熱くなったのだろう。
今回の取材ではセンターから600㍉とリモコンの400㍉で撮影した。号外も発行するとあって、プレー再開後直ちに送信処理も開始した。情けないがこういう時は何歳になってもテンパッてしまう。一瞬川崎のことを忘れそうになったが、ギリギリのところで気が付き、何とか2人のからみを撮影することができた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 川出 剛(かわで たかし)
(2013年7月31日撮影 8月2日付4面掲載)
<取材者の弁>
スポーツの取材をしていると思いもよらない場面に遭遇するときがある。それが「これは見事な逆立ち!」と言いたくなる様なこの場面。
5回、日本ハム・大野が放った打球がセンターへ飛んだ。普通ならセンターフライになりそうな打球がマリン球場独特の風に押し戻され、ロッテ2塁手・早坂のグラブの中へ。ところがキャッチの瞬間、捕球しようとしていたセンター・伊志嶺と早坂が交錯、スライディングした伊志嶺が早坂の足を払うような形となり、空中をポーンと2メートル程飛んだ早坂は三点倒立のような形で着地した。
その後、首を痛めても仕方のない状況となった早坂は苦悶の表情を浮かべ心配されたが、幸いなことに大事には至らず。なかなかお目にかかれない“大技”にスタンドのファンも大喜びだったのだが、画像を確認した私を含め、他社のカメラマンたちも思わずニンマリだった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 山本 壮一郎(やまもと そういちろう)
(2013年6月20日撮影、22日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
朝日新聞の記者がチェルノブイリ4号機の「石棺」内に入り、紙面に掲載したのは、1990年以来のはずだ。当時、放射線測定器は毎時30マイクロシーベルト。今回は7マイクロシーベルトだった。
4号機制御室へ続く通路は、ぞうきんがけされた後のように湿っていた。取材が入ることで、直前に「除染」をしてくれていたのかもしれない。事前の打ち合わせなどで、制御室内は照明がなく「真っ暗」で、計器類も取り外されていると聞いていた。「石棺」の中の制御室に入っても、暗いだけで制御室だったことを思わせる雰囲気が残っているのか不明で、放射線量よりも「チェルノブイリ原発の内部」だという写真が撮影できるのかが大きな不安であった。照明に関しては、動画撮影も予定したいたこともあり、ヘッドランプを準備して持って行くことにした。
原発職員の先導に従って4号機へ向かう。チェルノブイリ原発のタービン建屋は1~4号機まで一続きになっており、1号機側から入っていった。1~3号機までは、表示や扉などで通過して行くのを確認できた。チェックポイントが設けられており、そこを過ぎればいよいよ4号機だ。正直、どこからが「石棺」内部なのかわからないまま、職員について通路を歩いていた。職員が扉を開けると、そこがもう制御室だった。本当にほぼ真っ暗だった。
被曝線量の上限に達しないよう、時間は限られていた。壁や床に放射性物質が付着しているため、触れないよう細心の注意が求められた。事前の話の通り、計器類は取り外されていたものの、制御室だった原型はそのまま残っていた。
ヘッドランプをつけた同行記者や通訳に立ってもらい、ライティングした。1986年、史上最悪の原発事故を起こしたチェルノブイリ原発4号機。その制御室は、暗闇の中に死骸のように朽ち果て、残されていた。室内にいた時間は8分。
建物を出ると、4号機を覆う「石棺」は老朽化し、新たなドーム型のシェルターが建設中だった。27年前に爆発事故を起こした原子炉に、溶けた燃料はそのまま残っている。「燃料を取り出すまでに100年かかるかも」と技術担当副技師長は話した。事故を起こした原発の廃炉には、気の遠くなるほどの時間がかかる。それは、福島第一原発にも当てはまるのだろう、と実感した。
【写真説明】
「石棺」内にあるチェルノブイリ原発4号機の制御室。左奥上の丸い部分は原子炉の状態を示すパネルの跡。モニターのガラスなどが割れたままになっている=ウクライナ
--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞社写真部 繁田 統央(しげた のりひろ)
(2013年7月22日撮影、22日付夕刊社会面掲載)
<取材者の弁>
JR京浜東北線・南浦和駅のホームで午前9時15分過ぎ、「人がホームと電車の間に挟まれています」とアナウンスが流れた。私は、子供たちに写真の撮り方を教える出前授業のため、埼玉県蕨市の公民館へ向かう途中だった。
ホームに出て、駅員が集まっているところに行くと、30歳代ぐらいの女性がホームと電車の間に挟まれている。駅員が4、5人がかりで、女性を引き上げようとしているが、車体が重いためか、なかなかうまくいかない。女性は上半身をホームに横たえて、ぐったりしていた。
その直後、アナウンスを耳にした乗客から「軽くするために降りましょう」と声が上がり、みんなが続々とホームに降り始めた。駅員が懸命に車体を押す姿を見て、乗客も作業に加わる。ほどなくして車体が大きく傾き、女性が救出された。ホームは「出たー」という歓声と、大きな拍手に包まれた。女性は意識もあり、病院に運ばれたが、目立ったけがもなかったという。
乗客の善意に、私の胸にも温かい思いがあふれた。駅のアナウンスから救出まで5分足らずだろうか。新聞社のカメラマンといえども、決定的なシーンに立ち会えることはあまりない。私がiPhoneで撮影した写真は紙面で大きな扱いになったが、何よりもこの素晴らしいシーンを記録できたことがうれしかった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

時事通信仙台支社編集部 田口 元也(たぐち もとや)
(2013年7月3日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
紆余曲折を経て「奇跡の一本松」が帰ってきた。少しばかり残念な見た目になった気もするが、被災建物の解体が進み、更地が広がる街の中では、ひときわ目立つシンボルとなった。
「枯死した松に多額のお金をつぎ込むより、他に使い道があるはず」「つらい記憶を呼び起こす松を見たくない人もいる」など批判的な意見があるものの、見物にきた地元の主婦は「街はボロボロになったけど、松を見て故郷の記憶がよみがえってきた」と笑顔を見せていた。
広島の原爆ドームも、被災当初は存廃の議論がわき起こったという。複雑な被災地事情を抱えた一本松がどんな存在になっていくか、これからも注目していきたい。
完成式典では、地元の保育園児たちがくす玉を割り、盛大な拍手に包まれた。いささか派手すぎる演出との印象もあったが、未来に向けた前向きなシーンが垣間見えたことは何よりだ。
--------------------------------------------------------------------------------------------

スポーツニッポン新聞社写真部 荻原 浩人(おぎわら ひろと)
(2013年6月25日撮影、同日スポニチ・アネックスに掲載)
<取材者の弁>
6月25日のヤクルト・DeNA戦の試合前、ユニークなキャラクター同士の始球式が行われた。スワローズの球団マスコットの「つば九郎」と西国分寺出身のゆるキャラ「にしこくん」。「くまもん」ら昨今のゆるキャラブームの中でも「にしこくん」は大人気で2011年のゆるきゃらグランプリで堂々3位に入った実績を持つ。打席では満足にバットを振れず、つば九郎に怒られっぱなしだったが、この写真は「にしこくん」が一塁に走るところだ。人気キャラクターの登場に球場は大いに沸いた一コマだった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 前田 利宏(まえだ としひろ)
(2013年6月8日撮影、同11日付紙面にて掲載)
<取材者の弁>
2013年6月8日、大人数女性アイドルグループAKB48の32ndシングル選抜総選挙が横浜の日産スタジアムで行われた。
AKBの取材と野球の取材は似ている。まず使うレンズが長い、通常の芸能ものだとワイド(24~70mm)、ズーム(70~200mm)で事足りるのだが、今回は600mmで取材。また、記者とも事前に「今日の狙いはだれ?」といった様な野球的打ち合わせが必要となってくる。通常の芸能ものならば聞かなくともそのイベント自体の主題が決まっている事が多いのだが、AKBはそうではない。とりあえず大人数なので野球選手と同じような感覚にとらわれるのだ。
もちろん記者が持っているネタによって写真を撮るテーマも変わる。その日好投した三浦大輔が必ずしも原稿になる訳ではない、記者によってはベンチのラミレスの写真を要求される事もある。時には誰かと誰かがからんでいる、中畑清監督とトニ・ブランコが同じワンフレームに収まっている様な写真が要求される事もネタによってはある。
今回の選挙では1位が発表された瞬間を逃さず、ドラフトで1位クジを引いた球団と同じようなテンションで撮影しなくてはならない。とりあえず2位まで発表されて、壇上に残っためぼしい選手は大島優子と指原莉乃の二人。特にどちら推しでもないのだが、とりあえず昨年1位だった大島選手がメインテーマだろうとふみ、指原選手も入れ込んだフレーミングで大島選手スタートという感じでピントを置いておいた。
2位が発表された瞬間に、多分1位であろう大島選手のガッツポーズを狙うのが撮影意図である。野球でもままある状況なのだが、サヨナラホームランの時に誰にピントを置くか、誰からスタートして写真を撮るかが結構悩みどころであり、その瞬間が必要とされるので経験に基づいた“読み”が必要とされるところなのだ。という事で順位の発表は7万人の雄たけびと共に、徳光和夫アナウンサーの司会で続いた。
「第2位、AKB48チームK、13万6503票、大島優子!」。そして次の瞬間、顔をおさえる大島優子、なんだがピントのあってない画面奥の指原莉乃も顔をおさえている、そう1位は指原選手、自分の見事な“読み”は普通に外れた。信じられないといった感じで笑顔がこぼれる大島選手から、大慌てで指原選手にピントを送って撮ったのがこの写真なのだ。
AKBと野球取材は似ているのだが、瞬時にボールや選手が目まぐるしく動くスポーツでない分、決定的瞬間のタイムラグが結構ある。今回はそのおかげで事なきを得た一枚となった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 伊藤 智昭(いとう ともあき)
(2013年5月23日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
「あと10分ぐらいで山頂です」。
まだ30分はかかると考えていた登頂時間がかなり早まるという支援隊員の無線連絡を聞き、エベレスト稜線を歩く三浦雄一郎隊の写真を送信していた私はかなり動揺した。
軽いからという理由で持ってきた三脚の雲台はあまりに貧弱で倍テレを4枚つけた500ミリf4レンズをきちんと支えることができなかった。岩の上にレンズを載せ、カメラ本体に取り付けた三脚の脚の長さを調整してレンズの向きを変えるという情けない状況。エベレスト南峰付近に合わせてあったレンズを再び山頂に戻すのには手間がかかる。数ミリ単位で3本の脚を微調整し山頂を狙うも、暗いファインダー内に現れるのは黒い岩場かぼんやりした空。
「もしかして登頂の瞬間、撮り落としちゃうの?」。三浦さんが挑戦したエベレストとは比較にならないが、撮影場所の標高5545mでも酸素濃度は平地の約半分。焦ると酸欠で顔や手足がピリピリ痺れてくる。激しい呼吸を繰り返し10分近くかかってやっと捉えたエベレスト山頂に三浦隊の姿はまだ見えない。無線連絡ほどには登頂が早まらずラッキーだった。
午前9時ちょうど、山頂でストロボのような光が何度もきらめく。やがて赤いジャケット着た三浦雄一郎さんと見られる人物が山の陰から現れ、ゆっくりと最も高い頂に立った。無線で流れる喜びの声を聞きながら、80歳で世界最高峰に立った三浦さんの快挙に心から拍手を送った。
--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 播磨 宏子(はりま ひろこ)
(2013年4月17日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
27年ぶりに来日したアウン・サン・スー・チーさん。民主化に舵を切った新生ミャンマーへの関心の深さと期待の高まりから、行く先々にメディアが押し寄せた。写真は、日本記者クラブの記者会見場を拍手で迎えられるスー・チーさん。鮮やかな黄色の民族衣装を身にまとい、やわらかな表情でゆっくりと歩いて行く姿が印象的だった。
会場後方にはカメラがずらりと並び、「どんな質問にも正直にお答えします」を口切りに約2時間に及んだ記者会見、何1つ見逃すものかと彼女の一挙手一動に注目するカメラマンたちのシャッターの音が鳴り響いていた。
この日はミャンマー暦の新年にあたる特別な日。「ハッピー・ニュー・イヤー」――会見最後にスー・チーさんがこぼした笑顔に、まもなく訪れる新しい季節を感じた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞東京本社事業管理部(写真担当) 奥西 義和(おくにし よしかず)
(2013年5月5日撮影、同6日付朝刊社会面掲載)
<取材者の弁>
「四番サード、長嶋茂雄、背番号3」。始球式のアナウンスに鳥肌が立った。「ミスタープロ野球」が、グラウンドに帰ってきた。投手・松井、捕手・原監督、そして球審が安倍首相という豪華メンバー。外野スタンドに一礼する松井の後方に見えるミスターは片手でバットを構え、打つ気満々。もしピッチャー返しでセンターに抜けたら、すぐにミスターから松井にピントを合わせなければ・・・。予想される様々なシーンが脳裏に浮かんだ。松井が投げた山なりのボールは、デッドボールかと思うような内角高め。それでも、「燃える男」はよけずに打ちにいった。バットは空を切ったが、そのスイングは満員の観客の心を芯で捉えた。
巨人担当だった20年前、スポーツ紙の先輩記者から「写真は場所だよ」と教えられた。その言葉を思い出し、右打者と右投手がバランスよく収まる場所を探した。リハーサルではバックスクリーンからも狙ってみたが、いまひとつ構図が決まらない。通路は撮影禁止、客席は満員。それではと、中継テレビ局の後方で撮れないか頼んでみた。許可を得て当日行ってみると、もう1台TVカメラがスタンバイしていた。予定より後方になってしまったが、レンズ1本入れば何とかなると腹をくくった。
セレモニーが終わり、ファンの大歓声の中、手を振って球場を後にする「背番号3」。そして、控えめに三歩下がって「背番号55」が続く。最高の師弟だ。いつかミスターが両手でフルスイングできるようになった時、もう一度、その勇姿をファインダーに収めてみたい。その日が一日も早く訪れることを心待ちにしている。
--------------------------------------------------------------------------------------------

毎日新聞モスクワ支局 大前 仁(おおまえ ひとし)
(2013年4月11日撮影、同26日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
チェルノブイリ原発を訪れたのは1年ぶり。1986年の事故で爆発を起こした4号機から数百メートルの地点では、「新たな光景」が広がっていた。高さ150メートルぐらいの矢倉が建ち並び、その横でサッカー競技場のようなアーチ状の建物が作られている。事故直後にコンクリートで覆った4号機で腐食や老朽化が進んでいることから、新たに覆うシェルターだ。完成予定は2015年。完工後にスライドさせて、4号機をすっぽり収める計画である。
現場では資材を運ぶ車や作業員が行き交い、活気が伝わってきた。事故発生から27年。付近の放射線量は自然界が発する12倍超を記録しているが、多くの作業員や原子力事業体の職員はマスクも付けずに歩いている。昼寝をしている猫に声をかける職員もいた。訪問客にとっては非日常の光景だが、作業員や職員にとっては日々の光景のようだ。
ガイドの職員に付き添われて、新シェルターと4号機を一望できる建物の屋上へ。高い地点から眺めると、敷地内に建設用の資材や機器が整然と並ぶ光景を確認できた。原発の関係者は「作業が急ピッチで進んでいる」と強調する。それでも気になる光景も目にした。敷地内の別の箇所を眺めると、さびた機器や資材が山積みになっていた。新シェルターの建設が進む一方で、瓦礫の行き場はあるのだろうか? ポケットに入れていた線量計は、ピーという音を鳴らしていた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 岩本 旭人(いわもと あきと)
(2013年3月4日撮影、8日朝刊掲載)
<取材者の弁>
「立ち上がろうと頑張っている被災地の姿です」。福島県立いわき総合高校の生徒たちは壁に描かれた桜を見上げて笑っていた。東日本大震災から2年となるのを前に、福島県の今を取材した。テーマを特に決めることはなかったが〝復興への兆し〟のような写真を撮りたかった。
いわき総合高で、被災して取り壊される校舎に生徒が桜の絵を描いたという話しを聞き、足を向けた。教頭に案内され、初めて見た桜は、今にも壁から花びらが舞い踊るように満開だった。制作に携わった生徒3人が取材に応じてくれた。桜への思いを聞くと、冒頭の言葉が3人の口から真っ先にあふれ出た。
その言葉に一人胸を打たれていると、3人は桜の下で新学期への思いを語り始めた。その姿を正面から撮った。あの日からもう2年、まだ2年。いまだ思うように進まない福島の厳しい地で花を咲かせた生徒たちのたくましさに確かな〝復興への兆し〟を感じた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 仙波 理(せんば さとる)
2013年3月19日撮影、20日朝刊国際面掲載
<取材者の弁>
イラク戦争開戦から10年。3月20日の「開戦の日」を翌日に控えた19日には、バグダッド市内で計27件もの連続爆弾事件が相次ぎ、約50人が死亡した。市内に宿泊していた自分の耳でも、この日は朝から、重低音の爆発音が何度も確認できた。写真の現場は市中心部に近い市場の一角。焦げた路上の付近にはアメのように曲がった自動車が残っており、付近の建物の窓ガラスは爆風や衝撃により、ほとんどが飛散していた。ここではまず午前8時ごろに最初の自動車爆弾が爆発。その約20分後に2発目が炸裂し、少なくとも4人が死亡、20人が負傷した。1発目の爆発後、被害者の救助などに集まった人たちを再び殺傷する狙いで2発目を爆発させる手口は陰湿極まりない。
戦時下を取材した一人として、10年後の現地はどうしても見たかった。しかしながら、決して短くない時を経て訪れた街では、至る所に分厚いコンクリート壁が並べられ、撤退によって米兵の姿こそないものの、壁の間隙を自動小銃や機関銃で武装した軍隊や警察が警戒をしている。現地スタッフによれば、「壁」はテロに対する防御のほか、サダム・フセイン体制崩壊後顕著となったイスラム教シーア派とスンニ派の対立を隔てる役割もあるという。まさに「剣と楯」による治安維持の様相だ。
その一方、忘れられない言葉がある。南部サマワから陸路バグダッド入りした14日、市内の劇場で政治を風刺したコメディの舞台があるというので着いたその足で向かった。暗に政治を批判することは独裁体制下では想像もできなかった光景だ。しかもこの日は、やはり市内の司法省に武装勢力が突入して自爆するなどし、およそ80人が死傷するテロ事件があったばかりだった。ところが会場はほぼ満席。午後8時の開演から深夜にまで及ぶステージに、観客たちは途中退席することもなく、絶えず笑い声と喝采を送り続けていた。
いつ自分が巻き添えになるかも知れないテロの「恐怖」と舞台に贈る「笑い」。この違和感を観客のイラク人男性の一人に質問してみた。「そう。これが今のバグダッドさ」。彼は続けた。「いつか自分が被害者になるかもしれないからって、萎縮してなんかいられない。身を守るために閉じこもるだけなら、それこそテロに屈したことにならないかい?」。ひょっとしたら死に至るかも知れない恐怖を感じながら、それでも今を精いっぱい生きることを選ぶ。イラクの人たちの強さが込められていた。
本当の平和がいつこの国に訪れるかはわからない。ただ、逆境に負けじと生活する人たちの姿をこれからも見続けていきたいと思う。
--------------------------------------------------------------------------------------------

日本経済新聞社写真部 寺澤 将幸(てらざわ まさゆき)
(2013年2月14日撮影、15日付け日経産業新聞デジタル・エンターテインメント面掲載)
<取材者の弁>
4月に再開場する歌舞伎座で2月14日、夜間ライトアップの試験点灯が行われた。約150台のライトが設置され、全体がきれいに彩られていたが、中でも背後のオフィス棟から照らされた瓦屋根が際立っていた。
しかし、建物の美しさに気を取られている余裕はない。集まった報道陣はざっと見て50人以上。撮影時間は制限され公道の片隅に列を作って順番に撮影していく。明るさや色が小刻みに変化する照明にカメラマンたちは悪戦苦闘。その姿を尻目に、着物姿の女性が悠々とスマートフォンでパシャ、パシャ…。気楽な様子がうらやましかった。
最近は仕事で「iPhoneで撮る」こともあるが、そんな気楽さはない。カメラを持つとつい神経をとがらせてしまう。性格のせいか、それとも職業病か。
--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社ビジュアル報道局企画委員 原田 浩司(はらだ こうじ)
(2013年3月11日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
「俺も、福島も未来が見えない」。松村直登さんは言う。福島第1原発事故直後から自宅のある富岡町に戻り、同町が警戒区域に指定され全住民が避難した後も留まり続けている。日々、動物保護の活動ばかりでなく、被災者たちの留守宅の見回りも行う。
東日本大震災の取材で、東北一帯を見てきた。不謹慎な表現かもしれないが、福島県の悲惨さは格別だと感じる。今もなお放射能を放出し続ける原発のせいで、復興はおろか、瓦礫の片付けさえ進んでいない。区域内には、崩壊した家屋、流された車両や船の残骸が残されたままだ。
3.11を前に、松村さんと語り合った。何度も、一緒に警戒区域内を見てきた。ローソクの灯りの下、支援者から送られてきた日本酒が進む。「ここで生きることが闘い」という気丈な男だが、こぼすこともある。区域内で牛の殺処分に出くわし、「殺さないでくれ。俺が世話する」と保護したものの、人手も資金も足りない状況は続く。やはり、東京電力への批判が繰り返される。ましてや、富岡町にある福島第2原発再稼働の兆候もみられる。原発事故が発生して、彼はすぐに単身で東京電力本社に抗議に向かったこともある行動派だ。いつしか「(原発に)石でも投げてやっぺ」ということになった。3.11は鎮魂の日。だが、静かに黙祷する被災者ばかりでなく、怒りを表明する被災者がいても良いではないか、と思った。
動物愛護家から「ダチョウの生死を確認して欲しい」という要請があった。ダチョウ園は、福島第1原発と同じ大熊町内にある。同町に向かっているうちに、原発に寄ることになった。途中、何度もパトカーの集団とすれ違った。3.11の警戒区域内には、警察車両が目立った。なおも海岸付近を進むと、福島第1原発が目前に見えた。距離にして約1km少々。原発から遠く離れていても毎時数十マイクロSVの場所もあるのに、意外にも毎時1.5マイクロSVだ。「富岡町より低い」と、松村さんが怒ったようにつぶやいた。そして、無言で石を2度投げた。私も投げた。原発に届くはずもなく、それは手前の海に落ちた。まるで、巨大な力を前にした、ちっぽけな人間の力のようでもあった。夕暮れ時が近かった。我々に冷たい風が吹きつけてきた。しばらく、原発を見つめた。よく見れば、原発も津波に遭った2年前の姿のままだった。
デジタルカメラのモニターを確認すると、力強い後ろ姿が映っていた。それでいて、何か明るいものを感じさせる後ろ姿だ。たった一人で、この2年間、警戒区域で運命と闘ってきた男の背中、その向こうに巨大な福島第1原発の威容もあった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 山本 壮一郎(やまもと そういちろう)
(2013年2月20日撮影、21日朝刊2面掲載)
<取材者の弁>
科学医療担当の編集委員から、東京電力福島第一原発への単独取材が決まったと写真部に連絡があった。部長に呼ばれ、意思確認を受けた後、準備に取りかかった。
私は暗室時代の最後を経験し、デジタルカメラの進歩とともに仕事をしてきた40代のカメラマン。まさか、カメラだけでなく新聞そのものが「紙」と「スチール」から、「ウェッブ」と「動画」へと急展開していくとは思ってもいなかった世代だと思う。
防護服に身を包んでマスクをかぶり、養生したカメラを手にする。写真を撮るだけでも一苦労のうえに、パノラマ写真に360度VRパノラマ、さらには動画素材も用意せねばならない。制限された環境と時間の中であれもこれもできるのか不安のまま、取材当日を迎えた。
免震重要棟から4号機へ向かう。事故後に建屋外側に据え付けられたエレベーターで5階のオペレーティングフロアへ上がった。昨年5月に代表撮影された写真と同アングルで変化を見せようと考えていた。だが、散乱していたがれきは完全に撤去され、「展望台」のようになっており、鉄骨がぐにゃりと曲がる3号機、その奥に2号機が見通せる。比較するものがないほど変わっていた。頭が真っ白なまま、写真とパノラマ、三脚を据えてVRと撮り分ける。動画までは手が回らず、編集委員のヘルメットに固定して撮影した。
これまで、バスの中から外観を見るだけであったという、セシウム吸着装置「サリー」や汚染水などを淡水化する施設の内部が報道機関に初めて公開された。巡視の検査官が施設内の放射線量を確認した後、中に入る。薄暗い「サリー」内部に円筒形のセシウム吸着塔が並ぶ。撮影しながら検査官について進むと、「放射線量が高いから、検査官の他はさがって下さい」と制止された。
取材を終えてJビレッジに戻ると関係者が交わす雑談が耳に入った。「東京」と「福島」との職場内での温度差を嘆く内容だった。事故からまだ2年。津波で横転したまま放置された車両や爆発で飛び散ったがれき、増え続ける汚染水タンク。廃炉への道ははるか彼方だと、映像で伝えられるものが有りすぎる。
--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞東京本社写真部 松本 剛(まつもと つよし)
(2013年1月31日撮影、2月1日付け朝刊一面掲載)
<取材者の弁>
辺り一面には、鼻の粘膜を刺激するような腐臭が立ちこめる。
テロリストの攻撃を受けた北アフリカ・アルジェリア東部イナメナスの従業員居住区。砲撃の跡が生々しい建物が目に飛び込んできた。地面には犠牲者が倒れていたのだろうか、無数の染みが残る。軍の装甲車が配備され、銃を手にした多数の兵士がはるかな地平線をにらみつけていた。
サハラ砂漠のただ中に立つガス田プラント。日本の企業戦士10人を始め多数の命が奪われた現場には、緊張した空気が張りつめていた。
私が報道規制下にあるイナメナス入りの機会を待っていたのは、1000㌔・㍍以上離れた首都アルジェ。道行く人たちが、日本人と見ると「あなたがたは私たちの友人。今回の事件は本当に残念だった。犠牲者のご家族を始め、日本の皆さんに心の底からのお悔やみを伝えて欲しい」などと、事件を悔やむ声をかけてきた。が、90年代に多発したテロによって、多くの肉親や友人を失った人たちからは、自国軍の作戦への支持が強い。市内の通りの辻々には常に警察官が立ち、往来する車両に厳しい監視の目を向けている。
「あの凄惨な時代に後戻りはしたくない」。平和な日本に暮らす私には理解しがたいアルジェリア人たちのその思いは、現場に放置される黒こげの車両の残骸を目撃した私の心の中にも、確かに芽生えた感触があった。
この現実を伝えなければと、我を忘れてカメラのシャッターを切った。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 久野 功(くの いさお)
(2013年1月14日撮影、未掲載)
<取材者の弁>
2013年1月14日の成人式。天気予報は、雨のち雪だが都心では積もることはないと言っていた。午前10頃から雨に雪がまじりはじめた。細かい雪は背景が白っぽいとはっきり写らないので、あれこれと場所を変え会場入りする新成人と雪を狙う。何とか安心の一枚を撮り終え、式典会場に入る。
濡れた機材をタオルでふきつつ、会場内ではしゃぐ新成人を見ながら「若いっていいなぁ」とぼんやり考えつつ態勢を整える。40分ほどたって外の様子を見に行くと唖然。辺りはすっかり真っ白になっていて、大粒のぼたん雪がなおも降り続いている。積もらないって言っていたのに…。
式典が終わり、新成人がぞろぞろと出てくる。安心の一枚がゴミになってしまったので、必死に撮影。成人式の取材経験のある写真部員なら誰もが覚えがあるだろうが、男子の存在は申し訳ないけど完全に刺身のツマ。望遠レンズで引っ張って雪と振り袖姿を撮影したいのだが、ツマが邪魔でなかなかはまらない。式典前の撮影ですでに機材が濡れていたこともあり、レンズやファインダーがいくら拭いてもすぐにくもってしまう。寒さと今にも止まりそうなカメラ機材と格闘しながらの撮影。
「あー、もう、さいあく-!」と声をあげながら、振り袖の裾をまくり、シャーベット状態になった雪道を歩く新成人。ゴアテックスのブーツが全然役に立たなかったくらいだから、足袋の足下はさぞ冷たかっただろうと想像する。大変な日にあたってしまった平成25年度の新成人たちだが、きっと良きにつけ悪きにつけ記憶に刻み込まれる成人の日となったことでしょう。
--------------------------------------------------------------------------------------------

日本経済新聞社写真部 小林 健(こばやし けん)
(2012年12月4日撮影、13年元旦紙面別刷りフロントに掲載)
<取材者の弁>
「光学迷彩を使え」。被疑者の自宅に忍び込んだ特殊部隊の女性隊長が部下達に指示すると、部下達の姿がすっと消える。10年ほど前、人気を博した近未来SF漫画「攻殻機動隊」のワンシーンだ。「光学迷彩」とは、目の錯覚を応用した技術による「超現実」の世界のこと。自衛隊などが着る迷彩服やカメレオンと同じように、周囲の風景と溶け込むことにより、違う現実を見せることができる。
慶応義塾大学大学院の稲見昌彦教授は、この技術の実証実験として、車の後ろに設置したカメラでとらえた映像が車内に映って見えることで、後部座席のシートが透けて車の後ろが見える「透明プリウス」を開発した。
映像は運転席と助手席の間にあるプロジェクターから半透明の鏡を使って投射する。映像がよく見えるよう後部座席には光を反射する素材を使った。運転手は鏡越しに後ろの映像を見るため、車の窓の風景とつながって見えるわけだ。この技術が確立すれば、楽々と車庫入れができるという。
しかし、まだこの技術は、あくまで研究開発途中のもの。実際はそれほどクリアな映像ではない。プロジェクターから投射された映像は薄ぼんやりしており、反射角の関係で、数センチ横にずれるだけで、車の後部はおろか、何も見えなくなる。撮影に同行してくれた研究員とミリ単位で場所を調整した。更に車内と車外とプロジェクターの露出差の開きが大きく、ストロボセッティングがやたらと面倒くさい。一番の苦労は、撮影する場所がないことだ。何度か試したのち、バックミラーとフロントガラスの隙間にカメラだけを入れて、ノーファインダーで撮影した。
稲見教授はこれ以外も、同じ技術で「透明マント」なるものも実験している。読んで字のごとく、特殊素材のマントをかぶると周囲の背景に完全に溶け込むという技術だ。これさえあれば、規制線をくぐり抜けて事件や事故現場に入り、スクープ写真も楽々と撮影できるかもしれないなあと取材帰りにぼんやり考えた。実用化を待ちたい。
--------------------------------------------------------------------------------------------

毎日新聞東京本社写真部 須賀川 理(すかがわ おさむ)
(2012年12月31日撮影、2013年元旦朝刊1面に掲載)
<取材者の弁>
「母ちゃんも娘と孫とじきけえってくっから、こっちで休んでて」。玄関を開けた私たちを小野俊光さんは笑顔でこたつに招き入れた。小雪舞う大晦日 の夕方、福島県川内村の避難指示解除準備区域にある小野さん宅を取材した。
この年末年始、「せめて正月くらいは自宅で」という声に押され政府は6市町村の避難指示解除準備区域、居住制限区域で最大5泊の宿泊を特例で認 めた。小野さんが現在住んでいる村内の仮設住宅から自宅まではわずか3キロ。それでもこれまで自宅に寝泊まりすることは許されていない。俊光 さんは「やっぱりあったけえ」という我が家でいつも通りの正月を迎えることにしていた。
やがて妻の悦子さん、次女の平野久美さん、孫の智大君が出先から戻り、にぎやかな宴が始まった。智大君の好物というカニが石油ストーブの上で芳 ばしい香りを放つ。悦子さんが焼きあがったカニを皿に盛りながら今年、夫婦が金婚式を迎えると教えてくれた。「どちら かが欠けて祝えないのが当たり前の世の中だから、2人で迎えられる金婚式は格別」と言う俊光さんに、「本当はそう思っていないでしょう?」と 悦子さんが照れくさそうに応戦。食卓はさらに笑いに包まれた。2年ぶりに自宅で正月を迎える喜びが4人の顔からあふれていた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社編集局ニュースセンター 冨田 晴海(とみた はるみ)
(2012年12月15日撮影、未配信)
<取材者の弁>
「2012年 報道写真展」が衆院選の投開票日を翌日に控えた15日、日本橋三越本店で始まった。東日本大震災から1年以上を経た被災地の表情、5月に開業した東京スカイツリー、7月から8月にかけて行われたロンドン五輪など、国内外のニュース写真約250点を展示。オープニングセレモニーでは、五輪で金メダルを獲得したボクシングの村田諒太選手とレスリングの小原日登美選手がテープカットした。
2人は式典後に自らのパネルにサインしたあと、スポーツ紙デスクの無理なポージングにも笑顔で答え、和やかな雰囲気で報道展のスタートが切れた。私も村田選手の金メダルを手にしてみて「意外に重いもの」なんだと感じた。その後も気さくな2人は、パネルの前で各紙の写真部長たちとの記念写真にも快く応じていた。金メダルを手に2人と記念写真に収まる部長たちの表情が、子どものように見えたのは私だけではなかったのでは・・・
今年はオープンと同時に高円宮妃久子さまが早速観賞に訪れたが、18日未明には新しい政権の枠組みが固まり、26日には組閣が予定されている。期間中に次期首相が来場するのは難しい状況だ。19日までには新政権誕生のパネルを追加せねばならず、忙しい報道展になりそうだ。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 納冨 康(のうとみ こう)
(2012年11月25日撮影、27日付1面掲載)
<取材者の弁>
私だけかもしれないが、競馬取材のカメラマンがレース取材で最も神経を使い緊張する撮影ポジションはゴール正面(直線の先)の場所ではないだろうか。
600ミリなどの望遠レンズを使用し、十数頭が並んで勢いよくこちらに向かって来るのを狙うと望遠レンズの圧縮効果もあり、一体どの馬が1着でゴールするのか何度撮っても感覚が掴めず会場の巨大スクリーンを横目で確認しながらハラハラする撮影は未だに慣れない。
1着の馬のゴールと騎手のガッツポーズを逃さずうまく撮影できればと思って臨んだジャパンカップ。注目は3冠牝馬ジェンティルドンナ、現日本最強馬と呼ばれるオルフェーヴル、凱旋門賞優勝馬ソレミア、秋の天皇賞1着のエイシンフラッシュ・・・。どの馬が来てもおかしくない。以前から競馬担当キャップの先輩にジャパンカップは「正面(のポジション)でやらせて下さい!」と志願した手前、1着馬を簡単に撮り逃すことはできない。
600ミリのレンズを構え「オルフェが大外から差したらこの画角に入るだろうか?いやインから来るかも。ガッツポーズは出るか?やっぱりこの撮影ポジション辞めときゃ良かった」など色々頭の中で考えているうちにメインレースのゲートはいつの間にか開かれていた。
蓋を開ければ「この一枚」。最後の直線で3冠牝馬と最強馬の馬体を激突させながらのまさに肉弾戦。ファインダーを覗いてぶつかり合う2頭は確認できたが、ゴールを過ぎてもどちらの騎手もガッツポーズを出さない。デッドヒートをどちらが制したか正直分からなかった。
長時間の審議の末、ハナ差でジェンティルドンナ(写真右)が1着。無我夢中でシャッターを切った写真の中から見つけたジェンティルドンナ鞍上の岩田康誠騎手が隣のオルフェーヴル(写真左)と池添謙一騎手に向かって何か吠えてドヤ顔をしているかのようにも見えたこの一枚。勝者の岩田騎手は強引な進路変更で2日間の騎乗停止処分となり後味悪いレースとなったが、迫力のあるレースに立ち会い撮影することができ、正面のポジションも捨て難いなとスッキリした気分で私は仕事を終えた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 前田 利宏(まえだ としひろ)
(2012年11月24日撮影、九州スポーツ芸能面に掲載)
<取材者の弁>
2009年11月に覚醒剤取締法違反(使用、所持)の罪で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けた女優・酒井法子が執行猶予期間があけた11月24日に都内のスタジオで主演舞台の会見と芸能界復帰の会見を行った。
200人を超える報道陣、各社大勢のカメラマンが居並ぶ中で思うような写真を撮るのは々骨の折れる作業である。とりあえず場所取りが重要なポイントになるのだが、今回は会見現場に自宅の近い同僚の納冨カメラマンが3時間前位から先乗りし、スチールの中では2番という好順位をキープしてくれた。この好順位をいかし、納冨カメラマンは酒井法子の真正面で最初から最後まで涙と表情狙い、自分は会見場中をテレビカメラの邪魔にならないように姿勢を低くしながらいろいろな場所に動き回って写真を撮るという役割分担で臨んだのだった。
とりあえず復帰会見撮影のポイントは2つ、アップで撮影する流れ落ちる後悔の涙と、左指、左くるぶしにあったタトゥーの様子。ところが結論からいうと両方とも今回は無し、微妙な感じではあったものの流れ落ちる涙は見受けられず、むしろ会見全体では吹っ切れたような笑顔の方が印象的であった。タトゥーに関しても「いらないと思いました」というご本人の言葉通りきれいに消されてしまっていたのだった。事前のプランなどは儚いものである。
この写真は笑顔で会見場を一度引き上げる酒井法子、縦位置で撮るか横位地で撮るか直前まで考え、最終的には悩み続けたため若干斜めになり、綺麗な足が入っていないという芸能写真ではかなりダメな出来栄えに仕上がった。だがこの彼女の絶妙な笑顔に助けられた一枚となったようだ。当たり前の結論としては撮影前にプランを頭でいろいろと考えても、その場の被写体の持つパワーや表情の前にはかなわないのだなぁという事である。
--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 樫山 晃生 (かしやま てるお)
(2012年11月8日撮影、14日付朝刊3面)
<取材者の弁>
「江沢民さん、そろそろ権力を譲ってくださいよ」
「胡錦濤君、まだまだ渡すわけにはいかないよ」
第18回中国共産党大会の開幕式。そんな会話が聞こえてきそうなシーンだった。
党総書記のポストは習近平氏が引き継ぐことが決まっていたが、党常務委などの指導部人事をめぐって水面下の権力闘争が続いていた。高官の子弟グループ「太子党」の実力者が江沢民元総書記、共産主義青年団出身の「共青団」派を束ねていたのが胡錦濤前総書記だ。
実際は高齢の江沢民氏を胡錦濤氏がいたわって着席を促したのを、「大丈夫、大丈夫」と断っているところだが、周りの中国人カメラマンたちのシャッター音もひときわ大きくなっていた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞社写真部 立石 紀和(たていし のりかず)
(2012年11月7日撮影、8日付朝刊国際面)
<取材者の弁>
今回の大統領選挙は、現職で再選を目指すオバマ大統領と共和党のロムニー候補の史上まれに見る接戦だった。投開票日直前まで支持率は拮抗していたため、当日はどちらの会場に行くのか迷うほどだった。
私は投開票日の10日ほど前に米国入りし、激戦州のひとつオハイオで写真グラフの取材を始めた。ほとんど何の知識や情報もないまま出発してしまったため、取りあえず各候補者のボランティア事務所行って話を聞こうとしたが、激戦州ゆえに多忙を極めており、担当者に「日本の新聞に掲載されても1票にもならないから」と冷たくあしらわれた。スタッフが有権者に電話をかける様子の取材では、「とにかく忙しいから取材は1分だけ。今後は二度と来ないで」とまで言われた。悪意は無かったと信じるが、少なくともそれほど激戦だったと言える。
投開票日の勝利宣言の取材は、オバマ大統領の地元シカゴに決めた。激戦州の集計に時間がかかったため、途中経過で一喜一憂する支持者たちとオバマ大統領の登場を待ちわびた。そして深夜0時半過ぎ、「Four more years!」(あと4年)という大歓声の中、大統領はミシェル夫人と2人の娘と共に現れ、笑顔で手を振った。ファインダー越しに見えた大統領の表情は、激戦が終わってホッとしたと同時に、あと4年の重責をかみしめているように見えた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

時事通信社大阪写真部 桐明 靖之(きりあき やすゆき)
(2012年10月9日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
2012年のノーベル医学・生物学賞の受賞発表から一夜明けた10月9日、山中伸弥京大教授と知佳夫人の記者会見が同大学本部棟で行われた。受賞当初の興奮が一段落し、取材する報道各社も山中教授の人柄や家族に興味の焦点を移していた。
午前10時すぎに会見が始まり、夕刊帯の締め切り時間が迫っていた。会見の冒頭ですばやく写真を送っている他社カメラマンに焦りを覚えつつ、2人の間に流れる「歴史」や「時間」など、夫婦の関係性をフレームに収めることだけに集中した。じっと待ち構えていると、山中教授は受賞の喜びを語った後に研究所の同僚や関係各位にお礼を述べ始めた。次に語る内容は家族の話にちがいない。
その瞬間は直ぐに訪れた。カメラのファインダーの中で、知佳夫人や家族への感謝を語る彼の左奥には、少し照れながら旦那様の表情を見詰める妻の笑顔が浮かんでいた。狙い通りの写真を撮ったと確信し急いで写真電送した。
後日、本社写真部の上司から一言。「いい写真だと思うと同時に、君の感情がよくでているね」。自分の妻に対する思いに苦笑いしながら、あの瞬間の知佳夫人のやさしい眼差しを思い出していた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞社写真部 林 陽一 (はやし よういち)
(2012年11月3日撮影、4日付朝刊1面)
<取材者の弁>
日本シリーズの巨人対日本ハム。巨人が3勝2敗と王手とし、迎えた第6戦。札幌から本拠地へ戻った巨人の優勝を一目見ようと超満員に膨らんだ東京ドームは熱気にあふれていた。
試合展開は、3対0とリードしていた巨人がこのまま決めるかに思われた6回、日本ハム4番の中田がスリーランを放ち同点に追いついた。しかし、7回、今度は巨人の4番打者で主将・阿部が放った適時打でまた1点をリードした。そのまま9回表2死、あと一人で巨人が日本シリーズを制する。
最後の優勝の瞬間を逃すまいと1塁側ベンチの巨人が見えるレフト側取材席からレンズをのぞく。最後の打者が1塁でアウト。マウンドに向かう捕手・阿部が手を広げ、山口投手へ駆け寄る。ベンチから飛び出してきた内海投手らナインが次々と歓喜の渦に加わっていく。その渦がファンの声援とともに外野席まで伝わってきた。
阿部を中心に中継ぎや控えが活躍した巨人、来年も同じ光景の1枚をおさえたいと願う。
--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 金子 淳(かねこ じゅん)
(2012年11月1日撮影、2日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
11月1日は灯台記念日なのだそうだ。福島県相馬市にある名勝・松川浦の鵜ノ尾埼(うのおさき)灯台は東日本大震災の津波で送電線が切れ、消灯した。昨年4月、乾電池式の仮設灯火で弱めの明かりを発してきたが、このたび電源が復旧し、記念日のこの日に報道公開された。
福島の取材は取材班をつくり、各自がローミングで回している。約5カ月ぶりの福島入りだった。前回取材に入った6月、弱々しくも鵜ノ尾埼灯台に照らされる相馬漁港の「試験操業開始」に同行取材した。あの時、試験操業とはいえ、久しぶりの水揚げに相馬漁港は沸いていた。だが、今回この取材前に立ち寄った漁港は人影もなく、整地されたとはいえいまだ津波の傷痕がそのまま残っている。この「傷痕」と「灯台の光」を絡めて撮れないかと考えた。
遠くからのアングルをいろいろ探っていたが、暗くなるにはまだ早かった。灯台内部からのアングルも取材できると聞きつけ、ワイドレンズ1本で灯台に挑戦した。福島海上保安部が用意した取材用のヘルメットや手袋を装着し、テレビ、スチール各社交代で灯台の光源部分に登った。内部のはしご階段を登ると、すでに16万カンデラの光がぐるぐると回っている。同業他社カメラマンと交代で職員を絡め撮影。もう少し引いて撮りたいところだが、引きようがない。ストラップを右手に巻き付け、柵に足を絡めて固定し、上体を反らせて外にせり出し、頭の上にカメラをかざして撮影した。背後に相馬漁港が入り、また夕暮れ時も重なり、「想定外」の写真が撮れたのではないかと思う。その後、当初思い描いていた遠景の「傷痕と灯台の光」も粘って取材したが、紙面ではこの「想定外」の写真が採用され、よかったと思っている。
灯台に初めて登った。数十センチの間近で直視したものの、それほどのまぶしさは感じなかった。後で分かったことだが、この16万カンデラの光は32㎞先まで届くという。まさに「灯台もと暗し」とは、このことか……。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京中日スポーツ写真課 北村 彰(きたむら あきら)
(2012年10月7日撮影、8日付け東京中日スポーツ1面掲載)
<取材者の弁>
F1日本GPの公式予選を4番目のタイムで走り、J・バトンの5グリッド降格により決勝レースを3番グリッドでスタートすることになった小林可夢偉。日本人ドライバーが久しぶりに表彰台に上がるチャンスと期待が高まる中、決勝レースがスタートした。
決勝レースが終わりに近づき、未だ3番手を走行する可夢偉。いよいよ表彰台が現実味を帯びてきた時、「これは必ず一面になる!」と確信。F1初の表彰台をどういう絵柄で表現すべきか考えた。
「自動車レースの表彰台ならシャンパンファイトだ」。そう考え、バストアップくらいの大きさで表情を狙おうと、レース中にマシンの走りを撮影していた600ミリレンズをそのまま表彰台撮影に持って行った。
レースが無事終了し、可夢偉は3位を獲得。日本GPで日本人が表彰台に上がるとこんなにも観客が盛り上がるのか!と感動する空間を体験しながら、始まったシャンパンファイト。いつもは無表情な可夢偉も穏やかな晴れやかな表情でシャンパンを掛け合っていた。
日本人が表彰台に上がるという希有な場面に遭遇してカメラマン控え室に戻り送稿していると、鈴鹿サーキットの広報スタッフたちが写真を見て、「いい表情している!」、「こんな表情見たことない!」と口々に言っていた。日本人表彰台ということだけでなく、可夢偉の表情も希有な場面だったようだ。
--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 桑名 敏之(くわな としゆき)
(2012年9月25日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
機上から眼前に一直線に魚釣島を目指す船団。まるで太平洋戦争の記録映像を見ているようだった。島に接近する台湾漁船に海保の巡視船が後進しながら放水をする。これ以上の領海侵犯を許さないという海保の強い意志を感じた。漁船団の中には台湾企業の名前が書かれた横断幕に船上には報道と思わしき人びとの姿も。直に見た尖閣諸島周辺は日中台の各国の思惑が交錯する、まさに“戦場”のようだった
--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 上田 潤(うえだ じゅん)
(2012年9月19日撮影 同日朝日新聞デジタルに掲載)
<取材者の弁>
19日夕方、東京都心で大きな虹が見られた。本社がある中央区付近は午後から時折雨が降ったが、日没間際、雲の切れ間から夕日が顔を出すと、照らされた東の空に、大きな橋がかけられたように虹が現れた。
何げなく職場の同僚と虹を眺めていると、「おい、カメラ!」とデスクの声。
慌ててカメラを手にテラスに出ると、同じフロアの報道局の記者も続々と出てきた。鮮やかな夕焼けと虹の競演に、記者らは歓声を上げながら携帯電話をかざしている。
すると彼らの中から時折、「全部が入らない」と言う声を聞こえた。広角がきかない携帯カメラでは、大きな弧を描く虹が画角に収まらないらしい。「記者なのに一眼レフカメラは持っていないのか?」と、余計な猜疑心を抱いてしまったが、当初は手ぶらで眺めていた私に、そう思う資格はなさそうだ。
--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 堀 英治(ほり えいじ)
(2012年7月23日撮影、24日朝刊一面掲載)
<取材者の弁>
東日本大震災から9月11日で1年半がたつ。東京電力福島第一原発事故で全町避難している福島県浪江町の馬場有町長は10日の定例議会で、「今後5年間は街に戻れない。生活できない状態だ」と述べた。苦痛を与え続ける原発事故。福島原発事故の現状はまだまだ伝えなければならない。
震災から500日過ぎた7月23日、福島第一原発事故の政府の事故調査検証委員会が最終報告を提出した。それに関して夕刊掲載予定だったので現状の福島第一原発の姿をとらえようと、23日早朝、羽田空港から朝日新聞航空部「ゆめどり」で向かった。
現場まで約1時間。首都圏は薄曇りだったが、途中から低い雲がべったりと張り付いたような天候だったので進路を変更、海岸線を北上した。現地の天候は回復しており、途中の福島第二原発からも第一原発が見えてきた。
現地は今年2月末に飛行禁止空域が半径3キロ規制に変更になった。それまでは30、20キロと遠ざけられていたが、3キロでは福島第一原発がより鮮明に見えるようになった。
実は18日も核燃料プールから試験的に保存中の燃料棒抜き取り作業の取材をしていたが、4号機の崩壊していた屋根部分が、えらく取り除かれていると思った。プールを覆う白いシート、黄色い原子炉格納容器の蓋などが露出し、変貌に驚いた。この時は作業も終わり、作業員の姿もない写真となった。
今回は超望遠レンズをのぞくと、建屋の屋上などに白い防護服をきた数十人の作業員の姿をとらえることができた。廃炉まで40年かかるという。まだまだ不測の事態が起きるかもしれない。今後も「福島」をウォッチして伝えていきたい。
--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 前田 龍範(まえだ たつのり)
(2012年7月13日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
ロンドン五輪の盛り上がりで紙面上扱いが小さくなった感のある首相官邸前の「原発反対デモ」。今年3月から始まり、今なお毎週金曜日の夕方に行われている。現在、首相官邸前から国会議事堂の正面に拡がりを見せ、報道各社にとってはデモ取材と事件警戒で目が離せない状態のままだ。
デモ参加者は回を重ねるごとに増え、主催者発表で17万人に。警察も大型車両を何台も首相官邸前に横付けし鉄柵などでデモ参加者の動きをコントロール。周辺地下鉄出入口も制限するなど警察の威信をかけた警備に、集まった参加者は分散されて官邸前の道路が占拠される可能性は、これまでより少し低くなったかのように見える。
取材当日は警戒のため二人で取材。国会記者会館側でデモ取材を中心に撮影する同僚の反対側に移動。デモ参加者の叫びと警備を一枚に切り取ることが出来た。制限されたエリアでのデモとはいえツイッターでの呼び掛けで集まるエネルギーは計り知れない。主催者側はマイクで整然とした行動を呼び掛けるが大きなうねりは、国会を取り巻くどの場所で”決壊”してもおかしくはないと肌で感じた。WEBに載せた写真は少し前の撮影だが、秋風が吹きだした今も同じ光景が見られる。
--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞東京本社写真部 池谷 美帆(いけや みほ)
(2012年8月20日撮影、同日夕刊1面掲載)
<取材者の弁>
ビルの上でパレードの始まりを待っていた。和光の鐘が11時を告げる。スタート地点は見えず、ちゃんとスタートしたのだろうかと思っていると、遠くの群衆の手が上がり始め、波のようにこちらへ近づいてくるのが見えた。後で聞くと人出は50万人。予想をはるかに超えた人波が眼下に広がっていた。
前週から、五輪メダリストのパレードを計画しているとの情報があったが、コースがなかなか確定せずやきもきしていた。そんな中、場所は銀座に決定。実はこのコース、巨人軍優勝パレードとほぼ同じ順路だ。過去の写真を捜すと、様々なポジションから撮影した写真が見つかった。当時先輩がかなり歩き回り、苦労の末に確保した場所だそうだ。その結果急な開催決定にもかかわらず、様々な協力の下、通りを見渡せる抜群のポジションで取材をさせてもらうことができた。まさに読売新聞写真部としての蓄積が生きた取材だった。
選手を乗せたバスが、次々に銀座四丁目交差点を通り抜ける。ビルからではどの選手がどこにいるかの判別は難しかったが、必死にバスを見上げる人たちの表情は、うだるような暑さの中で長時間待っていたとは思えないほど、明るく、歓喜に満ちていた。
パレードが終わり帰社すると、人混みにまみれながらの取材した先輩の苦労話が次々と飛び出す。若手が一番楽していたのでは?との疑念(というより確信?)がわきあがり、うつむき気味でゲラを見る私だった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 鈴木 大介 (すずき だいすけ)
(2012年8月12日撮影、同13日配信)
<取材者の弁>
17日間にわたった祭典のラストを飾るロンドン五輪の閉会式。五輪スタジアムには8万人の観客が詰め掛け、会場はロックの演奏と花火で彩られた。日本選手団のメダルは実施26競技、302種目を通じて、金7、銀14、銅17の計38個と、過去最多だった2004年アテネ五輪の37個を更新した。
WEB上の写真は閉会式終了時に打ち上げられた花火。客席の最前列に指定されたカメラマン席の手すりに、クランプ(固定工具)でカメラを据え付けて撮影した。今回の五輪ではクランプの使用について厳しい安全基準が設けられたため、ワイヤーでぐるぐる巻きにして固定し、さらにレリーズを使用した。
この写真は2秒ほどの長時間露光で撮影したもの。これ以上のスローシャッター写真は白くとんでしまっていた。しかし、個人的には「花のように外に広がる日本式の花火」を想定していたため、スタジアム上部から打ち上げられた花火は「線の花火」で、貧相な感じは否めない。また、通常はあるはずの「閉会式開始直後」の花火もなく、全体として2回ほどしか絵になる花火撮影のチャンスはなかった。(※1回の花火で連続して打ち上げられるが、すぐに煙で白くなってしまい、チャンスはそれぞれの初めのほうだけしか撮影できない)。
帰国後、各紙に掲載された写真をチェックしたが、皆同じように苦労していたようだった。いずれにせよ、この写真を夕刊1面で使用してくださった地方紙も多く、「会場の全景写真」の差し替えとしての「花火写真」の重要性を再認識されられた一場面だった。目の錯覚なのか、一見上から撮った空撮花火のように見える絵柄が珍しいようだ。
--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 森井 英二郎(もりい えいじろう)
(2012年8月12日撮影、13日夕刊1面掲載)
<取材者の弁>
204の国と地域から約11,000人が参加して実質19日間にわたって開かれた世界最大のスポーツイベント、ロンドン五輪。26競技302種目が行われた。私は、初めての五輪取材で、もちろん疲れはあったが、この舞台で写真が撮れること、取材できることが嬉しくて、毎日一番乗りで競技会場に向かった。この日も午後9時から始まる閉会式に向け、5時から聖火の裏に席を取ってカメラを構えた。
いよいよ閉会式が始まり、これまで競ってきた選手たちが一緒に写真を撮ったり、お互い撮りあったり、閉幕を惜しむかのように華やかなステージが繰り広げられたりする中、日付が変わる直前、聖火台近くから次回の開催国ブラジルをイメージした花火が上がり、聖火がゆっくりと消灯していった。閉会式は午前0時すぎまで続いた。
無事に取材を終えることができた安堵の気持ちと、少し寂しさを感じながら最後の閉会式取材を夢中でシャッターを切った自分があった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

読売新聞東京本社写真部 松本 剛(まつもと つよし)
(2012年8月12日撮影、13日付け夕刊五輪面掲載)
<取材者の弁>
ロンドン五輪の閉会式。聖火台の炎がいよいよ消える段になると、その背後に巨大な不死鳥が現れた。「スポーツを通じて平和でよりよい世界の建設に貢献する」という五輪の精神が、不滅であることを世界に示したのであろうか。その意図はともかく、天に舞い上がるような火の鳥の雄姿に、明るい未来の予感を感じ取ったのは私だけではあるまい。
大会を振り返れば、我らが日本選手団の活躍も次へつながる内容だった。メダル獲得数の史上最多も立派だったが、バドミントン、ボクシング、ウエートリフティングに卓球などなど、それぞれの競技で数十年ぶりのメダリストが続々誕生した。競技人口のすそ野を広げ、今後も更なる飛躍が期待出来ることだろう。
大きく羽根を広げたフェニックスが見守るフィールドで、無邪気に記念写真を撮り合う日本選手の姿が見えると、思わず胸が熱くなった。カメラのファインダーをのぞきながら、「ありがとう、また頑張ってくださいね!」と叫んでいた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 西村 庸平(にしむら ようへい)
(2012年8月9日撮影、同11日付4面掲載)
<取材者の弁>
「バカヤロー!お前は何をやってるんだ!」神聖なオリンピックのレスリング会場に響き渡る怒鳴り声の主はアニマル浜口。いわずと知れた浜口京子の父である。この日、レスリング女子72キロ級に出場した娘・京子がまさかの初戦負け。敗者復活の願いもかなわず、北京五輪に続きメダルを逃してしまった。
父は試合内容に納得いかず、娘を見つけると柵の向こう側から怒鳴り散らしたのだ。
試合直後からあまりに不機嫌モードの父。浜口京子の出場する試合後は親子3人の感動のシーンが撮影できる可能性が高いのだが、待ち構える我々カメラマンもこれには思わず心配になってきた。そして父と娘が対面。「お前は勝っていたんだ!最後押すだけだったんだ!このバカヤロー!」あまりの勢いに警備員たちも駆け寄ってきた。撮影しているこちらが圧倒されてしまうような迫力。
すると横にいた母・初枝さんが夫の暴走ぶりに激高。「アンタはバカか!この道化師が!そこまで言うならアンタが出ろ!」と応酬、すると父は「お前は帰れ!リーオ、リーオ!」と4年後のリオデジャネイロ五輪で雪辱しろと絶叫。「このバカオヤジ」と叫ぶ母。こちらは親子仲を心配していたのだが、いつの間にか夫婦ゲンカである。
しかし我々の心配をよそに、いつの間にか親子3人は笑顔になっていた。メダルを取れなかった事を叱る父、謝る娘、慰める母、こんなに真っ直ぐで、人間味溢れる親子は見たことがない。メダル獲得は果たせなかったが、4年間必死で努力してきた京子選手の笑顔を見ると、私の心まで温かくなっていた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 下田 知仁(しもだ ともひと)
(2012年8月9日撮影、同11日付4面掲載)
<取材者の弁>
ロンドン五輪も終盤にさしかかり、日本期待のレスリングが始まった。高速タックルを武器に、2004年アテネ、2008年北京で金メダルを獲得し3連覇を目指しロンドンに乗り込んできた吉田沙保里。4年前も北京で彼女を取材し、その圧倒的な強さは分かっている。
今回もやってくれるだろうと期待し、その最高の姿を撮影するために試合開始の4時間前から場所取りをして試合に備えた。指定されたカメラマン席の中でも、審判やセコンドのコーチなどが手前にかぶってしまう位置があり、少しでもかぶる可能性のない位置、そして光線具合やバックに邪魔なものが写らない位置など、ベストなポジションを巡って試合前から各国のカメラマンと競争である。
まずまずのポジションを確保し、そして試合開始。吉田は危なげない試合運びで順調に勝ち進み、決勝進出を決めしばしの休憩時間。その時胸ポケットの電話が鳴った。声の主は東京の会社にいるデスクからで第一声「おーい、お前テレビに映りすぎ!」。そんな事言われても・・・。こっちだっていい写真を撮るために必死に取った場所なのだ。人の苦労も知らないでデスクは好き勝手なことを言ってくる。
気を取り直して決勝戦。吉田は期待通りバービーク(カナダ)に第1ピリオドで得意のタックルを決め、第2ピリオドでもポイントを奪い完勝。見事五輪3連覇を達成。涙も見せずに国旗を手にすると貫禄の表情で場内を周った。最高の笑顔を見せてくれた吉田選手に感謝です。
--------------------------------------------------------------------------------------------

スポーツニッポン新聞社写真部 西海 健太郎(にしうみ けんたろう)
(2012年8月4日撮影、同6日五輪面掲載)
<取材者の弁>
競泳男子の松田、入江、藤井の3選手が「康介さんを手ぶらで帰らすわけにはいかない」と、北島康介本人には伝えずにこれまで頼りっぱなしだった北島への恩返しの思いで心をひとつして、男子400㍍メドレーリレーで見事、銀メダルを奪取、絆の力を見せつけた。
メドレーリレー決勝で入江、北島、松田、藤井は「馬鹿力」を出した。取材する我々にもそのパワーが伝わってきた。中でもリレー第2泳者・北島は、先頭で戻って松田につないだ。「足引っ張れねぇなぁと思っていた。チームに貢献できたのがうれしい」と北島。個人種目の3連覇はかなわなかったが、この絆の銀メダルで3大会連続のメダルを獲得したのだ。
自由形専門の選手が選考会で代表権をとれず、バタフライと兼職の藤井が自由形に回り、バタフライには200㍍が専門の松田が担当、不安や疲れがあった中、お互いの責任感、チームの絆でもぎ取った銀だろう。決まった瞬間、ちょうど私の方を向いて全員がガッツポーズ、ばっちり撮れた。これは銀以上のカメラアングルだった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

共同通信社写真部 佐藤 優樹(さとう ゆうき)
(2012年8月2日撮影、同3日配信)
<取材者の弁>
「跳馬が一番よかった」内村航平がインタビューに珍しく自画自賛していた。自分のファインダーの中で、肉体はしなやかに、足の指先はまっすぐ伸び、美しく回転しながら着地もぴたり止まった。この内村の美しい技を切り取り、14枚の連続写真で表現した。実は苦難の中で生まれた連続写真なのだ。
まずノースグリニッジアリーナの体操会場を説明すると、胸の高さの木の板でフィールドとフォトポジションが完全に仕切られていた。世界体操などでは背の低いパーテーションかロープなどの簡単な規制線が張られている程度だが、状況が違う。カメラをあおって撮った方がよりいい写真になることが多く、カメラマン泣かせの会場だ。しかも、テレビクルーがフィールド内にあふれんばかりにいて、脚立に乗っても彼らの頭がひっかかるという状態。おまけに五輪マーク絡みが少なく悩ましいというか、気の利いたいい写真は、「もう無理」状態だった。
木の板で仕切られている「壁」は、カメラをおけるほどの幅があったので、自分のカメラと連動させて固定カメラを仕掛けることにした。そのためには場所取りが必須。内村選手のつり輪の演技を終え、ダッシュで跳馬のポジションへ。他の日本人カメラマンも同じ考えで、狭い通路をみな全速力。なんとかポジションを確保。しかし、その次に立ちはだかるのは監視の目。テレビ局がその「壁」の上に固定されたムービーカメラを設置しているため、少しでも「壁」に触るものなら飛んできて、「触るな!」。
あまりに私が「壁」に触れすぎたのか、途中からテレビ関係者の監視が横からジーっときつくなった。こうなったら、ぎりぎりでカメラを設置するしかない。選手とはまた違う胸の高鳴りを覚えたほどだ。
いよいよ内村選手の出番がきた。「やっちゃえ!」と気合を入れて、テレビ関係者が最初、何かブツブツ言ってはいたが完全無視。急いで準備しないと跳馬はあっという間に終わってしまうので必死だった。その必死さが伝わったのか、そのうちテレビ関係者は何も言ってこない。何とかピントも画角も合わせ、内村選手が助走を始めた。見事着地を決め、ガッツポーズ。こちらは固定カメラを急いでチェック。撮れた写真を確認し、「連続写真はいける」と、心の中でガッツポーズ。横で監視していたテレビ関係者にさえありがとうと言いたかった。そんな余裕をかましていたら、次の平行棒に出遅れ、いい撮影ポジションが無かった…。内村の結果は、この“ひと跳び”で出場24選手中最高の16.266点を記録。個人総合で金、よかった、結果オーライとしよう。
--------------------------------------------------------------------------------------------

(2012年7月30日撮影、同31日配信)
時事通信写真部
撮影
・山崎 秀夫(やまざき ひでお)
文
・大高 正人(おおたか まさと)
<取材者の弁>
「まさか」-現場のカメラマンは皆、目を疑っただろう。ロンドン五輪体操男子の団体総合決勝。日本のエース、内村航平はあん馬の演技のフィニッシュで大きくバランスを崩した。常に冷静な内村がめったに見せない「しまった!」という表情がすべてを物語っている。
「中国を下して団体金」が最大の悲願だった今大会。しかしやはり五輪という大舞台には魔物が棲むのだろうか。内村ほどの選手でも歯車の狂いが生じた。予選では鉄棒、あん馬で落下。決勝でも悪い流れを断ち切れず、このシーンを迎えた。内村のこの演技で日本は全種目を終え、採点結果はメダルに届かない4位。その後、日本チームの抗議で内村のあん馬の得点が修正され、最終的には銀メダルを獲得したが、判定トラブルの多い今大会を象徴するようなドタバタの展開に、表彰台でも内村の表情は硬いままだった。
しかし、このままで終わらないのが今の内村の底力。中一日置いた個人総合決勝では見違えるように吹っ切れた動きを見せた。この種目で日本人28年ぶりの金。精密機械のような正確さと、美しさを兼ね備えた演技は会場全体を魅了した。この大会のハイライトシーンとして多くの写真が各社の紙面を飾り、年末には報道展の会場を賑わすに違いない。
だが、団体でミスに苦しんだ内村の姿もぜひ後世に残したい。日本中の期待を背負うプレッシャーに負けそうになりながら、気持ちを立て直し、最後は自分の持てる力をすべて出し尽くした内村に「天才でも人間なんだ」と励まされた人は多いはず。地獄から天国に駆け上った、この数日間の物語はいずれ本人の口から明らかにされるだろう。カッコ悪くても泥まみれで戦う姿をとらえたこのショットを「一押し」することを内村選手には許してほしい。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 中田 卓也(なかた たくや)
(2012年7月26日撮影、同28日付2面掲載)
<取材者の弁>
サッカーは何が起きるか分からない。これまでこれほど鳥肌が立った経験はなかった。ロンドン五輪サッカー男子の1次リーグ初戦の相手は優勝候補の世界王者スペイン。その強豪スペインを前半34分、コーナーキックからMF大津祐樹(ドイツ・ボルシアMG)のゴールで撃沈したのだ。
茶髪にピアス、大津は「チャラ男」と呼ばれ要領はよかったが、初めはチームで定位置すら確保できなかった存在だった。五輪予選が始まった昨年は代表に招集されなく、J1柏レイソルからドイツのボルシアへ移籍した。ドイツのリーグ戦には、たった3試合しか出場できなかったが、しかしそこでの厳しい生存競争経験で、球際に強い大津に生まれ変わったのだ。
「グラスゴーの奇跡」ではない。扇原の右からのコーナーキックにゴール前にこぼれたボールに相手のDFをかき分けるように飛び出し、玉を浮かさぬようにスライディングして押し込んだ。先制ゴールを決めて喜びながら駆け出した清武、吉田、酒井の先頭に大津が弾けている。たいした22歳のチャラ男だ。試合終了後、インタビューで、「出られないメンバーのためにも勝ちたかった」。いやはや、チャラ男ではなく、立派な好青年。これからに期待しよう。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 河口 貞史(かわぐち さだふみ)
(2012年7月16日撮影、17日朝刊一面掲載)
<取材者の弁>
7月16日に代々木公園サッカー場で行われた「さようなら原発 10万人集会」。気温33度を超える酷暑の中、原宿方面や、六本木方面から続々と参加者が集まってくる。開始時間に近づくとサッカー場に入れない人たちで外の公園まであふれかえっている。後ほど空撮の写真を見ると、会場に入れない人であふれかえっているのがわかる。
会場内で先輩とポジションを前後に分け、私が後方を担当。今日の集会を一枚で表現することを考えていると、暑い・・・暑すぎる・・・真夏の暑さと群衆を表現したいと青い空と、参加者が差していた日傘などを入れ、めいっぱい人がいるように見せようと広角レンズで表現した。太陽も入れたかったが、ほぼ正午に近い時間のため断念し、夏の青い空と群衆で表現した。
回を追うごとに参加者が増えている反原発の集会。今回の主催者発表は17万人。原発に対する国民の関心度が現れている。会場は、酷暑にも負けない参加者の暑さであふれかえっていた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

産経新聞大阪本社写真報道局 門井 聡(かどい さとし)
(2012年6月25日撮影、28日運動面掲載)
<取材者の弁>
ロンドンに到着してから連日の雨で気が滅入る。「五輪開幕まで1ヶ月」という紙面企画が刻々と近づいて来るからだ。デスクからの至上命題はへりコプターからの空撮だった。なんとしても、「開幕を控え準備が進む五輪公園」の空撮で紙面を飾りたい。が、悪天候のためヘリコプター会社との調整はなかなか進まない。ようやく、25日月曜日の午前という日程が決まったのは、週末の22日金曜日だった。
ヘリ会社マネージャーのおすすめの日程は的確で、ロンドン入りしてから一番の晴天に恵まれた。が、機体を見たら不安が再燃。社で普段しているEC135より一回り以上は小さく見えるロビンソンR44。そして機体の大きさよりも気になるのは、コパイ席のドアが外されていることだった。
このヘリ会社はテレビの仕事が主で、機体に取り付けられたカメラを機内で操作して撮影する。そのため、窓だけが開く機体が無いのでこういう措置になったというわけだ。これで、事前に伝えられていた注意事項に納得がいった。「レンズ交換はなるべくしない。スタビライザー付きのズームレンズがおすすめ」、「暖かい服装で。ただしポケットには何も入れないこと」などなど。
乗り込んでみると、やはり狭い。左肩にカメラを掛けると外に出そうなので、持ち込んだ3台とも首からぶら下げることにした。シートベルトは乗用車のような3点式で、留め金はテープで固定。脱出の際は、力一杯引っ張ってテープをやぶるのだとか。
しかし、色々な不安をよそに、いざ飛んでみると開放感が有って気持ちが良い。到着以来一番の天気に厚着だったので少々汗をかいたが、ドアが無いおかげでむしろ快適だった。風も静かでとても穏やかなフライトだ。小回りが利いて、限られた時間内で様々な競技会場を資料撮りするのにもちょうど良い。「ロビンソンって良い機体かも」と手のひらを返す。機長も慣れたもので、特に注文を付けなくても良いポジションを取ってくれ、細かい調整もこちらの希望通りにこなしてくれる。飛行場に戻ると、贅沢な空の散歩をさせてもらった気分で一杯だった。実際に見た五輪サイトのスケール感が少しでも伝わっていれば幸いです。
--------------------------------------------------------------------------------------------

毎日新聞社写真部 須賀川 理(すかがわ おさむ)
(2012年6月28日撮影、28日夕刊社会面掲載)
<取材者の弁>
宿直明けの28日朝、横浜・八景島シーパラダイスから午前4時過ぎに国内9例目のシロイルカの赤ちゃんが誕生したとプレスリリースが届いた。同日中に一般にも公開されるというので早速取材に向かった。
飼育プールに母親のパララと泳いでいた生後6時間ほどの赤ちゃんは海洋生物とは思えないほど不器用な泳ぎ。水面からはパララが下から必死に支え 呼吸を手助けしているのが見えた。水中の様子を撮影しようと思ったが、アクリルから見えているのは水面から50センチほどだけ。5メートルほど離れた撮影場所からは母親の陰に隠れた赤ちゃんの姿がちらちらとしか確認できない。「赤ちゃんが壁にぶつからないようにパララが外側を泳いでいるんです」。広報担当者が解説してくれた。
ほほえましいが撮影者としてははっきりと姿をとらえたい。しばらく待っていると母親の背中をするりと超え、赤ちゃんイルカがアクリルに近づいた。パララはアクリルと赤ちゃんの間に体を割り込ませようと頭をアクリルに押しつけ、まるで抱き上げるように赤ちゃんを背中に乗せた。
シロイルカの赤ちゃんの飼育は極めて難しい。過去8例の出産のうち現在も生存しているのは2頭だけという。母性を発揮するパララに支えら れ赤ちゃんが順調に育つことを祈りたい。
--------------------------------------------------------------------------------------------

静岡新聞社 写真部 藤井 晴雄(ふじい はるお)
(2012年6月13日撮影 同14日、朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
午前8時。本社から富士山が薄曇りながらもよく見えたので航空取材を計画。
午前9時。4号目付近に雲が横長にかかってきた。
午前9時30分。ヘリポートを飛び立ったところ静岡市側からは雲に隠れて富士山は見えなくなっていた。
朝霧高原上空にまわれば見えるかもしれないとのパイロットのアドバイスで、雲の上に出たところ富士山が雲海からそびえ立っていた。窓を開けて取材を始めようとしたところ右上に虹が見えた。何回も富士山の写真を撮影してきたが、富士山と虹の航空写真は初めての遭遇で感激した。バランスのいいアングルへと誘導してもらい撮影した。
地上の虹もそうだが、はっきりと写らないのでは?と思ったがデジタルカメラのモニターでも分かるように写っていたので、朝刊用に出稿した。日本気象協会で確認したところ「環水平アーク」という大気現象の一つで、まれに見られるが珍しいとの事だった。偶然とはいえ約30分、きれいなものが見え、残り少ない現職のいい思い出にもなった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 戸田 泰雅(とだ やすまさ)
(2012年5月28日撮影、29日付朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
雨が一時的に激しく降った5月28日。「開業したてのスカイツリーに雷が落ちるところが撮れるかもしれないから」というデスクの指示で隅田公園に行った。雷を今まで撮ったことがなく、どうすれば写るのか雨の中で難儀すること十数分、多分こうだろうという設定で撮っていると次第に空が明るくなりはじめ、太陽が見え始めた。空は明るいが雨はまだ降っていたのでひとまずデスクに電話すると「虹は見えない?」とのこと。良く目をこらすと雲がなくなった辺りから虹が見え始めていた。
雷同様虹も撮ったことはないので、虹はすぐ消えるという知識から急いで撮ることに集中。最初に立っていた所からでは虹とスカイツリーが絡んでなかったので隅田川沿いをダッシュ。吾妻橋あたりから撮ったのが最終的には掲載された。
カメラの背面モニターで確認すると、雷は全く写っておらず、虹も慌てて撮影したためレンズの水滴に気付かず、所々滲んだ写真になってしまった。また偏光フィルターもカメラバッグに入れていたのに使わなかった。使えばもう一本の虹もくっきり撮れていたのではないかと反省。
日々初めてのものを撮るばかりなので、ある程度知識をつけて練習できるようにしないといけないと反省する1日だった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞写真部 葛谷晋吾(くずたに しんご)
(2012年5月8日撮影 5月12日夕刊掲載)
<取材者の弁>
国連の平和維持活動に同行し5月8日、政府軍と反体制派の戦闘が続くシリア・中部ホムスに入った。中心部の広場に近づくと、同行した政府側の警察が「ここから先は自己の責任で…」と念を押した。周りのビルには反体制派のスナイパーがいるという。
激しい攻防のあったハルディア地区。足を踏み入れると無人の街が広がっていた。ビルから砕け落ちたガラスが道路一面に散らばり、乗り捨てられた自転車が転がっている。焼け焦げた商店の前には略奪された商品の箱が捨てられていた。壁には銃弾の痕が残り、足元には無数の薬莢が散らばっていた。
「パン、パン、パン」。断続的に銃声が聞こえる。時折、「ドーン」という砲弾の音も響く。生活音のない街に乾いた銃声はよく響いた。国連の目指す「停戦」がここでは全く実現してない。
戦闘が最も激しかったババアムル地区。居住用の建物は破壊され、残された壁には砲弾の穴が所々にあいていた。ほとんど形をとどめない建物もあった。街に色はなく、荒涼としていた。
その荒涼とした街を自転車に乗った少年が通り過ぎた。決して急ぐでもない様子が、戦闘が日常化していることを印象づけた。断続的に響く銃声はその間もずっと続いていた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

信濃毎日新聞社写真部 太田 一彰(おおた かずあき)
(2012年5月21日撮影、21日付夕刊社会面、22日付統合版朝刊社会面)
<取材者の弁>
広い範囲で金環日食が確認できた5月21日朝。観察イベントも各地で開かれ、大勢の人たちがさまざまな形で楽しみ、長野県内では173年ぶりという天体ショーに盛り上がった。
当日、私は金環日食になる地域での取材ではなく、部分日食の長野市内で雑観を担当した。欠け始めから金環日食になるまでの連続写真や多重露光を担当するため県内各地に出向いた同僚記者より遅めの取材開始。青空が広がっているものの薄暗く肌寒い朝だったが、自転車で自宅から長野駅まで向かう間にも、駐車場やマンションの踊り場から観測用メガネで日食を観測する人の姿をちらほら見かけた。通学の小学生たちは「安全に」空を見上げることなく整然と登校していた。
駅に到着すると、通勤途中の数人が日食グラスで空を見上げていた。その内の一人から「見てみます?」と手渡されて覗くと、まさに食の最大を迎え、三日月のようになった太陽が目の前に。思わず「すごい」と声を上げると、まるで子どものようだったのか、笑われてしまった。
駅前での撮影に粘り過ぎたことを後悔しつつ、もう1カ所の撮影ポイントで同僚が教えてくれたパンチ穴の空いた百貨店の立体駐車場へ。太陽の高度がうまく合えば、ピンホール効果で一面に日食の影が現れるはず-と期待して向かった。到着すると、影を見に来たという1組の親子連れがいた。思惑通り、三日月形になった太陽の影が1階部分の駐車場一面に広がっていた。ただ、「食の最大」を過ぎていたため、借りた日食グラスで覗いた時と比べると、欠けた部分は少なくなっていた。焦る気持ちを抑えながら、くっきりと無数の三日月模様が浮かび上がった親子の姿と車を撮影した。「きれいだね」と見入る親子連れ。母親は、「上の子が小学校で見るので、下の子と見にきました。日食グラスは買いそびれて、もう売っていませんでした」と、太陽が影で見えることを思い出してこの場所に来たという。
一通り取材を終えた頃には、薄暗かった空もいつもの明るさを取り戻し始め、駐車場の「三日月」も真ん丸に近づいていった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 山本 裕之(やまもと ひろゆき)
(2012年5月7日撮影、8日付け朝刊1面)
<取材者の弁>
今年の大型連休は例年になく大荒れの様相になりました。
関越道の高速バス死傷事故や、北アルプスを中心とした山岳遭難は悲惨でしたが、大型連休最終日に北関東を襲った竜巻は想定外の出来事でした。大きく黒い渦が地表をはうように走り、次々に家屋をなぎ倒しました。基礎の土台ごと吹き飛ばされた住宅では、中にいた男子中学生が命を失いました。国内最大級の竜巻として観測されたこの竜巻の出現には誰もが驚きました。
一夜明けた現場で、被害状況を早朝から茨木県つくば市の北条地区で撮影取材していました。上空には各社ヘリコプターが空撮しています。俯瞰したさまざまな写真が送られてきているはずです。地上班は地元・被災者が実際に見ている高さを意識しようとする狙いに切り替えて、撮影取材していました。
この写真は商店街の一角にある住宅屋上から撮影したものです。この住宅もほとんどの窓ガラスが割れて、家主さんは室内の清掃作業に追われていましたが、撮影許可をもらう事ができました。
屋上から下の階へと続くはしごを降りて、修復作業をされていた工事関係者の方を点景として、写しました。夕刊用に送稿した写真でしたが、紙面は休刊日あけの初報ということもあり、リリースされず朝刊に回りました。自分としては写真として落ち着いた構図ではなかったかと反省しきりでしたが、朝刊一面での掲載となり、朝起きて一番驚いたのが自分でした。恥ずかしいかぎりです。
--------------------------------------------------------------------------------------------

時事通信社写真部 喜多 信司(きた しんじ)
(2012年2月24日撮影、未配信)
<取材者の弁>
福島市内中心部から車で10分ほど、阿武隈川の河畔にある渡利地区。震災発生から1年を間近に控えた2月22日、空間放射線量が高い、いわゆる「ホットスポット」とされるこの地域の除染作業が本格的に開始された。
全面除染が始まった2日後の24日、住宅の除染作業に同行する形で撮影を行った。高圧洗浄機による屋根の除染に始まり、庭の表土の除去、側溝や屋根の隙間に入った枯れ葉を取り除くなど、地道な作業が続く。除染を行う作業員も、同行する市の職員もまだまだ手探りの状態。地表面の線量をこまめにはかりながら、話し合いを重ね除染を進める。試行錯誤の作業が続く中、夕暮れにシルエットで浮かび上がったのは、見えない相手に黙々と立ち向かう作業員の姿だった。
取り除いた表土の仮置き場もなく、自宅の庭に埋却して一時的に保管したり、住宅に隣接する山林の除染など課題も多い。地区の児童公園には空間線量計が設置され、遊具の使用も禁止されている。この日も誰もいない公園に入ると、隣接する体育館の窓越しに子供たちが無邪気に声をかけてきた。放射性物質と向き合う市民の日常をどのように伝えていくか、これからも、長く相対していきたいと思う。
--------------------------------------------------------------------------------------------

東京新聞写真部 笠原 和則(かさはら かずのり)
2012年4月17日撮影、18日付け朝刊地方面掲載)
<取材者の弁>
5月22日の開業を約1ヶ月後に控えた17日、これまで公開されていなかった東京スカイツリーの上部展望台「天望回廊」が報道関係者に公開された。こうした報道公開の際、今まで東武タワースカイツリー社は取材カメラマンを1社1名としてきたが、公開場所が2つの展望台と4、5階フロアと広範囲のためだろうか、人数制限はなく、複数名で撮影することができた。当日は天候に恵まれず、都心方向は丸の内のオフィスビルすら霞んでしまうほどだったが、日本一の眺めの一端を撮影することができた。メーンは当然地上445mメートルから450メートルに棟体をほぼ1周して眺望を楽しめるチューブ状のガラス張り部分。しかしそこは構造上の問題だろうか、広い窓ガラスはなく、“鉄骨だらけ”の状態で、撮影者は眺望とチューブ状の通路を絵にするのに苦労した事と思う(もちろん私も苦労した)。
掲載の写真は最高到達地点451.2メートルの「ソラカラポイント」からの眺め。450メートルのチューブ回廊の終点からさらに“おまけ”のように1.2メートル登った場所だ。そこではガラスに光線を当てて「451.2メートル」の文字が映し出されている。ここには高度の他、日付や東京スカイツリーなどの文字が繰り返し表示される。ソラカラポイントを撮影している時にファインダー上部にちらちらした白い物が見え、初めて存在に気づき、場所を移動してシャッターを押した。
「次のグループになりますから移動して下さい」という広報担当者の声に押されて、最高地点を降り、350メートル地点の「天望デッキ」に下るエレベーターに乗ったが、短時間にあれもこれも絵にしようとカメラをかまえ続けたためか、天望回廊の眺望がどんなものだったのか余り覚えていない。感想が一つあるとすれば、高すぎてヘリに搭乗しているのと同じ感覚で、足がすくむような高度感がない、というもの。次はチケットを買って、ヘリに乗せてあげたことのない妻子と楽しみたい。
--------------------------------------------------------------------------------------------

河北新報社報道部 成田 浩二(なりた こうじ)
(2012年3月3日撮影、11日朝刊特集面掲載)
<取材者の弁>
「3・11」が遠い過去に思えるような穏やかな光景だった。すらりと伸びた幹の周りで子どもたちが遊ぶ。雲間の青空から降り注ぐ柔らかな光が、苦難に耐えた生命を慈しむように浮かび上がらせた。
人口約2万4000人のうち1707人が死亡、25人が行方不明(2012年4月現在)になった岩手県陸前高田市。名勝「高田松原」は、海岸線の延長約2㌔に7万本の松が密集していた。あの日、白砂青松は津波と共に姿を消した。残ったのはたった一本。濁流にもまれながら、大地をしっかりとつかんで離さなかった。
「奇跡の一本松」。いつしか、そう呼ばれるようになった。
大量のがれきがぶつかった幹には痛々しい傷跡が残る。潮水に漬かった根元は腐食が進む。人々は、松原の再生へ動き始めた。松ぼっくりを拾って種を採取した女性がいる。苗木の育成に挑む市民グループがある。「何百年かかっても松原を取り戻したい」。被災地を励まし、勇気をくれた一本松に感謝し、明日への思いを重ね合わせる。
東北地方に未曽有の被害をもたらした東日本大震災から1年がたった。失ったものはあまりにも大きく、被災者は筆舌に尽くせない苦悩を抱えながら一日一日を懸命に生きてきた。悲しみはなかなか癒えない。復興の道のりは険しい。だからこそ、「希望」を伝えていきたい。
--------------------------------------------------------------------------------------------

朝日新聞社写真部 上田 潤(うえだ じゅん)
(2012年4月5日撮影、6日付け西部本社朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
北朝鮮の長距離弾道ミサイル発射に対応するため、防衛省が沖縄県宮古島市と石垣市に地対空誘導弾パトリオット3(PAC3)を配備した。まず4月3日に宮古島に陸揚げされたが、搬入された航空自衛隊の分屯基地が宮古島で一番の高台にあるため、実際に配備されたPAC3を撮影することは困難だった。本来はここで帰任するはずだったが、5日に陸揚げする石垣島には自衛隊の基地がなく、市街地に近い場所に配備されると記者から聞き、急遽石垣島に転戦した。
石垣島では石垣港の対岸にある埋め立て地に配備されたが、港に海上保安庁の巡視船が停泊していて見えない。埋め立て地も自衛隊と警察が立ち入りを規制していた。石垣市役所で別件を取材していたところ、沖縄の提携紙の記者からチャーター船に同乗しないかと持ちかけられた。ありがたく同乗させてもらったのだが、自衛隊員がお昼休みに入っていたのか、PAC3の発射台は降ろされたままで隊員の姿もなかった。せっかく岸壁付近まで近付けたのに、野ざらしにされたような写真しか撮影できなかった。
徒労感を味わいながら下船し、遅めの昼食に石垣そばを堪能した後、再び港に向かった。すると、それまでなかった車両や自衛隊員がPAC3を取り囲んでいるのが見えた。発射台も上空に向けられている。海保の巡視船も停泊していない。慌ててレンタカーから飛び出して撮影を開始。タイミング良く手前を観光船が通過してくれた。思うように取材ができずモヤモヤしていた頭が一気に冴え渡った瞬間だった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「センバツ 大阪桐蔭が初優勝」
毎日新聞社写真部 久保 玲(くぼ れい)
(2012年4月4日撮影、5日大阪本社版朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
今大会注目を集めた大阪桐蔭の197センチの長身、“浪速のダルビッシュ”
こと藤浪晋太郎投手は投球内容もさることながら喜び方も圧巻だった。
逆転勝ちした準々決勝ではまるでもう優勝したかのように顔を上げながら両手でガッツポーズ。顔が上に向きすぎてセンターポジションで撮影していた私からは鼻から上が見えなかったほどだ。
迎えた決勝でも優勝を決めた瞬間両手を挙げて喜びを表現。その姿に私も胸が熱くなり、今度は顔がはっきり写っていたことを確認してほっとした。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「スカイツリーと光の競演」
毎日新聞社写真部 三浦 博之(みうら ひろゆき)
(2012年3月26日撮影、27日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
全国各地の西の空で3月26日、金星、月、木星がほぼ一直線に並ぶ天体ショーが見られるということで、さっそく場所探しに走った。その前に、天体の取材はほとんど経験がないので先輩カメラマンにまずコツを伝授していただいた。さらに、ただ星だけを撮っていても仕方がない。「今年の天体ショー」ということで東京スカイツリーと絡む場所探しだ。ツリーの高さ634㍍と角度30度だと、どの辺で撮ればいいのか先輩のアドバイスを頼りに地図とにらめっこ。あちこち月と金星を頼りに移動したが、スカイツリーのてっぺんを入れて天体ショーが写るところを墨田区の都営住宅の横でようやく探し当てた。
天体ショーに関しては脇役の東京スカイツリーは、開業を5月22日に控え、ライトアップの試験点灯が始まったばかりだ。その脇を明るく輝く金星と月、木星がゆっくり移動していく。雲の合間に出たり入ったりの天体ショーだったが、運良くスカイツリーの横に絡ませて撮れた。データはISO200、F5,6、8秒間の露光だった。
三つの星が一直線に並ぶのは、04年11月以来だという。次回は15年11月には火星を含めた四つが並ぶという。これまた頭が痛い。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「生活を支える〝屋台骨〟」
日本農業新聞 写真部 福本 卓郎(ふくもと たくお)
(2012年3月6日撮影、10日付特集最終面掲載)
<取材者の弁>
「とにかく、イチゴ栽培ができるのが一番うれしい」。宮城県気仙沼市の農家三浦拓也さん(28)は、心待ちにする新しく建つイチゴ栽培用のハウスを見に来ていた。東日本大震災の津波でビニールハウスが流され収入を無くして生活費を稼ぐためのアルバイトに向かう途中のことだ。午前中は雨が降っていたが、午後3時ころには青空が広がった。
被災して約1年たっても、再起の道のりは厳しいものの、農業収入の道筋が何とか見えてきたようだ。どことなく哀愁漂う空の色を背景に、建設中のハウスの柱は、これから三浦さんの生活を支える〝屋台骨〟に見えてきた。この施設は3月末には完成。「9月にはイチゴの苗を定植して12月の出荷を目標にしている」という三浦さん。辛さを我慢しながらも笑顔になった表情が目に焼き付いた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「3㌔圏の空から福島第1原発を見た」
共同通信社ビジュアル報道センター企画委員 原田 浩司(はらだ こうじ)
(2012年2月26日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
警戒区域と計画的避難区域の上空で測定した放射線量調査に基づき、12年2月25日、福島第1原発の飛行禁止区域は半径20㌔圏から3㌔圏に縮小された。これを受け、同26日、ヘリコプターで、3㌔圏まで近づいてみた。
震災前には何度も飛んだ空域だが、震災後として初めて見た福島第1原発の惨状に改めて驚く。かつて、整然と並んでいたサイコロのような原子炉建屋は、鉄骨がむき出しになり、元の形状をとどめていなかった。「この1枚」に掲載している写真は、福島第1原発の4号炉(手前)だ。中央左に黄色い格納容器の一部が見える。海側の施設は、震災当日のまま、破壊されたままの残骸が放置されていた。
何よりも目立ったのは、原発の少し離れた場所に置いてある数百の汚染水貯蔵タンク。この先、汚染水の置き場所は確保できるのか、憂慮するほかなかった。一見して、がれきや放射線の影響で、復旧作業が順調に進まない様子が伺い知れた。
結果として、原発周囲を6周した。逐一、パイロットと「今はいくつ?」と放射線測定器の数値をやり取りしながら。意外なことに、針が振れるのは北西側を通過する時だけだ。それでも高度1千M前後で、毎時1.7から2.6マイクロシーベルトの間を振れる程度。その他の方角では、針が振れることはなかった。現時点では、原発からの放射線はそれほどでもなく、汚染された地上からの放射線が高いということなのだろう。取材を終え、羽田空港に戻って積算線量計を見ると、数字は「0」を表示していた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「復興 大漁旗に誓う」
河北新報社写真部 高橋 諒(たかはし りょう)
(2012年1月15日撮影、16日社会面掲載)
<取材者の弁>
宮城県南三陸町歌津の寄木地区に伝わる小正月行事「ささよ」。法被姿の子どもたちが、「おめでたいヤナー、ササヨ、ヨイトコラ、ヨイトナエー」と独特の節をつけた唄で大漁と海上安全を祈願する 。例年、1月15日に地区の家々を回り軒先で歌っていたが、震災により半数以上の家屋が被害を受けたため、今年は漁港と仮設住宅の2カ所での開催となった。
「ささよ」は藩制時代から続く町指定の無形民俗文化財で、中学生以下の男子よって受け継がれてきた。譜面などは無く、子ども同士の口頭で伝えられてきたため1年でも休むと存続が難しくなると言う。子どもたちは仮設住宅に併設された集会所や学校で連日のように練習を重ねてきた。
まとめ役の「大将」を務めた歌津中2年の畠山信斗君(14)が担ぐさおには、津波で流失を免れた大漁旗がはためいていた。地域の人々の願いが込められた旗ざおは例年以上に重く感じられたことだろう。「復興を願いみんなを元気づけたかった」と話す畠山君の引き締まった表情が印象的だった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「ハートは戦争の痛み」
東京新聞写真部 木口 慎子(きぐち しんこ)
(2012年2月2日撮影、同9日付夕刊1面掲載)
<取材者の弁>
東日本大震災で津波を受けながら、奇跡的に残った陸前高田市の「高田松原」が、被災者の生きる希望となった。同じように災難や戦禍を生き抜いた都内の樹木を取り上げた企画が夕刊一面で連載した「希望の木」だ。ストレートなニュース写真と違って、企画写真は実際に撮影にかかるまでの準備が労力の半分以上を占める。連載予定回数の倍以上の撮影候補を探し出し、その下調べとロケハン、そして仕上がる写真のイメージを練ることの繰り返しだ。地味な作業だが、企画の全体像を描き出すには労を惜しむことはできない。
今回の企画は複数のカメラマンが担当したため、絵柄の相似に気を使わなければならなかった。連載が進むにつれて、光の使い方や構図が〝撮り〟尽くされていくので、後半になるほど苦労が多い。しかし、最終回となった「ハートは戦争の痛み」は、撮影と記事のみを担当。前段の下調べなどはデスクと諸先輩方が済ませてくれていたので、現場には2回通っただけで合格点が出た。別の木を担当した時は、時間帯を変えながら8回も通ったことを思えば、ちょっと楽をさせてもらったかな。
間もなく大震災発生から1年を迎える。人と木の係わりを描いたこの企画を通じて、復興にほど遠い被災地への思いを新たにした。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「眠りから覚めた葵御紋」
朝日新聞社写真部 恒成 利幸(つねなり としゆき)
(2012年2月10日撮影、同11日付朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
1月9日まで勤務していた福岡市に拠点を置くNPO団体・アジア水中考古学研究所が熱海沖で潜水調査をしていることを知ったのは、昨年末。異動先の東京に現場が近く日程があえば、調査に同行させてもらえることになった。水深15メートル、水温14度。バディーには同僚の橋本弦カメラマンに来てもらった。彼とは2010年7月に沖縄で潜って以来だったが、ブランクを感じることなく水中でも意思疎通でき、問題なく取材が出来た。
取材場所(静岡)、徳川家(愛知)、製造場所(大阪)、調査団体(福岡)と日本各地に縁がある取材だったため4本社紙面の1面で掲載できた。2012年、水中初シャッターは、幸先のいいスタートが切れたと思っている。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「歓喜の雄叫び」
読売新聞東京本社写真部 松本 剛(まつもと つよし)
(2012年1月30日撮影、同日付け朝刊運動面掲載)
<取材者の弁>
日中から冷たい雨が降る1月23日は泊まり勤務の予定だった。夜には雪に変わるとの予報に喜ぶ5歳の息子の隣で、憂鬱な気分で防寒着を準備する私。モコモコのダウンの脇をシャカシャカ擦らせながら駅に向かっていると、ポケットの携帯電話が「錦織、全豪テニス8強入り」の号外メールを着信した。同時にデスクから連絡があり、突如、真夏の豪州・メルボルンに飛ぶことになった。
期せずして、全英、全仏に続きグランドスラムの取材は3大会目となったが、全豪で決定的に違うのが夜間照明完備で日没サスペンデットがないこと。お陰でセンターコートの最終試合は日付けを跨ぐのが普通となっていた。
29日の男子決勝は世界ランク1位と2位が互いに譲らず、第5セットにもつれ込んだ。5時間53分の熱闘を制した世界王者ジョコビッチ(セルビア)は喜びを爆発させ、ユニホームの襟もとに両手を掛けると渾身の力を込めて左右に引っ張った。ファインダーを覗く私は、恐らくコート上の彼も、真っ二つに破り捨てられるだろうことを想像していた。が、それは驚異の伸縮性を発揮し、ご覧の通りと相成った。
表彰式まで終わったのが午前2時過ぎ。帰国便の離陸まで4時間を切っている。テニス4大大会の歴史に残る、史上最長ファイナルマッチを見届けた余韻にひたる間もなく、厳寒の日本に向かうエコノミークラスの座席に日焼けした顔を埋める私であった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「復興の“竜”」
(2012年1月9日撮影、同日配信)
時事通信仙台支社
撮影・石塚マリコ(いしづか まりこ)
文・大高 正人(おおたか まさと)
<取材者の弁>
「竜がカメラマンを走らす」?-2012年の年明け早々、多くの報道カメラマンが宮城県気仙沼市の岩井崎海岸に押し掛けることになった。ここにある松が今年のえと「竜」のように見えると評判になり、年明けの話題として各社に取り上げられたからだ。その松、東日本大震災の津波で枝葉がほとんど流されたが、残った幹と枝は確かに「竜」の形に見える。この事に初日の出を見るために訪れた人たちが気付き、口コミや報道で多くの見物客が来るようになったという。
石塚カメラマンは他社よりやや出遅れる形となったが、「絵柄を工夫しよう」と夕暮れ時を狙いシルエットで表現した。キラキラと夕日が反射する海が美しい。昨年の3月11日、猛り狂った、あの海と同じとは思えない穏やかさだ。
ちなみに「岩井崎」という地名は「祝い崎」に由来しているそうだ。新しい年、被災地にこの海のような静かな平和が戻り、「昇り竜」のごとく復興のピッチが上がっていくことを願わずにいられない。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「やっと出た笑顔」
毎日新聞社写真部 梅村 直承(うめむら なおつね)
(2012年1月19日撮影、同日夕刊1面掲載)
<取材者の弁>
静岡県東伊豆町で行われる「雛のつりし飾りまつり」。今年で15回目ということもあり、各社の諸先輩方も手を付けたことのあるクラシックなネタだ。いつもの写真と変えたいと、28ミリ、F1.8の単焦点レンズ一本で勝負。開放値で撮ることで、つるし飾りをふんわりと表現しようという作戦だ。
例年、開幕前日に報道公開しており、和装をした地元幼稚園児が招かれ、モデルとなってくれる。集まった報道陣はタウン誌、地方紙記者、全国紙カメラマン、TV局など20名ほど。言い方は悪いが「おっさん」20人が、6歳の女の子2人を取り囲み、「笑って!」、「もっと笑顔で!」とはやし立てる。
女の子は時間が経つにつれ、ますます表情が固くなる。夕刊の締め切りが迫り焦るわたしは「じゃあ、にらめっこして!」と一言。2人は見つめ合い、はにかんで笑ってくれた。次は単焦点のレンズじゃなくて、なんかおもしろグッズでも持っていこうかな。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「市船の奇跡」
東京中日スポーツ写真部 澤田 将人(さわだ まさと)
(2012年1月9日撮影、中日スポーツ5面に掲載)
<取材者の弁>
サッカーの第90回全国高校選手権。市船橋と四日市中央工という伝統校同士による決勝は延長後半、市船橋の和泉竜司主将のゴールでついに決着がついた。和泉主将は勝利を確信し、拳を突き上げてベンチの選手の輪に飛び込んだ。歓喜の表情で出迎える仲間たち。劇的な瞬間だ。
しかしこの写真、手前左に肩を落とす四日市中央工の選手2人が写っており、視界がすっきりしない。あと少し左にいてくれれば、両校の明暗という表現ができたかもしれないが…。
私より内側の撮影位置を選んでいた共同通信のカメラマンが、四日市中央工の選手が写っていない、より出迎える市船橋の選手の表情が分かる写真を撮っていた。加盟各社に配信されたその写真を東京中日スポーツは選択し、1面のメーン写真にした。絵柄が劣っているとはいえ、自社の写真があるのに通信社の写真を使われるのは、とても悲しいことだ。
唯一の救いは、中部圏を中心に販売している姉妹紙の中日スポーツ5面に、私の写真が署名入りで使われたこと。さすが地元紙だ。たとえピンぼけでも、郷土の選手が写っている写真を選んでくれたのだろう。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「火花散る?握手」
(2012年1月6日撮影、未配信)
時事通信写真部
撮影・安藤 秀隆(あんどう ひでたか)
文・大高 正人(おおたか まさと)
<取材者の弁>
まだ、おとそ気分の消えない12年1月6日、東京都内のホテルで開催された時事通信社グループの新年互礼会で野田佳彦首相と自民党の谷垣禎一総裁が顔を合わせた。ともに「剛」というより、ていねいな語り口で知られる「柔」の政治家だが、ねじれ国会を背景に年内解散も取りざたされる中、両トップの“接触”に居合わせた出席者は耳目を集中させた。
まず、あいさつに立った野田首相は、焦点となっている消費税増税について、「国民の多くは議論を渇望している」と野党に協議への参加を要請した後、「目の前に谷垣総裁もお見えですがよろしくお願いします」と軽く先制のジャブ。続いて登壇した谷垣氏は「素案の段階で協議を呼び掛けるのは、連立の組み替えをやろうぜと言っているのといっしょ」と野田首相の送った秋波を切って捨て、「(消費税云々なら)国民との再契約が必要」とかねての主張である早期解散を改めて迫った。
谷垣総裁が壇上で“ファイティングポーズ”をとって降壇し、野田首相の前を通り過ぎようとしたその時。両氏はどちらともなく手を差し伸べ、握手した。新年の宴というおめでたい席でもあり、儀礼の域を超えない行為には違いない。とはいえ、そう遠くない将来、選挙という血で血を洗う戦いを繰り広げる運命の両雄だ。計量を終え、試合を控えたボクサー同士の握手のごとく見えない火花が散っているようにも感じられる。
しかし、両氏のわざと合わさぬ視線はファイト満々というより、どこか弱弱しい。野田首相率いる民主党は、昨年末に消費増税の是非などをめぐり9人が離党したばかり。谷垣総裁も党内をまとめ切っているとは言いがたい。両氏とも、選挙をはさんだ政局の流れや政界再編の道筋を「間違いなく自分がリードできる」という確信はないだろう。舵取りを誤れば、あっという間に濁流に呑み込まれて木っ端微塵になるかもしれない。
時事の互礼会には菅直人前首相も出席していた。あまりにも早い最高権力者交代のサイクル。今年の年末、この写真を見て「野田さんや谷垣さんにもこういう時があったんだ」と感慨にふけっていないとも言い切れない。2012年は激動の年になりそうだ。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「クレーンで除夜の鐘」
読売新聞東京本社写真部 永尾 泰史(ながお やすふみ)
(2012年1月1日撮影、同日付け1面に掲載)
<取材者の弁>
2011年12月31日、宮城県石巻市で東日本大震災後初めての迎春準備の様子を取材していた。山形から来たボランティアが年越しそばを提供するという情報を得て、石巻市湊町の松巌寺に行くと、一般的には新年を迎える頃に鳴らされる除夜の鐘を、午後2時から突き始めるという話を聞いた。
鐘は被災を免れたり、被害を受けて修復されたものではなく、山形県の会社から借りたということだったが、時間帯が早いので早版用にはなりそうだと思って取材した。写真を本社に送信後、この場所が市街地に近く、多くの被災者が集まりそうだったので、この場所で新年を迎える瞬間を取材することになった。
震災以来ほぼ毎月被災地を取材しているが、震災直後は自分や自宅が受けた被害について口が重かった被災者の方々が、自ら津波にあった時のことや被害状況について話してくれるようになったと思う。
それぞれに震災と向き合い、復興への第一歩を踏み出し始めたと感じる。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「スターの競演」
東京スポーツ写真情報システム部 菊池 六平(きくち ろっぺい)
(2011年12月18日撮影、未掲載)
<取材者の弁>
間違いなく2年後のブラジルワールドカップでも主役になるメッシとネイマールの若きスーパースター。そんな2人がクラブワールドカップの決勝で対戦するということで、世界中が注目したバルセロナ×サントスの舞台横浜国際競技場には約6万8千人もの観客が詰め掛けた。
もちろんカメラマンたちが注目しているのもメッシとネイマール。撮りたいのは迫力のゴールシーン、歓喜に沸く選手たち、そしてメッシとネイマール。
この大会は試合数時間前に撮影場所を決めなければならず、移動もできない。同僚とああだこうだと言いながら先着順で撮影位置を決定。
サッカーに限らずスポーツは予想できない。ただ選手のポジション、利き足やプレースタイルからある程度の推測はできる(勝手な願望とも言うが)。攻撃的なポジションのメッシとネイマールが試合中に絡む可能性はかなり少ない。絡むとしたらメッシが中盤でドリブルをした時、そしておそらく右から切れ込んでくる時じゃないか。そんな話をしながらそれぞれの撮影位置を決めて試合が始まった。
前半、自分とは反対のサイドでメッシが見事な先制ゴールを決める。そしてあっという間にバルセロナが2点目、3点目・・・・。今日はダメかな~と思い始めた後半途中、ドリブルを始めたメッシの背後からネイマールのモヒカン頭が見えた。待ちに待った瞬間。結局この試合で二人がボールを競り合った場面はこの1度くらいだったのではないだろうか。
ただのドリブルの写真。そこにいれば誰にでも撮れるだろう、特に何も考えなくてもそこにいたかもしれない。それでも考えたとおりに事が進み“ハマった”時は嬉しいものだ。すべては早朝から場所取りの為に並んでくれた後輩のおかげ。そんな彼もメッシの先制ゴールを素晴らしい位置で撮影できたのだから、やはり早起きは三文の徳である。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「家族の肖像写真」
朝日新聞東京本社写真部長 渡辺 幹夫(わたなべ みきお)
(2011年11月5日撮影、同6日、社会面掲載)
<取材者の弁>
「結婚式以来だな、女房の肩に手を回すのは・・・・」と照れくさそうに話すおじいさん。久々の記念写真の撮影に緊張する子どもたち。仮設住宅の集会所に特設されたスタジオは熱気に包まれる。それでもカメラを前にした家族はしだいに笑顔が広がった。
福島県相馬市で、11月から東日本大震災で避難生活を強いられている被災者らを撮影し、アルバムなどを贈る「頑張る家族の肖像」撮影プロジェクトが始まっている。 全日本写真連盟(田沼武能会長、約1万6千人)の主催で、相馬市内で希望者を募り、ボランティアのカメラマンたちが撮影を担当する。被災地では、津波などで大切な写真を失った人が多い。そこで、「ここから新しい歴史を作って」という願いを込めて写真を撮影し、アルバムの1ページ目に飾って無料で贈るプロジェクトを企画した。来年1月までに同市内の仮設住宅8カ所を巡回し、14回の撮影会を開く。
11月5日の初日は、同市柚木にある仮設住宅で、ここに住む7組の家族がカメラの前に立った。ひ孫まで一緒に並んだ家族もいれば、遠くに住む子や孫に見せたいと1人で写った女性もいた。化粧品会社の協力で訪れたプロがメークを担当。初回は写真家で全日写連会長の田沼さんと会員の榎並悦子さん、2人のプロが撮影した。とびっきりの笑顔でカメラに納まった。
久しぶりに化粧をしてもらい、「10歳ぐらい若くなったかしら」とほほえんだ木幡幾子さん(81)は1人で撮影。ポーズを指示されながらの撮影に「ちょっと緊張した。写真は仮設住宅に飾り、福島市に住む娘や孫が来たとき、こんなにきれいに撮れたよと自慢したい」と喜んだ。
12月半ばまでの間に、100組を超える家族が撮影された。撮影を支える地元ボランティアのほとんどが、津波の被害や原発事故による影響も受けている被災した人たちだ。しかし、写真の持つ力を信じてこのプロジェクトに参加しているその姿は光輝いて見えた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「タイ中部 まだ見えぬ陸/空から見た洪水」
朝日新聞社報道局写真部 林 敏行(はやし としゆき)
(2011年11月2日撮影、同3日、国際面写真グラフ)
<取材者の弁>
タイ中部の洪水取材で、バンコクに10月末から3週間あまり出張した。観光客が訪れる繁華街や、日本人が多く住む場所への浸水はなく、平穏が保たれている。連日の取材では、車高があるピックアップワゴンに乗り、かかと付きのサンダル、速乾性のズボンを着て、浸水した場所まで出かけた。また、4人乗りの小型機をチャーターした空撮取材では、バンコク北部に大量の水が残っていることが確認できた。
出張2日目。川のようになった道路で、膝まで水に浸かって写真を撮っていた。避難する住民を乗せたボートを撮ろうと、道路の端に数歩踏み出したら、側溝に足を取られた。あっという間に、顔の下まで水の中。2台のカメラを突き上げバンザイしながら水没していく私を、さっきまで被写体だった住民が2人がかりで抱え上げてくれた。おかげで、携帯電話を1台水没させただけで済んだ。
情けない日本人の「水没」がすぐに噂になったのか、ずぶ濡れで写真を撮っていると、多くの人から声をかけられた。その中に、2階に家財道具を上げて、完全に浸水した1階でくつろいでいる一家がいた。
母親に「どこから来たの?」と話しかけられた。日本だと答え、しばらく話していると、「今の状態はツナミみたい」と一言。そして、片言の英語で続けた。「ツナミの時、タイは日本を助けた。次は日本が助けて欲しい。現状を伝えて」
東日本大震災後、タイからは多額の援助が日本に寄せられた。昼食代やわずかな生活費を削って募金した人も多いという。日本で多くの人が、心を痛めて募金を寄せたのと同じように。
バンコク都心への浸水が回避できそうな一方で、浸水した場所では排水経路が確保できず、今も多くの人が被害を受けたままだ。多くの人が自宅を追われ、収入をたたれている。震災を経験した私たちができること何なのか、考えさせられた出来事だった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「市民ランナーが五輪に名乗り」
共同通信福岡支社写真映像部 矢島 崇貴(やじま たかき)
(2011年12月4日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
ロンドン五輪代表選考会を兼ねた福岡国際マラソンで、〝市民ランナーの星〟川内優輝選手が日本人トップの3位に入り、五輪代表に名乗りを上げた。
レース中盤に遅れた川内選手が、終盤に壮絶なデットヒートを繰り広げると、平和台陸上競技場に詰め掛けた観客は大興奮。大型ビジョンの映像に大きな歓声を上げていた。注目度の高い川内選手が日本人トップで力走するなか、ゴール脇で待つカメラマンの脳裏をよぎるのは、川内選手の代名詞とも言うべきゴール後の姿。完全燃焼型の川内選手はレースの度に力尽き、意識朦朧その場に倒れ込むのだ。時には車いすで、時に担架で運ばれる川内選手を取り囲むカメラマンの姿を、私もテレビで何度か目にしていた。
ゴールシーンを狙う200ズームを手にしながら、各紙カメラマンの神経はその代名詞を狙おうとワイドレンズに向いていたに違いない。全力疾走でゴールを駆け抜けた川内選手は予想通り倒れ込み、それを合図とばかりに一斉にカメラマンが殺到した。
最後まであきらめない姿勢。仕事をしながら練習を重ねる努力家。多少印象が先行してしまっているような気もするけれど、川内選手はそのキャラクターも相まって走る度にファンを増やしている。来年2月の東京マラソン出場も表明したため今後も注目され続けるだろう。
「この1枚」の写真は運び込まれたテントの簡易ベッドで、ねぎらいの言葉を掛けられ笑顔を見せる川内選手。彼と遭遇したのはこの時が初めてだが、なんだかこの人らしいワンショットが撮れたような気がした。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「“平壌の奇跡”」
共同通信社写真部 関根 孝則(せきね たかのり)
(2011年11月15日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
ブラジルW杯アジア3次予選で22年振りに敵地、北朝鮮の平壌で行われたサッカー日本代表の試合を取材した。言うまでもないが日朝間に国交は無く、拉致問題、核開発にミサイル発射と日本が譲歩できない問題が山積している中で行われた注目のゲーム。2泊3日の取材は一筋縄では行かない予想通りの展開となった。
今回は北朝鮮側が取材者を10人に限定したことで大きな波紋を呼んだ。取材ビザが下りなかった各社の怒りは察して余りあり、その中で我々が取材機会を得られたと知った時は正直身震いした。
実は取材できるとなってからが大変だった。現地の取材環境、段取りに分からないことが多すぎたのだ。写真送信、移動手段、経費など事前に現地視察した日本サッカー協会の担当者に聞いても全くらちが明かない。同僚の荒木甫浩カメラマンと私は日々強まるばかりのプレッシャーと少々の不安を感じつつ平壌へ向けて日本を飛び発った。
事前にあらゆることをシミュレーションした。写真送信のことはもちろんだが、例えば飛行機が平壌に到着できないケース、スタンドに観客がいなくて空っぽだったら・・・、選手や関係者、サポーターが・・・などなどここでは書けないようなことまで想定し、できることは何かを考えた。相当に奇天烈なこともあり得るのではないか、と経由地となった北京の夜は遅くまで話が尽きなかった。
そのお陰で“想定内だった”とは言い過ぎかもしれないが、北朝鮮入国時に選手が4時間、取材陣が5時間待たされたこと、試合開始1時間前まで競技場に入れなかったこと、競技場から写真を送れると確認できたのが試合開始直前だったことなど諸々の“異常”事態を「北朝鮮流のもてなし」と冷静に受け止めて対処できた。
結果として試合は満員の競技場で予定通り午後4時過ぎにキックオフ、写真配信は案内通り午後7時半までにスタートできた。本当は自分たちを褒めてあげたいとの気持ちが少しある。しかし長時間電話連絡がつかなくなる場面があり、加盟社から殺到する問い合わせの対応を迫られた本社デスクが冷や汗ものだったことなど一連の出来事を振り返ると、大過なく終了した今回の取材は“平壌の奇跡”だったのかもしれないと今は思う。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「オリンパス損失隠し」
毎日新聞社写真部 久保 玲(くぼ れい)
(2011年11月8日撮影、9日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
記者会見の取材は、会場に入るところから始まり、終えて出て行くまで続く。会見の内容を象徴するようなカットをいつ切れるかが勝負どころだ。記者会見の写真取材でも特ダネと特落ちがある。その一瞬を捉えるためにファインダーから目が離せない。
例のオリンパス会見の取材に行った。これまで「適切な支出」と説明してきたオリンパスが、過去の有価証券の損失隠しを一転して認めた。1人で会見に出席した高山修一社長は何度も頭を下げ、終始口を真一文字に結び記者の質問に答えた。その表情をできるだけ反映させたいとアップで狙い続けた。一般的には、会見者を正面のほか左右などからまんべんなく狙うが、今日は「アップだ」と狙いを定めた。
ただ損失隠しの詳しい経緯などについては「今は申し上げられません」を繰り返すのみ。厳しい会見を表す厳しい表情が撮れたと思う。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「パリコレってタイヘン」
読売新聞東京本社編集局写真部 伊藤 紘二(いとう こうじ)
(2011年9月27日撮影、28日朝刊3社面掲載)
<取材者の弁>
初の海外出張でしかもヨーロッパは初めての地。ミラノ、パリのコレクションを取材した。パリの初日のショーはエッフェル塔の中で行われた。一見、華やかそうな取材に思えるのだが、取材の舞台裏では、想像を絶する場所取り争いが繰り広げられている。
いい位置で撮影するために2時間前から会場前に並ぶのは当たり前。会場入りするとさらにがく然とする現実が待ち受けている。地元のカメラマンたちは、自分たちのアシスタントを先に会場入りさせ、ガムテープとマジックで名前を書き、場所を確保しているのだ。そのため、「おいしい位置」はすべて彼らに押さえられており、私に残されたのは、「後ろの高い位置」か「端っこ」。それでも、少しでも低くて中央寄りの良い撮影位置に移動するため、並んで、はじかれ、打ちのめされ、現地で長年活躍しているフリーの日本人カメラマンの方々に励まされ助けられ、また並んで、またはじかれ、また打ちのめされる日々。「紛争地での取材の方がまだマシだ」とつぶやく読売の先輩部員がいたのもうなずけた。
読売新聞社は2000年から、ミラノ・パリコレクションに写真部員を派遣してきた。初代のパリコレ写真部員は、場所取り、踏み台の役割を果たしている日本のスタンダードとなっている「脚立」をパリコレで広めた。当時、背の高い欧米人の後ろから悠々と撮影していたそうだ。日本の脚立は、軽くて丈夫、持ち運びに便利ということで、コレクションカメラマンの間で脚光を浴び、にわかに脚立の需要がわき上がったという。「脚立を売ってくれ」という人もいたほどだ。
ところが、今では脚立ブームも下火に。なぜならば、脚立だと、横に広く場所を取られる上に、高さの調整が極端で、融通が利かない。今では、多くのカメラマンは箱を持ち込み、箱の上に自作のブロックを積み上げる「積み木方式」が主流になっている。どうしてもレンズが抜けないときは「積み木」の様にブロックを積み重ね、足場を確保する。この積み木方式を考案したのも、現地で活躍するフリーの日本人カメラマンなのだという。「すごいぞニッポン!!」
かつては場所取りで殴り合いのけんかをして、現場に血が流れることもしばしばあったコレクション取材。先に会場入りして、場所取りを済ませてしまうというのも、無用な争いを避ける、コレクションカメラマンたちが長い歴史を経て生み出した一つの智恵なのだ そうだ。妙に納得してしまったのは私だけでしょうか・・・。
次にミラノ・パリコレクションに取材に行く人たちよ。是非、打ちのめされてください。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「大川小学校に鎮魂の明かり」
朝日新聞東京本社写真部 飯塚 悟(いいづか さとる)
(2011年10月16日撮影、18日社会面掲載)
<取材者の弁>
私はこれまで国会写真記者クラブに席を置いていたため東日本大震災の被災地を取材で訪れたのは震災から7カ月以上が経過した10月の半ば過ぎだった。
宮城県の被災地では、がれきは一定の場所に山積みされ、家の土台だけが残る更地となった場所も多く見られ復興へ向けた工事関係者や工事車両の数が目立っていた。そんな中でも、被災した人たちと話す機会も多く、何度も質問をされたであろう私の質問にもいやな顔をすることなく多くの人は答えてくれた。
津波で74人の児童が死亡、行方不明となった石巻市「大川小学校」について語る人が多かった。そこで、校門前の祭壇に太陽電池を利用した明かりがともされたという情報があり、大川小学校を目指した
立ち入り禁止の校舎前の校門に祭壇できていて、震災から7カ月が過ぎているというにもかかわらず多くの花束が手向けられていて、その数の多さに驚いた。土手向こうには北上川が流れ、心地よい風が抜け、祭壇の大きな風車が音を立て回っていた。
日没とともに辺りは急に暗くなり、2灯の明かりがともった。それまで震災以降、街灯もなくなった大川小学校周辺はみるみる暗闇に包まれていた。日没後学校前に来た車は宮城県警のパトカー1台。仕事帰りに必ず寄ると言い、2人の警官は手を合わせた。
それから待つこと約1時間。暗闇に1台のバンが近づき、中から2人の人影
紙面掲載された2人の子どもを失った鈴木義明、実穂さん夫妻だった。毎日訪れている鈴木さんは、花の水を代え、祭壇を整えながら子どもたちに声をかけていた。実穂さんの友達は今でも夜に祭壇を訪れ、泣きに来ているという話も聞いた。
津波がひいたときには全ての集落がなくなっていたこと、震災後しばらくは学校に来るのも道が悪く大変だったことなどいろいろな話を聞かせてくれた。取材を終え、鈴木さん夫妻が立ち去ると辺りはまた暗闇に包まれた。校門から少し離れた車に戻るのも大変なほど真っ暗だった。
実穂さんが話していた「この明かりで子どもたちも迷わずに戻って来られる・・」という言葉を聞き、残された人たちには、このほんの小さな光で癒やされていると思った。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「中日・落合監督 セ・リーグ連覇の胴上げ」
東京中日スポーツ写真部 佐藤 哲紀(さとう てつのり)
(2011年10月19日撮影、20日付1面掲載)
<取材者の弁>
中日ドラゴンズの優勝、そしてそれを最も象徴する監督の胴上げ。これは我が社にとっては特別な意味を持つ。紙面での大展開はもちろん、関連出版物や販売促進用のグッズ、各地で開かれる写真展などなど。多くの人の目にさらされることになるので絶対に失敗は許されない(もっとも失敗が許される仕事などないのだが…)。
試合当日の撮影ポジションはライト外野席。普段は一般客席でもあり、自身初めて入る場所だ。もちろん、球場にいる撮影者は自分だけでない。心強い先輩も、ちょっと心配な後輩も一緒だ。試合は同点のまま10回裏へ。試合時間は3時間半を越えているので、ことしの〝節電ルール〟では、この回で終わり。10回裏を抑えれば引き分けで優勝が決定する状況だ。
「露出はシャッタースピード優先じゃなくてやっぱマニュアルだな」「感度を上げてシャッタースピードを速くした方がいいよね」「いや、でもノイズ増えるのイヤだしなぁ」「どうすっかなぁ」。1/800、1/640,1/500、ISO1600、2000、2500、と数字がぐるぐる頭の中を巡り、今さらと思うようなことが心配になってくる。
そうこうしているうちにマウンドは浅尾投手のまま2死一塁。緊張の度合いは最高潮を迎え、心臓バクバク。軽く吐きそうになる。あれ?マウンドに森コーチが行ったのに押さえのエース・岩瀬投手に代えないの?浅尾投手のまま?マジで?と思ってる間もなく、浅尾投手が筒香選手を三振に仕留め、ゲームセット!
ベンチから飛び出す中日ナイン、マウンドでの歓喜のシーンを一脚につけた400ミリで撮影。すぐにカメラボディを三脚に設置した600ミリへ付け替えて胴上げに備えた。しばらくしてベンチから落合監督が登場。そして胴上げ。合計で6回宙に舞った。必死で撮った。監督の顔が見える!! これ僕んとこハマってるんじゃないの?
いや、でもセンターの席から狙ったコマもいいかもしれん。内野の最上部席からも高さがあるから面白いかもなぁ…などと必死でピントを合わせながら思った。すぐに撮影した写真を確認。落合監督の笑顔が見えるし、ピントも合ってる!よかった!自分のポジションでの責任は果たした!ホッとしたのもつかの間、すぐに写真を本社に送りながら祝勝会の会場へと向かった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「岡崎、見事!ヘディングゴール」
共同通信社写真部 荒木 甫浩(あらき もとひろ)
(2011年9月6日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
サッカー取材でのゴールシーンの写真。どのレンズでその瞬間をものにするか、非常に悩ましい問題だ。試行錯誤の末、私の場合はキヤノンの40ミリと70-200ミリズーム(テレコン無し)の組み合わせを選択している。
ウズベキスタン・タシケントで行われたサッカーW杯アジア3次予選の第2戦。前半8分、先制を許した日本は苦戦気味。特に「これ」といったシーンがないまま後半へ。そして後半20分、内田の右クロスが上がった。70-200ミリズームのファインダー内で私の目は左から飛び込んだ李を追っていた。てっきり頭で合わせたと思った。しかし、同点ゴールを決めたのは、その奥でかなり低い位置からダイビングヘッドで合わせた岡崎。
決して狙って撮ったものではない。左指でピントを送ったかどうかも定かではない。その証拠に次のコマに写った岡崎は完全にピントを外していた。ただ、画角の広いレンズを選択していたためにたまたま写っていた一枚である。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「脱北者の移送現場を発見」
共同通信社写真部 桑名 敏之(くわな としゆき)
(2011年9月13日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
石川県・能登半島沖で見つかった脱北者を保護した海上保安庁の巡視船を探すため、夕闇が迫る小松空港からフライトした。しかし事前に情報があった金沢港付近に船影が見つからず途方に暮れているその時だった。「沖合に船らしき影があります」。百戦錬磨のパイロットがその視力を活かし20㌔以上沖合の船影を見つけた。近づくと2隻の巡視船「ひだ」と「えちご」が並んで航行しその間を海保のヘリが往復している。
迷う間もなく「えちご」の艦上に降りる海保ヘリに近づきレンズを向けた。日没間際で見づらいが、顔を隠した人たちがヘリから降りて海上保安官に付き添われて船内に消えていく。これはもしや脱北者を移送しているのでは?巡視船を発見してわずか5分の出来事だった。
撮影後すぐにデスクに連絡すると「脱北者を他の船に移すという情報はない」との返事。「とにかく写真を見てください」と送信。しばらくすると「確認取れた、フロント(共同通信社の1面用写真候補)で行くぞ」と連絡が。現場がやはり一番強い。あらためて実感した瞬間だった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「テロ10年目の祈り」
産経新聞東京本社写真報道局 奈須 稔(なす みのる)
(2011年9月11日(現地時間)撮影、同12日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
2001年9月11日に発生した、「米中枢同時テロ」。10年の節目を迎えたニューヨークの世界貿易センターや、バージニア州のペンタゴンなどを中心に取材を行いました。この写真は、9月11日の夜、テロ事件の舞台となった世界貿易センターに隣接する消防署で撮影したものです。テロでは、大勢の警察官や消防署員も犠牲になっており、犠牲者の遺族や友人、そして市民が、節目の日に花束を手向け涙を流していました。ニューヨークは10年前と同様に、追悼と愛国に染まっていました。
「9/11」では、約3000人の民間人が犠牲となり、アメリカはアフガニスタンを空爆し、イラクとの戦争を行いました。テロは「世界の針路を変えた」ともいえます。しかし、サダム・フセインとビンラディンの首をとる過程で、米兵を含め22万人以上が命を落としたのも事実です。
唯一の超大国と言われたアメリカが内包する問題や矛盾。高い失業率や財政赤字、進まないイスラム社会との共存など、「アメリカの通った10年」を写真で表現したいと考えました。
思えば10年前、テロ発生直後にニューヨークに入り、約2カ月間、取材を行いました。そして2002年には「テロ1年」を取材。私にとってのライフワークは今回、ようやく完結しました。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「東京湾の『脚立釣り』再現」
東京新聞写真部 澤田 将人(さわだ まさと)
(2011年9月10日撮影、同日夕刊1面掲載)
<取材者の弁>
1960年代に東京湾から姿を消した特殊な釣りの手法「脚立釣り」が1日限定で復活するというので取材に向かった。海中に立てた木製の脚立に釣り師が乗ってアオギスを狙う釣り。江戸時代後期に東京湾内の干潟で見られ、初夏の江戸の風物詩として浮世絵にも描かれた。
取材前は、いったいどこで写真を撮るのか、どんな写真が撮れるのか想像ができなかった。海に入ることも想定してサンダルと短パン、着替えを用意した。会場の千葉県木更津市に到着すると、脚立を立てる場所が沖合約1キロのはるか遠くで、小船で現場に赴いて撮影することが分かった。海に入る心配は取り越し苦労に終わった。
船に揺られること数分。遠浅で水深約1.2メートルの海中に脚立5脚が並び、帽子をかぶった参加者が釣り糸を垂らしていた。何とも不思議な光景だ。東京湾アクアラインが背景に写る方向に回り、5脚が1枚の画面に入る瞬間を狙って船を何度も往復させた。
夕刊に間に合わせるため早めに現場を切り上げた。短い時間だったこともあり、魚が釣れた瞬間をしっかりと目撃することはできなかった。残暑厳しい直射日光の下で、長時間脚立に乗り続けた釣り師たちの釣果が気になるところだ。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「相撲でも一本背負い」
時事通信社写真部 松井 勇樹(まつい ゆうき)
(2011年9月15日撮影、このカットは未配信)
<取材者の弁>
大相撲2階席からの取材にあまり技術はいらない。必要なのはただひたすらに集中力である。秋場所5日目、前日に続いて東39番の報道席に陣取り、中入り後の取組を淡々と撮影していく。チェコ出身隆の山が5連敗を喫し、前日に足を痛めた舛ノ山は休場。「もうすぐ半分、そろそろ勝負審判交代だな」と感じる頃には、若干の睡魔にすら襲われていた。
次の取組は東・磋牙司(西前頭9枚目)に西・栃乃若(同7枚目)。2勝2敗同士。前半戦のよくある取組の一つだ。立ち会い、優勢は突き押しで攻める栃乃若。守勢の磋牙司は腕をたぐって勢いを殺そうと必死だ。手前の土俵際もつれる2人。的が大きくピントが合いやすい分、とっさの技でオートフォーカスが後ろに抜けるととんでもなく恥ずかしい写真になってしまうという、まさにその緊張の一瞬。投げを打ち合うかに見えた2人を追いながらシャッターを押しこんで連射する。
次の瞬間、栃乃若の足が高々と天を指し、体は一回転。秒間10コマに間違いなく記録された。心の中で「一本!」と叫びつつ、当の磋牙司はと見れば、四股を踏んだような体勢で腕を抱え込んだまま「してやったり」の表情。後で聞けば、「一本背負い」が決まり手となるのは幕内ではなんと7年ぶり。ちなみに磋牙司は角界一、二を争うチビッコ力士だそうで、正に「柔よく剛を制す」?いやあ、いい物見せてもらいました。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「濁流の中、ロープを手に道路を渡る住民たち」
読売新聞大阪本社写真部 枡田 直也(ますだ なおや)
(2011年9月5日撮影、同日夕刊1面掲載)
<取材者の弁>
9月3日、台風12号により甚大な被害の出た和歌山県那智勝浦町へ入った。
翌4日、前日には向かうことの出来なかった幹線道路の水没や崩落で孤立した市野々地区を徒歩で目指した。途中の地区で陸上自衛隊による住民の救助などを取材しながら、土砂が堆積し一部が川に崩れ落ちた県道43号線を進むと、白く飛沫をあげる激しい濁流が道路を遮っていた。
地区の人の話では前日は腰より上までの水量があり、とても渡ることが出来なかったという。その道路に、警察官がロープを渡し始めていた。水量は膝下ほどになってはいるが流れる勢いは強く、ロープをつかんでいても足元はふらつき、ともすれば濁流に体を流されそうになる。そんな危険を伴う状態でも、住民たちは次々にロープを手に濁流を渡った。
ある人は孤立集落に運ぶのであろう大きな荷物を背負い、ある人はふらつく女性を支えて、ある人は老人に声を掛けながら。それぞれの目的のために、皆が対岸を目指して歩いていた。
今回の台風では多くの人命と、生活の場が失われた。今も被災地の全面復旧の目途はたたないという。1日も早く、元の地域で再び住民が暮らせる日が来ることを願わずにはいられない。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「秋めく富士」
静岡新聞社 編集局写真部 藤井 晴雄(ふじい はるお)
(2011年8月30日撮影、同日夕刊1社掲載)
<取材者の弁>
冬山の雪が積もった富士山の航空撮影は、比較的天候が安定しているため撮影機会が多く資料としても撮影はしてあるが、夏山の富士山は、天候が不安定で、朝、くっきり見えていても1時間後には雲にすっぽりと隠れてしまうことがよくある。
8月に入って夏山富士の撮影機会を待っていたが、なかなか気象条件が悪く30日になってやっと全景が見えた。高度4500㍍からは、真っ青な空にすじ雲が現れ「秋めく富士」が撮影できた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「中国高速鉄道事故」
朝日新聞社写真センター 樫山 晃生(かしやま てるお)
(2011年7月24日撮影、7月25日朝刊1面)
<取材者の弁>
2011年7月23日夜、中国浙江省南部の温州市で高速鉄道の追突事故が発生。出張中の上海からタクシーをチャーターし500キロを急行した。温州に到着したのは夜明けすぎ。鉄道高架下に脱線した車両が落下し、1両が垂れ下がったままの状態だった。下からでは衝突した部分の様子が分からない。高架脇に現場を俯瞰できそうな高い山があるので登ってみることにした。
主要な道は警察や軍隊が封鎖しているため、畑の間の細い道を進んでいった。夜通し降り続いた雨のせいで地面はぐちゃぐちゃ。肥やしのにおいもきつい。泥だかなんだか分からないものにまみれながら山頂にたどり着き、撮影したものが紙面を飾った。
この取材で改めて感じたのは中国での貧富の差だ。最新鋭の鉄道が走る高架の下の村は完全に開発から取り残されていた。高層ビルが立ち並ぶ上海から来たためいっそう強く感じたのかもしれない。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「うごく七夕」
朝日新聞社写真センター 森井 英二郎(もりい えいじろう)
(2011年8月6日撮影、8月12日朝刊特設面)
<取材者の弁>
震災から5ヶ月が経とうとする中、がれきが残る岩手県陸前高田市の中心部を「うごく七夕」の山車が進んだ。山車が被災し、中止の話も出たが、「こんな時だからやろう」という地元若者の声が祭りを開催に導いた。
私は毎月11日の前後には必ず岩手県で最多の死者が出た陸前高田市を訪れる。山のようになっていたがれきもだいぶ減った。その分、殺風景になった景色が、もの悲しさを感じさせた。その中を華やかな飾りを付けた山車が進む。お囃子の音が加わり、震災の悲劇を少しでも忘れさせてくれた。きっと被災者の人も、こんな心の安らぎを味わいたかったのだろうと思った。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「石巻川開き祭り」
毎日新聞社写真部 石井 諭(いしい さとる)
(2011年7月31日撮影、8月1日朝刊1面)
<取材者の弁>
震災で壊滅的被害を受けた宮城県石巻市の旧北上川で、犠牲者の冥福を祈って約1万個の灯籠(とうろう)流しが行われた。石巻市では、7月29日現在で死者3149人、行方不明890人。「石巻川開き祭り」の一環で、犠牲者の名前が読み上げられる中、残された家族らのメッセージが書き込まれた灯籠が流された。
この日初めて石巻を訪れた私は、川辺に集まった人の多さに驚いた。それまで岩手県の一部の被災地しか見てこなかった私の頭の中には「被災地=全て失われた街=人のいない街」という図式が出来上がっていたのだ。
死者を悼む人。全国から集まった支援者。警備関係者。見物人・・・。「人が集まる」という単純なことが、次のステップに進む可能性を確実に秘めていることを、被災地で初めて実感した。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「暑さに負けない」
時事通信社写真部 家根 和一(やね かずいち)
(2011年6月24日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
8月に入ってやや暑さが和らいでいるとは言え、節電の夏、猛暑が身にこたえる。6月24日には早くも暑さの名所?埼玉県熊谷市でぐんぐん気温が上昇。国内観測史上初めて6月に39度台を記録した。夏生まれの私は暑さには強い方。夏バテをしたこともないし、趣味のサイクリングでも汗だくになって乗れるこの季節は大好きだ。
しかし、熊谷の暑さには参った。日差しだけでなく、吹いてくる風までが熱い。特大のドライヤーの前に立たされているようで、息をするのもつらいくらいだ。JR熊谷駅から20分ほど歩き、百貨店「八木橋」前に到着。ここは入り口付近に気温を表示する看板を設置しており、ハンカチで汗をぬぐいながら歩く通行人とからめて撮るのは言わば定番の絵作り。
そこへ、かねてから節電対策のネタ集めをしていた後輩カメラマンから耳よりの情報が入った。市内の小学校で熱中症予防グッズ「クールスカーフ」が配布されるという。スカーフはポリエステルなど水が蒸発しやすい素材を使用。水にぬらし、気化熱により冷却効果が生まれるそうだ。
突然の申し入れにも関わらず、校長先生にも快く取材に応じていただき、配布されたばかりのスカーフを水に浸し、首や頭に巻く児童たちを首尾よくカメラに収めることができた。猛暑の雑感写真だからといって暑苦しい写真では読者もげんなりしてしまうだろう。この1枚は子どもたちの笑顔が一陣の涼風のようで、配信先の契約紙にも好評をいただいたようだ。
私はといえば、取材後、案内された校長室でごちそうになった冷たいお茶が旱天(かんてん)の慈雨のようで、今でもそののどごしが鮮やかによみがえってくる。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「復興願うともしび」
共同通信社写真部 泊 宗之(とまり むねゆき)
(2011年7月27日撮影、同日配信・産経28日1面)
<取材者の弁>
乗客460人を乗せた豪華客船「飛鳥Ⅱ」が、ことしも岩手県の大船渡港に入港した。北海道や東北各地を巡るクルーズで、大船渡への寄港は先代の飛鳥から数えて20年連続24度目。震災で津波など大きな被害を受けた大船渡への入港も一時危ぶまれたが、例年通り寄港し、復興を願ったキャンドルイベントなどが開かれた。
大船渡の夏の夜空に浮かび上がる巨大客船と幻想的なキャンドルのともしび。一見、ここが被災地かと目を疑うような華やいだ光景も、周りを見渡せば未だ大量のがれきが街を覆い、震災の爪痕が深く残る。
被災地に足を運ぶ度、厳しい現実を目の当たりにしながら自然とカメラは子どもの方へ。母親とイベントに来ていた姉妹(写真)は、「早くみんなに笑顔が戻りますように」とともしびに願いを込めていた。
キャンドルの柔らかな光に包まれ、ほんのりオレンジ色に染まる笑顔の女の子。被災者だけでなく、取材する自分も子どもたちの笑顔に幾度となく助けられた。キャンドルのともしびと同じように輝く子どもたちの笑顔が、震災で大きな傷を負った市民の希望の光になることを願わずにはいられない。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「やった!なでしこ世界一だ」
共同通信社・大阪写真映像部 水野 陽介(みずの ようすけ)
(2011年7月17日撮影=現地時間、同日配信)
<取材者の弁>
サッカー女子W杯の決勝。夢の舞台で「なでしこジャパン」が優勝した。過去の大会では、決勝トーナメントに進出したのが1回。あとはすべて予選敗退だった。今大会では日替わりヒロインが登場し、決勝戦を前にした練習でも笑顔が絶えず、チーム内の雰囲気は最高だった。
決勝戦では開始直後から世界ランク1位の米国の猛攻を受け、いつゴールを奪われてもおかしくない状況だった。後半、ついに先制ゴールを奪われ、会場の雰囲気が一気に米国優勝へと流れた。米国には過去24戦して3分け21敗と一度も勝った事がないため、私自身ここまでかと正直思ってしまった。
しかし、後半36分にクリアミスのボールを宮間がゴール左隅に同点ゴール!派手に喜ばず、すぐボールを拾ったのを見て、まだ全然あきらめていないのだと感じ、自分自身も気を引き締めた。
準々決勝のドイツ戦に引き続き、延長戦へ突入。延長前半12分に米国のエース、ワンバックにヘディングで勝ち越しゴールを奪われた。沢とともにMVPと得点王候補だった同選手の得点に、米国優勝に加えMVPと得点王はワンバック選手!という米国にとって完璧なシナリオが出来たと思った。
そのまま延長後半に入り、残りが5分ほどになった時、米国のGKが足を痛めてピッチでもがいていた。その治療で時間が過ぎていく中でも不思議と日本イレブンは落ち着いているように見えた。焦っている選手など一人もいなかった。その直後のCKで沢が同点弾を決めた。
勢いに乗ってPKに臨んだ日本と同点に追いつかれた米国。その時すでに勝負は決まっていたのかもしれない。優勝を決め、駆けだすイレブン。MVPと得点王に選ばれた沢選手。金色の紙吹雪が舞う中、W杯を掲げ大喜びの日本イレブンなど、すべてが現実とは思えない光景を生で見られた事を幸せに思う。
帰国したなでしこジャパンを成田空港で迎えた報道陣は同空港史上過去最高の260人という。中部国際空港から出発した時の10人前後と比べると、いかに偉業を成し遂げたかがわかる。
しかし今回、なでしこジャパンに1カ月弱同行して、華やかな部分だけではなく普段は仕事をしながら夜練習している選手がいるなど、決して待遇は恵まれていない事を知った。
「ブームはすぐ過ぎ去るのでこれからが大事」と宮間選手が記者会見で言っていたが、私も一過性のブームではなくこれからどんどん人気が出ていく事を願っている。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「なでしこ沢ガッツ、W杯決勝へ」
共同通信社・大阪写真映像部 水野 陽介(みずの ようすけ)
(2011年7月13日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
サッカーの女子ワールドカップ(W杯)で、今まで一度も勝った事のなかった優勝候補のドイツを準々決勝で破り、波に乗るなでしこジャパン。
4万人を越える観衆の中、決勝進出をかけた大一番で相手は比較的相性のいいスウェーデン。勝てばメダルが確定する大事な試合で沢が見せくれた。
前半、自身のパスミスから先制点を奪われ嫌な雰囲気が漂う中、初先発の川澄が同点ゴール。そのまま後半に入り、次の1点が勝負を分けるシーンで沢が輝いた。前線に入ってきたボールを安藤とスウェーデンのGKが交錯するようになり、ボールがこぼれた瞬間に沢が頭で値千金弾を決めた。
私は一瞬ボールの行方を見失い、シャッターを押すタイミングが少し遅れた。次の瞬間、背中を向けて駆けだす沢。先制ゴールを決めた川澄に飛びつくも背中で顔が見えない。
ファインダーをのぞき焦りながら「こっちを向いてくれ」と願った。次の瞬間、沢を下で支える川澄が180度回転したのだ。そのおかげで勝ち越し弾の沢、2得点の川澄に駆け寄るイレブンの姿が一枚に収まった。
思い出してみると、グループリーグのメキシコ戦で沢がハットトリックした時も川澄に抱きつき、川澄が回転してくれていい写真が撮れた。2度ある事は3度あると信じて、過去24戦して3分け21敗と一度も勝っていない国際サッカー連盟(FIFA)ランキング1位の米国との決勝戦に臨みたい。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「古民家守る面格子」
日本農業新聞写真部 山田 晃太郎(やまだ こうたろう)
(2011年5月23日撮影、同26日1面掲載)
<取材者の弁>
木造家屋を地震から守る技術を取材した。間伐材を格子状に組んだパネル「耐震面格子パネル」を家の中の柱まわりに取り付ける。地震がくると、格子の部分が揺れに合わせてしなることで力を逃がし、家を守る。
取材のきっかけは、東日本大震災の発生から5日後の3月16日に、宮城県美里町で撮影した、地震で崩れた木造の牛舎だった。この農家宅では、牛舎の2階部分が崩れ、9頭が圧死した。息絶えた牛が運び出される様子を撮りながら、建物がもう少しだけ地震に強ければ、こうはならなかったのではと感じた。
日本農業新聞の読者である農家は、住居や納屋、畜舎などさまざまな木造家屋に囲まれて暮らしている。築100年を超えるような「古民家」で暮らす人も多い。知り合いの農家にも、断続的に続く余震に「うちの家は大丈夫なのか?」と口にする人がいた。
耐震面格子パネルは、被災地から帰ってきたあと、古い木造家屋を活かすような耐震改修はないものかと思っている中で見つけた話だった。
取材をして興味深かったのが、地震を受け入れ、一緒に揺れることで被害を少なくする伝統家屋の考え方だ。地震を拒絶し、揺れないようにして家を守ろうとする現代建築との違いが浮き彫りだった。
今なお全国各地で大きな地震が続く。伝統家屋の地震との付き合い方が、震災後の一人一人の暮らしの参考になるのではないかと思う。
--------------------------------------------------------------------------------------------

 【写真】気仙沼
【写真】気仙沼
題名「小学校に避難した子供たち~南三陸」
産経新聞写真報道局 植村 光貴(うえむら こうき)
(2011年3月19日撮影、「産経フォト」で公開中)
<取材者の弁>
産経新聞の写真サイト「産経フォト」のコンテンツの一つ「パノラマ写真館」では、東日本大震災の360度パノラマ写真を100枚以上アップしている。このパノラマ写真は、日本より海外での反響が大きかった。米国MSNBCやシンガポール、ドイツ、インドなど多くの国のMSNサイトが掲載。またゲッティ・イメージズやドイツのシュピーゲル紙にも配信した。「FUKUSHIMAのパノラマはないか」との問い合わせがくるほどだった。またフェイスブックなどの書き込みがかなりの数になっていたと聞いている。
パノラマ写真は、海外のマスコミでは時々使われている。2年前のオバマ大統領の就任演説ではニューヨーク・タイムズ紙、今年4月にはBBCとゲッティ・イメージズが英国のロイヤル結婚式を撮影。昨年のハイチ大地震ではCNNがパノラマ動画で取材している。
日本のマスコミでは産経のほか、朝日新聞と一部地方紙のサイトがパノラマ写真を公開しているぐらいで浸透していないのが現状だ。海外のパノラマ写真家からは「日本は、カメラは先進国だがパノラマ写真に関しては後進国」といわれているという。
パノラマの技術は「企業秘密」と思われがちだが、ネットで調べると撮影方法は出ている。全方向に撮影した複数枚の写真をパソコンを使ってつなぎ合わせているだけ。産経のパノラマは、主に魚眼レンズを使用しているが、場合によっては広角や400㍉望遠レンズを使うことも。通常4-7枚、多い時で100枚以上をつないで「1枚」の写真にしている。
産経新聞がパノラマ写真の撮影を開始したのは、2009年2月。これまで、硫黄島の壕の中や首相官邸、ジャンボ機のコックピット、サッカー日本代表戦、水着の女性など硬軟取り混ぜてさまざまなジャンルを500枚以上アップしてきた。今年2月には、南極観測隊に同行した芹沢伸生記者が昭和基地や南極大陸でパノラマ撮影を行い、代表配信をしている。
今回の震災パノラマ、当初は現場の写真記者に抵抗感があった。パノラマ写真はマウスで自由に視点移動できるため、ユーザーは遊ぶような感覚で写真を見ることになる。「被災地を本当に撮ってよいのか。不謹慎では」との声も一部にはあった。
現場には「サイトに公開するかどうかは、こちら(本社)で判断するから、とにかく撮るように」と指示したのを覚えている。これまで東北各地に散らばった東京・大阪本社の写真記者総勢10人以上が通常の紙面用の取材の合間を縫ってパノラマ撮影を行っている。
ツイッターなどの書き込みを見ると「本当に現場に立っているようだ」「被災状況が良く分かる」などの声がたくさんあった。今までの新聞写真では伝えきれていない現場の臨場感を、パノラマ写真として後世に伝え残していくことも写真記者の役目だと考えている。今後も復興が完了するまで撮影していくことになるだろう。
参考:「産経フォト」(http://photo.sankei.jp.msn.com/)
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「ソユーズロケット、姿現す」
共同通信社写真部 佐藤 優樹(さとう ゆうき)
(2011年6月5日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
古川聡さんら3人の宇宙飛行士を乗せるソユーズロケットが発射台に起立。左右のアームでがっちりと固定された。
朝4時すぎ、早すぎる朝食を口に押し込みホテルを出発。オレンジに色に染まった荒野を走り、カザフスタン・バイコヌール宇宙基地のソユーズロケット組立工場に到着した。初夏を思わせる気候で、風が心地よい。
しばらくすると、工場の扉がゆっくりと開く。横倒しの状態で機関車にけん引されるため、巨大なエンジンの噴射口が眼前に広がる。圧倒されながらも、時速5キロの超スロースピードのため写真は撮り放題。おまけに柵もなく、銃を持った警備も立っているだけだったのでロケットに触れられそうな距離だった(触ったら間違いなく撃たれていたと思うが…)。
その後、何度かスイッチバックを繰り返し、約10キロ先の発射台へ。設置されたその巨体は、多くの関係者に見守られる中、ゆっくりと持ち上げられた。
無事その日の工程がほぼ終了。安堵していた矢先、外国通信社のカメラマンがわさわさと集まりだしていた。気になり、近くに行ってみると彼らが柵の中に入ろうとしているではないか。入りたいが、どうせ「イポーニェ(日本人)、ニエート(だめ)」と言われるだろう。と思いきや、予想外にも入ることができた。より近くあおったり、真正面からも、逆サイドからも撮りまくった。
そして今回の予想だにしていなかったロケットが固定される場面。ホテルにはそのような写真がいくつも飾られており、指をくわえて眺めていた。その写真の光景が今まさに目の前で繰り広げられている。打ち上げ前だというのに、すでに満足感でいっぱいだった。ロストバゲージで機材の大半がなくなっていたことも、一瞬忘れた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「クレーン撤去開始」
読売新聞東京本社写真部 松田 賢一(まつだ けんいち)
(2011年5月23日撮影、同日夕刊1面掲載)
<取材者の弁>
「あれ?動いてるんじゃない?」パイロットの声で振り返った私の目には、第2展望台付近にぶら下がったオレンジ色をしたマスト(支柱)の一部が見えた。3月に634メートルに達した東京スカイツリー。外観の工事を終え、5月23日は建設にはかかせなかった大型クレーンの撤去作業が始まった。
朝から撤去に向けた準備が進められ、午前9時すぎには北側に設置されたクレーンが約6メートル下がり、それによって上方に出てきたクレーン自体のマストを自らはずす予定だった。しかし私のもとに届いた情報では現場は強風、作業は遅れ気味で9時すぎに行われる予定だった行程は10時半ころになりそうとのことだった。良い構図の写真を撮るにはもう少し待たなければならないだろう、そう思ったが夕刊早版の締め切りも近づいてきたこともあり、作業の進捗状況はさておき羽田を離陸した。
10時半現場着。案の定、動きはなかった。あまりの動かなさに「もしや作業が終わってしまったのでは」と少々不安になったがとりあえず早版用に数枚電送するために現場を離れた。送信を終えスカイツリー上空に戻ってきたものの相変わらず変化はない。ファインダー越しに見えるクレーン周辺の作業員にも慌ただしさを感じなかった。時計回りにツリーの周回を重ねていると、南北に設置されたほぼ同じ高さだったクレーンの高さが若干変化していることに気付いた。「もう1周回ったころ、ちょうど良いあんばいになるな」そう思い、視線をカメラのモニターに向けたところパイロットから冒頭の一言。
シートベルトで固定された体を180度、いやそれは大げさだ120度右側にひねりクレーンからつり下げられるオレンジ色の物体を撮影した。自分では撮影ポイントに納得がいかず、もう1周近く回ったところで撮影したい旨をパイロットにリクエスト。思い描いたポジションに到着したころには、取り外されたマストははるか下、第1展望台付近だった。約1時間20分の飛行時間だったが、実働は10秒あっただろうか。
気を抜くことができない航空取材。この緊張感が・・・楽しい・・・。
--------------------------------------------------------------------------------------------
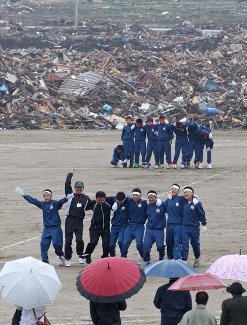
題名「がれきをのけて運動会」
毎日新聞社写真部 武市 公孝(たけいち きみたか)
(2011年5月22日撮影、同23日別カットが1面掲載)
<取材者の弁>
被災した岩手県陸前高田市立小友(おとも)中学校の運動会が隣接する小友小学校の運動場で行われた。被災後、市内小中学校では初めての運動会。朝から雨で開催が危ぶまれたが1時間遅れで始まった。
36名の生徒が校旗を先頭に入場行進、徒競走、騎馬戦、全員リレーなどが行われ、特に借り物競走では先生、報道関係者も参加してとても盛り上がった。
閉会式で「この運動会ができたのは先生、親、地域の方々、ボランティアの皆様のおかげ。感謝の気持ちを持ってこれから学校生活に頑張ります。そして小友、陸前高田のために何ができるかを考えていきます」との生徒のあいさつに大きな拍手が起き涙を流す来賓の姿も。
「どうしても開催するんだ」と大人たちが運動場を整備し、生徒も1週間の短期間で準備したという。単に一中学校の行事ではなく地域復興のシンボルとなっていた。運動場の広さに比べ生徒数が少ないためリレー等では寂しい写真になってしまうと考え出場者が一番多い「親子綱引き」をメインに。校舎3階のベランダから撮影中、震災直後の光景と開催までの道のりを思い運動場が明るく浮かび上がるように感じて、うっすらファインダーが曇ってしまった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「防護服でわが家へ」
時事通信社写真部 大高 正人(おおたか まさと)
(2011年5月10日代表撮影、同日配信=各紙主に1面掲載)
<取材者の弁>
福島第1原発の放射能漏れ事故で避難を余儀なくされている住民の一時帰宅が実現。第1回目となった川内村への帰宅に随行して代表取材した。
写真は、防護服に身を包んで久しぶりの我が家で持ち出す荷物を整理する住民。この男性もそうだが、取材を許可してくださった方々は皆、(シューカバーを付けているとはいえ)土足で上がり込んできた記者、カメラマンに声を荒げるでもなく、質問にもていねいに答えていた。もし私が逆の立場だったら、「少しは人の気持ちも考えろ」と怒鳴りたくなるところだろう。
「我慢強く、優しい」東北人気質は、今回の震災報道でもたびたび取り上げられている。しかし、天災と原発事故のダブルパンチで、ある日突然、住まいや職という「日常」を一気に失うという不条理に人はどれだけ耐えられるだろう。先の見えない不安、腹の底に渦巻く怒り…。
この出張後、私はまた安穏とした日常生活に戻っている。「がんばろう日本」とは気恥ずかしくて大声で言えない自分を感じる。写真の男性はまだ20代の若い方だった。もし彼がまだ未婚であれば、数年後に幸福な結婚をして子供にも恵まれ、「あのつらい日々」が風化しますように。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「原発10キロ圏内、時間が止まったままの町」
産経新聞写真報道局 大山 文兄(おおやま ふみえ)
(2011年4月14日撮影、未掲載)
<取材者の弁>
防護服を着用し、福島第一原発から10キロ圏内で行われた福島県警の行方不明者捜索に同行した。10キロ圏内での大規模捜索はこの日初めて。震災から一カ月過ぎても手付かずの3月11日の光景がそのまま残されている。次々と見つかるランドセルやアルバム。年齢が不明にまでなってしまった遺体が発見された。
福島県警の捜索場所からさらに海側へ移動すると、捜索がいまだ行われていない請戸漁港が広がった。原発からの距離は7キロ。風向きのせいなのか、放射線量は驚くことに東京よりも低い。津波で壊滅となった請戸地区の後方には福島第一原発の建屋が見える。
「やっとここまで来ることが出来た」 県警捜査員の一言が福島の今を現していた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「福島第1原発20キロ圏、捜索に同行」
毎日新聞社写真部 佐藤 泰則(さとう やすのり)
(2011年4月7日撮影、8日付朝刊1面に掲載)
<取材者の弁>
福島第1原発から20キロ圏内の避難指示区域内で行方不明者を捜索する警視庁機動隊に同行した。機動隊員が着用する防護服と同じ物を着て、線量計を首から下げて捜索現場に入った。放射能汚染の心配から、この場所の捜索は始めてで、津波に押し流された民家などのがれきがそのままの状態で残っていた。
約1時間の取材では線量計に変化はなかった。しかし、目に見えない放射能の恐ろしさ、不気味さが消えたわけではない。取材後、スクリーニングを受け、低い数値を聞いて一安心した。原発に近いという理由で放置された被災地。「せめて遺体を回収して欲しい」という避難民の気持ちは痛いほどわかる。その声に答える警察官の仕事ぶりには頭が下がった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「がれきの中で水を運ぶ少年」
共同通信社写真部 八田 尚彦(はった なおひこ)
(2011年3月14日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
この少年には震災から4日目の宮城県気仙沼市で会った。
向こうから水を持って歩いてきて、数枚シャッターを切って、一言二言の会話をした。そのときの受け答えが、とても礼儀正しかったことを覚えている。
写真に収めてから1カ月後、避難先のアパートを訪ねた。姉や親戚の子どもとはしゃぐ少年らしい顔に戻っていた。
実はこの少年、空手の全国大会で準優勝した経歴を持つ。両腕のたくましさはそれによるものだったのかと、後から納得した。今年の大会では優勝をと練習に励んでいた最中だった。しかし、震災の影響で県大会すら開催されるかわからない。大切なトロフィーや道着も、自宅とともに流れてしまった。
後日、新聞で写真を見た香川県の一家と少年一家との間に、交流が生まれていたことを知った。同い年の女の子が手紙で「こわかっただろうなと思います」「町がなくなってしまって、びっくりです」とつづっていた。「お兄ちゃんといっしょにおこずかいでかったので送ります」と、UNOとワンピースのトランプが同封されていた。少ない娯楽のなかでの生活に、UNOは重宝したという。ワンピースのトランプの方は、使わずに大事にしまっているとか。
2家族の交流は、今回の取材のなかで唯一ほっとできたエピソードだった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「ままへ」
読売新聞東京本社写真部 立石 紀和(たていし のりかず)
(2011年3月22日撮影、同31日1面掲載)
<取材者の弁>
震災から約1週間後、岩手県宮古市の漁村を訪れた。入り江の小さな港は津波を押し上げ、場所によっては30メートルの高さにまでなったという。そんな場所で、私は4歳の昆愛海ちゃんに出会った。
震災直後、自宅にいて両親や妹と津波に流されたが、愛海ちゃんだけが偶然にも漁に使う網に引っかかり、奇跡的に助かったという。家族が行方不明になっていることをある程度は理解しているようで、表情は固かった。
それから時々会いに行った。トランプで遊んだり、絵本を読んだり、おやつを食べたり。カメラは構えなかった。
ある日、いつものように“ババ抜き”をしていると、突然「ママに手紙を書く」と言い出し、お絵かき帳代わりの大学ノートを広げた。私は急いで車に置いてあったカメラを取りに行った。愛海ちゃんは色鉛筆でゆっくりと1文字1文字手紙を書き始めた。
「ままへ。いきてるといいね おげんきですか」。1時間くらいかけてそこまで書くと、疲れてしまったのか、寝入ってしまった。
東日本大震災では、親を失った震災孤児が数百人にのぼるとみられる。私たちも長期にわたり震災と向き合うことになる。今後も時々愛海ちゃんとトランプをしに行こうと思っている。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「勝利確信のVサイン」
読売新聞 ニューヨーク支局 小西 太郎(こにし たろう)
(2011年2月11日撮影、同12日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
エジプトのムバラク大統領の退陣を求めるデモを取材するため、11年2月1日にカイロに入った。身動きがとれないほどの大群衆、治安警察や大統領支持派による報道陣に対する暴行や取材妨害、デモ隊の衝突に巻き込まれる危険。数時間ごとに変わる状況を肌で感じながら、デモが行われていたタハリール広場を中心に緊張する取材を続けていた。
この写真を撮影したのは2月11日の金曜日。イスラム圏では抗議行動が金曜礼拝後に盛り上がることが多く、デモ隊が警察や軍と衝突するという最悪のシナリオを含め、幾通りかの展開を想定しながら取材していた。しかし、厳かな礼拝が終わると、広場は意外にも和やかな、まるでお祭りのような雰囲気に戻っていった。家族連れも多く、輪になって歌ったり踊ったりしているグループもあった。
交通信号の制御盤の上によじ登ってそんな様子を眺めていると、若い父親らしい男が幼児を肩に乗せこちらに向かってVサインをしているのに気がついた。レンズを向けたからポーズをとってくれたのではなく、私が気づくのを待っていたのだ。フレーミングを変えて何通りか撮影をしている間も笑顔を絶やさず、こちらに向かって力強く手を突き上げていた。
ホテルに戻ってこれらの写真を送信し終わった頃、ケーブルテレビからムバラク大統領がカイロを脱出したという未確認情報が流れはじめた。そして数時間後、まさに朝刊最終版の締め切り間際に「大統領辞任」が国営テレビを通じて正式に発表された。
歓喜する人々の写真に差し替えるには時間がなかったため、この写真がそのまま「ムバラク政権崩壊・独裁30年に幕」という歴史的ニュースを伝える見出しと共に一面に残った。写真の若い父親は、こんなに早く希望が実現すると思っただろうか。異なる宗教や宗派、様々な職業や年齢の人々と肩を並べてタハリール広場に立っていた時、独裁を打ち破り市民革命が実現することを確信したのにちがいない。
「世界中の人たちも見守って応援してくれ。必ず我々は勝利するから」。電柱にしがみついているカメラマンに、そう伝えたかったのだと思う。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「涙がとまらない」
朝日新聞社写真センター 恒成 利幸(つねなり としゆき)
(2011年3月13日撮影、同14日朝刊1面掲載。なお、14日付け米ニューヨークタイムス紙1面、15日付け仏ル・モンド紙1面、14日付け米ワシントンポスト紙グラフ面などにも掲載)
<取材者の弁>
(撮影者は現在も取材で忙しく、「この1枚」は写真説明だけにします)
地震発生から3日目の朝。大津波で壊滅的な被害を受けた宮城県名取市閖上(ゆりあげ)地区で、がれきと化した街を徒歩で取材していると、橋の上で座り込む女性が涙を流していた。失った大切なものを捜しているという。方々を歩いてきたのだろうか。その姿は疲れ切っていた=3月13日午前10時57分
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「大津波の被害壮絶」
中日新聞社写真部 畦地 巧輝(あぜち こうき)
(2011年3月14日撮影、同15日付け東京新聞朝刊24面に掲載)
<取材者の弁>
(取材者は現在も取材で忙しく、「この1枚」は写真説明だけにします)
壊滅的被害を受けた岩手県大槌町。行方不明者の捜索が続く市街地では建物の上に大型の客船が取り残されたままになっていた=14日午前9時8分、東京新聞ヘリ「まなづる」から
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「大津波の被害壮絶」
中日新聞社写真部 畦地 巧輝(あぜち こうき)
(2011年3月12日撮影、同12日夕刊10面に掲載)
<取材者の弁>
(取材者は現在も取材で忙しく、「この1枚」は写真説明だけにします)
津波で木造家屋や船舶が流された気仙沼市街地。地震から一夜明けても数カ所から火の手が上っていた=3月12日午前8時36分、東京新聞ヘリ「まなづる」から
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「木が倒れたあぜ道を、手をつないで歩く男女」
報知新聞社東北支局長 関口 俊明(せきぐち としあき)
(2011年3月14日撮影、同15日2面掲載)
<取材者の弁>
東日本大震災4日目。津波で死者、行方不明者が多数出た宮城県仙台市若林区の荒浜地区まで仙台駅前の支局から約10㌔、自転車を使って取材に向かった。
メインの道路は警察がバリケードを張って封鎖していたが、周囲に田んぼのあぜ道が何本もあり、たどって行くと津波で流された場所まで行ける。自転車を止め、中まで歩いて向かっている途中、荒浜に住んでいた女性(84)と話をした。
家族、親類は全員無事だったが、家で飼っていた猫を置き去りにしてしまったという。姪、孫と一緒に避難していた七郷小からペットを探しにやって来た。「避難所にいてもやることないんで、にゃんこ(猫)を探しに来たんです」と涙を浮かべて話した。
地震の時は家族が仕事に出ており一人で家にいたため、近くに住んでいた姪が車で駆けつけた。姪は「目の前がドライアイスのように真っ白で見づらかったですが、必死でした」と振り返り、「おばさん、どこまで行っても浮かんで来ないから帰ろうよ」と行って引き揚げて行った。
苦しいながらも、元気よく必死に生きようと手をつないで歩く男女がいた。木が倒れたあぜ道をつたって自宅のあった場所に向かっているようだった。その直後、遠方で警察、消防のスピーカーから鬼気迫る避難勧告の声が聞こえた。「津波が来ます。逃げてください」。
「えっ、まずい」と思い、止めてあった自転車まで倒れた木を乗り越えながらの500㍍ダッシュ、そこから約1.5㌔ある避難所の七郷中まで猛スピードで走った。警察が私を見つけると「早く、早く、津波が来るぞー。早く逃げてー。早く、早く。逃げてー」と促された。何分で到着したのか覚えていないが、かなりのスピードだったと思う。中学校に到着して持っていたお茶を飲み、ようやく一息ついた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「家屋をのみ込む大津波」
毎日新聞社写真部 手塚 耕一郎(てづか こういちろう)
(2011年3月11日撮影、同12日1面掲載)
<取材者の弁>
私はヘリで仙台の上空を飛行中に巨大地震に遭遇しました。
仙台空港で給油するため、1度着陸したものの、空港は完全にクローズ。職員が津波を心配して建物の屋上などに避難していました。
残りの燃料は少なくなっていましたが、ここにいたら危険とパイロットが判断してすぐに飛び立ちました。その直後、巨大なヘドロのように濁った津波が沿岸の堤防や防風林を乗り越えて住宅街に流れ込む光景を目撃しました。
2階建ての民家が簡単に押し流されるほどの巨大な津波が、はるか彼方までの沿岸一帯を一気に飲み込みました。
あの場にとどまっていたら…。血の気が引く思いで、夢中でシャッターを切りました。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「東京マラソン、スタート前」
産経新聞写真報道局 大西 史朗(おおにし しろう)
(2011年2月27日撮影、同28日朝刊1面掲載・代表撮影)
<取材者の弁>
今年で5回目を迎えた東京マラソン。
共催となる産経新聞では多くのカメラマンをあちこちに投入し、取材に当たった。しかし、開催日は雨やみぞれなど悪天候になることが多く、撮影者にとっては悩ましいところ。今年も天気が気になったが、幸い見事に晴れ渡り、まさに「マラソン日和」となった。
その日は都庁の渡り廊下の上から代表撮影の役割でスタートシーンを撮ることになった。 スタート前に何か撮れるものがないかと思ったが、撮影位置からランナーまで距離があるので300ミリをつけてのぞいてみることにした。
すると、レンズで圧縮されたランナーの顔がファインダーいっぱいに浮かび上がった。スタート前に両手を上にあげ、体を伸ばす人。じっと号砲を待つ人。なかでも、思い思いに仮装したランナーがあちこちに散らばり、スタートを待つ様子はアクセントとなって面白い。その人たちを入れて、何枚かおさえた。
今年の東京マラソンは、これまでで最多の約3万6000人が参加。市民ランナ―の川内優輝選手が2時間8分37秒で日本勢最高の3位と健闘。世界選手権代表に内定するなど話題となったが、この一枚は、ランナーのスタート前のそれぞれの表情がわかる写真になっただけでなく、ランナー一人一人の熱気が伝わる写真になったと思っている。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「“恐竜”2頭、出会えた」
朝日新聞写真センター 竹谷 俊之(たけや としゆき)
(2011年2月27日撮影、同28日朝刊社会面掲載)
<取材者の弁>
離ればなれだった2頭の「恐竜」が結ばれた。東京湾の入り口で建設が進む「東京ゲートブリッジ」。恐竜のような形をしていることから東京スカイツリーとともに、新たなランドマークとして期待されている。
写真は、「恐竜」の口先に長さ約108㍍、重さ約1600㌧の橋桁を大型クレーン船でつり上げて設置する最後の橋桁架設工事の場面。午前8時過ぎ、報道陣ら約20人を乗せた船が海面からそびえ立つ「恐竜」にゆっくり近づいていった。時折、雲間から柔らかな太陽の光がのぞき、橋を境にして青とオレンジ色に染まる背景の中、逆光で橋がシルエットになって浮ぶ様子を撮影した。江東区の若洲海浜公園など両サイドから見ると、角度によっては「恐竜」がキスしているようにも見えるので面白い。
いち早く、海上60㍍の「恐竜」の背中にも乗った。都心の高層ビル群や房総半島が一望でき、気持ちがいい。2011年度中に開通予定の橋は全長2・9㌔で片側2車線の道路と歩道があり、車も人も無料で渡れる。夜間はライトアップされるとあって、人気の夜景スポットになるのは間違いないだろう。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「ハウスを覆う火山灰」
日本農業新聞 編集局写真部 染谷 臨太郎(そめや りんたろう)
(2011年2月6日撮影、21日特集面掲載)
<取材者の弁>
52年ぶりに噴火した宮崎県と鹿児島県境にある新燃岳。冬季特有の風「霧島おろし」に乗り宮崎県側に降灰の被害が集中、農業被害が相次いだ。
写真は火口から約7キロにあるキンカンの栽培ハウス。避難勧告が出た地域で農家の声を聞こうと記者と2人で1軒1軒回っていた時に発見した。持ち主は畜産も経営している農家で、牛の避難や牛舎と自宅の灰を除く作業に追われ、ハウスにまでとても手が回らないとのこと。ハウスは昼間なのに薄暗く、噴石でところどころビニールが破れている。積もった灰は風に吹かれて不気味な模様を描き、まるで農家の無念が形になって現れているよう。噴火の恐怖を改めて実感しながらシャッターを切った。
口蹄疫、鳥インフルエンザに加え火山の噴火。昨年から続く宮崎県の災難に、取材した農家は口をそろえて「なんで宮崎ばかり・・・」と肩を落としていた。
当初は3日間だけの取材予定だったが、被害が深刻になり日程を延長。久しぶりに東京の事務所へ戻ると、いつもとは違い他部署の同僚までニコニコと出迎えてくれ、労をねぎらってくれた。よくよく聞いて見ると、日程延長が決まった際にデスクが「染谷はパンツを1枚しか持って行ってない」と余計な一言をニュースセンターや整理部の前で言ったそうで、しばらくは下着の話ばかりでした。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「国技館揺れる!」
東京中日スポーツ写真部 北村 彰(きたむら あきら)
(2011年2月15日撮影・16日付朝刊は別カットを掲載)
<取材者の弁>
力士らの八百長問題に揺れる日本相撲協会。大相撲の野球賭博事件に絡み、警視庁が家宅捜索で押収した現役力士数人の携帯電話に八百長行為をうかがわせるメール記録が残っていた。捜査関係者の取材で表面化した2月2日以降、両国国技館は大勢の報道陣でごった返している。
メールの内容がすごい。「立ち会い強く当たって流れでお願いします」「流れで少しは踏ん張るよ」と直接対決での取り組み方や銀行の口座番号、金額をうかがわせる数字まで。ここまではっきりと見せつけられると、怒りを通り越して、呆れるしかない。
春場所と年内の地方巡業の中止が決まり、5月の夏場所も開催が危ぶまれている。新聞はむろんだが、テレビも連日、この八百長問題を取り上げている。ワイドショーには元力士や相撲ジャーナリスト、評論家などが登場し、大相撲のあり方や将来性について、けんけんごうごうだ。
この時期、スポーツ新聞は1面ネタの薄さに悩まされる。プロ野球のキャンプが唯一の救いで、かなり無理やり紙面を作っているのが本音だ。ここに降ってわいたような大相撲の話題は、本来は大歓迎のはず。だが、スポーツ報道を生業としている身からすれば、八百長相撲などもってのほか。前記の通り、怒りに震え、呆れの気分で連日、取材に当たっている。
この冬一番の大雪となった15日。屋根が真っ白に雪化粧した両国国技館では、体の小さな入門希望者を対象にした第2新弟子検査が行われていた。従来の体格基準(173センチ、75キロ以上)に満たない力士希望者に門戸を広げるために2001年に設けられた制度だ。
この日は昨年同時期より1人多い9人が受験。ボール投げや短距離走など瞬発力や敏しょう性を測る8項目の運動能力テストを行い6人が合格した。体が小さいと言っても、みんな見るからに相撲体形。果たして走れるのかなと心配したが、なんのなんの…。見守っていた記者たちもびっくりするような快走ぶり。この時ばかりは国技館の床が本当に揺れたように感じた。
春場所が中止となり、デビューがいつになるか分からない状況での受験。検査に立ち会った貴乃花審判部長は「ありがたい。感謝の気持ちが強い」と温かいまなざし。幕内豊ノ島が第2検査出身の関取第1号。ここにも悲喜こもごもの15の春。「頑張れ!」。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「佑と有」
サンケイスポーツ写真報道局 財満 朝則(ざいま とものり)
(2011年2月1日撮影、同2日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
学生野球界のアイドルスター、斎藤佑樹投手。もはや社会現象ともなった「ハンカチ王子」「佑ちゃん」のプロ生活の皮切りは、北海道日本ハムファイターズと決まった。日ハムの一員となってのち、斎藤の一挙手一投足もさることながら、チームが誇るWBC日本代表のエース、ダルビッシュ有投手といつ公の場でツーショットになるか・・・が、取材の焦点となった。
1月の新人自主トレ期間中や親会社主催のイベント、またキャンプ地沖縄県名護市への移動などのタイミングでは、残念ながら「絡み」は実現せず。そして迎えた2月1日、キャンプ初日。400人を超える報道陣が、沖縄・名護市営球場に詰めかけた。各新聞社ともカメラマン2人、3人体制。テレビ局は、一系列でカメラ7台というところもあったようだ。
その「有・佑」のコラボ。場合によっては、無理やりフレームインさせなくてはとも思っていたが、意外とあっさり実現した。集合写真撮影の終了後。ウォームアップ。斎藤に、ダルビッシュが歩み寄って、声をかける。気難しい?イメージのある若きエースだが、プロ初キャンプで緊張含みの新人を気遣う優しさをみせた。
場所をサブグランドに移して、投内連携練習。ともに二塁手役のダルビッシュが再び斎藤に近づき、何やら話し込む。400mm望遠で、2人に向けて連写、連写。周囲からも、シャッター音がけたたましく響く。
そして2人の顔から笑みがこぼれる。”本日解禁”となったこの日3度目のツーショットは、最高の表情をプレゼントしてくれた。
プロ初登板、初勝利、そして強打者との対戦、エースとの投げ合い…。佑ちゃんフィーバーは当分続くだろうけど、どんなプロ投手になるのか、楽しみだ。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「ザックの喜び」
スポーツニッポン新聞社写真部 西尾 大助(にしお だいすけ)
(2011年1月29日撮影・現地時間、31日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
サッカーアジア杯決勝・日本対オーストラリア戦で優勝が決まった瞬間、ピッチに走り出した控えメンバーの後ろで両手を大きく挙げガッツポーズをしたザッケローニ監督。すかさず本田圭が監督に飛びつき抱き合った。
選手と抱き合い称えるザック監督の姿がピッチのあちこちにあった。どの写真を会社に伝送しようか迷うほど監督は喜びを爆発させていた。
ザック監督。これまでも練習後クールダウンする選手に付き合ってグラウンドにいつまでも残っていた姿。試合終了後にはピッチに出向き、それぞれの選手を祝福した姿。多くの選手と通訳を交えて話し込んでいた姿。日本帰国の際、出番のなかったGK権田とDF森脇に優勝トロフィーをわざわざ持たせたエピソード…。
気配りのできる監督がチームを一丸にし、サッカー日本代表を引っ張っていく。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「黄昏のスカイツリー」
時事通信社写真部 石塚マリコ(いしづか まりこ)
(2010年12月31日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
2010年の大晦日、出社すると「今年最後の夕日とスカイツリーなんてどう?」とデスクに声を掛けられた。昨年は何かと話題になった東京スカイツリー。契約紙向けの新年企画でツリー取材を担当し、しこたま撮影していたこともあり、正直「またか」との思いもあったが、自分が今まで取材した風景を頭に巡らせてみた。しかし何も思い浮かばない。しばらく考え込んだ末、「芸がないな」と思いつつ、「ダイヤモンド富士」ならぬ「ダイヤモンドスカイツリー」を狙うことにした。
太陽とスカイツリーの位置を地図で確認し、おおよその見当を付けたのが荒川付近。とりあえず絡みそうな場所に向かい、後は太陽を見ながら荒川の土手沿いを動けば何とかなるだろうと楽観的に考えて会社を出たのが午後2時半すぎ。甘かった。冬の太陽は低い。そしてスカイツリーは高い。現場に到着し、荒川の土手に上ったのが午後3時半ごろ。何と太陽はすでにスカイツリーのてっぺんよりはるか下に。「スカイツリーってなんであんなに背が高いんだ?」と腹を立てていると、地元住民にとどめを刺された。「夕日とツリー撮るの?この辺りでは冬場は全く重ならないよ」
このままでは「ダイヤモンドスカイツリー」はおろか、夕日との絡みすら撮れない。慌てて移動するが太陽はどんどん沈んでいく。自分の適当な性格とスカイツリーの高さを恨みながら、なんとか絵になりそうな場所にたどり着いたのは午後4時半ごろ。太陽はほぼ沈みかけていて撮影できる時間はあとわずかなのに、荒川の土手に通じる橋ははるか彼方。移動すれば太陽は沈んでしまうと思い、すべてをあきらめて、今この場所で撮れるものを撮ろうと腹をくくったのが大逆転につながった。
荒川の土手に、夕日を眺めようと集まった見物客のシルエットが浮かび上がり、まるで影絵のようになっている。スカイツリーの足下には夕日が重なり鉄骨から光が漏れた。なんだか懐かしさを覚える風景だなと、一瞬にして気持ちが和み、シャッターを切った。
頑張ることをあきらめることで撮れる写真もあるんだなと、改めて写真が持つ偶然性のおもしろさを感じた取材だった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「親から子へ」
毎日新聞社大阪本社写真部 小松 雄介(こまつ ゆうすけ)
(2011年1月17日撮影、同日夕刊1面掲載)
<取材者の弁>
阪神大震災から16年となる1月17日、神戸市中央区の東遊園地で朝を迎えた。この日、神戸の最低気温は氷点下0・4度と冷え込み、会場の人の数は例年よりも少なく感じられた。写真は、竹灯ろうに火をつける親子。ろうそくの火を見つめる1歳の女の子に父親が語りかけている様子を写した。3歳の男の子も連れて来ていた父親は「子どもが生まれてから、震災のことを伝えようとこの日は足を運ぶようにしている」と話していた。
関西で仕事をするカメラマンにとって、1月17日組の紙面で何ができるかというのは毎年悩むことの一つだと思う。昨年、毎日新聞は「15年目の1日を生きる」というテーマで、その日に神戸の産院で生まれた赤ちゃん▽15年前の1月17日に生まれた中学生の「今」▽震災で亡くなった子や孫を思い船上で涙ぐむ漁師▽墓地で一人静かに手を合わせる男性──などの写真をグラフにした。「一見、何のグラフだか分かりにくい」という意見もあったが、いつもとは違う紙面を作れたと感じることができた。
さて、今年は何か残すことができただろうか。グラフは各地で行われた追悼行事や集いの会場で撮られたものが主に使われた。関西での取材が長く、1月17日を何度も経験している東京の同僚からは「今年は新しい写真がなかった」という指摘があった。確かにそうかもしれない。私が撮影した冒頭の「親から子どもへ受け継がれる震災の記憶」の写真はこれまで何度もこの日の紙面で繰り返されたものだ。だが、新しくはないが大切な写真というのもあると思う。「同じ苦しみを繰り返してはいけない」という思いで被災地の心が一つになる日なのだから。
来年は何ができるだろうか。震災で大切な人を亡くした方や被災した方たちの思いを大切にしながら、カメラマンとしてできることを考えていきたい。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「晴れ着舞う」
朝日新聞社 写真センター 橋本 弦(はしもと げん)
(2011年1月10日撮影、同11日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
成人の日を数日後に控えたある日、当日当番のデスクから「今年ならではの写真を」というお題が出された。同僚やキャップらとさんざん智恵を絞りあった末、いちばん最初に話題に上り、「もうお腹いっぱいの感もあるよね」と言い合っていた東京スカイツリーと新成人というごくごく平凡な結論に帰結することとなった。
撮影にあたっては、スカイツリーに詳しい先輩から事前に撮影ポイントを指南してもらった。駅から会場に向かうペデストリアンデッキで路地の間にスカイツリーがキレイに抜けて見える場所があり、きっと式典前後には新成人がスカイツリーをバックに記念撮影をするに違いない。そうでなくても、式典を終えた新成人は記念撮影するためにツリー近くに集まるだろう。そう期待して撮影に臨んだ。
根拠のない見通しは、強い寒気と北風にみごとに吹き飛ばされた。朝からの冷え込みは日が差し始めてもゆるむことはなかった。期待していた撮影ポイントはビル風が吹き抜ける日陰。立ち止まって記念撮影どころではなく、新成人たちは「寒い、寒い」と身をこわばらせながら足早に素通りしていく。それに、よく考えてみれば墨田区民は毎日ツリーを見上げているわけで、メディアが想像するような記念撮影の光景はなかなか見ることができなかった。
半ばあきらめに近い気持ちでツリーをあきらめ式典会場へと足を向けた時、ふと振り返るとビルの谷間に差し込む光で、風にあおられる裾や結い髪を抑えながら歩く振り袖姿の新成人たちが暗い背景に浮き上がった。スカイツリーは今年のニュースかもしれない。だけど、朝早くから着付けをした着物が風で乱れないように必死に抑えたこと、冷たい風で手や足がしびれるように凍えたこと、そういうことこそが家族や本人が成人式の記憶として思い起こす「今日」として記憶されるのかもしれない、そう思った。
寒さに耐えながらじっと待ちながら振り袖姿を狙い続け、これから開ける将来への期待を感じさせる新成人らしいさわやかな笑顔と、一陣の風を感じさせるように舞い上がった着物をとらえたのがこの一枚。少しだけ、送り出した親御さんには申し訳ないと思いつつ。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「ワセダ18年ぶりの栄冠」
産経新聞社 写真報道局 寺河内 美奈(てらごうち みな)
(2011年1月3日撮影、同4日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
正月の不摂生が祟ったのか今年の1月3日、私は体調を崩しフラフラになりながら(周りに多大なる迷惑をかけながら)泊まり明けを迎えていた。
入社一年目に取材チームに加えてもらって以来、何度か撮影する機会のあった箱根駅伝だが、今年は私にとって特別なものだった。母校の18年ぶりの総合優勝がかかっていたからだ。体調が悪いなんて言っていられない。「なんとしても立ち会わなくては・・・でもどうせだったら例年と少し違う角度から見られないものか」と思い、取材チームと相談の結果、弊社の屋上に上ってみることになった。というのも、ゴール地点となる旧読売新聞社ビルの隣という好立地だからだ。
さっそく上がってみたところ、ぎりぎりゴールテープ付近が見えるポイントを発見。ただし、大問題が。上半身をかなり乗り出さないとほとんど下が見えないのだ。眼下に広がる光景に体調不良とは関係なく(?)胃がむかつき、足がすくんでしまった。写真部に戻りデスクと相談したところ「とにかく機材を落としたらまずいから、柱にロープを巻いて体と一緒に固定する」という結論に。すぐに数人で社内を探し回り、登山用のロープをゲット。
ゴール到着予定時刻30分前くらいになって再び屋上へ。まず柱にロープを通し、体を固定させる作業に入った。さらにカメラのストラップにも結びつける。取材用のヘリコプターが頭上を飛ぶ音が聞こえてくる。「もし見られたらかなり間抜けな格好だと思われているんだろうな」と一瞬冷静に考えながら、携帯電話でワンセグをチェックしその瞬間を待った。エンジ色のユニフォームがゴールテープを切った時、私は地上30階以上の高さからつま先立ちで落ちそうになりながら撮影していた。そして選手の胴上げ・・・が始まるも後ろ姿で見えない。「まだチャンスは来るはず」と言い聞かせ、しばらく同じ体勢でカメラを構えていた。すると、なんと監督がやってきて素晴らしい笑顔を空に向け胴上げが始まったではないか。
思えば18年は長い年月だ。総合優勝は渡辺監督が一年生の時以来、今度は「監督」として栄冠をつかんだ。「何事も簡単にあきらめないで今年一年また頑張らなきゃ」と年明けからすがすがしい気持ちになれたのがこの一枚。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「2010年を振り返る」
共同通信社写真部次長 冨田 晴海(とみた はるみ)
(2010年12月17日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
26日、東京都中央区の日本橋三越本店で行われていた恒例の報道写真展が終了した。今年はオープニングにプロ野球ロッテの井口資仁選手と宇宙飛行士の山崎直子さんを招きスタートした。例年同様約280点余の写真が展示され、10日間で約4万人の来場者が訪れた。期間中に見学に訪れるはずだった管直人首相は政局がごたごた続きのためか来場しなかった。
今年を振り返ると、2月のバンクーバー冬季五輪に始まり、6、7月のサッカーワールドカップ南アフリカ大会、11月の広州アジア大会と大きなスポーツイベントが続いた年だった。また、1月のハイチ、2月のチリ、4月の中国青海省で大きな地震が発生し、多くの犠牲者を出した。チリ地震では太平洋を越えて三陸沿岸などに津波が到達した。8月にはチリの鉱山で落盤事故が起き、作業員33人が地下約700メートルに閉じ込められたが、69日ぶりに全員が無事救出された。9月には北朝鮮の金正日総書記の後継者として三男金正恩氏が決まったが、11月末に同軍が韓国・延坪島(ヨンピョンド)を砲撃し、朝鮮半島情勢は一気に緊迫度を増している。
国内に目を向けると6月に鳩山内閣に代わって菅内閣が誕生したが、7月の参院選で大敗し、現在も支持率が伸びず不安定な政権運営を続けている。今年の夏は観測史上最高の猛暑が全国を襲い、熱中症で救急搬送される人が相次いだ。9月には沖縄県・尖閣諸島周辺の日本領海内で中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突する事故が発生。逮捕した船長は中国サイドの圧力に負けて釈放。11月初旬に衝突時の映像がインターネットの動画サイトに流出するなど暗いニュースが目立った。
しかし、小惑星探査機「はやぶさ」が6月、数々の苦難を乗り越え約60億キロの長旅を終え地球に帰還した。大気圏突入時に燃え尽きる機体本体の写真や映像が多くの人たちに感動を与えた。東京の新名所となりつつあるスカイツリーも順調にその高さを伸ばし、各社がそれぞれ工夫をした撮影手法で記録に残している。
年明け1月8日からは横浜の日本新聞博物館に場所を移し、3月6日まで展示が続けられる。各社のカメラマンが日本だけではなく全世界を飛び回り撮影した報道写真が一度に見られるこの写真展は年々来場者が増えている。来年の写真展でも、「さすがはプロ」と称賛されるような素晴らしい写真の展示を心掛けたい。
皆さん1年間お疲れさまでした。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「戦場・延坪島」
共同通信社写真部 鹿野 修三(しかの しゅうぞう)
(2010年11年25日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
11月23日、韓国軍の射撃訓練に対し北朝鮮が約170発の砲弾を発射した。7平方キロメートルのほどの小さな島に約80発が落下、うち約20発が住宅密集地に落ちたとされた。
砲撃から2日後、一時帰島する島民と共にフェリーで現場に入った。全焼し骨組みだけを残す家屋、砕け散った窓ガラス、コンクリートの壁に空いた大きな穴。砲撃のツメ後はまだ生々しく残されまさに「戦場」だった。砲弾が直撃した家の屋根を撮影しようと建物に上った。ペシャンコにつぶれ地面に落ち込んだ屋根、崩れたレンガ造りの壁はお世辞にも頑丈には見えない。建築当時、こんな状況にさらされることなど家主は想像もしていなかったのだろう。
「国境線は人為的に引かれたもの。距離も近いし、親近感さえ感じていた」という島民に向かって砲弾は打ちこまれた。赤ん坊の頃に北朝鮮からこの島に移住してきたという老人は「生まれた国から攻撃を受けるとは・・」と絶句し、涙をぬぐっていた。取材中、島の北方で腹に響くような砲音を聞いた。砲音はかなり遠方で聞こえたため危機感を覚えなかったが、間を置かずに毛布を持った女性が自宅を飛び出し、防空壕に駆け込んだ。「あんたたちも避難しないとやられるよ!」女性の必死の形相は体験した砲撃の恐怖を物語っていた。
12月20日、延坪島周辺の黄海で行われた韓国軍の射撃訓練。世界が緊張して見つめる中、北朝鮮の「報復」は無かった。総書記の三男の指導力誇示には十分だったのか。外交を有利に進めるためのデモンストレーションだったのか。それとも、次は確実に空爆されると読んでの沈黙か。いずれも推測の域は出ないが、今後も半島情勢から目が離せない。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「渋-い、おじさん対決」
時事通信社写真部 山崎 秀夫(やまさき ひでお)
(2010年11月17日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
先日行われたアジア大会広州大会で行われたビリヤードの日本人対決の一コマ。アジア地域の五輪であるアジア大会は、ボーリング、囲碁、チェスなどのボードゲーム、ダンススポーツやドラゴンボートなど、五輪にはない様々な競技が行われる。ビリヤードもその一つなのだが、そんなビリヤードの中でも、8ボール、9ボール、スヌーカー、イングリッシュビリヤード、3クッションといろんな種目があったりする。
今回取材したのは ビリヤード男子3クッション・シングルの決勝。競技場のカメラ取材位置は、会場を見下ろす観客席と平場の「pool(代表取材)」の2箇所。ビリヤードは態勢を低くして下を向いて行うので、 顔が見えやすい poolに入りたい、そう思って試合前に競技場の担当者に申し入れた。しかし、前日申請しなければダメ、と最初は突き返された。粘ってpoolは何人入るのか尋ねたら5人だという。試合開始ぎりぎりまで待つから、5人来なければ入れて欲しいとお願いし、結局2人しか来なかったため、競技開始2分前にpool取材者に与えられるベストをゲット。なんとかpool位置にもぐりこんだ。
初めて取材するビリヤード、それもポケットと呼ばれる穴がない3クッション。ルールもわからず、最初は両選手が絡む瞬間に必死で写真を撮っていたが、使える写真が撮影できたと感じたあたりから、取材はそこそこにして、試合に見入ってしまった。
3クッションは一つの玉を突き、壁に反発させながら残り二つの玉に当てると得点になる。精密に読んだ軌道を思い通りに転がせる技術と精神の強さ勝負を握るという。ファインダーから目を外し、じっくり二人のプレーを観戦していると、ついた玉が吸い込まれるように見事に二つの玉に当たって行く。手品でも見ているような感じだ。一緒に取材していたカメラマンと共に、一球ごとに感心のため息を漏らした。
今回の決勝の二人は、アジア大会の日本選手最年長で54歳の甲斐譲二選手(後方)と39歳の鈴木剛選手。実は心の中で日本選手最年長の甲斐選手を応援していたが、若干若い鈴木選手が逆転で見事に金メダルを獲得した。3時間以上に渡る激戦の後の表彰式での二人のおじさん(失礼)は、どちらも嬉しそう。フォトセッションで、恒例のメダル噛みも快く応じてくれた。
ところでビリヤードに関係する方々には誠に失礼ながら、素朴な疑問。ビリヤードってスポーツ?
大辞泉で調べてみました。
スポーツとは
楽しみを求めたり、勝敗を競ったりする目的で行われる身体運動の総称。陸上競技・水上競技・球技・格闘技などの競技スポーツのほか、レクリエーションとして行われるものも含む。
ということでした。まさにスポーツです、ね?
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「闇に伸びた一瞬の光」
産経新聞 写真報道局 芹沢 伸生(せりざわ のぶお)
(2010年11月17日撮影、同11月20日3面掲載)
<取材者の弁>
今、2度目の南極観測代表取材者として、観測船「しらせ」で昭和基地に向かっている。南緯60度までくると、真夏の南半球でも凍てつく寒さ。テーブル型の巨大氷山を見て、再び極地に来たことを実感した。
日本からアフリカ大陸の真下にある昭和基地まで、1万4千キロ。観測隊員は西オーストラリアのフリーマントル港から観測船に乗り込むが、白瀬矗(のぶ)陸軍中尉が南極に旅立って100年の節目でもあり、私は晴海から船で向かうことにした。秋深まる日本を出たのは11月11日。灼熱の赤道を通過、初夏を迎えた豪州で補給をして極寒の地へ。約1カ月で季節をいくつ経験したのか。新聞社で働いて四半世紀以上、締め切り時間に追われてきた身にとって、こんな贅沢はない。
南の果てへの道中、常夏のインドネシア・マカッサル海峡で撮った、この1枚。11月17日は不思議な夜だった。船の真上は晴れているのに左右いずれにも真っ黒な雷雲が出ていた。雲の中でピカピカと光る稲妻。不気味で幻想的な風景を写真に収めようと、高感度に強いニコンのD3Sを三脚に据えた。艦首と雷に照らされた海を撮るため右舷と左舷、はたまた中央と、最上部の甲板を黙々と行き来した。2時間近くたった時、突然、闇に向かって青白い強力な光が照射された。予期せぬ出来事に息を飲んだ。照らされたのは、氷山の視認に使うキセノン探照灯だった。
この時、艦橋では緊張が走っていた。レーダーに映った「影」。陸が近い海域では無灯火の漁船に出くわすことがある。暗い海を不規則に動き回る小船はやっかいだ。不審船が出ないとも限らない。単なる波かそれとも船か。最終的に信頼できるのは自分の目。当直士官は約五キロ前方を照らした。暗闇に目を凝らす当直員に光は禁物で点灯は一瞬だけ。レーダーが示した位置に船舶はなかった。
写真記者で複数回、観測隊に同行したのは私だけかと思う。取材は日本新聞協会代表扱いで同行者枠は「2」。私は2回とも取材者が自分だけという幸運に恵まれた。カメラマンはペン記者と一緒では、取材姿勢が受け身になりがちだ。が、1人だったら取材の対象や場所、方法、そして切り口まで全部、自分で決められる。原稿のボリュームも自分の判断だ。そのうえ、新聞社、通信社、テレビ局までカバーする代表取材。これ以上やりがいある現場はない。
同行取材は来年3月20日まで計130日間。前回、14年前の38次隊の時と何が変わったのか、変わらないものは何なのか。カメラマンの視点でじっくりと見極めてレポートしたい。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「目」
東京スポーツ新聞社 岡 宏信(おか ひろのぶ)
(2010年12月7日撮影、同9日1面掲載)
<取材者の弁>
市川海老蔵が暴行され入院してから10日以上、病院や所轄の警察署に張り込みの毎日。時には寒空の下で朝を迎えることもあり体は疲れ切っていた。この日も早朝から警察署で張り込んでいて交代の時間になったので会社に電話すると、本人が退院し夜に会見する予定だという。
一体どんな顔になっているんだろう?誰もが興味を持つことをストレートに表現しようと、顔をアップで撮るために400ミリの望遠レンズを持参し会見場に向かった。会見場に着いてみると始まるまでに2時間以上もあるにもかかわらず、集まった報道陣でごった返していた。
スチールカメラマンは約100人、しかもみんな考えは同じで殴られた左顔が見える側は望遠レンズを持ったカメラマンが集中、海老蔵が何かを話すたびにものすごい数のストロボが光った。顔の傷は特に目立ったものはなかったが左目は赤く充血し表情は暗かった。長時間に及ぶ会見になり何枚撮ってもあまり変わりない写真ばかりが増えていき、何とかならないかとシャッタースピードやストロボの光量をいろいろ変えて撮影してみた。すると赤く充血した目にピントを合わせ一番目が開いた瞬間にシャッターを押した1枚だけ、瞳孔までもが赤く染まった目が写っていた。
暗い場所でストロボを使うと目が赤く写る「赤目現象」というのがあるが、この時のような明るい照明下での会見で赤目現象が出る可能性はかなり低い。本当に瞳孔まで血で赤かったのか?今回の事件を象徴するような海老蔵の「目」が写っていた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「槍ケ岳、騒然」
日本経済新聞社編集局写真デザインセンター写真部 柏原 敬樹(かしわばら たかき)
(2010年8月13日撮影、11月7日電子版ライフセクション掲載)
<取材者の弁>
8月中旬、本紙電子版の新連載コラムの取材で、夏山シーズン真っ盛りの北アルプス・槍ケ岳(標高3180㍍)に登った。山頂の肩には山小屋に併設された夏季限定の診療所があり、登山者たちの安心のよりどころになっている。この「雲の上の診療所」で、どんなドラマが生まれるのか。ボランティア医師、看護師らに同行し、取材を始めた矢先のことだった。
「山頂付近で滑落事故」――。一般の登山者から知らせを聞いた山小屋の救助班と東京慈恵会医大・槍ケ岳診療所の医師が現場に急行する。私もヘルメットをかぶり標準ズームレンズをつけたカメラ1台だけを肩にかけ後を追う。日ごろの運動不足の上、相手はほぼ垂直の岩壁。カモシカのようにぐいぐいと高度を稼ぐ彼らの後ろ姿が次第に小さくなり、やがて消えた。息を弾ませて現場に着いたころには既に救助作業が始まっていた。
けが人は30歳代の女性。首の骨を折る重体だ。畳1畳ほどの岩棚の上で苦悶(くもん)の表情を浮かべている。ヘリコプターでの搬送を要する一刻を争う事態だ。落石の恐れもある状況で冷静沈着に手当をする医師、女性を背負い必死の表情で山小屋のヘリポートまで降ろす救助班。人命を救おうと奮闘する彼らの一挙手一投足を撮り逃すまいとファインダーをのぞき続けた。
興奮のせいか下りでも全く恐怖感はない。ヘリポートまであと少し。救助のヘリが爆音をとどろかせて旋回し始めた。ふと山小屋の方を見下ろして、はっとした。カラフルなウエアの登山者が人だかりを作っていた。みな心配そうにこちらを見上げている。「この慌ただしい雰囲気を写真に写し込めないだろうか」。それ以上、救助作業は追わず、高い位置からヘリの離陸シーンを撮影しようと決めた。着陸したヘリはけが人を収容すると即座に離陸。狙い通りに山小屋の手前を通過すると、この夏最大の事故で騒然とした槍ケ岳を象徴する一コマが出来上がった。
一連の救助作業やその後の診療所の様子は電子版で10月末からスタートした「ほっとニュースPhoto」で紹介した。「こころがほっとする写真ニュース」をコンセプトに、日常のちょっとしたいい話を組み写真と短文で絵本のように紹介するコラムだ。写真の枚数や記事の行数にとらわれない電子版という懐の深い舞台で日経写真部が臨む新たな試みだ。紙の新聞とはひと味違う「ほっとニュース」を探して、部員たちは全国を飛び回っている。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「魔法のフィルム、野菜すくすく」
日本農業新聞 編集局写真部 染谷 臨太郎(そめや りんたろう)
(2010年9月22日撮影、同11月7日1面掲載)
<取材者の弁>
土を使わず、厚さ0.06ミリの透明なフィルムの上で野菜を栽培する?そんなことが出来るのだろうか。
確かマンガの「ドラえもん」でこんな道具があったなぁと思いつつ、新技術の「フィルム農業」を開発した神奈川県平塚市のベンチャー企業に向かった。
研究員に話を聞くと、「水を含むことのできる高分子が……」となにやら難しそうな話。ぽかんとしている私に「細かい事はウィキって下さい」。その後、動画と丁寧な言葉で説明を受け「砂漠でも宇宙でも屋内であればどこでもOK」ということを理解した。
この魔法のようなフィルムは、腎臓病患者が人工透析などに使う医療用膜の技術を応用したものだそうで、水や養分だけを通し、菌やウイルスは通さないという優れもの。その上、与えた養液のほとんどを植物が無駄なく吸収し、水や肥料が最小限で済むというのだ。水不足が深刻な国からの注目も高く、アラブ首長国連邦の砂漠でトマトの栽培に成功。宇宙でも実験済みとのこと。「土耕よりも簡単で、水耕よりも低コスト。点滴栽培よりも品質の良い野菜ができる」と研究員は自信満々。
百聞は一見にしかり。早速、栽培サンプルを見せてもらうと、水を張ったバット内で、ベビーリーフがすくすくと育っていた。根が広がるフィルムを試しに指で押すと、ぷにぷにとした感触で気持ちがいい。
さて、撮影に入りいろんなアングルで撮ってみるものの、水耕栽培と似てしまい、いまひとつフィルムが分かりづらい。そこで、研究員にお願いして、逆さまに持ってもらい天井の蛍光灯を透過光にしたところ、納得できる被写体が現れた。
屋内(ハウス内含む)であればどこでも実践可能な日本発の新技術が世界を救うかもしれないと思いながらシャッターを押した。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「32年ぶりメダル!」
サンケイスポーツ写真報道局 大里 直也(おおさと なおや)
( 2010年11月14日撮影、同15日朝刊掲載)
<取材者の弁>
打って、飛んで、はしゃいで、泣いて。
バレーボール全日本女子の木村沙織選手は1つのプレーのたびに、感情をストレートに表現します。 いいスパイクが決まれば渾身の笑顔が炸裂し、ミスが続けば泣きそうになることも。
野球を中心に様々なスポーツを取材していますが、最近はポーカーフェイスの選手が多いように感じます。 勝っても負けても喜怒哀楽を見せない。
冷静を装った方がなんとなく「カッコイイ」と当の本人たちは考えているのでしょうが、 見ている方としても撮影する方としても、今ひとつ残念な気持ちになるのは私だけでしょうか。
そんな中で、バレーボールというのは木村選手に限らず、どの選手も喜びや悔しさをコートの上で隠さない。 個人的には貴重でおもしろい撮影対象だと思っています。
そんなバレーの世界大会で32年ぶりのメダルがかかった試合。これだけ感情表現が豊かな競技で、メダルをとったらどんな状況になってしまうのだろう、と恐る恐るレンズを構えました。
いつも以上の喜びの1枚を撮影しなくては。 メダルが近づくにつれて、高まっていく会場の熱狂を少しでも伝えたいと四苦八苦していた矢先、 木村選手が輪の中心で飛び上がってのガッツポーズ。これは!と思いシャッターを切りました。
髪の乱れ具合がいいアクセントになった、心からの歓喜の瞬間が写っていました。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「飲んで語るぜよ」
朝日新聞社写真センター 遠藤 啓生(えんどう ひろき)
(2010年10月27日撮影、同28日朝刊社会面掲載)
<取材者の弁>
今年はNHK大河ドラマ「龍馬伝」ブームで、各地で坂本龍馬にちなんだイベントが行われている。そんな中、東京・お茶ノ水のバーでは、お客が龍馬と妻おりょうに扮して歴史談議に花を咲かせていると聞いた。
お店に到着したのは午後7時すぎ。わずか10席あまりの小さな店のカウンターにはすでに紋付き袴、着物姿の男女数組が日本酒を片手に盛り上がっている。中には名前が全く同じ会社員「坂本龍馬」さんの姿も。薄暗い店の明かりを生かして、ストロボを外して撮影に入った。
しかし「龍馬とおりょう」とは言え、お客さんの扮し方も様々。おしゃれなメガネをかけた現代風の龍馬もいれば、金髪のおりょうもいる。撮り方を間違えれば、単なる成人式の帰りの若者にしか見えなくなってしまう。かろうじて龍馬然とした長髪の男性を手前にシャッターを押し始めた。
それでも、なかなか当初頭で描いていた幕末の風情が写し込めない。狭い店内で撮影アングルも限られており、締め切りを気にしながら四苦八苦していた。すると席を外していた先ほどの会社員・坂本龍馬さんが、刀を腰に、カツラをかぶり戻ってきた。
「助かったぜよ!」。そんな思いで締め切りギリギリの時間帯、彼を手前に数カットを撮影。無事翌日の社会面に紹介することができた。少しでも良い写真を、と撮影に協力してくださったお店の方々やお客さんには本当に感謝している。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「イチロー10年連続200安打達成」
共同通信社写真部 猪狩 みづき(いかり みづき)
(2010年9月23日現地時間撮影、24日配信)
<取材者の弁>
カナダ・トロントの球場ロジャーズ・センターのベンチの壁は高い。センターのカメラマン席から、イチローが安打を放って一塁に駆け込んだところをスタンド絡みで撮ろうとすると、ヨコ位置では拍手する観客がほとんど写らない。
「イチローが一塁に駆け込んでからタテにゆっくり持ち変えればいいんじゃない」。試合前、デスクが言った。9月23日、米大リーグ・ブルージェイズ対マリナーズ最終戦の第3打席。イチローは88マイルの直球を右前に打ち返し、10年連続200安打を達成した。得意の初球打ちだった。
私はといえば、インパクトの手応えはなし。いや、少し早かったかも。デスクとの打ち合わせ通り、イチローが一塁を駆け抜けたのを確かめてからカメラをヨコからタテに持ち変えた。観客が次々に立ち上がって拍手を始めたのを見て「よしよし」と思っていると、画面の端っこでチームメイトがベンチ前に整列して拍手しているのが見えるではないか。
急いでヨコ位置に持ち変え、ベンチバックの写真を撮った。塁上でコーチと話したり、一塁手に笑顔を見せたりして少しの間ためらっていたふうのイチローが、とうとう帽子を取ってスタンディング・オベーションに応え始めた。まずベンチに向かって、次に一塁側、センター、三塁側と体の向きを変えた。おぉ、センターを向く!と思ってカメラをタテに持ち直すと、肝心のイチローはもう三塁の方を向いてしまっていた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「地球に優しく COP10会場に自転車で通うオランダ代表団」
読売新聞中部支社 稲垣 政則(いながき まさのり)
(2010年10月26日撮影、同27日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
世界の生態系保全について話し合う生物多様性条約第10回締結国会議(COP10)が、10月18日から29日まで名古屋で開催された。11日に始まった関連会議も含めれば世界中から190か国・地域から約1万人が参加したという。
美しい地球を次世代につなげる重要な会議ではあるが、会議の写真というのはカメラマン泣かせ。良い写真はなかなか撮れない。国際色豊かな様子を写真に出来ないかと考えていたところ、社会部から耳よりな話を聞いた。オランダの代表メンバーが自転車で会場に通っているという。
7時から8時の間に来るということなので、念のため朝6時半に会場前に着いた。そのまま1時間が過ぎた。オランダ代表はなかなか来ない。当日は閣僚級会議の初日。そちらも取材をすることになっているため、8時には入り口の手荷物検査場に並ばなければならない。時計何度も見ながら、さらに待った。7時58分、あきらめて並びかけた時、遠くに自転車の一行が見えた。まず急いでシャッターを押したが、撮れた写真は今ひとつ。取材の意図をつたない英語で説明し、集まってもらってから自転車で入るシーンを撮らせてもらった。
時計を見ると8時3分。会議に間に合わないと大変だ。お礼もそこそこに手荷物検査場に走り、何とか間に合った。
寒い朝だった。タクシーで会場入りする関係者が多い中、自転車で会場入りするオランダ代表団。片言の英語を理解し、快く撮影に応じてくれた事に感謝している。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「川面を照らす巨大な灯籠」
時事通信社 写真部 今泉 茂聡(いまいずみ しげさと)
(2010年8月7日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
畳一畳分もある巨大な灯籠(とうろう)を浮かべる「古利根川流灯まつり」。埼玉にある開催場所は私の実家からわりと近く、帰省のついでに撮ってみた。
最近、なぜか故郷が面白い。郷土愛に目覚めてしまったのかもしれない。大学時代から東京に住み、就職、転勤先の大阪から戻り、また東京住まい。故郷がやけに新鮮に映る。これは中年の感覚だという自覚はあるが、要は自分が面白ければいいのだ。時間があるときに実家に帰り、老いた両親に変わりがないことを確認すると、当てのないドライブへ。10代の頃に何もないと思っていた場所で、目についた人や風景などを撮るようになった。
今回の写真は、そんな休日に撮った一枚。8月は「灯ろう」ものは結構多い。またかと言われそうでためらう気持ちもあったが、まあいいやと出稿した。三脚なしでも最近のデジカメは優秀だな、と思いながら帰路についた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「緊迫の尖閣沖 海保巡視船、中国漁業監視船にピタリ」
朝日新聞写真センター 越田 省吾(こしだ しょうご)
(2010年9月28日撮影、同29日朝刊社会面掲載)
<取材者の弁>
中国漁船と海保巡視船の衝突事件後、にわかに再燃した「尖閣問題」は、中国人船長の釈放後もくすぶり続けていた。そんな中、中国当局の漁業監視船が周辺海域に現れたという報を受け、本社機「あすか」で東シナ海に向かった。
「中国船は尖閣諸島の西側20数㌔を航行しているはず」。そんな情報を頼りに現場海域を飛んだ。中国から来た船ならば諸島より大陸寄りにいるだろう、示威行為が目的ならば日本の領海に接する接続水域を航行しているだろう、という見立てだ。
しかし、石垣空港を離陸して約2時間、それらしい船はまったく見あたらない。雷雲に覆われた魚釣島周辺で、雲間をぬって海上に目をこらすものの、出会うのは数隻の日本漁船や水産庁の船のみ。レーダー上の「船影」に近づいてはガッカリ、を何度も繰り返した。
「こっちにはいないだろうけど…」。目減りする燃料計をにらみながら、パイロットは機首を諸島の東側海域に向けた。レーダーに長細い影がいくつか。「帰る前にこれをつぶそう」。果たしてそれは、海上保安庁の巡視船だった。計5隻。みな同じ方角に進んでいる。そしてその先に見慣れない船がもう1隻。船尾に五星紅旗がはためいている。
中国の漁業監視船だ。機長らクルーの根気とプロ意識に感謝した。
一隻の漁船が起こした小波がいつしか大波となって、日中両国を揺さぶる外交問題に発展した。なんともはかなく、一筋縄ではいかないご近所づきあいなのだろう。「戦略的互恵関係」…。鈍色の波間に砂上の楼閣を見る思いがした
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「空飛ぶコメ」
産経新聞社 写真報道局 三尾 郁恵(みお いくえ)
(2010年9月26日撮影、同29日朝刊社会面掲載)
<取材者の弁>
記録的な猛暑がようやく終わり、秋の到来を告げる稲の天日干しの時期がやってきた。新潟県南魚沼市の石打円山スキー場では地元名産のコシヒカリをリフトにかけて乾燥させる「天空米」の天日干しが最盛期を迎えていた。
ゲレンデに到着、天空米が列をなしているように見える撮影ポイントを探そうとゲレンデを見上げると、身の丈を越すススキが生茂っていた。この中に入っていって蜂にでも刺されたら労災はおりるんだろうかと思いつつ、草むらに乗り込む。一歩進むたびに虫が飛び回り、体中にオナモミのような種がくっついてくるが、なかなかよい撮影ポイントは見付からない。だんだん体がかゆくなってくるばかり。頂上のリフト降り場から下を眺めたらどうだろうと行ってみたものの、リフト降り場付近には落下防止用の網が邪魔をして撮影できない。
ため息をつきながら草むらに戻り、撮影に邪魔なススキを踏み倒し、視界を広げやっとの思いで撮影した。次の日朝起きると腕や顔が虫食われで変形するほど腫れていた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「地上470メートルの競演 東京スカイツリー、中秋の名月と」
朝日新聞写真センター 関口 聡(せきぐち さとる)
(2010年9月22日撮影、同23日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
撮影者名こそ私の名前がクレジットされていますが、実際には取材に関わったデスク、記者、カメラマンたちの総力のチームプレーがあって、はじめて可能になった一枚です。
9月中旬、写真センターの川崎卓哉デスクが「中秋の名月の晩に、月のウサギが東京スカイツリー(以下、ツリー)を建設している写真が撮れないか」と切り出しました。同センターの安冨良弘カメラマンと私が撮影を担当することとなり、準備が始まりました。
レンズが長ければ長いほど、フレームの中で月が大きく写ります。その写真に小さくツリーを入れるためには、所在地の押上からずっと離れる必要があります。日没前後の空の明るさ、月の出とともに空を昇って行く月の明るさ、その時間と位置と角度、様々な条件が刻々と急速に変化してゆきます。
都心部は建物が多いため、地上に立つと視界を遮られてしまい、すべての場所からツリーが見えるとは限りません。そのため撮影には見晴らしの良い場所か、建物の屋上が適しています。月はほぼ真東からの上り始めることが分かったため、安冨カメラマンがツリーの真西に近い方角で、実際にツリーが見える場所を探しました。
いよいよ中秋の名月の当日。私は東大の敷地内の校舎の屋上に向かいました。建物への立ち入り・撮影取材許可は事前に交渉し許可を受けていました。
屋上に着き、三脚を立てて600mmレンズを設置し、月の出を待ちました。ツリーと月の競演を一枚の写真に入れるためには、両者の露出差も重要です。明るさに関しては当日の天候にも左右されるため、露出はほぼ「ぶっつけ本番」で撮影に臨みました。地変線近くの空気が霞んでいて、かつ日没前のため空も明るく、月の出の時刻を過ぎても月がなかなか姿を現しません。不安に思っているとそのとき第一展望台のすぐ左隣の空にうっすらと月が見え始めました。月は徐々に白い輝きを増しながら、体感的には非常に速いスピードでツリーのてっぺんをめがけ右上に昇って行きます。
この角度で昇ってゆく月が、ツリーの最上部と本当に重なるのか、祈るような気持ちで撮影を続けました、結果的にバランス良く中心に重なった写真を撮ることが出来ました。月が見え始めてからピークまで約6分間、ツリーに月がきれいに乗っていたのは約10秒間、あっという間の撮影でした。同一時刻には別のポジションで安冨カメラマンが別角度の写真を撮っています。彼が撮影した写真もとても迫力あるカットですが、紙面ではたまたま関口撮影分が採用になりました。まさに総力のチームプレーでした。
一枚の写真の中に人工と自然が入り交じり、どこかユーモラスで面白い。しかも工事中のツリーの姿は今しか撮れません。毎日が途上であり、毎日が旬な建造物。今年一年限りの東京の新しい光景です。将来、読者の皆さんが2010年の当時を思い出す、そんな記憶に残る写真になれば、撮影者としてこの上ない幸せです。
また現在、東武博物館(東京都墨田区東向島4丁目、03-3614-8811)で朝日新聞写真センターのカメラマンたちが撮影した東京スカイツリーの写真パネル16点を展示する「東京スカイツリー報道写真展」が開催されています。10月11日まで。写真展は無料ですが、入館料がかかります。内容は、完成時に実現する450m展望台からみた東京の新風景を空撮したパノラマ写真や、定点観測の写真、四季折々の街とツリーなど、紙面で紹介した写真を中心に構成しています。同展は10月26日から31日まで東京都中央区築地5丁目の朝日新聞東京本社2階コンコースで、11月には東京都墨田区吾妻橋1丁目のアサヒビールでも予定されています。お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「未来の植物工場」
東京新聞写真部 戸上 航一(とがみ こういち)
(2010年9月13日撮影、同16日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
それにしても野菜が高い。近所のスーパーではキャベツが1玉250円だ。冬の寒さと夏の猛暑。異常気象が消費者の懐を直撃している状況を変わった切り口で表現できないか、と頭をひねり、思いついたのが玉川大学の実験だった。以前から取材するタイミングを探っていた情報の1つで、まさに今がタイムリーと判断してアポイントを入れた。
天候の影響を受けずに野菜を生産できる「植物工場」。その光源に利用する人工光は蛍光灯が主流だ。同大農学部の渡辺博之教授は1990年代からLEDによる栽培研究に取り組み、現在は自らが開発した「ダイレクト水冷型ハイパワーLEDパネル」なる先端技術を使い国内最大規模の実験施設を管理している。
LEDについて渡辺教授から詳しい説明を受けると、「赤外線を出さず熱を伝えないため至近距離から照射しても植物の成長を妨げない」、「光合成に適した波長に制御しやすく、栄養価や品質の高い野菜を安定生産できる」ことが白色蛍光灯に勝る特色だという。課題のコストも、LEDの劣化原因である発熱を水で抑えて耐久性を増すことにより軽減させ、2―3年後の実用化が見込まれている。
クリーンルームになっている実験室へ入ると、まさに「未来の植物工場」だった。無機質にズラリと並んだ多段式の栽培装置を冷たい光線が照らす幻想的な空間。「Oh!」と撮りたい素材だが、記事の取材でエネルギーを使いすぎて意外なアングルが発想できない。栽培中の野菜も「最も少ない時期」(渡辺教授)だった。LEDの強い光を見つめるうちに目の感覚も異常になり、実際の色がさっぱり分からい。結局、14㍉レンズで野菜を手前にして仰ぐ無難な構図で、あとはカメラの性能に色の再現を任せて撮影した。
3日後の朝刊1面を見て驚いた。いわゆる「写真もの」としては破格の横位置でタテ3段半の大きさ。長めの記事も削られることなく、1字1句違わずに載っていた。さすがに色は階調と透明感がなくなり、絵の具をベッタリ塗ったようになってしまったが、新聞印刷の宿命だ。いろいろと夢を見させてもらった。感謝。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「大雨増水2人救助」
読売新聞東京本社写真部 冨田 大介(とみた だいすけ)
(2010年9月8日撮影、同9日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
9月8日、台風9号の影響で関東甲信地方は記録的な豪雨となった。東京でも激しい雨が降ったものの夕方にはあがり、一息ついたと思っていた時だった。神奈川・小田原市の酒匂川で男性2人が中州に取り残され救助を待っているとの一報が入った。
「今から出てもとても救助する場面には間に合わないだろう」などと考えつつ、東京・大手町の本社を出た。デスクから「NHKのニュースで救助隊が中州に到達した様子が出ている」「現場ではストロボが何度も光っている」と次々情報が入る。そして、何度も現在地を聞かれた。
午後7時すぎに現地付近に到着。消防車の赤回転灯で現場の方向はすぐにわかったが、周辺は報道陣の車がズラリ。車で川沿いの道を入っていくことは出来そうもない。リュックとカメラ、400㍉レンズをかついでダッシュした。悪天候に備えて長靴やカッパを車の中で身に着けたのだが、風雨はおさまっていた。雨具は動きにくくて暑いだけ。汗だくになりながら走っているうちに目に飛び込んできたのが、男性が川を渡っている姿だった。
露出もアングルも考える暇はなかった。すぐにカメラを構えてシャッターを押した。テレビのライトと投光器がきれいに現場を照らしていた。増水した川の流れる様子や夜の川の恐ろしさはストロボを使わないほうがいいだろうと、スイッチは切った。男性2人の救助作業は1人目が川を渡り始めて約10分で終了。間一髪で撮影できた。
最新の情報を伝えてくれたデスク、現場まで正確に誘導してくれた支局記者、デスクとのやりとりを聞きながら冷静に運転してくれたドライバー、全員の協力がなければ撮れなかったに違いない。写真取材にはチームワークが必要なのだと、つくづく思った。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「キス?」
東京スポーツ新聞社 仙波 宏一(せんば こういち)
(2010年9月1日撮影、同3日付け、17面に掲載)
<取材者の弁>
まるでキスをしているかのような小沢一郎&菅直人首相。
民主党、代表選挙立候補者共同記者会見での1コマ。先に登壇した菅首相が後から来た小沢氏を出迎え笑顔で握手。そして小沢氏が自分の机に向かうその立ち去り際をとらえたものだが、二人の間合いが絶妙なタイミングとなった。
その後に繰り広げられた「菅VS小沢」の舌戦。三段脚立の天板から400ミリレンズを手持ちで撮影していた私は、不安定な所からの撮影に汗だくで膝が笑っていたが、この写真を見つけたときは思わずニヤついてしまった。
絶妙なタイミングがもたらしたこの写真、記者の記事原稿の内容と相反していてますます面白くなる。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「東京スカイツリー、400㍍に」
共同通信社写真部 尾崎 優美(おざき ゆみ)
(2010年7月30日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
7月30日に400メートルを超えた「東京スカイツリー」。午後3時前後に建材が吊り上げられる時点で400メートルを超えるという情報が入り、空撮に臨んだ。デスクからの指示で、資料として高さ1500フィートの定点観測用の位置からも押さえようとしたところ、ちょうどその高さには雲が、途切れ途切れではあるが連なっていてヘリが入れないという不運な状況であった。
しかも建材がつり上がる気配も全くない。仕方がないのでヘリを上昇させ、旋回しながら待っている間に撮ったのがこの写真。パッチワークのように広がる雲と、その切れ間から時折見えるスカイツリーのバランスを考えながら撮影した。邪魔だと思っていた雲が、今や日本一を誇るスカイツリーの高さを際立たせていい脇役となってくれた。
結局建材は1時間半後に上がることになり、一旦ヘリポートへ引き返す羽目になったが無駄なフライトにはならずに済んだ。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「緑のカーテン」
東京新聞写真部 嶋 邦夫(しま くにお)
(2010年8月23日撮影、同24日夕刊1面掲載)
<取材者の弁>
「列島各地で最高気温更新」「東京都練馬区で38.2度」、「四日連続猛暑日」…連日、新聞やTVで猛暑を報じるニュースが続く。
“暑さ”を伝えるニュース写真には「満員の海水浴場」「かげろうが立つアスファルト」「ビル街で打ち水」「水辺で夕涼み」など様々な表現方法がある。しかし、衰える気配のなく続く暑さに、デスクや現場のカメラマンも新ネタ探しに四苦八苦。
ゴーヤーやヘチマなどで作られた「緑のカーテン」は、地球温暖化対策として「屋上緑化」と並んで、学校や役場などで導入が進められている。目新しさはないが注目したのは、その大きさ。東京・杉並区役所の壁一面を覆う緑のカーテンは、高さ25メートル(ビル7階)で日本最大級。「世界一背の高いヘチマ」として、区はギネスブックへ照会したほど(該当するジャンルが無く未公認)。9月下旬には屋上まで達する予定だか、酷暑が続く8月に掲載した方が、より読者に涼感を届けられるのではと考え「処暑」にあたる23日付夕刊用に取材した。
被写体が“巨大”なため、超広角レンズ(14ミリ)と、魚眼レンズ(10.5ミリ)を用意。魚眼レンズは歪み具合が非現実的にデフォルメされるため、できれば使いたくない。下からあおって、広角レンズ特有の歪みが出るのを抑えるため、写真部が保有する最大の7段脚立も持参した。
現場に到着すると状況は最悪。壁面に平行に伸びる遊歩道の端から、被写体までは僅か7~8m。七階建てのビル全てを収めるには近すぎる。庁舎は青梅街道に面しているので、道路の反対側からの撮影も想定していたが、手前の街路樹が高すぎて、ビル屋上に登っても全容が見えない。
「14ミリでは全体が収まりきれない。しかし、ゆがみの大きい魚眼レンズをニュース写真で使用していいのか…」。答えが出ないまま、締め切りが迫る。とうとう判断ができず、双方のレンズで建物だけを撮って、デスクに送信。どちらの撮り方で本番を撮るかの判断をゆだねてしまった。「魚眼の方が迫力ある。面白い方でいこうよ」。デスクの即決で撮影開始。写真を撮り終え、パソコンで写真を送り終えたのは締め切り時間とほぼ同時刻。デスクの英断で無事掲載できた一枚だった。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「大輪 競演」
朝日新聞社写真センター 古川 透(ふるかわ とおる)
(2010年7月31日撮影、8月3日オピニオン面に掲載)
<取材者の弁>
2010年の墨田川花火大会は、建設中の東京スカイツリーをからめた絵柄でいこう。2010年の「隅田川」は各社ともねらいが同じで、7月31日午後7時前には、打ち上げ場所とスカイツリーを中心に報道各社のヘリコプターが旋回していた。
空撮で花火を撮った例は過去にあまりなく、超高感度でも画像に影響が少ないカメラ(キャノンEOS―1D MarkⅣ)で、ASA感度は6400まで使い露出をかせいだ。花火の開く様子とヘリの振動に注意しながら、シャッタースピードは60分の1から125分の1の間を使った。
午後7時5分、第1会場から打ち上げ開始。日もすっかり暮れた午後7時半、第2会場からも打ち上げが始まる。町の明かりが灯った頃には、花火の色も鮮やかに見えるようになった。しかし、飛行している場所が関係するため、華やかな花火とスカイツリーがからむ構図は多くなかった。
何度か旋回している間に、第1と第2会場の花火が同時に打ち上がる。スカイツリーの手前にある第1会場では真っ赤な「しだれ」が炸裂、下にある隅田川の川面を赤く染めた
パイロットの操縦技術と、カメラ性能の進歩があってこそ撮れた写真だと思う。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「オレ流の隙」
東京スポーツ新聞社 野沢 俊介(のざわ しゅんすけ)
(2010年7月9日撮影、同11日4面掲載)
<取材者の弁>
球界きってのポーカーフェイスで知られる落合博満監督。投手陣がいくら打たれようが打線がいくら爆発しようがめったに表情を変えないのが“オレ流”。中日戦の取材といえばデスクから「今日の原稿は落合監督」と写真の注文を受けるたびに「すいません、こんな写真しか…」と言葉に詰まることがもっぱらだった。
首位巨人をナゴヤドームに迎えた7月9日、1対1の白熱した戦いにも落合監督は微動だにしない。「今日もデスクに謝らなきゃいけないのか」。そう嘆きながら三塁側カメラマン席から試合をのぞいていた。
すると4回裏、中日の森野将彦が1塁ベンチ前に放ったファウルボールを巨人の捕手鶴岡一成が猛烈な勢いで追った。鶴岡の背中をレンズで追っていると、ベンチの奥でみるみる顔が強張っていく落合監督の姿が見えた。「ウソだろ、こっちに来るなよ」と言わんばかりだ。すぐに落合監督に焦点を絞った。
次の瞬間、ボールしか見ていなかった鶴岡はフェンスに膝をぶつけ、その拍子で頭から勢いよくベンチにダイブしてしまった。夢中でシャッターを切った私の写真には上半身がベンチに埋もれ、名古屋城の天守にある金の鯱の様に体が反れた鶴岡に度肝を抜かれた表情の落合監督が写っていた。幸いベンチに飛び込んだ鶴岡、落合監督に怪我はなかった。「しっかりしろよ」。落合監督は苦笑いで鶴岡をグランドへ送り出すと何事も無かったかのようにいつものポーカーフェイスに戻った。
「まさかあの落合監督がこんな顔をするなんて」という驚きとともに、勝負師が見せた一瞬の“隙”を撮ることができ、今日くらい少しは胸を張って写真が出稿できるなと思えた瞬間だった。

題名「知床の夏」
毎日新聞社北海道報道部写真グループ 木葉 健二(このは けんじ)
(2010年6月18日撮影、7月13日夕刊1面に掲載)
<取材者の弁>
世界自然遺産5年に合わせて知床に取材へ向かった。知床と言えばヒグマだろうとまずはヒグマの撮影にチャレンジする。ヒグマが活発に動くのは夜明けの早い時間。北海道の夜明けは朝3時半ぐらい。事前に情報収集していたヒグマがよく出没するポイントに朝3時から車で移動しながら張り込むが初日は空振り。2日目も出ない。3日目も。出張の日程もあるのでさすがに焦る。かと言って徒歩でヒグマを探しに奥地に入る勇気はない。
次なる手段としてヒグマウォッチング船を頼ることに。聞けば遭遇率は9割近くとのこと。初めからこっちにすればよかったと一瞬後悔しながらも一般客と一緒に船に乗り込む。「こちらがフレペの滝です」との船長の案内に観光客は歓声を上げてシャッターを押すが私は滝には目もくれずヒグマを探す。船は滝や海鳥を紹介しながら知床の断崖沿いをゆっくりと進む。
まさか残りの1割に入ったかなあと心配し始めた時、船長の「親子がいるよ」の声。いた!親子ヒグマが海岸沿いに仲良く歩いている。あわててカメラの望遠レンズを構えるが船が揺れるためファインダーに収めるのに一苦労。船長の「昨日までは凪だったんだけどなあ」の声が恨めしい。その後、ヒグマの親子は船を気にすることなく、エサを探したり、木登りをしたりして森の中へと姿を消した。
他のお客さんも大満足し、さあ知床岬に向かいましょうと船長が船のエンジンをかけるとトラブルが。2つのエンジンの内の1つが動かない。そのまま港に引き上げることになり、1時間で戻れるところを超低速で3時間ほどかけて港に。結局ついていたのか、ついていなかったのか。まあ写真は撮れたのでついていたということか。

題名「左手一本 復活シュート」
朝日新聞社写真センター 河合 博司(かわい ひろし)
(2010年6月12日撮影、7月4日社会面掲載)
<取材者の弁>
僕の趣味はバスケットボール。子供たち3人全員が小学生の頃、地域スポーツでミニバスケットボールを教えてもらったのがきっかけだ。3人がミニバスを卒業した今も、家族の暮らす山梨県勝沼町で、自らプレーしながら地元の小学生にミニバスを指導している。同時に、選手の励ましになればと、全国大会目指す有力な高校生やミニバスチームの試合撮影を続け、迫力ある表情の写真をプレゼントしている。
高校バスケ部でプレーする僕の息子たちの試合撮影に出かけた体育館で、ライバル校に逆境にめげず頑張っている選手がいる、という話を聞いた。中学までは県選抜チームでスタメンに選ばれるほどの「スーパースター」。高校入学直前に脳出血で倒れ、右半身が不自由になった、という主人公の田中正幸君のことだ。ハンディを負ってもバスケを続けている。そんな気迫をチームの全員が理解し、みんなで田中君を全国大会に連れて行こうと日々練習に励み、本人も高校生活一度でいいから試合に出たい、とリハビリに精を出している、という話だった。
聞いた瞬間、社会面の人ものコラムで、彼を紹介しようと思った。これを記事にできなかったら、25年間写真記者を続けた僕の存在意義はない。何回も練習会場に通い、田中君の想いや行動を丁寧に聞き出し、飾らない言葉で事実だけを並べよう。
翌日、ライバル校の監督に取材を申し込むと、本人、母親、監督は快諾してくれた。しかし、ひとつ大きな問題があった。息子の学校と田中君の学校は毎年熾烈な試合を繰り返し、今夏の高校総体代表も、この2校のうちどちらか、との前評判だったからだ。取材と称して親がライバル校のスパイに来ている、と勘ぐられたらたまらない。両チームの父母たちは必ず試合観戦に集まり、お互いに総体の開かれる沖縄行きのチケットを予約済みだ。僕の顔も相手チームに割れている。
取材初日、ライバル校の体育館で選手にあいさつした。最後に「実は息子がバスケット部で……。目にした戦術は決して口外しませんから」と付け加えると、監督や選手は大笑いした。監督は「全然気にしていませんから。好きなようにやって下さい」。「○×君のお父さんですよね。大丈夫ですよ」と近づいてきた部員もいて、これでずいぶん気が楽になった。
田中君の試合出場をめぐり、監督と母親は直前まで迷っていた。彼は走れるようになったとはいえ、右手は使えないし右足には装具が欠かせない状況。リハビリを山にたとえるなら、やっと五合目にさしかかったくらいだ。格闘技まがいの激しい試合に出場させたら、相手チームに失礼ではないか。彼が試合でみじめな想いをしたら、今まで守り通した数少ないプライドさえ失ってしまうのでは、と。結局、試合3日前に監督が田中君の意志を確かめた。「それでも試合に出たい」と彼は即答した。
高校総体県予選初日の試合会場。体育館2階席で控え選手の取材をしていると、監督は「4クオータの最後に出しますから」と叫んだ。監督も選手も、試合とは別の問題で興奮していた。田中君と一緒にコートに立つ予定の選手は、専用のフォーメーションを前日練習したそうだ。ベンチの選手、体育館2階席から応援する選手たちは、彼の出番を待ち続けた。実は早朝、父母会から田中君出場を知らせる緊急連絡網がまわり、関東の大学に散らばっていた同期7人の大学生も集まっていた。
そのときが来た。監督は田中君らコートにたつ5人を集めてベンチに座らせ、入念に作戦の再確認をした。ただ試合に出すのではなく、シュートを決めさせる、という執念に満ちていた。大歓声に送り出されてコートに展開した選手たちは、懸命にボールを集めた。パスをつなぎ、ゴール左45度にいた田中くんにアシストパス。彼は片手で受け止め、片手でいきなりゴールを決めてしまった。
僕が撮った写真の背景に、「夢」と書かれた高校の応援幕、2階席から見守る同期の大学生、ベンチで泣きそうになりながら拳をにぎりしめる選手たちが写っていた。
田中君の学校は、流れをつかんだ。最大の山場だった息子の学校との対戦にも勝ち、6戦全勝で沖縄行きを決めた。田中君たちの晴れ姿を撮影したくて、僕は迷わず沖縄行きを決めた。

題名「オーバーヘッドが顔面を直撃」
報知新聞社写真部 杉山 彰一(すぎやま しょういち)
(2010年7月6日撮影=現地時間、8日付本紙7面に掲載)
<取材者の弁>
白熱する南アW杯がいよいよ大詰め。決勝進出をかけた準決勝の第1戦、ウルグアイ・オランダ戦での1シーン。オランダが先制した後、劣勢を跳ね返すように攻めるウルグアイにチャンスが訪れる。
前半28分、オランダゴールのペナルティエリア外でふわりと浮いたボールに、オランダ代表MFデゼーウとウルグアイ代表DFカセレスが反応。ヘディングでクリアしようとするデゼーウに対し、ゴールに背を向けていたカセレスがジャンプ。さすが南米の選手らしく、ファインダーを通してもオーバーヘッドシュートを放とうとしていることが判った。
タイミングを計りシャッターを切り、カセレスの左足がデゼーウの顔面を直撃する、何とも痛々しいプレーの瞬間を収めることに成功した。
今大会、開催地が南アフリカと地理的問題と決して治安の良い場所ではないため、取材するフォトグラファーの数が従来大会に比べ少ないようだ。ここまで数多くの試合を取材する機会に恵まれた。それでもさすが準決勝、あまり空席はない。
個人的にはゴールライン沿いのポジションが好きだが、やむなくタッチラインに席を確保して試合に臨みた。ここはゴールシーンを撮影するにはあまり適切な場所ではない。むしろゴールを決め歓喜する姿を追うことのできる席だ。
ただ、唯一オーバーヘッドキックだけは‘見える’位置なので想定はしていた。残念ながらゴールはならなかったが、悲願に向け両者一歩も引かない激しいシーンを撮影することができた。

題名「狂喜が狂気に」
東京スポーツ新聞社 仙波 宏一(せんば こういち)
(2010年6月15日撮影、翌16日付け17面に掲載)
<取材者の弁>
サッカーW杯・日本初戦のカメルーン戦、それまでの不調ぶりから『予選突破どころか1勝すらできない』との下馬評であった。そんな中でのまさかの勝利と、サッカー界の新たなるスターの誕生を感じさせる本田圭佑の鮮やかなゴールにサポーターも狂喜乱舞した。
東京・渋谷でパブリックビューイングの取材に当たっていた私は、深夜の渋谷が大変なことになると確信していた。試合終了とともに急いで渋谷駅前に向かった。既にサポーター達の宴は始まっていた。最初のうちは『ニッポン、ニッポン』とサポーター同士で勝利に狂喜していただけだったが、その行動は次第にエスカレートしていく。あちこちで街灯登りが始まり、発炎筒、花火、スクランブル交差点の占拠とまさに無法地帯だ。警戒の薄かった警察も手出しができない。
そして1台のタクシーが交差点内に取り残された。集団でそのタクシーを取り囲み、代わる代わるクルマに飛び乗って奇声を上げる様はまさにフーリガンだ。タクシーのちょうちんは非常を告げるランプが点滅し、タクシーメーターからは『SOS』の表示が空しく点灯していた。
まさに狂喜が狂気に変わる瞬間を目撃した。

題名「サッカーW杯、4強呼んだ“神の手”」
サンケイスポーツ写真報道局 財満 朝則(ざいま とものり)
(2010年7月2日撮影=現地時間、4日付けサンスポ9面に掲載)
<取材者の弁>
サッカーW杯南アフリカ大会の準々決勝、ウルグアイ対ガーナ戦。大変失礼ながら、あまり食指の動かない、話題性の乏しいカード。本音は、同日に別都市で行われる「オランダ対ブラジル戦」を取材したかった。だが、移動の航空券が満席で確保できず、やむなくこの試合を取材することになった。
試合会場に開始6時間前に到着。ヨハネスブルグのサッカーシティ競技場では、ピッチ際取材席の場合、当該国でないフォトグラファーには場所の選択権がない。担当者の気分で、ランダムにチケットを与えられ、そこで取材するしかないのだ。
この日指定された場所は、バックスタンド側タッチライン沿いのほぼ中央。これでは、どちら側でゴールが決まっても、まず背中しか映らない。歓喜してこちらに向かってくることはかなり期待薄。選べるなら、まずチョイスしない席だった。失望しながらフィールドに向かった。
試合は、90分を終えて1-1の同点。その後も得点がないまま迎えた延長後半の終了間際、ガーナが絶好の得点機になった。CKからの混戦で、浮き球をFWアディエが頭で押し込んだ――いったかと思った直後、ウルグアイのFWスアレス⑨がゴール寸前でボールをはね返した。しかも「両手」で――。
DFフシレも腕を伸ばしており、まるでバレーボールの2枚ブロックのようだった。明らかかつ確信的な得点阻止だった。
もちろんハンドの反則。スアレスはレッドカードで一発退場、かつガーナはPKを得る。しかし、何とFWジャンがまさかのPK失敗。程なく延長戦も終了。結局PK戦となり、ウルグアイが勝利をつかむ。結果的にこのハンドは、絶体絶命のピンチを救い、4強進出を呼び込む“神の手”ということになった。
その問題のハンドのシーン。ボールを止めに行くスアレスの手と顔が、ちょうど自分の取材席からよく見えており、絵的に「はまる」結果となった。他選手がかぶったり、角度が良くなかったり、撮影位置が写真の出来を大きく左右するサッカー取材だ。どの場所が絵になるか分からない。取材席の不遇を嘆いていたが、「こんなこともあるのだな」と感心しながら写真を電送した。

題名「鳩山首相のグッドサイン」
産経新聞社写真報道局 栗橋 隆悦(くりはし たかよし)
(2010年6月1日撮影 2日付朝刊掲載)
<取材者の弁>
6月1日夕、鳩山首相、小沢幹事長、輿石参議院議員会長(いずれも当時)の会談を取材する報道陣で国会の大臣室前は混雑していた。
首相の進退にかかわる会談は30分程で終了、先に大臣室を退出した小沢幹事長を大臣室から少し離れた廊下で撮影。まだ室内に鳩山首相が留まっていることを知り、再び大臣室前に戻るが、待ち構える報道陣はそのまま厚い壁となり、遅れてきた者が入りこめる場所はなかった。
前列に出ることはあきらめ、後方から腕を伸ばし、ノーファインダーでの撮影を試みることにした。待つこと20分、鳩山首相が大臣室を出てエレベーターに乗り込むまでのほんの数秒の間、前方のカメラマンの動きを頼りに、シャッターを押した。しばらくしてカメラの液晶モニターを確認すると、グッドサインを出した鳩山首相の姿があった。
会談に出席した3者は当日、沈黙を通したままだったので 翌日の紙面は首相が「続投に意欲」と報じ、グッドサインの真意も謎のまま様々推測されたが、その後の鳩山氏の発言を聞く限り、その時点ですでに「小沢氏を抱き込んだ自爆退陣」の意志は固まっていたようだ。

題名「突っ込め!」
共同通信社映像音声部 原田 浩司(はらだ こうじ)
(2010年5月19日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
「!!!!!!!!」
5月19日午前10時26分、バンコク市内、装甲車の拡声器から、声が響いた。タイ語は分からない。それでも、「突っ込め!!」という言葉だと雰囲気で分かった。若い兵士たちの顔に、戸惑いの色が広がっていった。バリケードの向こうには、重火器で武装したタクシン派が待ち構えているのかもしれないのだ。若い兵士たちの逡巡は、しばらく続いた。そして、意を決したように、彼らは竹やタイヤで組まれたバリケードを次々に乗り越えていった。
タイ国軍は、元首相タクシン派が占拠する地域へ強制排除に乗り出した。首都の中心部で、銃声や爆音が鳴り響く。数の力で、軍の優勢は明らか。短時間で、タクシン派側からの応戦は消えた。装甲車は陣形を崩し、兵士たちの表情も穏やかになり、初日の作戦が終了したことを感じさせた。そんな時に、「!!!!!!!」の声が響いたのだ。
聞くところによれば、やはり初日は威嚇目的で完全制圧は作戦に含まれていなかったそうだ。兵士たちの戸惑いは、当然のことだったろう。軍幹部の気まぐれな作戦変更に翻弄されていたのだ。
今回のタイ騒乱は、2カ月に渡った。私は、1カ月に及ぶ動画とカメラの両取材。肌で感じたことは、今回の騒乱は単なる政権争いではない。「金持ちvs貧乏人」の争いなのだ。タイには、相続税も贈与税もないそうだ。つまり、富める者は子孫の代まで繁栄が保証され、貧乏人は子孫の代まで貧乏だ。タクシン元首相は、決して正義の政治家だったわけではない。しかし、結果として、この厳しい現実に対して貧乏人の目を開かせる役割を果たした。
タイでは、くじ引きによる徴兵制度がある。公平なようであるが、高校に通いながら軍事教習プログラムを受講すれば免除という、“前線”への配備を逃れる手段はいくつかある。今回取材した限り、“前線”に立つ兵士には、地方出身の貧しい家庭の若者が目立った。そして「軍にはスイカが多い」という隠語がよく聞こえてきた。「軍服は緑だが、中身はタクシン派(赤はタクシン派のシンボルカラー)」という意味だ。
貧乏人同士が殺し合う・・・、高層ビルが立ち並ぶ近代都市バンコクで、悪い冗談のような話が現実のものとなった。杞憂に終われば良いが、きっと悪い冗談は今後も続いていくだろう。格差社会の落とす陰は、日本人にとっても他人事ではないはずだ。

題名「気さくというよりエキセントリック?中年ボーイの玉置浩二」
東京スポーツ新聞社 川出 剛(かわで たかし)
(2010年5月23日撮影、同日付13面に掲載)
<取材者の弁>
5月23日早朝。私は「安全地帯」のボーカル玉置浩二を追って、人影もまばらな成田空港につめていた。この日はアジアツアーの発表会見のため香港に出発する予定だったが「交際中の青田典子も連れていく」という情報を手に入れていた。もし本当なら、交際発覚後初めてのツーショットになる。待つのも苦にならなかった。
いよいよ玉置の乗った車が到着。しかし…降りてきたのは玉置と事務所関係者数人。どこにも青田の姿はない。「お預けか…」とがっくりし、とたんに手の中のカメラが重く感じた。だがこれくらいであきらめてはいられない。同時刻に青田が別便を予約しているという情報を思い出す。記者と手分けすれば別便もカバーできる。が…記者もカメラを持っているとはいえ、2ショットがあるのなら自分が撮りたい。いや、撮らねばならない。だが、どちらを追うべきか…どれだけ悩んでも結論はでず、結局デスクに相談した。返答はこうだ。「川出は玉置を追って、別便は記者にいってもらえ」。迷いの吹っ切れた私は急いで玉置の乗る便の搭乗ゲートに向かった。
するといた!玉置が青田と一緒に関係者に挨拶している。すぐに2人は特別待合室に向かってしまったが、居場所を見つければこちらのもの。あとはもう撮るだけだ。ほどなくして2人は免税店に現れた。周囲の人間が2人に気付く。だが完全に2人の世界に入っており、それを気にするそぶりもない。
「さすがスターだな」と妙な感心をしつつ、撮影開始。フラッシュが光り、記者が質問を始める。ここまでの様子から邪険にはしないだろうと予測はついたが、玉置の反応は、刺激慣れしているはずのマスコミをも仰天させた。
人目を気にして遠慮がちに後ろを歩く青田を「こっちこい」と呼び寄せ「結婚するね。俺も5回目。これで打ち止め。絶対別れない」と期待以上のコメントのオンパレード。恋愛モードに入った玉置はすごいとは噂には聞いていたが、これほどとは思わなかった。だが、ここで感心するのは早すぎたのである。
この直後だった。ある女性記者が「ジャズ歌手のマリーンさんとクラブで抱擁していたと報じられたが…」とぶつけたのである。恋愛真っ盛り、しかも新恋人の前ではまさに禁断の問い。玉置は怒るのか、笑うのか、それともスルーか?ファインダー越しにそのリアクションの瞬間を待ち構えていた私は思わず目が点になった。
玉置は両手を広げ、その女性記者をかたく抱擁したのだ。「マリーンは昔からの大切な友達だから」といって。もちろん青田の目前で。その青田もうろたえることなく冷静に見ていたのには「さすが」と思わず唸ってしまった。
だがこの抱擁も、マリーンが特別だからというわけでもなかった。玉置は搭乗待合室に来る間、誰彼かまわず抱きしめていたのだ。もちろん、男も。玉置の名曲はすべて恋愛中に作られていると聞く。まさに恋愛ゾーンど真ん中。「こりゃ新曲が楽しみだ」と思わずにはいられなかった。

題名「ちょんまげ」
共同通信社写真部 八田 尚彦(はった なおひこ)
(2010年5月9日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
大相撲夏場所初日の土佐豊―豊響。土俵際の投げの打ち合いで勝敗を分けたのはちょんまげだった。ファインダー越しには同体に見えて、どっちが勝ったんだろう?と、カメラのサムネイルを開いてみたら、豊響のちょんまげが土俵にフニャリとのっていた。物言いもついたが軍配通り、土佐豊が勝った。豊響もちょんまげが土俵についた時、負けを自覚していたかもしれない。
それにしても目を見張るのは、力士の力強さと身体の柔軟さを象徴するようなこの“3点倒立”と、組体操やシンクロ選手顔負けの開脚ぶり。“倒立”を支える土佐豊の右足と豊響の左足はピンと張り詰め、両力士、似たような体型なのも手伝ってきれいな好対称を見せてくれた。
もう少し右から、つまり、正反対の位置から撮れていれば、もっときれいなM字型のシンメトリーだっただろう。向正面側の溜まりから見ていた観客はきっとその瞬間が脳裏に焼きついているに違いない。
砂かぶりにいるカメラマンにとってはしかし、「豊響のちょんまげが先についており・・」との審判長の館内説明に沸く観客をよそに、目の前であんなアクロバティックな投げの打ち合いをされたら、生きた心地がしない。幸い、正面側のカメラマンがいないところに落ち、力士も擦り傷程度で済んだそうで、何よりだった。

題名「棚田に浮かぶ逆さ富士」
静岡新聞社写真部 塚原 勝二(つかはら かつじ)
(2010年4月30日撮影、5月1日付け朝刊1面で掲載)
<取材者の弁>
逆さ富士と言えば田貫湖(富士宮市)があまりに有名だ。田植えに備えて水を張った棚田の逆さ富士も捨てたものじゃない。そんな話をしてくれたのは富士宮市柚野むらおこしの活動を続ける80才の会長さんだった。季節限定、晴天で水面を波立たせるような風がなく、水田の水が澄んでいることなどいくつかの条件を挙げた。
その時は話題提供ぐらいにしか受けとめていなかったが次に立ち寄った造り酒屋でも「ここからの富士は稜線が長くたおやか(女性的)」など雑談の話題となり撮ってみようかと写欲が沸いた。
逆さ富士がよく見える棚田を捜しまわること小一時間。あぜ道の草刈りをしていた70代の男性と出会う。水面には刈り取られた草が浮いている。その合間に雪をかぶった逆さ富士が顔を見せていた。
「ここだ!」とシャッターを切る。もう少し後へ下がりたいがスペースがない。腰を落としてローアングルで撮ってみる。見る見るうちに逆さ富士が歪んでくる。しかし、うまく撮れた後、風が吹きはじめた。ラッキー。
本来の取材は別にあり副産物の1コマ。大型連休と言えば行楽や渋滞、混雑ばかりに目が向くが、中山間地の農家は都市部に出て行った息子や娘の手が借りられる農作物の時期。そんな視点も加わり1面を飾ることが出来た。
たっぷり時間のある写真愛好家は来年チャレンジして欲しい。数日前から天気予報を読み、じっくりと腰を据え好条件になるまで待つ。きっと我々報道カメラマンよりきれいな写真が撮れるだろう。
実は私この5月末をもって報道カメラマンを卒業します。デジタルからまたアナログカメラに後戻り、ゆっくり、のんびり締め切り時間に追われることなくカメラ片手にスケッチを楽しみます。

題名「金総書記を激写」
共同通信社中国総局 岩崎 稔(いわさき みのる)
(2010年5月3日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
4年ぶりに訪中した金正日総書記訪中取材のため丹東駅に行ったが総書記一行はすでに大連に向かっていた。急ぎ後を追い大連に急行した。大連までは車で約5時間、長い移動でぐったり。ようやく総書記が宿泊しているホテルに到着すると、警戒線の引かれたホテルの周りには、警察官が数メートル置きに立っていた。
ホテルに入ると厳重な荷物検査を受け、一旦喫茶店に向かった。白いカバーで覆い隠されたホテルの正門には高級車が何台も停車している。北朝鮮政府関係者の姿も見える。
喫茶店でしばらく様子をうかがっていると警備関係者が大勢現れ、リムジンが門の近くまで動いた。まもなくカーキ色のジャンパーにサングラス姿の金総書記が足を引きずりながら姿を見せた。ガラス越しに400ズームを構えて慌ててシャッターを切った。総書記が車に乗り込むまであっという間だった。
撮影を終え、早速現場を離れようと喫茶店のカウンターでジュース代を払っていると警察官が二人やって来て取り囲まれ、拘束された。総局に連絡しようとするが、携帯電話を奪われ、そのまま派出所へ連れて行かれた。
結局、約1時間半拘束された後ホテルに戻り、写真を送信することができた。

題名「中国青海省地震」
読売新聞北京支局 青山 謙太郎(あおやま けんたろう)
(2010年4月15日撮影、同16日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
「青海省で大きな地震があったらしい」。
4月14日午前7時50分の発生直後、読売新聞北京支局の同僚から連絡が入った。
成長著しい中国に赴任して約半年。西安に出張中だった私はすぐに空港に向かった。2つの飛行機を乗り継いで現場に一番近い西寧空港に着いたのは午前4時。近いと言っても被害が大きいチベット族自治州玉樹県までは900㌔の道のりだ。車をチャーターして現地入りを目指す。途中、標高5,000㍍の山脈越えがあった。同行した記者は頭痛や吐き気など高山病の症状で苦しんでいた。私はフルマラソン経験が生きたのか、多少めまいを感じたぐらいで乗り切れた。
約16時間かかって玉樹に到着したのは2日目の夜。朝刊の締め切りが迫っていた。何かを探さなければ。あせっていると闇の中から重機の音が響いていた。行方不明者を捜しているという。必死でシャッターを切った。
もっと別なカットを撮りたい。現場を歩き始めたが体が思うように動かない。ここも標高約4,000㍍。空気が薄い。
次の朝、見渡す限り崩れ落ちた建物の中から次々と遺体が運び出された。「ホォー、ホォー」とチベット僧の犠牲者への弔いの読経が静かに続く。
私も合掌しつつ、祈るような気持ちでカメラを構えた。
--------------------------------------------------------------------------------------------

題名「絶対王者陥落」
東京スポーツ新聞社 岡 宏信(おか ひろのぶ)
(2010年4月30日撮影、5月2日付け4面に掲載)
<取材者の弁>
WBC世界バンタム級タイトルマッチ、長谷川穂積×フェルナンド・モンティエルは誰もが予想しなかった結末を迎えた。
「絶対王者」と呼ばれている長谷川の勝利を疑う者はいないと言っても過言ではない試合、我々カメラマンもリングサイドでこのような結末になるとは誰も思っていなかった。
今日は乱打戦だったから1枚くらい・・・と思ってもなかなかいい写真がないのがボクシング取材の難しさ。特にパンチをタイミングよく撮影しようとするとどうしても勝ちそうな選手の体の動きに注目してしまう。この日もそんな感覚で撮影していたが
この瞬間だけ長谷川の右のガードが一瞬下がった、挑戦者・モンティエルの左フックが出たとたん無意識でシャッターを押していた。
タイミングよくシャッターを切れた時はシャッター幕が下りている瞬間だからファインダーでは確認できない。パンチを受けてロープ際までふらついて行く長谷川がそのままTKOされてしまうとは思わなかった。
本来このような時は取材が終わっても充実感で満たされるものだが、日本人ボクサーがまさかの敗戦とあってどこかそのような感覚を感じることができなかった。
「言い訳できない。悔しさはある」試合後の会見で目に涙を浮かべながら語った長谷川。その言葉、日ごろの取材で苦い思いをする私にとっては身に沁みる言葉であった。「絶対王者」その言葉が似合う長谷川だけに再起を願いたい。
---------------------------------------------------------------------------------------------

題名「勉教がしたい 南米人学校で」
日本経済新聞社写真部 剣持 常幸(けんもち つねゆき)
(2010年4月9日から日経電子版に掲載中)
<取材者の弁>
3月下旬にスタートした日経の電子版に、写真ビューアーができた。ストレートニュースのほかに、撮り下ろしの企画や紙面に連動したものをアップしている。
今回掲載したのは、景気の悪化で就学が危ぶまれた子どものルポ。主人公の少年は日系ブラジル人2世と日系ペルー人の間に生まれ、顔立ちは日本人と変わらない。組み写真にするような感覚で取材に臨んだが、インパクトのある写真がなかなか撮れない。いわゆるメーンが決まらないのだ。少年はクラスの中でも特に物静かな方だった。途中で発想を変えてみた。スペースの制約を受けないのが電子版。少年の内面が、全体を通して伝われば良いと思った。
普段の紙面では出来事のピークをとらえた写真を使うことが多い。えりすぐりの1枚を載せるのが報道写真の妙味だ。しかしそれだけが仕事ではないことを、少年から教えてもらった気がする。写真ビューアーには、17コマの写真を掲載して少年の「有り様」を表現したつもりだ。
この「一押し、この1枚」の趣旨とは若干反するかもしれないが、「一押し」のない写真を組んで表現する企画もありかもしれない。
(日経ホームページの「写真一覧」をクリックすると「テーマ特集」があり、その中に「勉強がしたい 南米人学校で」がある)
---------------------------------------------------------------------------------------------

題名「日本一競演」
東京新聞写真部 笠原 和則(かさはら かずのり)
(2010年3月30日撮影、未掲載)
<取材者の弁>
3月29日に東京タワーを超え、338メートルと日本一高い建造物となった東京スカイツリー。300メートルを超えた時は当日発表だったが、今回は3日前に「予告」されていたので、取材する各社は事前に撮影場所や記事を準備する時間があったのではないだろうか。
翌30日は真冬のような寒さだったものの、この時期には珍しく春霞のない快晴となったため、月1回の連載企画用に空撮を行った。最初はスカイツリーと東京タワーをからめた絵を撮るために千葉県松戸市上空まで離れて800ミリ、葛飾区上空で500ミリレンズを使ってそれぞれ撮影した。その後、スカイツリーに近づいてワイドレンズで撮影した写真がこの写真。この時期としては滅多にないくらいに視程が良く、東京タワーや西新宿のビル群など都心部と富士山をバックに撮影できた。
こんなチャンスを逃すまいと、さまざまな写真を撮っているとフライト時間は1時間半を越えてしまった。同乗した整備士によると外気温はマイナス6度とのことだったが、気分良く撮影していたためか寒さは感じなかった。スカイツリーの撮影を終えて着陸準備のためパイロットが東京ヘリポートと無線連絡を取った直後、東名高速道路で事故との一報。横浜市青葉区上空へ急行し、結局2時間以上もの長時間フライトとなった。
---------------------------------------------------------------------------------------------

題名「おきあがれ日本」
東京新聞写真部 松崎 浩一(まつざき こういち)
(2010年4月13日撮影、同14日朝刊2面(政治面)掲載)
<取材者の弁>
自民党に見切りを付け、新党「たちあがれ日本」を旗揚げした平沼赳夫元経済産業相、与謝野馨元財務相ら衆参両院議員5氏。記者会見では今の日本を憂い、「打倒民主党」を掲げた。石原慎太郎東京都知事の加勢もあって、血気盛んに見えたのですが…。
結党から4日目。「たちあがれ日本」にとって初となる衆院本会議。国民年金法の一部改正など重要法案を審議する議事日程だったが、報道各社カメラマンの狙いは自ずと新党メンバーに集まった。議場に入った平沼代表と与謝野共同代表の元には多くの与野党議員があいさつに訪れ、晴れやかな?滑り出だし。少し遅れて園田幹事長も自席に。「さてどうやって、メンバーを写し込むか…」と思案していると一人うとうと、二人うとうと…。
自民党離党劇から、政党要件を満たすために必要な5人の党員集めに奔走。ようやく新党結成にこぎ着け、マスコミ対応なども多々。平均年齢約70歳の超高齢メンバーには少々ハードな日々だったようで、レンズを通して見る限り、3人ともお疲れの様子がありあり。核保安サミット出席のため鳩山首相は訪米中。敵の御大将不在中に参院選に向けて妙案を思案中かもしれませんが、新しい議席はなんとも居心地がいいようで・・・。
---------------------------------------------------------------------------------------------

題名「NYに愛された男」
東京スポーツ新聞社 中田 卓也(なかた たくや)
(2010年4月13日現地時間撮影、未掲載。掲載は別カット)
<取材者の弁>
ファンに惜しまれつつヤンキースからエンゼルスに移籍した松井秀喜選手。
「ワールドシリーズのMVPなのになぜ?」と思った人も多いはず、私もそのうちの一人。新天地では開幕戦でのホームランやサヨナラヒットを放つなどエンゼルスの勝利に貢献し、エンゼルスファンも松井の存在を認めてきたようだ。
そんな松井秀喜がNYに戻ってくる!この日はヤンキースタジアムの開幕戦で試合前にワールドシリーズのチャンピオンリングの贈呈式が行われる予定だったのだが、報道陣の中では「チームが違うから贈呈式ではもらわず陰でこっそり渡すんじゃないか」とか「MVPなんだからもらうはずだ」など贈呈式に参加するかどうかの憶測が飛び交っていた。
そしていざ贈呈式が始まり、マリアーノ・リベラ、アレックス・ロドリゲスなどヤンキースの選手の名前が次々呼ばれ、最後にキャプテンのデレク・ジーターが呼ばれた。私は「贈呈式の最後に名前を呼ばれるのはジーターに決まっている、その後に呼ばれる人なんていない」と考えていたため、「もうだめか」、肩を落とした。
しかし、司会者がなにやら喋りはじめたではないか。何を言っているかさっぱりわからなかったが球場のファンが総立ちになり歓声を送っている。そして呼ばれた最後の名前が「HIDEKI MATSUI」。さっそうと3塁ベンチから飛び出す松井秀喜にあわててカメラを向ける。リングを受け取りファンの歓声に手を挙げ応える松井、その瞬間後ろで並んでいた選手、チーム関係者が彼の元へ駆け寄っていく。そして元チームメイトとの熱い抱擁。「日本人で一番NYに愛された男」そういっても過言ではない気がする光景。
カメラマン人生で初めて興奮し鳥肌が立った瞬間だった。私自身初めてのMLB取材、失敗ばかりで正直、嫌になることも多かったがこの瞬間、この場にいたことを心から感謝し今後の仕事に活かしていきたい。
---------------------------------------------------------------------------------------------

題名「春色競演」
東京新聞写真部 嶋邦夫(しま くにお)
(2010年年3月22日撮影、未掲載)
<取材者の弁>
「やっぱり桜には勝てないな」。この写真がボツになった時の私の感想である。
春分の日を含む連休中に掲載する目的でスケッチのネタを探した。デスクは「春らしく明るく爽やかなネタを」とリクエスト。この時点で、東京の桜の開花はまだ発表されていなかった。しかし、都内では八重桜、彼岸桜、川津桜などがソメイヨシノ以外の桜が街角をピンク色に染めていた。
「早咲きの桜なんかはどうですか」とデスクに問うと、「開花発表に合わせて取材するからダメだ」と却下。ならば桜よりも一足早く見ごろを迎える花を探そうと情報誌やインターネットなどで検索。「桜以外にも春の花は沢山あるんだぜ、見たことが無い初物の場所を出してやる」と、意地になってひねり出した。
場所は埼玉県八潮市木曽根の「中川やしおフラワーパーク」。少なくとも東京新聞には未掲載。中川の河川敷に120本の花桃が植えられ、すぐ脇にじゅうたんのように菜の花が広がる。ピンク色と黄色の鮮やかな春色の競演を楽しむことが出来る。
取材当日は快晴。朝刊用に人出が見込める昼時を狙って取材。現地は「桃まつり」なども開かれ、親子連れなどが一足早い春を満喫していた。人がいない場所でスケッチ写真を絵にするには非常に難しい。一般紙のカメラマンなら皆経験しているだろうが、ここは力ずくで“絵”にする必要もなく、カメラを向けていれば自然と作品が完成する素晴らしい現場だった。しかし・・・。
「開花が発表されたから、朝刊は都内の桜でいくよ、来週の夕刊にでも使えば」とデスクから連絡。ところが連休明けは雨、雨、雨…。そして、そのままお蔵入りに。
桜との勝負は、来年にお預けだ。
---------------------------------------------------------------------------------------------

題名「桜前線 異常あり」
日本農業新聞写真部 宗和知克(そうわ ともかつ)
(2010年3月21日撮影、同22日付1面掲載、写真企画「見桜前線」より)
<取材者の弁>
いま、農村各地の見ごろとなった桜を、カメラで追っている。
日本を代表する花木は、はかない美しさが魅力だと思うが、いつ咲くのか、いつ散るのか見極めが難しい。見応えのある満開を狙うとなるとなおさらだ。毎朝、各地の天気予報をチェック、役場や地元の人に、開花状況を確認することが日課になっている。
ただ、相手は自然。思いのほか満開が早まり、慌てて現場へ飛ぶことがある。かといえば開花宣言が出てから、10日ほど経っても見ごろを迎えず、地団駄を踏むこともあった。
この写真も苦心の一つ。徳島県神山町の伝統芸能「人形浄瑠璃」。地元農家たちが毎年、見事に咲き誇るしだれ桜の下で披露するものだ。
取材日は前日から、全国的に春の嵐が吹き荒れていた。事前に調べた現地の天気予報は、雨と強風。そうなれば屋外での上演は中止、桜とからめて撮れなくなる。荒天は取材当日の未明にさらに加速した。雷雨と強風に見舞われ、竜巻注意報まで出るありさま。しばしば窓の外を眺めては、憂鬱な気分に。幸いにも天候は、浄瑠璃の上演時間が迫るにつれて回復した。なんとか取材を済ませて、胸をなでおろした。
今年の桜前線は、少し変わっている。高知市で観測史上、最速タイの3月10日に開花宣言。これを皮切りに、九州・四国地方に早いペースで広がっていった。しかし下旬からは寒の戻りで太平洋側を中心に大雪警報が出る始末。この影響で各地の開花状況は大きく変化した。気象庁が2009年に「桜の開花予報」をやめた理由がよく分かる。寒暖が大きく、読めない・・・。
「世の中にたえて 桜のなかりせば 春の心はのどけからまし」(古今和歌集から)
学生時代に授業で習った、和歌を思い出す。作者の在原業平も同じような気持ちだっただろう。「桜を追っていなければ、どれだけのどかな気分でいられただろうか」。
これからしばらくの間、気象に振り回されると思うが、日本の春と向き合ってみようと思う。
---------------------------------------------------------------------------------------------

題名「This is GODZILLA !」
サンケイスポーツ写真報道局 吉澤良太(よしざわ りょうた)
(2010年3月24日撮影、同26日付サンスポ1面に掲載)
<取材者の弁>
新天地エンゼルスに活躍の場を求めて移籍してきた松井秀喜外野手。
初ヒットに初打点、初の守備と、何かにつけて「初」が話題になります。
でもみんなが待っているのは豪快な一発。初本塁打はいつ出るのでしょうか。
しかし、オープン戦9試合に出場してヒットはたったの4本。調子が悪いのかな?
そして、10試合目となるロイヤルズ戦の5回裏(多分この日、最終打席)
「今日もダメか・・」とあきらめかけていた時に松井選手が初球を強振しました。
鋭い当たりの大飛球がライトポール右に消えました。残念ながらファウル。
しかし、今年一番のスイングに心が震えました。
「これは来るかも・・」カメラマンとしての勘です。
豪快な一振りで自分の集中力が高まるのがわかりました。
2球目は余裕の見送り。そして3球目、松井選手が再び、鋭くバットを振り抜くと打球は青空へ吸い込まれました。
打球を追う松井の視線からホームランだとわかりました。
エンゼルスでの初ホームランが飛び出したのです。
「おめでとう!ゴジラ」
しかし、ゴジラらしさはこれでは終わりませんでした。
試合後、ホームランボールをカメラにおさめるために場外を歩いていると、
駐車場に停めてある高級車のフロントガラス(写真フロント左下)が割れていました。近くにボールが1つ転がっています。もしかしてこれに当たったの?
ありえません。本塁打は右中間でした。
しかし、この駐車場は右翼ポールよりもファウルグランド寄りです。
そうなんです。実は1球目の大ファウルが直撃したのでした。
球場の設計者も想定外の大飛球だったようです。
さらに驚いたのは破壊した車がエンゼルスのオーナーの車だったことです。
狙っても狙えないピンポイント爆撃です。
さすがはゴジラ、初ホームランにも武勇伝がつきました。
この男、やはりただ者じゃありません。
---------------------------------------------------------------------------------------------

題名「チリ大地震の影響で三陸海岸を襲う津波」
朝日新聞社写真センター 小宮路 勝(こみやじ まさる)
(2010年2月28日撮影、3月1日付け朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
2月28日早朝気象庁が大津波警報を各地に発表した。
私が担当する東北6県では過去同様にチリの地震による大津波で岩手や宮城の三陸海岸で甚大な被害があった場所だ。三陸海岸はリアス式海岸で波が大きくなり被害が広がる可能性がある。私が向かったのは浸水の可能性が高い宮城県気仙沼市。
本社からの指示で海岸沿いには近づくなと連絡が入り、漁港から数百メートル離れた避難所に移動して市民の表情を撮影した。
午後4時過ぎ津波が岸壁を越えて街中に入ってきた。避難所からも、海岸に向かう道路をゆっくりと進んでくる海水が見え騒然となった。道路で海水に気付いた自転車の人が慌ててペダルをこぎ始めた。小走りなら海水には追いつかれないがあっという間に周辺の道路を浸水させた。
水の深さは約20センチになった。ペットボトルやオイルの缶が流されてきて、あたりにはクラゲも浮いている。水しぶきを上げ走る車に、警察が大声で避難を呼びかけていた。津波は複数回押し寄せる。津波を知らせるサイレンに注意しながら高いビルに移動した。
上から見るとほとんどの道が浸水。まだ危険な状態だが人の気配もあった。側溝などがあり危険と思ったのか道の真ん中を歩く男性。まっすぐ進めば高台へ行く。避難しているのだろうか。何度もシャッターを切った。
三陸海岸沿いには防潮堤の不十分なところがある。本当に3メートルの津波が来たらと思うと怖くなる取材だった。
---------------------------------------------------------------------------------------------

題名「ワンルーム おひなさま」
産経新聞社写真報道局 緑川真実(みどりかわ まなみ)
(2010年2月22日撮影、同26日付社会面掲載)
<取材者の弁>
げた箱にきれいに並んだひな人形たち。
よーく見ると1人1人に表情があり、感情移入が始まった。ちょっぴり傷んだ顔からは歴史を感じる。ひな人形の歴史、バックにある校歌がかもし出す廃校となった学校の歴史、脳裏に入り乱れて消えていく。
表舞台からおりたものたちが再びスポットライトを浴びて、輝きだした。
見事再生を飾った新舞台には大勢の人々が訪れ、斬新なひな人形に驚きを隠さない。
昨年3月に廃校した千葉県勝浦市の旧行川小学校が、久しぶりににぎわいを見せた。
同市で3月3日まで開催された「かつうらビッグひな祭り」会場でのワンショットだ。
---------------------------------------------------------------------------------------------

題名「貧困直下大地震」
毎日新聞社写真部 梅村 直承(うめむら なおつね)
(2010年1月26日撮影、2月17日コラム面掲載)
<取材者の弁>
私は2万人以上の被災者と国連ハイチ安定化派遣団の部隊員約100人が衝突した現場の真ん中に立っていた。ハイチ大地震から13日がたった1月25日、首都ポルトープランスの大統領宮殿前の避難キャンプで食料の配布を国連が行った。われ先に食料へ進む被災者同士が押し合い大混乱となった。妊婦が卒倒し、高齢者は倒され、けがをする。武装した部隊員が被災者をけりつけ、殴り、鎮圧に乗り出した。装甲車の上から向けるレンズ越しに少年の姿が見えた。父親に肩車になり懸命に食料へ手を伸ばしていた。突如、目の前で部隊が威嚇発砲し、少年の目に恐怖が浮かぶ。国連部隊は鎮圧をあきらめ退去した。残り少なくなった食料に群衆が殺到する。地面にこぼれた麦を手ですくい、服の中に入れる。ののしり合いながら、米の袋をちぎれるほど引っ張る。大地震が最悪の貧困「直下」で起こったのだと、まざまざと見せつけられた思いがした。
おびえた少年の顔が脳裏に焼き付いて離れない。無事でいるのだろうか。
---------------------------------------------------------------------------------------------

題名「国母劇場」
東京スポーツ新聞社 下田 知仁(しもだ ともひと)
(2010年2月17日撮影(現地時間)、同19日、裏フロントに掲載)
<取材者の弁>
バンクーバー五輪、現地17日にサイプレスマウンテンで行われたスノーボード男子ハーフパイプに出場した国母和宏選手。
成田空港出発時に「腰パン」「サングラス」姿で登場。服装問題で日本オリンピック委員会に異例の警告を受けた。さらに、現地入り後は入村式の会見で「反省してまーす」。その後もジャパンハウスで謝罪会見を行うなど、日本国内で一躍〝時の人〟となった。もちろん、バンクーバーでも話題の的だった。
「何かが起こる予感がする」。サイプレスマウンテンで寒さをこらえながら取材をしていた私は、コースの中腹には登らず、フィニッシュライン付近で決勝の競技を終えた国母選手を待ち構えていた。
すると、決勝で8位入賞を果たした国母選手は不満の残る結果にかぶっていたヘルメット、ゴーグルを放り投げたではないか。慌てて近くに寄る。その後に口に含んだ水をピュー。私は夢中になってシャッターを切った。
試合後には「自分のスタイルを貫くことができた。いいことだと思う」と誇らしげに話した国母選手。今回は品格問題で猛バッシングを受けたが、競技では会場のファンから大歓声が送られていた。自分の感情をうまく出せない〝不器用すぎるスノーボーダー〟。私は今後もファインダー越しに注目していきたい。
---------------------------------------------------------------------------------------------

題名「超ミニ豚、医療用に期待」
日本農業新聞写真部 福本 卓郎(ふくもと たくお)
(昨年12月撮影、1月7日1面掲載)
<取材者の弁>
豚というと、食用というイメージが強い。しかし、今回、医療用実験動物として豚を育種する農家を取材、新しい農業の姿を見たような気がした。
現場の豚舎に入ると、ブッヒ~。生まれたての〝超ミニ豚〟のお出迎え。大きさは、世界最小級。体長12㌢、重さ300㌘、コーヒーカップにすっぽり入るほどだ。愛苦しい表情を見せているが、人の命を救う可能性を秘めていると思うと、尊敬の念を抱く。
ミニ豚の育種は、国家プロジェクトとして、取り組んでいる国もあるほど。臓器の機能や皮膚が人間に似ているため、治療法の確立や新薬開発にも結び付く可能性を持つ。最近、日本の大学や研究機関も注目している。このミニ豚は、「マイクロミニピッグ」と呼ばれる。静岡県富士宮市のベンチャー企業「富士マイクラ」が量産化に成功し、3月をめどに販売していくという。
一般的なペット用のミニ豚は、「ポットベリー」という品種。生まれたては、小さいものの、2年後には約50キロ以上にもなる。果たしてこれが〝ミニ〟と言えるのかと、疑問に感じる人も多いのでは?それでも食用の豚と比べ6分の1ほどの重さだ。
今回の「マイクロミニピッグ」は、成豚でも重さ10~15キロと、いかに小さいかが分かる。その分、餌代が少なく済み、飼育するスペースも少なくて済む。 販売価格は1頭25万円前後。豚の新たな分野での活用に期待したい。
---------------------------------------------------------------------------------------------

題名「花粉ロボ 出動前の最終調整」
産経新聞社 写真報道局 古厩正樹(ふるまや まさき)
(2010年1月中旬撮影、同23日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
「ポルーンロボ」は民間気象情報会社ウェザーニューズが一般家庭や企業、病院に設置する花粉観測機。人の頭を模したボールの口の部分から人間と同量の空気を吸い込み、花粉の飛散量が増えるに従って白、青、黄、赤、紫の五段階で目が光る。
本格的なスギ花粉シーズンを前に、同社の本部で最終調整の様子を取材させていただいた。見た目には光っている「目」だが、写真に写すのに一苦労。午後2時には取材現場に到着していたが、目の光が浮き上がる夕方まで待っての撮影となった。
嫌な顔一つせずカメラマンの光り待ちに付き合い、撮影時には抜群の笑顔をくれた同社キャスターのお姉さんのプロ意識のおかげで画にすることができた1枚でもある。

題名「大動脈ストップ!」
東京新聞写真部 淡路 久喜(あわじ ひさよし)
(2010年1月29日撮影、2月2日グラフ面掲載)
<取材者の弁>
新幹線が止まった! 日本の大動脈、東海道新幹線が架線事故で停電し、数千人が車内で缶詰めになっている。復旧までには時間がかかり、もしかしたら乗客が線路上を歩いて駅まで避難するかもしれない。そんな一報を受け急遽飛び出すことになった。
窓の外を見るとすでに夕闇が迫っている。ほとんどが高架上を走る新幹線。果たして車内や線路は見えるのだろうか? 大光量ストロボや望遠レンズなど持てるだけの機材を持ち新横浜方面に向け車に飛び乗った。現場に向かう途中、携帯電話のテレビでニュースを見ると、架線の修理が終わり、作業員が線路脇に待避している様子が映った。「これは、もうすぐ動きだすな。駅に向かうより乗客の表情を車外から撮る方が先決だ」と思い、線路上に止まった新幹線を探し出すことにした。地図とにらめっこしながら車を走らせると、程なく幹線道路を渡る高架で頭を出して停車した列車を見つけ出した。
下から見えるのは車両の天井付近のみ。やはり何も見えない。さて、どうしたものか。 どこか見下ろせる場所はないかとあたりを見回すと、高架に寄り添うように建っていた3階建てのビルが目に入る。屋上には手すりがついていて、どうやら上に出られる構造のようだ。明かりのついていたビル一階の建設事務所に飛び込み、事情を説明する。
私は生まれが関西。昨年12月までの8年間を大阪に勤務していたこともあり、話す言葉はすべて関西弁。「すんません、東京新聞のもんなんですが、新幹線が事故で止まってしもて、見えるとこ探してるんですわ。こちらの屋上から列車が見えるんで屋上に上げてもらえませんやろか?」 “東京”新聞なのに関西弁??? 対応に出た事務所の社長さんの顔には、明らかに“?”マークが浮かんでいるのがわかる。ひるまずにもう一度状況説明をすると、最後は苦笑いを浮かべながら鍵を開けくれた。
屋上に出て、私の目に飛び込んできたのは、上り線を挟んですぐそこに止まっている新大阪行きのひかり号。そして非常灯が灯る車内で疲れた表情を浮かべる乗客の顔だった。薄暗い車内で携帯メールを打つ人。非常灯の明かりで本を読む人。目を閉じシートに身を沈める人…。
寒さに震えながら考えられるだけの構図を撮り発車を待っていると、先ほどの社長さんが様子を見に再び屋上にあがってきた。「これ飲みな」手には温かい缶コーヒー。丁重にお断りしたのだが、「いいから!」と持たせてくれた。これまで事件や事故があるたびにいろんなお宅に上げてもらったが差し入れまでいただいたのは初めてである。
「お兄さんも寒いのに大変だね」と、ねぎらいの言葉をかけてくれる。空調が止まって蒸し暑いのだろうか。窓越しにこちらのやりとりを見ている薄着姿の乗客と目が合う。
「いやぁ、一番大変なんは閉じこめられた人たちですから…」程なくして車内にあかりが戻り、プアーンと汽笛一声、新大阪へと闇の中へと消えていった。
---------------------------------------------------------------------------------------------

産経新聞社 写真報道局 三尾 郁恵(みお いくえ)
(2010年1月23日撮影、同24日付朝刊社会面掲載)
<取材者の弁>
一年で最も寒い時期になろうとしている一月の終わり、東京・表参道に暑い夏を思い出させる祭りがやってきた。
東北三大祭りのひとつ「青森ねぶた」だ。午後5時、開始の合図とともにお囃子の太鼓や笛が鳴り響き、赤や黄色の色とりどりの造花をつけた傘に浴衣姿の跳人(踊り手)達が元気よく跳ね回る。巨大ねぶたも跳人に続いて「さあ、出発」、というところで原宿駅前の歩道橋が立ちはだかった。歩道橋の高さは巨大ねぶたとちょうど同じくらい、ねぶたの引き手達が必至にしゃがみこみ、巨大ねぶたを傾けて何とか歩道橋をくぐりぬけた。表参道冬ねぶたの関係者や沿道の観衆、みんながひやりとした瞬間だった。
その後、巨大ねぶたは神宮前交差点までの往復約600メートルを無事に運行。
迫力あるねぶたを間近で見ようと、週末でにぎわう表参道の歩道は人であふれかえり、運行を見守る観衆は盛んにカメラのシャッターを切っていた。

読売新聞ニューヨーク支局 小西 太郎(こにし たろう)
(1月14日撮影、18日夕刊グラフ面掲載)
<取材者の弁>
地震発生から24時間後の1月13日、ハイチの首都ポルトープランスに到着した。連日異様な光景を目にしている。一夜にして被災者キャンプと化した大統領府周辺の広場。じゅうたん爆撃を受けたかのようにがれきと化した中央市場。紙面化は難しいが、至る所に放置された遺体。眠るようにぽつんと路上に丸まっていた少年は、よく見ると額が陥没していた。
現地入り2日目の早朝、最初は歌声と聞き間違えた悲鳴に近寄っていくと、人だかりの中央に3人の女性が座り込んで泣いていた。目の前にある建物の中に母親が封じ込まれていることを知った直後だった。
3,4階はあったと思われる建物は、補強もろくにない積み木のような柱で支えられていたようで、強い地震の揺れに屋根と床だけが何層にも重なってぺしゃんこに潰れていた。中に取り残された者がいたとしても、重機を使わなければ救出は不可能だ。警察官の姿さえ目にすることはない状況で、救出作業など始まっていない。姉妹たちはなすすべもなく、時折腹ばいになってがれきのすき間を覗いては絶望の叫び声を上げていたのだ。
市内は停電、断水が続いている。撮影・通信機材の電源確保が困難だ。この原稿も手書きでメモ帳に記入してから、急いでパソコンで入力している。移動するために必要なガソリンを入手するのに半日かかったこともあった。取材に忙しいこともあり、食事は日に一食、一皿スパゲティを食べられればよいほうだ。
それでも迅速に現地入りに成功し、被災地で何が起きているのか多くの読者に伝える役割を少しでも果たせているのなら記者冥利に尽きる。
(1/18ハイチ・ポルトープランスで)

朝日新聞社写真センター 小宮路 勝(こみやじ まさる)
(1月14日撮影、翌15日朝刊2社に掲載)
2010年1月14日、福島県会津坂下町は零下3度、時折雪が吹き付ける。午後2時、下帯姿の男衆が役場前に列をなし登場すると約400年前から伝わる「大俵引き」が始まる。
雪をさけ周辺の建物に身を寄せていた観客も一斉に集まり、通りを埋めた。重さ5トンの大俵を挟み東西で向かい合う男たち。東方が勝つと米価が上がり、西方が勝てば豊作とされる。
さあ開始?と思ったら、関係者の長めの挨拶のためか、さすがの男衆もガタガタ震え出す。同じく特設やぐらの上で1時間近く本番を待ったカメラマンたちも頭に雪をつもらせ震えながら「早くはじめて」と願っていた。
暖かいところで育った私にはちょっと厳しい取材。息を吹きかけ凍りそうな指を温めながらシャッターを押した。ほとんど裸同然の男衆はさすがに東北育ち、大雪のなかでも力いっぱい綱を引き合う。東方が勝利。力のこもった勝負に私も一瞬だけ熱くなった。
景気の悪い話が多い中、昔から変わらない勢いのある祭りなどを見ると明るい気持ちになる。ぜひ皆さんも完全防寒でそんな「勢い」を見学されてはいかがだろうか。

東京新聞写真部 嶋 邦夫(しま くにお)
(2010年1月4日撮影、未掲載。紙面は別カットを掲載)
正月休みも終わり多くの企業が仕事始めとなる4日、新年の抱負や政治不信など、市民の生の声を伝える東京新聞こちら特報部の新年恒例企画「神田明神ルポ」で、朝から参拝客らの表情を追った。
商売の神様(えびす様)を祭ってあるため、参拝者のほとんどは大手町や丸の内などのビジネスマン。参道と境内はスーツ姿のサラリーマンらで通勤ラッシュなみの混雑。
TVや新聞で報道される明治神宮や鶴岡八幡宮などの初詣の光景は、着飾った親子連れや晴れ着姿の女性、流行の服を着た若者などで色鮮やか。しかし、4日の神田明神は濃い色のスーツやコートで暗く渋めのトーン。神田明神は賽銭箱の後ろにカメラが入れる構造のため、撮影したアングルはそれほど珍しい物ではない。
しかし、賽銭箱の後ろの位置からさらに離れた本殿の中から200mmレンズで境内を切り取ると、そこにはビジネスマンらの顔、顔、顔。子供や親子連れがほとんどいないため画面に空白が出来ることがなく、景気回復、商売繁盛を願うビジネスマンらの顔で埋まった。
参拝者からは撮影しているカメラマンが見えているはずだが、彼らの真剣な瞳はカメラマンを素通りして“えびす様”を見ているようだった。

時事通信写真部 写真・大石 剛(おおいし・つよし)
同写真部次長 文・大高 正人(おおたか まさと)
(写真は、2009年12月23日撮影、24日付朝刊用に配信)
公人中の公人である日本国内閣総理大臣。われわれ報道カメラマンが最も多くシャッターを押す被写体の一つだ。12月23日、開催中の「2009年報道写真展」に鳩山由紀夫首相夫妻が来場した。
会場には、09年の最大のニュースである「政権交代」に関する写真を集めたコーナーもある。そこで足を止めた首相は当然ながら上機嫌。衆院本会議で首相に指名された瞬間をとらえた写真のパネルに決め科白の「友愛」を書き込んだほか、渡されたデジカメで居並ぶ写真記者たちをパチリ。「いつも撮られてばかりだからなあ」と“逆取材”を楽しんだ。
幸夫人も負けていない。首相の髪の乱れが気になったのか、さっと手を伸ばして整えるパフォーマンスを見せた。
かつて首相といえば、重厚なオーラを放ち、黙って立っているだけで存在感があったものだ。が、こうした“静”の魅力は時代遅れなのか、今はパフォーマンス全盛だ。このスタイルを確立したのが小泉純一郎元首相だろう。逆に言うと、これが苦手な政治家はどうしても見劣りしてしまう。「絵になるか、ならないか」の判断はカメラマンの専門分野。各政党は次世代のリーダー選びにぜひわれわれ写真記者の意見も取り入れてほしいものだ。
さてその鳩山首相。衆院選での大勝による政権奪取で順風満帆なスタートと思われたが、このところ、重要な政策課題でのマニフェスト破りとの批判や自身の献金疑惑などで顔の曇る日が多い。本当の正念場は2010年だろう。「宇宙人」の異名があり、育ちの良さから来る茫洋としたキャラが持ち味の首相だが、内外に難問山積みのこの時代、それだけではいかにも頼りない。
時には「千万人といえどもわれ行かん」の気慨がほしいし、もっと言えば修羅場をくぐり抜けてきた政治家として、戦闘性を全開にして牙をむく場面を見てみたい。写真記者がハッとして思わずシャッターを押す気迫を首相が満天下に示す瞬間がいつ来るか。その時が日本にとってもターニングポイントになるだろう。
【事務局から】
「一押し、この1枚」に応募していただいた方たちに御礼申し上げます。2009年は、今回で終わりです。2010年も1月初旬から再開します。奮って応募してください。2009年分の「この1枚」は、報道写真展に展示された写真を収録した記念写真集の中に入れる予定です。写真集は2010年4月ごろ出来ます。

共同通信社写真部次長 冨田 晴海(とみた はるみ)
(2009年12月17日撮影、未配信)
<取材者の弁>
17日午前、写真でこの1年を振り返る年末恒例の「2009年報道写真展」が日本橋三越本店で始まった。今年は東京写真記者協会創立50周年記念ということもあり、初めて天皇、皇后両陛下が観賞に訪れた。お二人は、思い出の写真を見ながらにこやかに話す姿を見て、報道展実行委員のキャップとして、これまで苦労をしたかいがあったと実感した。
オープニングセレモニーには、この9月引退した元女子プロテニス選手の杉山愛さん、世界体操の女子個人総合で銅、種目別段違い平行棒で銀を獲得した鶴見虹子選手がテープカットして盛り上げてくれた。
写真展の作品は、一般6紙、通信社2社とスポーツ7紙から選出された15人の報道展実行委員が2カ月に1度、年6回集まって選考会を開き、各社指折りの作品の中から厳選している。各回ごとに持ち寄られる作品は約300枚で年間トータル2000枚以上になる。その中から実行委員の目と事務局長の目を通して選ばれた作品がこの報道写真展に展示されている。協会賞、部門賞、奨励賞は、優れた写真に実行委員の意見を添え、各社の部長が最終審査し投票で決めている。
会場でパンフレット配りや、案内をしている途中、来場者から「いい写真でした」、「感動しました」、「来年も楽しみにしています」などと声を掛けられると、1年間みんなで頑張ったかいがあったなとつくづく思う。この場をお借りして実行委員の皆さんと事務局長、関係者の皆さんにお礼を申し上げる。
また来年の報道展選考会は、オブザーバーとして希望する各社のカメラマンを招いて開催する予定だ。写真がどのように選ばれるのか、他社のカメラマンはどんな狙いで撮っているのか、などいろいろ刺激になると思う。皆さんの参加をお待ちしている。

東京スポーツ新聞社写真情報システム部 仙波 宏一(せんば こういち)
(2009年11月18日撮影、同20日付け夕刊1面に掲載)
<取材者の弁>
覚せい剤取締法違反の罪で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けたのりピーこと酒井法子元被告が、更生への第一歩として、介護福祉士の資格を取得するため大学へ進学することとなった。
進学先の大学を見学に訪れた際に私のカメラに向かって見せた『笑顔』は、まさに狙い通りの清純派アイドルそのものだった。
前日、酒井元被告が高崎市内の大学に見学に行くとの情報をつかんだ。当日は、早朝5時すぎに東京・青山の酒井元被告宅に3人のカメラマン、そして私を含む4人のカメラマンが大学に配置された。大学での撮影を担当する私は到着後、後輩カメラマンたちと学校施設をロケハンし、構内を見学するのりピーの姿を撮影できる場所を探した。私は、「自然に振舞う“女子大生のりピー”を撮りたい」と考え、車の中からその姿を狙うことにした。
11月とは思えないポカポカ陽気に加え、長時間のドライブで熱くなったボンネットから立ち込める熱気。おまけにフロントガラス越しと、ピントの合わせづらい悪条件の中、目の前に立ちはだかる電柱や木々などの障害物の隙間を、のりピーが通り過ぎる一瞬をカメラを構えて待ち続けた。
そして、ついにその時はやってきた。
突然、目の前に現れたのりピーの笑顔。「やった!」と喜んだのもつかの間、のりピーの現れた場所が、最も画像がゆがんでしまうフロントガラスの端の曲面越しになってしまったのだ。狭い車内で右往左往したものの、悪戦苦闘の末、無事に狙い通りの『笑顔』を撮影することに成功した。
今年は、8月の逮捕以来、送検、保釈と、のりピーのいろいろな顔を撮影したが、やっぱりのりピーには『笑顔』が似合う。

日本農業新聞写真部 福本卓郎(ふくもと たくお)
(2009年10月31日撮影、11月1日1面掲載)
<取材者の弁>
メード喫茶の聖地、秋葉原。ここで働くメードさんらが米づくりに挑む姿を追った。田植えから収穫、脱穀、精米まで一連の過程を経た米に、〝アキバ米〟と名づけ、イベントで試食した。
アイドルグループAKB48の活動拠点の秋葉原。この地から“アキバ型農業”を発信し、食料自給率の向上に貢献するのが狙い。特定非営利活動法人(NPO法人)「秋葉原で社会貢献を行う市民の会 リコリタ」が旗振り役で、日本農業新聞が後援した。メード喫茶や美容室などの店先でバケツに植えた稲を育てた。
イベントで使った米は、本社の屋上で育てた。バケツ25個分で茶わん10杯分。6月に種まきした稲はすくすく育ち、出来秋に収穫祭。この米を使った試食会では、メードさんがハートマークや名前など、参加者が希望した文字をケチャップでオムライスに描いた。
イベント参加者は、脱穀や精米のやり方をメードさんから教えてもらえるとあって、お気に入りの女性の前に陣取り、稲穂を牛乳パックでしごく脱穀のやり方を教わっていた。
若い男性参加者がお気に入りのメードさんに食べさせてもらいたいような仕草。すると、その傍らで「あーん」。メードさんにオムライス食べさせてもらう子どもをうらやましそうに見入っていた。
ほとんど、田植えや稲刈りをしたことがないという参加者。脱穀・精米のやり方に興味を持ち、デジカメやビデオで自分の作業を撮影していた。さすが、アキバならではの光景だった「ご飯を大切に食べたい」と参加者の言葉に、食の大切さを改めて実感した。

共同通信社写真部 稲熊 成之(いなくま しげゆき)
(2009年11月11日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
ここまで容疑者の顔が世間で注目された事件もあまりないように思う。何度も顔を変え、2年7カ月の間逃げ続けた容疑者の今の顔。やはりそれが逮捕当時、世間とメディアの最大の関心事だった。
私は、直前までバレーボール取材にあたっていたため、「市橋移送」で、新大阪駅での混乱を知らないまま東京駅に向かうことになってしまったのだが、現地に着くと一目見ただけでいつもの取材現場とは違うのが分かった。花道に警察官がずらりと並び、その後ろに報道関係者がぎっしり。それに大勢の見物人まで加わり、異様な光景だった。
午後11時45分に市橋容疑者を乗せた新幹線が東京駅に到着。しばらくして容疑者が改札に姿を見せてから、午前0時すぎに移送車が東京駅を出るまで、自分がどう動いたのかあまりよく覚えていない。ただフロントガラス越しに見た市橋容疑者の顔が、手配写真よりもやせて、やつれて見えたことはよく覚えている。
肝心の写真だが、カメラがマニュアルだったためピントも若干甘く、かなりアッパーで露出もかなりオーバーになってしまった。カメラのプレビューボタンを押したときに出てきた真っ白な写真を見て、自分の頭の中まで真っ白になった記憶がある。
恐る恐る帰社すると、デスクに「モニターの画面がまぶしくて輝いて見えたよ。けど、よく見ると、何だ、撮れてるじゃないの」と小言とも喜びともとれる一言でちょっと救われた気がした。

共同通信社写真部 尾形 祐介(おがた ゆうすけ)
(2009年8月7日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
女優・酒井法子が「容疑者」になった日、彼女の映像が都内の家電量販店で並ぶテレビにズラリと映っている様子を撮った。継母とともに山梨、東京、箱根と滞在先を転々としていたと後に明らかになったが、当時は山梨で携帯電話の電波をキャッチしたということ以外に有力情報は無く、居場所をつかめずにいた。当然酒井容疑者(現在は被告。執行猶予中)が失踪してからの様子を納めた写真は、どこの報道機関も持っていない。過去の資料写真が連日の紙面を飾っていた。
逮捕状が出たという一報を受け、数カ所の家電量販店に電話をした。夕方の繁忙時間帯での取材ということでなかなか良い返事が聞こえなかったが、一店舗だけOKしてくれた。テレビの並び方も手前に大型が一つ、奥に中型がズラリと並び、丁度店にいたお客さんにも了承を頂きバランス良く一枚に納まった。
撮るべき対象の「生」の姿が見えない状況であっても、工夫次第で紙面を割くに足る写真が撮れるのだと感じた。後日、大きく掲載された新聞数紙を持って店舗にお礼に伺った。覚せい剤事件という暗い話題の取材にもかかわらず快く撮影に協力して下さり、非常に有り難いことだと思った。
酒井法子被告には11月9日の判決公判で、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決が下った。初公判では「必ず覚せい剤をやめ、介護の仕事を勉強したい」と話したという。

日刊スポーツ新聞社写真部 浅見桂子(あさみ けいこ)
(2009年11月1日撮影、同2日付け朝刊2面に掲載)
<取材者の弁>
日本シリーズ第2戦。この日の最大関心事は「先発はだれなのか」いうこと。スポーツ紙の紙面ではダルビッシュの名前が踊っていたが、どこか半信半疑な空気が球場を覆っていた。そこに「日本ハム先発 ダルビッシュ有」のアナウンス。雪になりそうな外の寒さを吹き飛ばす盛り上がりを見せたところで、さらに始球式の特別ゲスト「新庄剛志」の名前が呼ばれた。
熱気は最高潮。札幌ドームでこの2ショットが見られるのは、新庄氏が引退した2006年以来とあって、地元ファンの地鳴りのような大歓声が響いた。久々に見る新庄氏は以前と変わらないオーラで少しうれしくなった。笑顔で握手までは想定していたが、腰に手を回し抱きつくように至近距離まで近づいて耳打ちする姿を見て「バラの匂いのガムでもかんでいるのだろうか・・・」と全く関係ないことを考えながら撮影していた。

産経新聞社写真報道局 栗橋隆悦(くりはし たかよし)
(2009年9月14日撮影、同15日付け朝刊掲載・代表写真)
<取材者の弁>
以前にも陛下は葉山で昨年9月と今年5月に和船に乗られていているが、今回正式に許可が得られての代表取材となった。当初は前日の13日の予定だったのが、海の状態が悪く1日延期された。
早朝、葉山御用邸近くの海岸に乗船される両陛下、そして悠仁さまを抱かれた秋篠宮妃紀子さまが到着、さっそく関係者総動員で和船を海岸近くの艇庫から海に出す作業が始まった。
両陛下も手伝われ、悠仁さまにライフジャケットを付けられる紀子さまの姿もほほえましかった。乗船された陛下がさっそく、和船をこがれ、続いて皇后さまもこがれた。
最初に想定していたよりもはるか沖まで進み、600mmのレンズにテレコンバーターを付けても足らないほど。舟の構造のせいか、座る位置によりしばらくは紀子さま、悠仁さまの正面の姿も見えずにいたが岸に戻る途中でなんとか見える瞬間があった。
下船の際には陛下が悠仁さまを抱き上げるなど、孫を思いやるおじいさまの姿そのものだった。

題名「奇跡の生還」
東京新聞写真部 沢田 将人(さわだ まさと)
(2009年10月28日撮影、同29日朝刊1面掲載)
<取材者の弁>
転覆漁船から3人救出
偶然、最高の瞬間に居合わせて撮れた1枚。でもその時点では、ことの重大さに気づいていなかった…。 10月28日午前11時40分ごろ、八丈島近海で消息を絶っていた漁船が発見されたとの報を受け、東京ヘリポートを離陸した。現場までは200キロ以上もある。夕刊最終版の締め切りにぎりぎり間に合うかという時間だ。
約1時間後、現場海域に到着した。転覆した漁船の周辺には海上保安庁の小型船とダイバーの姿。撮影を始めて間もなく、ダイバーは小型船に戻り、現場を離れた。そこまでで取材を終え、写真送信のため八丈島空港に向かった。
「漁船発見」という情報のみで急行したため、生存者がいることは知らなかった。ダイバーをアップで狙う余裕はなく、彼らは漁船を調べているだけだと思っていた。着陸後、写真部からの連絡でその事実を知り、急いで撮影したコマを見直した。「あった!」。ダイバーに交じって、救助される乗組員が写っていたのだ。
新聞各社の中で現場到着は遅い方だった。固定翼や大型ヘリを使った他社は、すでに撮影を終えていったん現場を離れていた。たまたまヘリが到着した時間が、救助活動のクライマックスだったのだ。幸運だった。
ちなみにこの文章を書いている30日現在、まだ八丈島にいる。立ち寄ったこの島に、救助された乗組員が搬送されたため、そのまま居残って取材を続けているためだ。
早く会社に戻り、自分の写真が掲載された新聞を見てみたい。
以上

題名「転げ落ちた把瑠都」
時事通信写真部・粟屋 克己(あわや かつき)
(2009年9月13日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
相撲を2階席から撮るときいつも悩むのはレンズの選択だ。キヤノンの場合は70―200ミリではちょっと短く、300ミリは画質が良いが、場合によっては決まり手で足が切れてしまう。
東京・両国国技館で大相撲秋場所初日、70―200ミリで取材して幸運だった。朝青龍が把瑠都を吊り上げたりしながら、怒とうの勢いで土俵下に押し出すまでを200ミリ側で撮った。普段はこれでおしまいだが、妙な歓声が上がっている。
(どこまで転がったんだろう?朝青龍と広めに絡めて撮ったら面白いかな?)
しかしズームアウトすれどもすれども姿が見当たらない。
(どこまで転がったんだ?)
70ミリまで引いたら、テレビカメラをなぎ倒して花道を数メートルも転がっている把瑠都の姿がようやく見えた。
観客、行司、カメラマンの視線が把瑠都に注がれ、朝青龍がどうだとばかりに引き上げて行く姿が一直線上に並んだ。2階席の撮影場所も良かった。色々な偶然がお膳立てして面白い写真が撮れることがあるものだ。

読売新聞ニューヨーク支局 小西 太郎(こにし たろう)
(2009年9月13日撮影=現地時間、紙面は未掲載、別カットを夕刊1面ほか掲載)
イチローのメジャー9年連続200本安打の記録達成が間近となり、ロサンゼルスに飛んだのが9月9日。ところが、4打数無安打で終わる日があれば、悪天で試合が中止になってしまったり、思うように記録が伸びない。
レンジャーズと対戦しているここテキサスでも記録が出ないと、更にシアトルへ移動しなければならない。直後に控えている取材予定が大幅に狂う。「今日もだめかなぁ…」、帰りの航空券を気にし始める他社カメラマンの焦りも理解できる。でも、イチロー本人が背負っている重圧に比べれば、取材陣なんて気楽なもんだ。
13日はデイゲームが行われ、続いて雨天で中止になっていた分がダブルヘッダーとして夜から行われることになった。そして、遂に記録達成。デスクからは「達成時は夕刊1面、スポ面、社面で大展開する。朝刊も返す。号外も出す。よろしく」と告げられている。とにかく絵柄を各面用に稼がなければ。
試合はマリナーズが勝利したおかげでチャンスが訪れた。健闘をたたえ合う選手たちの中で、試合中は決して見せなかった晴れやかな表情でイチローが笑っている。
米国駐在として赴任して既に1年近くになるのに、いまだ戸惑い、いら立つことも多い。そんな時、野球に専心して次々と記録を樹立していくイチローの姿は、時として己のふがいなさを思い知らしめ、また、それ以上に励みとなっている。
来年は「10年連続」に立ち会いたい。
---------------------------------------------------------------------------------------------

 題名「命を救う卵、生産急ピッチ」
題名「命を救う卵、生産急ピッチ」
時事通信社写真部 今泉 茂聡(いまいずみ しげさと)
(2009年9月11日撮影、同日配信)
新型インフルエンザの国産ワクチンはニワトリの有精卵にインフルエンザウイルスを注入し、培養、増殖させて製造する。新潟県新発田市の岩村養鶏は、有精卵を生育してワクチンを製造する研究所などに出荷している。
写真はスタッフが一つ一つの卵に光を当て、生育状況を確認している場面。暗室でスタッフの手さばきも早く、ブレるのでまとまりにくかった。ストロボを使うのもどうかと思い、検卵用のライトが卵と人を上手い具合に照らす瞬間を待ち、あきれるほど多くシャッターを切った。自分ながらの絵作りの虫がうずきだしたが、スタッフは真剣そのもので気軽に声を掛けられる雰囲気ではなかった。
撮影後、スタッフに感謝の意を告げると彼らは小さくうなずき、また作業に没頭。シャッター音が不快だったとは思うが集中していたのだろうか、意に介していないようだった。

共同通信社写真部 鈴木 大介(すずき だいすけ)
(2009年7月8日撮影、同日配信)
プロ野球・楽天球団の取材は、「ゲーム」プラス「野村監督」の取材だ。試合そっちのけで野村監督の一挙手一投足を狙うカメラマンがいれば、NHKを含めた在京テレビ局も、必ずスポーツニュースコーナーに「今日のボヤキ」を使う。これほどの丁重な扱いぶりは、12球団の監督でも野村監督ぐらいだろう。勝っても負けても「絵」になるのだ。
それゆえ、一般紙ではなかなか取材しない始球式についても、「捕手、野村が久々にキャッチャーミットを構える」となれば反応しないわけにはいかない。ただし、悩ましい問題が一つ。始球式を行う仙台市在住の沼田早苗さんは、全身の筋肉が徐々に動かなくなる「筋萎縮性側索硬化症」という難病を患い、今回の始球式は念願の夢舞台になるという。沼田さんを撮るために正面側から撮るか、野村監督を撮るためにセンター側から撮るか。正面にいれば、始球式を終えた後に沼田さんと野村監督の記念写真が撮れるという保険がかけられる。しかし、あくまでただの「記念写真」に終わってしまう。どうあがいても取材者は私1人…。
共同通信のカメラマンは、その現場ごとに一般紙寄りにもスポーツ紙寄りにも臨機応変に対応して、硬い写真、軟らかい写真を撮り分けなければならない。さっそく写真部のプロ野球担当デスクに声をかけ、仙台の編集部にも問い合わせてもらった。沼田さんをクローズアップさせた社会面サイド用の原稿は出稿されないという。ならば、狙いは「笑顔のノムさん」だ。
Kスタ宮城のセンター席から打席を撮るには多少レンズが短いが、400㍉に1.7倍のテレコンバータをつけて構える。笑顔の野村監督を中心に、沼田さんの車いすを押して登場した楽天・田中投手や打席のロッテ・西岡選手の笑顔もいいバランスに納まった。さらに野村監督の人気ぶりをうかがわせるかのように、多くのカメラマンで背景の「隙間」が埋まった。皮肉にも「短め」のレンズのおかげで、かえって面白い写真となり、スポーツ紙はおろか一般紙にも多く掲載していただいた。
今年の楽天は強い。10月2日現在の順位は、2位に浮上し、CS進出マジックが2になった。
今季限りで退団が有力視されているが、野村監督率いる楽天が、今年のプロ野球の台風の目になることは間違いない。

読売新聞東京本社写真部 上甲 鉄(じょうこう てつ)
(2009年8月13日撮影、同17日夕刊「ズームアップWEEKLY」で掲載)
計画から57年。群馬県長野原町で建設が進む八ッ場ダムの予定地には、3年前から時々訪れていた。衆院選で民主党が「ムダな公共事業」と名指し、マニフェストに建設中止を盛り込んだことをきっかけに、改めて現地へ向かった。
8月中旬、建設中の橋脚は順調に“成長”して、巨大な十字架のようになっていた。高さは約100メートル。日没後の濃紺の空を背景に不気味な姿に見えた。翌朝、ダムの底に沈むかもしれない田んぼに青々とした稲が育っている様子を残しておきたくなり、もう一度足を運んだ。
1時間も待っただろうか。雲が切れて青空がのぞいた時に撮影したのがこの1枚。米作りをしている男性がつぶやいた。「ここも(ダムの底に)沈むんだよなあ」。
長野原町で知り合った人たちは皆親切だった。食事に招いてくれたり、住民専用の小さな温泉に連れて行ってくれたり。帰るときには新鮮なトマトやナス、きれいな花々を山ほど持たせてくれた。電車で持って帰るのは少々大変だったけれど、うれしかった。
ダムは出来るのか。57年もの間、計画に翻弄され続けてきた人たちに、安心して暮らせる日が1日も早く訪れることを願っている。

朝日新聞社編集局写真センター 福留 庸友(ふくどめ ようすけ)
(2009年8月13日撮影、同日組み東京本社版夕刊2社面に掲載)
昨年の7月。
富士山山開きの取材で疲れた体を癒すため、地元の温泉で受けたマッサージのお兄さんとの会話がきっかけだった。「8月の深夜2~3時頃になると、富士山の山肌に登山者のヘッドライトの光跡が浮かび上がるんです。下界からはっきりと見られますよ」
大学時代に山登りをしていたけれど、そんな光景は見たことがない。
「一度でいいから絶対に見てみたい」今までにない新しいスケッチになるかも、という下心に思わずニンマリしてしまった。
帰社後、すぐにデスクに伝えると、「あ~あれねぇ。広告でも使われてたな」とそっけない反応。自分が見たことないだけで、過去に別のカメラマンが撮ったことのある写真だ。
「自分の目で見たい」今年の7月、一年間あたためてきた思いを再びデスクに伝えると、案の定「う~ん」と反応はかんばしくない。
しかし、数日後「13日の深夜にペルセウス座流星群が一番きれいに見えるみたいだから、流れ星と一緒に撮れたら過去の写真より面白いかも」と思いも寄らぬデスクの新案で取材をすることになった。
12日夜8時頃に日航機墜落事故24回忌の取材を終え群馬県上野村を出発、東京の本社にちょっとだけ立ち寄り、そのまま深夜の富士山を目指した。
唯一の懸案だった天気も快晴に恵まれ、あとは流れ星を待つのみ。長時間露光で狙ったが、一度シャッターを切ると、その画像処理の時間がほぼ同じだけかかり、カメラが動かず、すぐ次のシャッターが切れない。
そこで、いつ流れるか分からない流れ星をより確実に写すために、2台のカメラで交互に約20秒間露光を繰り返した。10分に1回ほどは、光の筋が天空をサーと駆け抜けるが、撮っていないときに限って流れ星が流れたり、富士山から遠い上空へ逃げていったり……。なかなか思い通りにいかない。
撮影を始めて約1時間後。1枚だけ、富士山頂上空に流れる流れ星が3つ写り込んだ。ほっと胸をなで下ろす。
隣りで撮影していた大阪の写真愛好家、「8月に入ってこんなに天気がよかったのは今日が初めて。ちょうど良いときに来たね」。車に泊まり込み、2ヶ月近く赤富士の撮影を続けているという。
その話を聞いて自分が取材した1日がたまたま晴れて、「撮った」というよりは「撮らせてもらった」と思った。
今度はヘッドライトの光跡も入って、もっときれいな写真を撮ろうと思っているが、天気を相手に考えると、その「今度」がいつになるか想像もできない。
写真は「瞬間との一期一会」という言葉をしみじみと感じた取材だった。

 題名「えさ、くれっ!」
題名「えさ、くれっ!」
毎日新聞社・内藤 絵美(ないとう えみ)
(09年7月28日撮影、紙面は別カットを掲載)
7月下旬、雨が降ったり止んだりの日。以前から興味があったコアジサシの子育てを撮影しようと営巣地である東京都大田区の下水処理施設へと足を運んだ。渡り鳥のコアジサシ。越冬期はニュージーランドやオーストラリアで過ごし4月ごろ日本に飛来し、5~8月に繁殖期を迎える。
てっきり沢山の巣があるのかと思いきや、親鳥の飛ぶ姿がパラパラと見えるだけ。現地を特別に案内してくれた調査員が「午前中探したのですが、ヒナが見つからないんですよ」と衝撃発言。天敵のカラスに食べられてしまったというのだ。
それでも「ヒナをどうしても見たい」と食い下がる私。双眼鏡片手の調査員にお願いし、再度一緒にヒナを探してもらう。
間もなくすると、調査員が「いますよヒナ。生まれて4日目ぐらいですね」とホっとした表情で教えてくれた。目を凝らして見ると確かに頭と背中が茶色の小さなヒナがちょろちょろと動き回っていた。
コアジサシは危険が迫ると糞で攻撃するという。やっと見つけたヒナを近くで撮影しようと近寄ると、案の定糞攻撃の嵐!シャツに糞を落とされながらも、借用した野鳥観察用のテント(ブラインド)を設置し、小窓にレンズ突き出し親鳥がえさをくわえて来るのをじっと待った。
観察していると、ヒナにもそれぞれ性格があるようで、じっとしている子供もいれば、「ここだよぉー」と力強く羽を広げ居場所を知らせ子供もいる。
4時間ほど夢中で撮影した。紙面は親鳥からヒナが餌をもらう瞬間を掲載したが、私はこの写真の方が気に入っている。ふわふわの羽毛がカワイイ。子供ながらにも、生きるために怒っているようにわめく必死の表情。自然界の摂理を教えられた瞬間でもある。
このヒナが無事に大きくなることを願いつつ、仲間と共に南に飛び立つ9月、もう一度会いたいなと思っている。
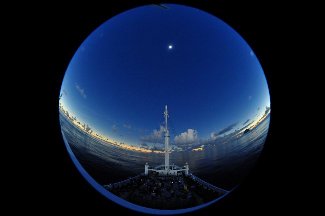
朝日新聞社編集局写真センター・川村 直子(かわむら なおこ)
(2009年7月22日撮影、未掲載。別カットを同日夕刊1面、社会面掲載)
約470人が参加する、貨客船「おがさわら丸」の「皆既日食クルーズ」に同乗した。
東京から南へ約1200キロの北硫黄島近海で、午前11時23分、太陽が完全に月に隠れる、皆既食が始まった。「わー、きれー・・・!」船上の歓声を聞きながら、私に感動に浸っている余裕はなかった。
部分食中、減光フィルターを2枚重ねて撮影していたのだが、皆既1分前を切って外したとたん、ファインダーの中は光があふれ、真っ白になった。ん?太陽はどこ?
船は進んでおり、太陽はすぐに画角から外れてしまう。ダイヤのような輝きを放つ瞬間に輪郭が見え、急いでシャッターを切った。
その後も雑観を撮ったり、コロナの周辺部撮影のために段階露出を繰り返したりで、長いはずの6分を超える皆既は、あっという間に過ぎた。
日食後、船長に話を聞くと「期待がかかっていたから・・・見せられて本当に良かった」と、何よりほっとした様子。ツアー担当者の方々の表情も緩んでいた。雲が多いなか、晴天域を狙って予定進路を変更しての観測だった。「みんなプレッシャーを感じてはったんやなぁ・・・」。親近感を一方的に抱きつつ、無事撮影できたことに改めて感謝した。
思い返せばやはり、闇のなか天頂近くに輝くコロナ、ピンク~オレンジに染まる水平線、気温が2.5℃下がり感じる涼しさは、非現実の感覚だった。

産経新聞臨海支局長・野村成次(のむら せいじ)
(2009年7月28日付け朝刊に掲載)
4月に、大手町からお台場に勤務先が代わって、今年は虹にツキがあるようだ。虹に出会ったのはもう3回目。虹というものが、希望のシンボルならば、景気回復を予兆しているのか、定年近い私の今後に、何かいいことがあると知らせてくれているのか、それとも単にネタを1度だけ提供してくれたのか、しかし世界には虹を不吉なものとする地域もあるとか、やれやれである。
その日は、天候が不安定で、朝は入道雲がモクモク。昼にはかなりの雨。そして夕方、日没の寸前に、夕日を浴びて東側に虹が出現。航空機は、お台場の上空を旋回して、羽田空港に着陸する。航空機が、その虹を横切るときにシャッターを切ったのがこれ。
支局の部屋の席で、パソコンに向かっていて、振り返ってパチリ。もう一度振り返って写真送信。効率のよすぎた1枚です。

毎日新聞社・須賀川 理(すかがわ おさむ)
(09年5月26日撮影 紙面は6月11日夕刊写真グラフで別カットを掲載)
重要文化財に指定が決まった高島屋東京店(東京都中央区日本橋)。1933年に完成した地上8階地下3階の鉄筋コンクリート造りで、三井本館や日本銀行本店、三越本店などと並ぶ日本橋界隈の顔で百貨店としては始めての指定となる。
建築当時、贅を尽くしたといわれる重厚な作りは東京大空襲などの戦火を逃れ、80年近く経った今も色あせていない。コンシェルジュの案内を受け建物を内外から撮影した。ルネッサンス様式の建築だが、柱の肘木や格天井など日本的な要素を随所に見ることができる意匠だ。
そんな中、建物の顔ともいうべき正面入り口に格納された鉄扉を紹介された。花菱文様が美しい重厚な造り。午前7時半から午後9時半まで壁面に格納され営業中は一部しか目にすることができない。扉が閉じた状態の建物を撮影することにした。
人通りの少なくなった午後9時半、格納されていた鉄扉を係りの男性が一つ一つ丁寧に閉め始めた。扉が広げられていくと同時に建物の重厚感がさらに増していく。最後の1枚がゆっくりと閉じられ、鉄扉の隙間から店内の明かりがもれる。オートマチックではない、関わりあう人の存在が無機質な石と鉄の壁面にぬくもりを与えていた。

産経新聞東京本社・写真報道局 植村光貴(うえむら こうき)
(2009年7月3日撮影、7月4日付朝刊1面に掲載)
衆院選を占う東京都議選の告示。麻生政権は危機的な状況下でのスタートとなった。今回産経新聞は2人で取材していたため、カメラ取材位置はもう1人に任せ、私はあえて離れた場所から選挙カーを狙った。
麻生首相は候補者、支援者、SPに囲まれながら聴衆の方を見て演説するため、ここからは、ほとんど見ることができない。私の周りの聴衆も少なかった。案の定、麻生首相の姿は最初と最後にチラっと見えただけだった。
ドロドロとした政治の世界を1枚の写真で表現するのは難しい。「赤信号」は、麻生政権の状況を分かりやすく表現したつもりで、個人的には好きな写真。しかし、読者はユーモアを理解してくれるかどうか…紙面掲載には判断が分かれるかもしれない。私自身も「選挙総括用の資料写真かな」程度の気持ちで出稿した1枚だった。
翌日の産経1面や夕刊フジに掲載され、社内的な評価も良かった。しかし読者からは「こじつけもいいところ。しばらく待てば青信号だろう」と“苦情”もきていた。
この読者のために次は「青信号になった麻生政権」を狙いたいと思っている。しばらく待っても難しいようだが…。

毎日新聞社・梅村直承(うめむら なおつね)
(09年4月27日撮影、紙面は未掲載)
アフリカ・ケニアの山間部にあるキエニ地区で、ノーベル平和賞受賞者、ワンガリ・マータイさんのNGO「グリーンベルト運動」が本格的な植樹活動を始めた。高原における困難な植樹活動を取材するため現地に入った私にも、幾多の困難が待っていた。
行われるはずの植樹が突然キャンセルされる、約束しても待ち人が来ない、等々、とにかく予定が立たない。土日になると「ホリデーだから」と誰も取材には付き合ってくれず、ボロボロのジープは、雨期の舗装されていない道で泥にはまりこみ数時間立ち往生・・・。これらを愚痴ると、NGOのスタッフに「ポレポレ、これがアフリカンスタイルだ」と笑われた。
苦闘を極めたのがムトゥカ地区。山間部の森林近くに地区の子どもたちが植林するとのことで向かった。雨でぬかるんだ赤土に足をとられ、機材を担ぎ歩く私は急勾配の山道に息を切らせた。村の子どもたちは私をからかいながら、歓声を上げ駆けるように登っていく。「まいったなぁ」と汗をふき続けた。植樹の現場に着くと、子どもたちは黙々と作業を始めた。カメラを手に私は覚えたばかりの言葉を叫んだ「チェカ(笑って)、チェカ!!」。変な発音が面白かったのか、子どもたちが大きく笑った。
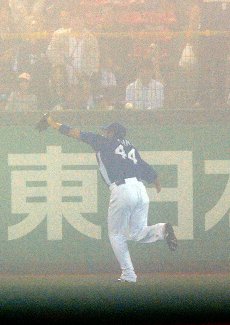
東京中日スポーツ・由木 直子(ゆうき なおこ)
(2009年6月10日撮影、未掲載)
プロ野球交流戦。Kスタ宮城で行われた楽天-中日の三回戦は、試合開始直後から雲行きが怪しかった。三塁側カメラマン席にいた私は、雨が降るのではとそわそわ。雨が降ると自分が濡れるだけでなく、カメラや送信用パソコンの雨対策がやっかいだからだ。
しかし、やってきたのは雨ではなく、なんと霧。時間とともに濃くなり、次第に内野手の顔さえ判別できないほどに。しかし、試合は続いて5回裏へ。この日、プロデビューとなった楽天・丈武の打球は小池の守るライト方向へ…と言っても実際には霧で打球が見えたわけではなかった。投手が振り向いた方向に合わせて瞬時にレンズを振ると、砂嵐のような視界の中に動く小池の白いズボンだけが見え、それを頼りにシャッターを押した。
この濃霧の中で捕球していれば超ファインプレーとなるが…。恐る恐るカメラの液晶画面で画像を確認すると、打球とは少し違った方向に懸命?にグラブを伸ばす小池の姿が写っていた。本人によれば「球を見失った」そうで記録は二塁打。頭の上に方向違いの白球がある姿は、ちょっと滑稽であり、ちょっぴり同情も。
天候に左右される屋外の球場はカメラマン泣かせなので、風雨にさらされることがなく、冷暖房完備のドーム球場はありがたい。しかし、霧にしっとりと濡れたカメラを片付けながら思った。いつもと違うシーンに出会うこともある。「屋外も悪くはないな」と。

読売新聞東京本社写真部・川口正峰(かわぐち まさみね)
(2007年3月23日撮影、5月2日夕刊グラフに掲載)
中国甘粛省・敦煌郊外の月牙泉(げつがせん)。鳴沙山のほとりにたたずむ三日月の泉は古くからシルクロードのオアシスとして旅人を癒やしてきたが、1980年代からの水資源の乱用により徐々に縮小している。
敦煌市は世界遺産の莫高窟(ばっこうくつ)や玉門関、陽関といった史跡を抱え年間120万人もの観光客が訪れる。元々砂漠の中の町だけに、地下水に頼る水の消費量も増え、水位が下がってしまった。
当時は中国の砂漠化取材を企画。写真グラフのメーンを模索するなかで、この月牙泉を空撮できないかと考えた。出発前、日本の旅行代理店から「現地の空撮は手配できた」という返事があり、一安心した。 河北省、甘粛省と砂漠化が進む地域を回り、植林の様子も取材したがインパクトが足りなかった。「これはまずい。手ぶらで帰るわけにはいかない」と藁にもすがる気持ちで空撮に臨むため月牙泉までたどり着いた。しかし、現場で待っていたのはオートバイにハングライダーの翼が付いたモーターハングライダー。要は翼をつけたバイクに二人乗りして空を飛ぶというもの。バイクだから当然足元はぶらんぶらん。
「これは落ちたら死ぬな」と思った。
離陸し200メートルほどの高度に達すると、地上からは想像もできなかった、砂がうねる鳴沙山と山すそに臨む月牙泉の姿が、息をのむ美しさで目に入った。観光客は点粒に見えた。これでも往年の半分の大きさだという。泉の周囲を3周ほどまわり地上に降りたときは、足が震えていた。
この写真は、夕刊の写真グラフ面で、1枚だけという異例のレイアウトで新聞
1ページ弱の大きさで掲載されました。思い出がいっぱいの1枚です。

朝日新聞社編集局写真センター
細川 卓(ほそかわ たく)
(2009年6月9日撮影、6月13日夕刊1社掲載)
今にもブルースでも歌い出しそうな、アシカの仲間、オタリアのクゥ。黄色いサングラスをかけて首をかしげる姿がとても愛らしい。7月22日に迫る皆既日食を見るべく、飼育されている東京・東池袋の「サンシャイン国際水族館」で、特訓中なのだそうだ(東京では部分日食ですが)。
実は、隣接するプラネタリウムに日食を疑似体験できる番組を取材に行った際、広報の方から「水族館ではこんなこともやってますよ」と教えて頂いたのが始まり。同じ日食モノということでプラネタリウムと2枚組で掲載された。
子どもの日は兜、クリスマスにはトナカイの角など、普段からかぶり物には慣れているようで、嫌な素振りも見せず、なかなか乗り気に見えた。「しょうもない」と言われてしまえばそれまでだが、朝、新聞を広げてクスッ、と笑っていただけたのなら幸い。

日本農業新聞 宗和 知克(そうわ ともかつ)
(2009年4月26日撮影、5月2日付1面で掲載)
田植えシーズンを迎えた長崎県松浦市の「土谷(どや)棚田」を上空から撮影した1枚。
空撮はヘリやセスナ機を使わず、専用のたこ(凧)につり下げたデジタルカメラで、高度約40㍍から写した。愛好家の間で「カイトフォト」と呼ばれている手法をとった。
水を張った土谷棚田は伊万里湾に面し、海側から心地よい潮風が吹いていた。たこを空に放ち、地上で糸を手繰る。シャッターはカメラ内のインターバル機能を使って5秒に1回切り続ける。撮影した画像は、映像送信機を使って地上の小型モニターで確認。画面を見ながら糸の長さを調整し、風向きが変われば風下に移動して最適なカメラポジションを探す。
一連の作業を繰り返すうちに、1枚ずつ形の異なる小さい田んぼが、魚のうろこのように並ぶ景色が飛び込んできた。ラジオコントロールで角度を調整して構図を決めると、掲載カットが生まれた。
カイトフォトによる空撮は天候に左右される。風が吹かなければ始まらず、撮影にたどり着かないことさえある。だから数日前から天気予報とにらめっこする。画面中の棚田で作られる米も、天候によってその年の作柄が決まるのだろう。手間の掛かる撮影だったが、少しだけ農家の苦労が分かった気がする。
今年1月から、カイトフォトによる「鳥の目線」で農村風景を切り取る写真企画『ふわり風撮』を、随時掲載している。タイトルには「風任せの空撮」という意味を込めて「風撮」という造語を付けている。

朝日新聞社編集局写真センター 樫山晃生(かしやま てるお)
(2009年5月11日撮影、同12日朝刊国際面で掲載)
<取材者の弁>
四川大地震発生から1年。再び被災地を訪れることができた。
少数民族であるチャン族の街・北川チャン族自治県曲山は最も被害の大きかった地域の一つ。建物の約8割が倒壊、行方不明者も含めて住民の約半数が犠牲になった。建物崩壊などの危険から立ち入りが制限されているが、5月12日の発生日前の3日間だけは追悼のため開放された。
復旧が困難なため20キロ離れた場所に新しい北川県が建設中。廃墟となった街は地震の記憶を後世に伝える遺跡として保存されることになっている。危険なので今でも街の大部分の地域は立ち入り禁止だ。通行できる道は1本だけ。昨年はホコリが舞い、ガラスの破片などが散乱していた道もある程度は片づけが進んでいる。震災直後、多くの遺体が集められ、埋葬された場所には芝生が敷かれ、その上に慰霊碑も建てられた。
被災者たちの思いは複雑だ。チャン族にとってそんな慰霊碑は意味を持たない。彼らの風習では死者の魂は自分の家に帰ってくるのだから。街ごと取り壊してしまうという噂もあったから「本当は戻って住み続けたいけれど、観光地となってでも姿を残してもらえるのはうれしい」。レストランやチャン族のおみやげを売る店も増え、12日には大勢の観光客が北川を訪れた。大地震の様子を納めたDVDや写真を売る人もいる。被災し生活基盤を失った人々にとって現実的に最も有望な収入源なのだ。
街の中心を流れる川に向かって祈りを捧げる人たちがいた。聞くと向こう岸の小学校で被災した子どものために祈っているのだという。対岸には立ち入りが禁止されているから大勢の人が石ころだらけの河原で紙銭を燃やし、花を手向けていた。川の上流では土砂が流れ込み、堰止め湖を作り、透明だった水も地震以来、濁ってしまったという。深い水色になった川があの世とこの世を隔てる境界線のように見えた。
以上

共同通信社写真部・金刺 洋平(かなさし ようへい)
(2009年6月7日撮影、未配信・出稿コマの別コマ)
<取材者の弁>
サッカー、岡田ジャパンが4大会連続4度目のW杯出場を決めた。
前半早々に先制点を奪ったものの、なかなか追加点が奪えない。逆に後半はウズベキスタンの猛攻を受け防戦一方。退場者1人、岡田監督も退席を命じられ、 ギリギリつかんだ勝利だった。
試合後、地元サポーターの大半は足早に引き揚げ、静まるパフタコル競技場。 テレビインタビューから戻ってきた岡田監督を選手が囲んでシャンパン(水)ファ イト。喜びが爆発した。選手、監督にとっては思い出深い地の一つになった事だ ろう。
一方、私は試合当日に激しい下痢に襲われ、“ハラハラ”ドキドキの90分間。 試合開始直前に駆け込んだパフタコル競技場の「トイレ」が思い出の地となって しまった。
以上

共同通信社写真部 尾崎 優美(おざき ゆみ)
(2009年5月7日(現地時間)撮影、8日配信)
<取材者の弁>
WBC出場後、初の故障者リスト入りを経てメジャーリーグ9年目のシーズンを迎えたマリナーズ・イチロー。開幕から2カ月間、全米各地でプレーする日本人メジャーリーガーを追いかけて連日移動と取材を繰り返す中で、何度か取材する機会があった。
ベンチは大抵、撮影エリアのすぐ脇に設けられているがテレビカメラが被って見えないことも多々ある。この球場の撮影エリアからは、端まで行けば柵越しにベンチの中が見下ろせたので試合前に覗いてみた。この日取材に来ていた日本人カメラマンは私だけで、柵で身体が隠れていたためか全く警戒もされず、先頭打者として準備中のイチローはチームメートに冗談でも言われているのか屈託なく笑っている。それまでは淡々とした表情の印象が強く、ここまでリラックスした笑顔を見るのは初めてだった。試合では安打3本に加え、盗塁にファインプレーと大活躍したため、この写真も無事配信された。
ただ、残念なことに写真の下部に柵の白い部分がぎりぎり入ってしまい、「あと10センチ、いや5センチ私の背が高かったら…」と、ジャスト150センチの身として思わずにはいられない1枚であった。
以上

日刊スポーツ新聞社 鹿野 芳博(かの よしひろ)
(2009年6月6日撮影、同7日付朝刊2、3面にワイド展開で掲載)
<取材者の弁>
サッカーW杯最終予選ウズベキスタン戦。FW岡崎慎司は倒れ込みながら得意のダイビングヘッドでゴールを奪い、2010年のW杯出場を決めました。この写真は、もちろん、ほふく前進でゴール裏に潜入し撮影したものではありません。試合前からワイドレンズを付けたカメラを設置し、ピントはゴールキーパー辺りに固定し、リモコンでシャッターを切りました。ただ、無線リモコンでは電波が弱く、シャッターがうまく連動しない事もあるので、約50メートルの有線コードでカメラを直結し、手元のカメラとすべてのコマが連動するようにしています。ゴール裏には頻繁にリモコンを仕掛けてますが、うまく撮れるのは10試合に1回あればいいという感じで、なかなか報われないものでもあります。
以上

毎日新聞社・長谷川直亮(はせがわ なおあき)
(09年2月17日撮影 紙面は未掲載)
<取材者の弁>
イスラエル軍の空爆と地上侵攻で1300人以上が死亡したパレスチナ自治区ガザ地区。停戦後約1ヶ月後の今年2月、復興が進まず厳しい生活が続くパレスチナの人々を取材するためガザ地区に入った。
最も被害の大きかった一つの街、ガザ北部のアベドラボに到着すると、辺り一面、がれきの山が広がっていた。イスラエル軍の攻撃を受け、今にも崩れ落ちそうな自宅に13人家族のムハンマド・アベドラボさんは暮らしていた。行き場のないアベドラボさん一家は風雨が吹き込む我が家で生活を続けるしかなかった。「ここ以外どこに行けというのか」と嘆きつぶやいた。
外壁はイスラエル軍の砲撃で吹き飛ばされ、外にはガレキの街が広がっていた。薄暗い家屋の中で所在なさそうにたたずむ家族の黒い影。その悲しげな影がパレスチナの人々の絶望を表しているかのように見えた。
一連の取材は2、3月の紙面で現地からの緊急報告と連載、写真グラフで掲載したが、この1枚は紙面の構成上掲載されなかった。しかし、お気に入りのワンショットで、「一押し、この1枚」で発表でき、私としても嬉しい。
注:この地方にアベドラボ姓が多いことから地名も同じになったという
以上

共同通信社写真部・江 天(こう てん)
(2009年5月1日撮影、同日配信)
<取材者の弁>
GWを丸々使って開催された卓球の世界選手権。地元開催と言うこともあってか、日本人選手の活躍が著しく、中でも印象深かったのは石川佳純選手が福原愛選手の記録に並び、シングルスでベスト8に入ったことだった。
写真は5月1日の福岡春菜戦。石川選手は、前日に世界ランキングで大きく上回る香港の選手を逆転で破る大金星をあげ、この日は今大会シングルスで唯一となる日本人対決が実現した。
写真としては二人の絡みがほしい。色々試したが、どれもいまいちだった。
勝ったときのガッツポーズで何かできないか。ほかのカメラマンがコート正面に並ぶ中、一人反対側に陣取った。初日から通しで取材する中で、石川選手が試合終了時に決まって後ろを振り返ってガッツポーズをすること気づき、今回もそれに賭けてみようと思った。感度6400、絞りを8まで絞り込み、その瞬間を待った。
翌日の紙面では、自社でカメラマンを出していた社も含め、複数の社がこの写真を掲載してくれていて嬉しくなった。
石川選手は巷で言うと花盛りの女子高生。しかし質素で飾らず、話をしてみると礼儀正しく好感が持てる。個人的にも応援していた選手だけに、お気に入りの一枚となった。
以上

時事通信社写真部・今泉 茂聡(いまいずみ しげさと)
(2009年4月29日撮影、未配信のため新聞には未掲載)
<取材者の弁>
大相撲夏場所を前に行われた横綱審議委員のけいこ総見。今場所も何かと注目される横綱朝青龍。この日は昨年12月に心臓の手術を受けた脚本家の内館牧子委員がけいこ総見に復帰したことも話題の一つ。
これまで内館委員は舌鋒鋭く朝青龍を批判してきた。この日の朝青龍はけいこ総見を無難にこなし、比較的「優等生」ぶりを発揮。最後に審議委員席に近づき一礼し、何事もなく終わるかに見えた。
しかしその後、朝青龍が内館委員の元に近寄り始めた。犬猿の仲と目される二人。すわ戦闘開始かと思い、カメラを持つ手に緊張が走った。しかし結果は予想外の握手。さらに顔を近づけ、朝青龍は内館委員に快気祝いの言葉を贈った。
内館委員は「(豊臣)秀吉のような人たらしだから」と精一杯、突っ張ってみせたが、撮影した一連のコマを振り返ってチェックして見ると満更でもない表情だった。
以上

産経新聞東京本社・写真報道局 大西史朗(おおにし しろう)
(2009年4月18日撮影、4月19日付朝刊一面に掲載)
<取材者の弁>
埼玉・秩父市街地を望む「羊山公園」の傾斜に咲き誇るシバザクラ。
ピンクや白の花のじゅうたんが見頃を迎えたということで取材に行くことに。
「変わったアングルのものをたのむよ!」出発前にNデスクからそう言われ、去年も取材に行った身としては「何としても今年は違ったものを撮りたい!」
そう思いながら現地へ向かった。
「いいな」と思ってカメラを構えると、何か去年撮ったような気が・・・
そんな思いをしながらしばらく歩き回っているうちにふと近くを見ると、
小さな花、一輪一輪が美しく咲き誇る姿に目を奪われた。
「そういえば花の形が分かる写真は見たことがないな」
「何とかこの小さな花と広大なシバザクラの模様が一緒に写らないものか」
そう考え、目の前で花が咲き、かつ背景に花のじゅうたんが見える位置を探した。
何とか場所を見つけ、ワイドレンズをつけたカメラを地面につけ、撮影。
カメラのモニターで確認すると、手前には花びら一枚一枚が写り、背景には花の模様が広がっていた。
この写真は背景が傾斜になっていたため撮れた一枚だが、後日
「今までに見たことのない写真だね」 「どうやって撮ったの?」などと言われ、
久しぶりに反応のあった一枚でした。

読売新聞東京本社写真部・小林 武仁(こばやし たけひと)
(2009年2月24日撮影、同25日付け朝刊一面掲載)
<取材者の弁>
今年2月下旬、オバマ米新大統領と麻生首相との日米首脳会談を取材する機会に恵まれた。両者は初顔合わせ。麻生首相はオバマ新大統領にとって、初めてホワイトハウス内に招き入れる外国人首脳となった。取材する私にとっても、初めてホワイトハウス内に入ることができる機会。機中2泊、ワシントン1泊という強行スケジュールではあったが、会談冒頭の「頭撮り」の一枚を撮るために政府専用機に同乗した。「撮影がうまくいかず外電写真を使われたら・・」。緊張と不安はもちろんあった。
ホワイトハウスは予想した以上に警備が厳しかった。ボディーチェックの他、あらゆる荷物は爆弾探知犬による検査を受けるほど徹底していた。またワイトハウスの中に入る前には、厳冬の屋外で1時間以上も待たされるはめに。
日本からの同行カメラマンの数は少なかったが、スチールやムービーの米国人カメラマンの総数は20人を超えていた。しかし取材場所の大統領執務室はとても狭く、カメラマン全員が納得ゆく位置で撮影できる状況ではなかった。
外国での慣れない環境のもとでの首脳会談取材を、さらにむずかしい状況にしたのが、巨体米国人カメラマンと屈強なSPの存在だ。出入り口では、はじき飛ばされるように、まずポジション取りに失敗した。「しまった、良い表情が撮れていない・・」。そこで無情にも「撮影終了」の合図。ほどなく、正面で撮影していた米国人カメラマンが移動。開き直って正面に移動した。「(麻生)総理、握手をお願いします」と必死に声をかけた。オバマ大統領も懇願する私の窮状を悟ってくれたのか、麻生首相とともに快くポーズをとってカメラに笑顔を見せるなど応えてくれた。米国メディアにはなかった、「笑顔で握手の写真」は、こうしたいきさつによって生まれた。
以上

報知新聞社写真部 関口 俊明 (せきぐち としあき)
2009年4月22日、巨人ーヤクルト戦(佐賀)で撮影 同23日付け2面に掲載
<取材者の弁>
ヤクルト・福地(写真)の地元・佐賀で行われた初の巨人公式戦。地元という事でハッスルしたのか、
8回裏2死三塁、巨人・松本の左翼ポール際に上がった打球を追ってヤクルトの左翼手・福地がフェンスに激突。捕球もできずファウルとなった。
私は通常のカメラポジションにとらわれない、他社には撮れないような違った角度、瞬間を狙ってスタンドにいた。当然、社の立場から巨人の松本を望遠で撮影していたが、左耳に飛び込んできた激突の音に反応し首に提げていたもう一台の70-200mmズームでフェンス越しに撮影した。「あ~っ」悔しいのか痛いのか、うめき声が聞こえる。激突の瞬間を撮影したわけではないので瞬間を捉えた写真ではないが、ここまで自分の目の前でけがのシーンを撮れることはなかなか珍しい。良い写真は腕が必要だが運もなければ撮れない。

毎日新聞社写真部 内藤 絵美(ないとう えみ)
2009年3月21日撮影 紙面は未掲載
<取材者の弁>
「ニッポニア・ニッポン」の学名を持つ鳥、トキ。「放鳥から半年」に合わせ、厳冬を無事に越えてたくましく生きるトキを撮ろうと佐渡に渡った。
トキは繊細な鳥らしい、と事前に聞いていた。脅かせばその場所に戻ってこないらしいということで、撮影場所は常にトキから100㍍ほど離れた場所と決めていた。
環境省、新潟県、佐渡市など多くの人間がトキ復帰に必死なのだ。私も離れた場所から見つめるのに必死だ。
3泊4日の取材期間で、田んぼでえさを啄ばみ元気に大空を飛ぶトキをバッチリ撮影。その様子は3月25日夕刊に1面で掲載した。
「いち押し」に応募した写真は、トキが田んぼで餌を探している時にこちらをうかがった(であろう)一瞬。
じっと待っていたらこちらに近寄ってきて片足をあげたまま「ハイ、ポーズ」。100㍍先から私に会いに歩いて来てくれたのかと思ったくらい嬉しい瞬間だった。
紙面には未掲載だが、とても気に入っているワンショットだ。

毎日新聞社・須賀川 理(すかがわ おさむ)
(2009年3月12日午前5時54分、横浜市鶴見区の大黒大橋で撮影、同12日夕刊一面掲載
<取材者の弁>
富士山の山頂に満月がかかる「パール富士」。その存在を知ったのは2年前、
デスクから太陽が山頂にかかる「ダイヤモンド富士を撮ってこい」と言われた時だった。資料を探していて偶然見つけた何とも不思議な写真。明け方の空に薄っすらと浮かぶ富士山頂で淡く光る満月。「ダイヤモンド富士よりもこっちの方が綺麗だな」と思った。
2月下旬、「次の満月でパール富士は見えないだろうか?」。ふと思い立ち富士山と天体の位置関係を計算するソフトで調べてみた。割り出したのが横浜市の大黒大橋で午前5時54分。空の明るさも丁度良い時間だった。
当日、現地に到着したのは午前5時。まだ高い月が照らす橋の上ではすでに数人がカメラを構えていた。「ここで間違いない」。少しほっとするが、西に見えるはずの富士山はまだ闇の中だ。「ガスで見えないのかも」。不安を覚えつつ準備を始めると隣の男性が「1年以上、パール富士を狙っているけど一度も撮れた事がない」と笑った。
寒風の中、不安を抱えて待つのに耐え切れず、みなとみらいに向けて意味もなシャッターを切ってみた。肉眼では見えない富士山の姿が液晶画面にはうっすらと写っている。心の中でガッツポーズしながらパール富士の一瞬を待った。

日刊スポーツ新聞社 ■見 朱実(たえみ あけみ) ※たえは"玄"ヘンに"少"
(09年2月24日撮影(現地時間)、同26日付け一面に掲載)
<取材者の弁>
タイガー・ウッズと石川遼が握手を交わすシーン、
とにかく大変な混乱ぶりでした。
日米のスチールカメラマン、テレビカメラマン、
警備員で50人ほどいたでしょうか。
殺到した男性カメラマンにはじき飛ばされ、
必死の思いでシャッターを押したことを記憶しています。
こんな状況になることは事前に想像できず、
撮影レンズは24㎜(17㎜を持参していたのですが・・・)。
そのため握手する2人の手が半分切れてしまいました。
おそるおそるかけた国際電話で、
やさしい?デスクに慰められたことも良い思い出です。

読売新聞東京本社写真部・青山謙太郎(あおやま けんたろう)
(08年5月19日撮影、5月21日付け夕刊「ズームアップ」面に掲載)
9万人近い死者・行方不明者、1000万人以上の被災者を出し、未曽有の大災害となった中国・四川大地震。
発生直後、現地入りし、被災した人たちでぎっしりと埋め尽くされた綿陽市・九洲体育館を取材中のことだった。
被害の状況を日本に迅速に正確に伝えなければ。緊張しながら、望遠レンズで被災者の表情を狙っていると、携帯電話を片手に泣きじゃくる少女の姿に目がくぎ付けとなった。
喧噪の中、少女の周りだけ時間が止まったかのようだった。
小学校1年生の喬思思ちゃん。母親は江蘇省に出稼ぎ中。一緒に暮らしていた祖父母は地震で亡くなり、親戚の元に身を寄せた。
そんな心細い避難所生活の中、地震発生以来不通だった電話が母親に始めてつながり、声を聞いた瞬間、感極まって泣き出した。
「お母さんにあいたい--」。ポツリとつぶやいた少女の言葉に私はなすすべもなく、突然、日本で私の帰りを待っている自分の子どものことを思い出した。
この5月で地震発生から、まる1年。子どもたちの生活環境がどうなっているのか。
今後も、四川に取材に向かう責任が自分にはあると、写真を見るたびに思い返す。
